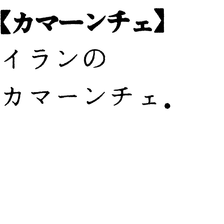改訂新版 世界大百科事典 「カマーンチェ」の意味・わかりやすい解説
カマーンチェ
kamānche[ペルシア]
西アジアや北アフリカの伝統音楽で用いられる胡弓ないしリュート型擦弦楽器。この名称はもともとペルシア語で〈小弓〉を意味し,馬の尾毛を張った弓で擦奏する種々の形態の楽器の呼名となっているが,その代表的なものとしてイランのカマーンチェとトルコのケメンチェが挙げられる。
イランおよびその周辺で用いられるカマーンチェは,椀形の共鳴胴を長い棒状の棹が貫通している型。共鳴胴の腹部には薄い羊皮(胎児の皮で半透明のごく薄いもの)を張り,金属弦(現在4弦が多いが2~3弦のものも地方によって用いられる)を用いる。奏者は棹の先端(中子先(なかごさき))を左膝上につけて楽器を支え,中国や日本の胡弓のごとく,右手の掌を上向きにして弓を持ち毛の張力を加減しながら左右にこする。これとほぼ同形の楽器がまた地方によって別名で呼ばれることもあり,ギチャク(アフガニスタン),ジョーザ(イラク),ウクルグ(トルコ),ラバーブ(エジプト)などがその代表的なもの。
トルコのケメンチェはカマーンチェのトルコ語形であるが,楽器の形態はいちじるしく異なり,西洋梨を縦割りにしたような形のネック型リュートである。これは本来ケメンチェ・ルーミー〈(東)ローマの胡弓〉と呼ばれたもので,ビザンティンの弦楽器の名残と考えられる。これは3弦で腹面は薄い板が張られており,近代ギリシアのリラやブルガリアのグースラはこれと同類である。
アラブ諸国では前述のイランのカマーンチェあるいはその変形が,アラビア語なまりでカマーンジャ(ないしカマンジャ,カーマンジャ)と呼ばれる。また近年はヨーロッパから伝来したバイオリンやビオラをカマーンジャと呼ぶこともある。
執筆者:柘植 元一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「カマーンチェ」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...