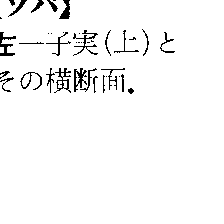改訂新版 世界大百科事典 「ソバ」の意味・わかりやすい解説
ソバ (蕎麦)
buckwheat
Fagopyrum esculentum Moench
タデ科の一年草で,種子は“そば”の原料として重要な作物である。草丈約60~130cm。三角に近い心臓形の葉を互生し,葉柄基部に茎を取り囲む鞘(さや)状の托葉をもつ。茎は片側にくぼみをもつ円筒形で,髄は中空。茎の先端数節に,総状花序で多数の花をつける。花は直径約6mm,花弁のように見える5枚の白または紅色の萼片と,8~9本のおしべ,1本のめしべからなる。めしべの基部にはみつ腺があり,芳香を放って虫を誘う虫媒花である。同一品種内にめしべの花柱が長くおしべが短い長花柱の花をもつ個体と,その逆の短花柱の花をもつ個体がほぼ同率に混在する。自家不稔性で,稔実には長花柱花と短花柱花とが交雑する必要がある。子実は瘦果(そうか)で,3稜のある三角錐形で,黒褐色あるいは銀灰色,長さ約6mm,幅約4mm,厚さ3~4mm,千粒重は16~35gである。やや硬い果皮(そば殻)の中に,薄い種皮に包まれた胚乳と胚があり,胚乳にはデンプンが多く包まれる。
原産地は,東アジアの温帯北部,バイカル湖付近から中国東北地方に至る冷涼地域といわれる。中国へは唐代に北域から伝わった。インドへは,8世紀ころに中国から伝わったと推定される。ヨーロッパへの伝播(でんぱ)は比較的新しく,13~14世紀ころという。
日本では,明治末年ころまでは15万~17万haの作付けで,約13万tの生産があったが,年々減少し,1970年以降は農林統計からはずされた。県別では北海道が全国の約4割を生産し,ほかに鹿児島,茨城,福島などに今日なおまとまった栽培が残っている。世界総生産量は従来平均約100万tで,そのうち大部分は旧ソ連で生産され,旧ソ連での生産変動が世界生産量を左右している。旧ソ連以外では,ポーランド,カナダ,日本がおもな生産国である。
ソバは冷涼な気候に適し,生育期間が2~3ヵ月と短いため,高地や高緯度地帯でもよく生育し,また気象災害などで他作物が被害を受けたとき,応急的に作付けされる救荒作物としての利用価値も高い。品種分化は十分進んでいないが,作期に対応して夏ソバ,秋ソバあるいは両者の中間型などに分けられ,いろいろな作付体系の中に組み入れられる。ただし霜には弱い。土壌は重粘土以外はさしつかえない。肥料は元肥を主体とし,少肥でよく生育する。夏ソバは,晩霜のおそれがなくなれば早くまく。秋ソバは,初霜の日から逆算し,寒冷地では70~80日前,暖地では80~90日前を播種(はしゆ)適期の限界とする。除草を兼ねて中耕を2~3回行い,とくに倒伏防止のため土寄せが必要である。全体の70~80%が成熟したころ,落粒を防ぐため早朝や曇天のときに根際から刈り取る。
ソバの種子はコムギよりもタンパク質がやや多く,アミノ酸構成も良質で,栄養価が高い。製粉してそば粉にする。日本での主用途はそば用で,ほかにそば粉菓子,そばがきなどに用いる。主食用にはそのほかに,半ゆでにして殻を除去したそば米がある。ほかに焼酎,ビールやウォッカの醸造にも用いる。日本では輸入が年々増加傾向にある。そば殻はまくら用にする。茎葉は緑肥や青刈飼料とする。またソバはみつ源植物としても重要である。
栽培種は本種のほかに,耐冷性のダッタンソバF.tataricum Gaertn.(ニガソバともいう),多年生のシャクチリソバF.cymosum Meisn.(シュッコンソバともいう)などがあるが,日本では作物としては栽培されていない。
執筆者:星川 清親
日本のそば
日本で古くソバを曾波牟岐(そばむぎ),久呂無木(くろむぎ)と呼んだのは,ソバの実が稜角で果皮が黒褐色のためである。5世紀半ばころすでにソバが存在していた事実は,長野県野尻湖底から採集した試料の花粉分析で明らかになった。文献では《続日本紀》の養老6年(722)7月19日の詔が最も古く,奈良時代に救荒作物として栽培されていたことがわかる。現在はそばといえば,細長い線状のそば切りを指すが,そば切りが考案されるまでの食べ方は,脱穀したソバの実(そば米)を雑穀類と混ぜて食べる粒食や,そばがき,そば餅などの粉食が行われた。そば切りの登場時期は明らかでないが,近江多賀大社の社僧であった慈性(じしよう)の《慈性日記》慶長19年(1614)2月3日のくだりには,江戸の常明寺でそば切りのちそうにあずかったことが記されており,格別珍しがっていないようすからみると,慶長年間(1596-1615)には普及していたとも考えられる。発祥地については,森川許六(きよりく)編の俳文集《風俗文選》所収の〈蕎麦切ノ頌(しよう)〉には,〈蕎麦切といっぱ,もと信濃国本山(もとやま)宿(現,長野県塩尻市)より出て,普(あまね)く国々にもてはやされける〉とあり,天野信景(さだかげ)の《塩尻》は甲州天目山の棲雲(せいうん)寺から始まったとするが,もとより伝聞,巷説の域を出ない。1645年(正保2)刊《毛吹草》の諸国名物のうち,武蔵と信濃には〈蕎切(そばきり)〉があげられ,信濃には〈当国より始ると云〉と注してあるが,時期が明確でなく,そば切りの発祥地だとは断定しがたい。
江戸初期におけるそば切りの製法は,《料理物語》(1643)によると,〈飯のとり湯にてこね候て吉(よし)。又はぬる湯にても,又豆腐をすり水にてこね申す事もあり〉とあり,つなぎに割粉(わりこ)(小麦粉)を使うことにはまったく触れていない。さらに1689年(元禄2)版の《合類日用料理抄》にも割粉を用いるとは書かれていない。その理由は,つなぎに小麦粉を混ぜる方法を知らなかったためと,当時雑穀を使っためん類,たとえば大麦切り,あわ切り,きび切りなどがつくられたが,これらはつなぎを使わずにその粉だけで打っていたことにもよると思われる。一説に,寛永年間(1624-44)奈良の東大寺に来た朝鮮の客僧元珍が小麦粉の使用を教えたというが,それを裏づける史料は見当たらず,実際に小麦粉をつなぎに使うようになったのは,早くても元禄(1688-1704)末期以後であろう。要するに,そば切りがつくられてから100年ほどの間,そば切りはそば粉だけの〈生(き)そば〉であった。
そば屋とそば売り
寛永ころには,地方の村々でもそば切りが売買されていたことは,1642年5月の御触書によって明白であるが,江戸の町でもほぼ同じころそば屋ができたという。江戸初期のそば屋は,三都とも菓子屋から船切り(生のそばを浅い矩形の箱に並べたもの)を取り寄せて使う店が多かった。1664年(寛文4)に〈けんどんそば切り〉が売り出され,4年後にははやりものの一つに数えられるまでになった。けんどんそばの元祖については,瀬戸物町信濃屋と堀江町二丁目伊勢屋との説があるが,吉原の江戸町二丁目仁左衛門とするのが正しい。〈けんどん〉は慳貪,見頓,喧鈍,巻飩,倹飩などの字があてられるが,あて字のうち,慳貪の本意である吝嗇(りんしよく)から,愛想がなく,1杯ずつ盛切りにして替わりをすすめず,給仕もしないのを建て前としたための名というのが通説である。やがて,そば屋,うどん屋をけんどん屋と呼ぶようになった。もともと,うどん屋では,出前に紅がら塗りの質素なうどん桶(おけ)を用い,汁はとくりに入れて別にした。けんどん屋になってからは2段棚の箱に変わり,これをけんどん箱,または略してけんどんといった。けんどん箱を仕切り,そばのほか汁次(しるつぎ)や薬味箱などもいっしょに収めたのが,〈けんどん提重(さげじゆう)〉で,忍(しのび)けんどんとも呼んだ。これに種々の蒔絵を施したのが〈大名けんどん〉である。夜間のそば行商がいつごろから始まったかは明確でないが,1686年(貞享3)には,めん類の夜売りが煮売り仲間から独立した業種として認められたばかりでなく,煮売りの筆頭にのし上がった。江戸ではこれを〈夜鷹そば〉,京坂では〈夜啼(よなき)うどん〉と称した。夜売りの期間は,陰暦9月から雛の節句である3月3日までと限られていたが,寛政(1789-1801)末以降は期限が延びた。
1728年(享保13)ころ,江戸の神田あたりに〈二八即座(にはちそくざ)けんどん〉の看板を出したそば屋があり,おそらくこれが〈二八そば〉の初めであろう。二八そばの名の由来には,二八十六の16文の代価説と,そば粉8割につなぎの小麦粉2割の二八とする混合率説とがあり,結論は出ていない。ただ,代価は1744年(延享1)から1860年(万延1)まで100年以上も16文の時代が続いたのに対し,二八が混合率を指すようになったのは,代価が16文を超えた文久(1861-64)ないしは慶応年間(1865-68)以後である。江戸後期になると,二八は駄そば(粗雑なそば)の代名詞となり,高級店は座敷を設け〈手打ち〉あるいは〈生そば〉を看板にして,二八そばとの格差を強調したが,幕末になると二八そば屋までが手打ちや御膳生そばを名乗り,店構えだけでは両者を区別できなくなった。そば屋の屋号には,〈藪(やぶ)〉〈更科(さらしな)〉〈砂場(すなば)〉をはじめ,享保(1716-36)ころからそば切り寺として知られた道光庵(江戸浅草の一心山称往院塔頭)にあやかるため,競って庵号をつけるそば屋がふえた。このほか,それぞれの系統があり,しにせでは独自の格式と味を保持している場合が多いが,一般にはのれんによる品質の差が見られないのが現状である。1860年における江戸府内のそば屋は夜売りを除き3763店を数えたといい,こうした普及に伴って,〈晦日(みそか)そば〉〈年越しそば〉〈引越しそば〉などの習俗が発生した。このうち前2者は,金銀細工師が飛散した金銀粉を回収するのにそば粉を用いたとすることから金銭の回収にかけ,後者は〈そば近く〉をもじって交誼(こうぎ)を願う意とされる。また,年越しそばはそれを食べると運が向くからといって〈運気そば〉,延命長寿や身代が伸びるというので〈寿命そば〉ともいった。
そばの加工
そば粉は石うすでゆっくりひいたものがよいが,ほとんどが機械製粉である。製粉されたものはふるいにかけて一番,二番,三番粉までをとる。一番粉は白いが粘りがなく,二番,三番粉の色は黒いが香りと粘りがあって,そば切りにつくりやすい。良質のそば粉の製粉歩留りは65~70%で,標準粉の新鮮なものはさらさらして薄緑色を呈し,ほのかな甘みがある。現在手打ちと機械製めんの両方が行われているが,機械製めんは1888年3月,佐賀県出身の真崎照郷が製めん機の特許を取得してから徐々に普及した。つなぎにはふつう小麦粉が用いられ,混合率によって,外一(そといち)(そば粉10,小麦粉1),一九,二八,七三,四分六,同割(どうわり)などと呼ばれる。これらのうち,二八は食いくちがよく望ましい配合であるが,現在では一部の店を除きそば粉と小麦粉が同量の同割になっている。これらに対して,そば粉の一部をのり状にして使う〈ともつなぎ〉のものが生そばである。このほか〈変りそば〉といって,つなぎに小麦粉以外の材料を加えたものがつくられる。おもなものにヤマノイモを用いる薯蕷(しよよ)切り,鶏卵を使う卵(らん)切り,タイのすり身を使うタイ切り,挽茶やユズを加えた茶そばやユズ切りなどがある。
そば切りは熱湯でゆでたものを,〈つゆ〉につけて食べるか,熱いかけ汁をかけて食べる。前者を〈もり〉といい,後者は,はじめ〈ぶっかけ〉といったが,寛政ころからそれを略して〈かけ〉というようになった。〈かけ〉にいろいろの具をあしらったのが種物で,加薬(かやく)そばとも呼ばれ,幕末ころまでに花まき,あられ,てんぷら,卵(玉子)とじ,鴨なんばん,おかめなどが売り出された。花まきは焼ノリ,あられはバカガイの柱をのせたもので,鴨なんばんの〈なんばん〉はネギのことである。おかめは結びゆば,かまぼこなどの具をのせておかめの面をかたどったもので,〈しっぽく〉もほぼ同じものである。地方の名物そばには,青森県の津軽そば,岩手県盛岡・花巻のわんこそば,福井県のおろしそばなどが知られ,岩手県陸中海岸のはらこそば,身欠きニシンをたくみに生かした京都のニシンそばも独特の風味をもっている。なお,そば切りのゆで汁であるそば湯を飲む風習は元禄ころ信州から起こり,江戸に広まったのは1748年(寛延1)以降で,そばのタンパク質が水に溶けやすい点からいって,栄養上きわめて合理的な利用といえる。
執筆者:新島 繁
民俗
ソバは山間の高冷地に適し,播種から75日で収穫できるといわれるように,短期間で取入れが可能なため,山村では焼畑の初年度作物として多く作られた。高知県高知市の旧土佐山村では,焼畑をソバヤマといったという。ソバの播種時期には各地で種々のことわざがあり,東日本では土用を目安としたが,岡山県では昴星をソバまき星と呼んで,スバルが中空に達するのを目安にまいたという。そばは奥羽や木曾などの山村ではそばがきや焼餅にして常食にされた。長野県木曾町の旧木曾福島町黒川では,大正初めまで,朝夕はそば焼餅で昼は粟飯が普通だったという。そばは初めは救荒食物や主食を補うものだったが,近世になりそば切りが流行しだすと変り物としてハレの食品にもされるようになった。年越しそばはその代表である。これは金箔業者が散った金粉をそば粉で取り集めたことに始まるといわれ,また金箔を狸の皮の上で叩き伸ばすことから,そば屋の店先にはよく狸の置物がある。神奈川県の旧家では,以前,婚礼や結納の宴席ではまずそばを出すしきたりだったという。また愛知県の山村ではかつて山の神祭の供物の一つにそば餅があった。そばを常食にすれば貧乏になるということわざも,そばがハレの食品とされたからであろう。小正月には,ヤロクロとかホガホガといって,豆やソバの殻を家の周囲にまきながら魔よけや田の代かきのまねをする風が東北北部で行われ,また岩手県久慈市の旧山形村では〈ソバ作り〉といって,正月15日晩にそばだんごで犬などの形を作って山桑の枝にさし,犬は害鳥を追うまじないにしたという。流行病の際には,〈ソバまで来たがアワしない〉といって,アワとソバを紙に包んで入口につるし,病気や厄病神を退散させる行事が行われた。このほかにもソバは厄災や穢れを払うのによく用いられた。昔話のなかには,ソバの茎根が赤いのは山姥の血で染まったからだという起源譚が伴っているものがある。また,ソバ畑は村はずれの地味の悪い所にあり,ソバの花は白く咲くため,夜道を帰る際には幻覚を起こさせ,よく沼や川などとまちがえられた。狐に化かされた話やソバを禁忌作物とする伝説には,よく水と見まちがえられたソバ畑のモティーフが登場する。
執筆者:飯島 吉晴
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報