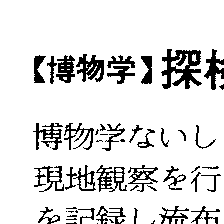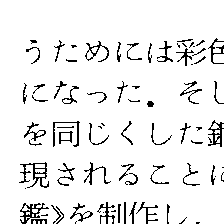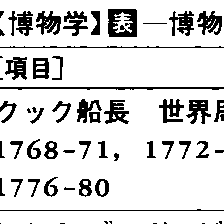精選版 日本国語大辞典 「博物学」の意味・読み・例文・類語
はくぶつ‐がく【博物学】
- 〘 名詞 〙 もと、動物学・植物学・鉱物学・地質学などの総称。天然物全体にわたる知識の記載を目的にする学の意。博物。
- [初出の実例]「科目は、実地適用を主とし、和学、漢学、〈略〉医学、博物学の類たるべし」(出典:公議所日誌‐八上・明治二年(1869)四月)
改訂新版 世界大百科事典 「博物学」の意味・わかりやすい解説
博物学 (はくぶつがく)
natural history
自然史,自然誌とも訳される。元来は,主として天然に存在する多様な動物,植物,鉱物(つまり自然物)の種類,性質,分布などの記載とその整理分類の学であった。その成果が自然誌(博物誌)であるから,博物学は自然誌学であったともいえる。古くは自然現象や地理,住民,産物なども対象とする自然学に包含されていたが(アリストテレスなど),科学の分化・発展にともない狭義の自然科学が確立されるにつれて,それと対置されるようになった。その意味では,自然の多様性または多様な自然物,それぞれの特殊性を明らかにしようとする科学であるということができる。16世紀後半から17世紀にかけて,ゲスナー,ブロン,アルドロバンディ,ドドネウス,チェザルピーノなどの博物学者が輩出したが,その努力のほとんどは鳥類とか昆虫とか魚類といった個別のグループ内の記載と分類に向けられていた。18世紀から19世紀にかけて,折からの帝国主義の台頭に合わせて,珍奇な動植物や未知の秘境を求めて多くの探検旅行が組織され,膨大な量の博物学的知識が蓄積された。やがてビュフォンの《自然誌》,カントとラプラスの太陽系起原論,ライエルの《地質学原理》,ラマルクとC.ダーウィンの生物進化論などの相次ぐ発展によって,これら多様な自然物(のみならず自然全体)は歴史的に形成されたものであるという認識が加えられて,博物学は自然史学としての性格も併せもつようになった。そして19世紀半ば以降,自然の多様性の研究は単なる記載・分類の学ではなくなった。その後,博物学ということばは,一方では記載・分類の学という意味に主として使われながら,一方では自然,とくに生物的自然の多様性とその歴史の研究という意味をもち続けてきた。生物学では多様な生態や習性の記載から始まった生態学や動物行動学が,20世紀になって進化学と結びついて,生物の多様性を中心に据えた〈進化生物学〉を形成してきたが,これは物理科学に基礎を置いた法則定立的な非歴史的〈機能生物学〉に対置されるもので,博物学の正統的後継者であるといえる。しかし,博物学の対象は古くから生物だけではなかったし,必ずしも天然物に限ったものでもなかった。自然の歴史の中に生じた天然物だけでなく,人類の歴史の中で生み出された〈人工の自然物〉がわれわれの周囲にどんどん増えている。家畜・作物の新品種はいうまでもなく,種々の高分子化合物や半導体などまで視野に入れるならば,単なる自然誌でも単なる自然史でもない学としての博物学を見直すことが今日では必要であろう。
日本の博物学
もともと日本語の博物学は,西欧語の訳語としてではなく,中国の《博物志》に想を得た〈博物〉,すなわち広く物を知るということばに由来し,明治期にnatural historyの訳語としてあてられたものである。江戸中期までの日本の博物学はほとんど,中国から輸入した本草学そのものであり,博物学の名に値する体系がととのうのは貝原益軒による《大和本草》の刊行(1708)以降とみてよい。享保年間(1716-36)には幕府の殖産興業政策によって物産学が盛んになり,博物学のすそ野が拡大された。この時期には田村藍水,平賀源内,小野蘭山,宇田川榕菴らの学者のほか,《目八譜》の武蔵石寿,《毛介綺煥(もうかいきかん)》《昆虫胥化(しよか)図》の肥後藩主細川重賢,《雲根志》の木内石亭,木村蒹葭堂(けんかどう)などのアマチュア博物学者も活躍した。
一方,17世紀からは断片的ではあるが西洋博物学の知識も入りはじめ,中でもドドネウスの《草木誌》とヨンストンの《動物図説》は当時の本草学に大きな影響を与えた。やがて,17世紀末のケンペル,18世紀後半のツンベリー,19世紀前半のシーボルトなどの来日を機に西洋博物学が本格的に紹介されるようになる。これに刺激を受けて飯沼慾斎の《草木図説》,岩崎灌園の《本草図譜》などの優れたしごとが生まれるが,全体としての博物学の近代化は明治維新をまたねばならなかった。明治初期にはマキシモビッチ,ブラキストンなどの博物学者のほか,モース,サバティエをはじめとするお雇い外国人教師の努力によって,帝国大学における生物学の研究体制が築かれ,博物学は新しい時代に入る。明治末期以降は大学における生物学からは,一部の分類学を除いて博物学の伝統はしだいに失われていくが,反面,牧野富太郎,松村松年,仁部富之助のようなすぐれた在野の博物学者も多数生みだした。なお,明治,大正から昭和初年にかけて,小・中学校の学科として博物学があり,動・植物学,鉱物学,地質学が教えられた(表およびコラム参照)。
執筆者:浦本 昌紀
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「博物学」の意味・わかりやすい解説
博物学
はくぶつがく
natural history
広義には動物・植物・鉱物などの自然物の種類・性質・分布・生態などを研究する学問。狭義には動物学、植物学、鉱物学、地質学の総称。同義語に博物誌、自然誌などがある。現代では自然物に関する各分野の科学が高度に分化、発展しているため、総称としての博物学という語が使われることはほとんどない。
人間の生活と深いかかわりをもつ動植物、鉱物などの自然物を薬用に用いる研究は古くから中国にあり、5世紀ごろに『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』『博物志』などの著作が出るに及んで本草学として初めて学問となった。この中国の本草学が『新修本草』として日本に入ってきたのは8世紀ごろと考えられる。その後、中国も日本も戦乱の時代が続いたため、学問一般の発展はみられなかった。17世紀初めに至り、徳川幕府が成立し、学芸が隆盛し始め、徳川家康自身も本草学に深い関心をもっていたことなどから、医師たちの間で薬用としての動植物の研究、記録が進められた。さらに中国の李時珍(りじちん)が著した『本草綱目』が日本に渡来し(1590)、当時の本草学者、貝原益軒、小野蘭山(らんざん)、稲生若水(いのうじゃくすい)らは大きな影響を受けた。なかでも貝原益軒は『大和(やまと)本草』をはじめ『花譜』『諸菜譜』などの書物を刊行し、本草、博物学の啓蒙(けいもう)普及に努めた。このように江戸時代に至って日本の本草学は成熟発展し、また博物学としての形を整えたと考えられる。
また江戸時代の中期、スウェーデンの博物学者ツンベルクが来日した(1775)。彼は、博物学の基礎となる動植物の分類学をおこしたスウェーデンの学者リンネに学んだ人物で、日本滞在の数年間に、動植物の標本など多数を得て帰国、『日本植物誌』(1784)、『日本動物誌』(1822~1823)などをまとめた。時を同じくして、日本でも蘭学の方面で、杉田玄白らの『解体新書』の完成(1774)があり、従来の実用を主とした本草学を基盤とした日本の博物学に対して、ヨーロッパの科学の方法を導入したものが生まれてきた。
ヨーロッパにおける博物学は、ギリシアのアリストテレス以来、動植物、鉱物など自然物についての研究がなされ、科学としての体系を形成してきた。イタリアのレオナルド・ダ・ビンチによる「解剖図」や、オランダのレーウェンフックの自家製の顕微鏡による微生物の観察記録などには、実用にとらわれない真理探究の情熱がうかがわれる。イギリスのハーベーの血液循環の原理発見や、イタリアのマルピーギのマルピーギ管の発見などがあり、学理研究としての博物学が17世紀に確立されていった。18世紀以後、ドイツのゲーテの『植物変態論』はじめ、フランスのラマルクの『動物哲学』、イギリスのC・ダーウィンの『種の起原』などが現れるに及んで、生物進化の思想を基本とした博物学となり、現代生物学への道を進むのである。
現代生物学は多くの分野に細分化され、その本質としての生物進化の探究から離れる傾向がなきにしもあらずである。実用の学問であった本草学が、科学としての博物学に発展したにもかかわらず、ふたたび実用のみのライフ・サイエンスにゆくようなことは避けなければならない。博物学は、「自然誌」ということばが示すように、あくまで自然のなかでの自然物の生活を研究し、記録する生物学の重要な分野である。
[國井嘉章]
『上野益三著『日本博物学史』(1973・平凡社)』▽『小野蘭山他著、上野益三解説『博物学短篇集』上下(1982・恒和出版)』
百科事典マイペディア 「博物学」の意味・わかりやすい解説
博物学【はくぶつがく】
→関連項目生物学|野呂元丈|大和本草
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「博物学」の意味・わかりやすい解説
博物学
はくぶつがく
natural history
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の博物学の言及
【自然誌】より
…自然の動物,植物,鉱物,また広くは天体,気象,地理や住民についても,網羅的に記載した編纂物を言い,〈博物誌〉とも呼ばれる。自然誌は〈自然について誌したもの〉という意味であるが,中国では誌を〈志〉とも書き,《漢書》以来〈天文志〉〈地理志〉〈食貨志〉などと呼ばれていた。〈自然史〉と訳されることもあるが,ここでのhistoryはstoryと同じ〈物語〉の意で,自然を歴史的に扱った自然史は18世紀までなかった。…
【格物致知】より
…近年,自然学の諸分野(宇宙論,天文学,気象学,化学,地理・地図学,生物学)における彼の卓越した見解が再評価されつつあるが,これも彼自身の格物の成果である。のちに,博物学は格致と呼ばれるようになり(清代に《格致鏡原》という本が編まれている),19世紀後半,欧米の科学技術が中国に入ってきたとき,科学にもまた格致や格物という語があてられ,軍艦や鉄砲などの生産技術は伎芸や製造と呼ばれた。また,アメリカのW.A.P.マーティンは,丁韙良(ていいりよう)という中国名で自然科学の概説書《格物入門》(1868)をあらわしたし,中国における最初の理科専門学校の名は格致書院(1875創設)であった。…
【生物学】より
…ガレノス(2世紀)はさらに医学の面から,解剖学およびこれと表裏一体のものとしての生理学の方向を確立した。これと,珍奇な生物や薬草の知識を主とする博物学とが,中世末までの生物学の内容であった。医学知識は人体の構造を中心としていて,比較と一般化の視点は乏しかった。…
※「博物学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...