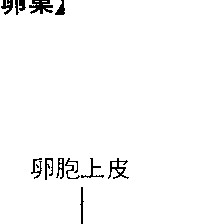精選版 日本国語大辞典 「卵巣」の意味・読み・例文・類語
らん‐そう‥サウ【卵巣】
- 〘 名詞 〙
- ① 動物の生殖器官の一つ。卵子を生じる器官で、無脊椎動物では体制により数および排列状態が異なる。脊椎動物では左右に一対ある。卵巣内の卵細胞は濾胞細胞にかこまれ成熟する。哺乳類では濾胞は脳下垂体前葉の濾胞刺激ホルモンの作用で成熟し、このホルモンと黄体ホルモンの相乗作用で排卵される。成熟卵巣は発情ホルモンを分泌し、排卵後は黄体ホルモンを分泌する。
- [初出の実例]「卵巣。其形平而鈍円。且有二小丸子一。多附レ之」(出典:解体新書(1774)四)
- ② 植物学で子房のことをいった。
- [初出の実例]「植体之可レ取二於目徴一者、凡三十四、〈略〉心蕋〈略〉之三部〈柱頭、花柱、卵巣〉」(出典:植学啓原(1833)一)
改訂新版 世界大百科事典 「卵巣」の意味・わかりやすい解説
卵巣 (らんそう)
ovarium
動物において卵の形成を行う器官。雌雄異体の動物では雌個体に,雌性生殖腺として存在する。雌雄同体の動物では,精巣とは独立した器官として存在する場合と,両性腺hermaphroditic gland(卵精巣ともいう)として,同一の器官に精巣と共存している場合とがある。両性腺は,軟体動物の腹足類や斧足類,脊椎動物では魚類にその例が認められるが,一般に卵巣機能と精巣機能が同時に発現することはまれで,個体の発達段階に応じて,精巣機能が先に現れ後に卵巣として機能を開始する場合(雄性先熟),逆に卵巣機能が先行して,精巣機能が後から現れる場合(雌性先熟)が多い。
脊椎動物の卵巣は原則として左右1対あるが,卵黄の多い卵をつくる種類ではしばしば一方が退化し,鳥類では右の卵巣,軟骨魚類では左の卵巣が痕跡的になる。脊椎動物では上皮と,それに包まれた髄質部から成る生殖腺原基の,髄質部分が退化して,上皮部分から卵巣が構築されている。上皮は生殖上皮と呼ばれ,卵原細胞oogonium(医学では卵祖細胞と呼ぶ),卵母細胞oocyteなどを含む。両生類や魚類では髄質部を成す結合組織が退化した後は卵巣腔となり,成熟した卵母細胞,または卵は,ここに排卵される。哺乳類の成熟した卵巣には生殖上皮は無く,濾胞細胞に包まれ濾胞follicle(医学では卵胞と呼ぶ)を形成した卵が,結合組織中に存在し,下垂体ホルモンの影響下に,成熟して排卵される。
脊椎動物の卵巣は,内分泌器官としても機能する。濾胞の成熟,排卵に伴ってホルモンの分泌パターンが変化し,それに伴って,生殖器,生殖器以外の体組織,行動などが変化し,交尾やそれに伴う受精,あるいは妊娠が起こりやすくなるように準備を整える。
執筆者:舘 鄰
ヒトの卵巣
ヒトの卵巣は,男性の精巣にあたる女性の生殖器であり,卵細胞をたくわえ,成熟させる器官であると同時に,卵胞ホルモンや黄体ホルモンなどの性ホルモンを分泌する内分泌腺である。ヒトでは骨盤腔の外側壁に接して卵管の直下に左右1対ある。前後に扁平な楕円形の白色臓器で,固有卵巣索および卵巣提索によって支えられており,長軸はほぼ上下方向をとっている。卵巣表面は,卵巣門と呼ばれる血管や神経の出入口を除けば,腹膜上皮で覆われているため幼児では平滑であるが,思春期以後は,卵胞(濾胞)や黄体の形成による膨隆や,それらの退化による陥没のため凹凸状を呈する。また老人では全体的に萎縮して,表面に細かいしわが多くみられる。大きさは成熟卵巣で長さ2.5~4cm,幅1.2~2cm,厚さ1cm程度であるが,その大きさは性周期による卵胞の発育変化や妊娠による妊娠黄体の形成などにより変動する。
卵巣の断面を観察すると,皮質と髄質が見られる。両者の境界は明りょうではないが,中心部の髄質が,結合組織と卵巣門を出入する動静脈やリンパ管,神経から成るのに対して,皮質は単層扁平の腹膜上皮で包まれ,その下に白膜と呼ばれる膠原(こうげん)繊維層があり,さらにその内側には,さまざまな成熟段階の数多くの卵胞や,それが変化してできた黄体や白体などが見られる。
卵巣皮質中に最も多く見いだされるのは,一次(原始)卵胞(一次濾胞)で,それぞれの中央に卵母細胞が位置する。卵母細胞は胎生期に卵巣に迷入した原始生殖細胞primordial germ cell(生物学では始原生殖細胞という)に由来する。かつては,腹膜上皮に由来すると考えられ,腹膜上皮を胚上皮と呼んだが,まちがいであることが明らかになった。原始生殖細胞は胎生期に分裂増殖し多数の卵祖細胞(卵原細胞)となる。これは,さらに分裂し減数分裂の前期の状態に入って,分裂が休止し卵母細胞となる。こうしてできた卵母細胞が,扁平な卵胞上皮細胞に包まれたのが一次卵胞である。一次卵胞は出生時には両側あわせて約40万個存在しているが,成人になるにつれて閉鎖退縮して数を減じ,閉経以後の婦人では見あたらない。卵巣の働きはこの卵胞と深く関係するが,それは脳下垂体前葉から周期的に分泌される2種の性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン),すなわち卵胞刺激ホルモンFSHと黄体形成ホルモンLHによって支配されている。思春期になるとこれらのホルモンが分泌され始めるようになり,両ホルモン(おもに卵胞刺激ホルモン)の働きで,一次卵胞は成熟する。すなわち,卵胞上皮細胞が分裂を繰り返して多層になり,顆粒(かりゆう)層と呼ばれるようになる。また卵胞上皮と卵母細胞の間に透明帯と呼ばれる粘液多糖類の層が出現する。このようになった卵胞を二次卵胞(二次濾胞)と呼ぶ。
二次卵胞の周囲は結合組織性の内・外卵胞膜に包まれる。このうち内卵胞膜の細胞は,繊維芽細胞の性質を失い,脂質滴が出現し,滑面小胞体が発達し,管状のクリスタをもつミトコンドリアが多く見られる。すなわち,ステロイドホルモン分泌細胞の形態をとる。この細胞から女性ホルモンであるエストロゲンが分泌されるが,これは子宮内膜を増殖させるほか,二次性徴をもたらす。なお二次卵胞はさらに成熟を続け,グラーフ卵胞(グラーフ濾胞,成熟卵胞)となる。グラーフ卵胞では二次卵胞の顆粒層(卵胞上皮,濾胞上皮)がさらに増殖多層化する。さらにこの細胞層の中のいくつかのすきまが融合し大きな卵胞腔(濾胞腔)を形成する。この中に卵胞液(濾胞液)をたくわえる。また卵胞腔はしだいに大きくなり,それとともに卵母細胞は一方へかたより,卵胞上皮細胞で覆われた卵丘を形成する。卵母細胞も径100μmあまりに達するが,卵母細胞は,停止していた減数分裂を行う。これを第一成熟分裂と呼ぶ。この分裂の特色として細胞質が不均等に分かれ,卵娘(じよう)細胞(生物学では第二次卵母細胞という)と,第1極体と呼ばれる小体になる。こうしてできた卵娘細胞は,受精を待つ状態にあるが,第1極体はやがて消失する。このようになると,グラーフ卵胞の直径は2cmにもなり,黄体形成ホルモンの作用により,卵巣のこの部分が破裂し,卵子が腹腔内を経て卵管へとび出る。これが排卵と呼ばれる現象で,思春期以後の女性では,平均28日に1回(閉経後,妊婦,産褥中には起こらない),両側の卵巣に交互に起こるといわれている。
これに対して,卵巣内に残された排卵後の卵胞は出血して赤体となり,さらに黄体となる。この黄体は脳下垂体から出る黄体形成ホルモンLHによって形成されるが,その中の顆粒膜ルテイン細胞(顆粒層の細胞の由来)および卵胞膜ルテイン細胞(卵胞膜細胞に由来)より黄体ホルモン(プロゲステロン)を分泌する。プロゲステロンは,おもに受精の子宮内膜への着床および妊娠の維持に働くほか,エストロゲンと協力して二次性徴を起こす。黄体は妊娠の起こらない場合は月経黄体と呼ばれ,排卵後10~12日で急速に退縮し,白体と呼ばれる瘢痕(はんこん)組織となる。これに対して妊娠が起こると黄体は大きくなり,妊娠黄体(直径4cm)を形成する。妊娠黄体からは出産までプロゲステロンが出されるが,妊娠3~4ヵ月ごろから胎盤の絨毛上皮でプロゲステロンが産出されるようになるため,そのころをピークとして退化し始め,出産後には白体となる。
卵巣は妊娠しないかぎり次期の排卵の周期に入るが,このような周期性は,中枢からのホルモンの支配のほか,それぞれのホルモンの相互作用や,フィードバックが深く関与している。なお卵巣からはおもに前述の2種類のホルモンが出るが,このほか少量の男性ホルモンも出されている。
→黄体 →月経 →排卵
執筆者:藤田 尚男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「卵巣」の意味・わかりやすい解説
卵巣
らんそう
脊椎(せきつい)動物と無脊椎動物の雌性個体に存在し、受精に関与する卵を形成し放出する生殖腺(せん)をいう。哺乳(ほにゅう)類では左右の卵巣とも発達するが、鳥類では右側の卵巣が退化的で、左側だけが著しく発達する。一般に卵黄の多い卵を形成する卵巣では、左右いずれかの卵巣が退化している動物が多い。哺乳類では子宮の末端がコイル状やらっぱ状の輸卵管になっていて、その輸卵管が卵巣と常時密着しているもの、あるいは排卵時だけ密着するものなどがあり、ここで受精するものが多い。哺乳類の卵巣は、卵を成熟させる濾胞(ろほう)、排卵後に濾胞が黄体化したもの、間質などからできている。濾胞や間質細胞は雌性ホルモンを、黄体は受精卵の着床や妊娠維持に必要なホルモンを分泌する。間質から雄性ホルモンを分泌する動物も多い。無脊椎動物の卵巣は1対だけとは限らず、各体節ごとに多数の卵巣をもつものや、放射相称に卵巣をもつものがある。卵巣は体腔(たいこう)上皮の生殖隆起からできるが、卵は卵黄嚢(のう)から移動してくる。
[高杉 暹]
ヒトにおける卵巣
ヒトの卵巣は女性の生殖器で、男性の精巣(睾丸(こうがん))に相当する。所在部位は大骨盤と小骨盤の境となる骨盤分界線のやや下で、子宮の両側に位置している。卵巣は扁平(へんぺい)な楕円(だえん)体で、かなり固い実質性臓器である。肉眼的には赤みを帯びた灰白色をしている。大きさは、日本人の場合長さ2.5~3.5センチメートル、幅1.2~1.9センチメートル、厚さ0.6~1.1センチメートル、重さは4~10グラムであるが、年齢、機能状態、個人差などでさまざまに相違がある。卵巣の表面は性的成熟期前では平滑であるが、大きな卵胞(らんぽう)が発育を始めると卵巣表面は膨隆し始め、排卵によって瘢痕(はんこん)が形成されるため、凹凸が多くなる。しかし、排卵現象がなくなれば萎縮(いしゅく)状態となる。卵巣は、小骨盤内でその長軸をほとんど垂直に向けているが、経産女性ではその長軸が水平に近くなる。
卵巣には内外2側面がある。内側面は骨盤腔(くう)に面し、その大部分は卵管に接している。外側面は骨盤壁に面している。また、後縁は遊離縁(自由縁)とよび、鈍円で強い隆起を示し、後内方を向くが、前縁は間膜縁とよび、直線に近く、前外方を向いている。間膜縁からは卵巣間膜が始まっている。間膜縁には血管や神経が出入する溝(みぞ)があり、卵巣門とよぶ。卵巣上端は卵巣端とよび、鈍縁となっているが、卵管漏斗(ろうと)に面し、卵管采(さい)に達している。卵巣下端は子宮端とよび、鋭く突出し、平滑筋を含む結合組織性の固有卵巣索(さく)によって子宮と連結している。卵巣の位置を固定しているのは、この固有卵巣索と、卵管端から骨盤側壁に張っている卵巣堤索(ていさく)である。
卵巣の内部は、外側部の皮質と中心部の髄質とに分けられるが、髄質には卵巣支質とよぶ線維の多い結合組織が充満している。皮質にはさまざまな発育状態を示す卵胞が含まれるが、排卵近い胞状卵胞(直径200マイクロメートルの成熟卵細胞を含んでいる)が著しく大きくなると皮質全層を占めるほどになり、卵巣表面に膨隆する。排卵直前の卵胞を成熟卵胞(グラーフ卵胞)とよぶ。排卵されたあとは、大きな空隙(くうげき)内に周囲の血管から血液が流入し、内部を満たすが、まもなく吸収され、結合組織性の黄体(おうたい)ができる。黄体には黄体細胞が含まれるが、この細胞が黄体ホルモン(プロゲステロン)を分泌する。卵が受精しないときには2~3週後には萎縮し、6~7週で消失してしまう(これを月経黄体という)。黄体が消失したあとに生じた瘢痕組織を白体(はくたい)という。卵が受精すると、黄体は発育して大きくなり、出産まで存在する(妊娠黄体(にんしんおうたい)という)。卵巣の中心部の髄質は柔らかい組織で、血管、リンパ管や神経が豊富である。
卵巣組織には、新生女児であっても、左右で40万個ほどの原始卵胞がみられるが、性成熟期から月経閉鎖期までに排卵に達する卵胞は、およそ400個ほどにすぎないとされる。
[嶋井和世]
百科事典マイペディア 「卵巣」の意味・わかりやすい解説
卵巣【らんそう】
→関連項目生殖腺|内分泌腺|半陰陽|無月経|卵|卵巣腫瘍|卵巣嚢腫
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「卵巣」の意味・わかりやすい解説
卵巣
らんそう
ovary
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「卵巣」の解説
卵巣
世界大百科事典(旧版)内の卵巣の言及
【性器】より
…すなわち男性では睾丸(精巣)で作られた精子が副睾丸(精巣上体)から精管を経て尿道に運ばれるが,付属腺として精囊や前立腺などがあり,交接器として陰茎がある。女性では卵巣とそこで作られた卵子を運ぶ卵管と,受精卵を育てる子宮,交接器としての腟などがおもな性器である。 このように,また,いうまでもなく,性器は男女で著しい性差を示すが,一般に性腺自身の特徴を一次性徴といい,それ以外の性別を示す特徴を二次性徴という。…
【生殖】より
…種子植物の花は全体として生殖器官に相当する構造であり,おしべや心皮のように生殖器官そのものである部分と,それを取り巻く花被(花弁と萼)やその他の構造で構成されているが,受粉のための機作が設けられているなど,受動的ではあるが生殖のための適応ははっきりと認められる。【岩槻 邦男】 動物の場合には,配偶子形成を行うための生殖腺(性腺)すなわち雄の精巣(または睾丸)と雌の卵巣と,そこでつくられた配偶子を排出するための生殖輸管すなわち輸精管,輸卵管である。生殖輸管は多様な分化を遂げ,交尾器官(交尾)や産卵(または出産)器官としての機能をもつにいたる。…
【内分泌腺】より
…(8)精巣 睾丸ともいい,脊椎動物の精巣のライディヒ細胞Leydig cellすなわち間細胞は,ステロイドである雄性ホルモンを分泌する。(9)卵巣 間細胞からステロイドである雌性ホルモンを分泌する。系統発生学的に考えて,精巣,卵巣は性細胞を形成するのが元来の機能であり,性ホルモンの分泌機能は進化の途上獲得されたものであろう。…
※「卵巣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...