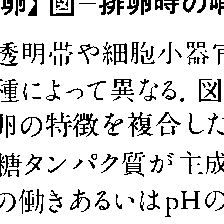翻訳|egg
精選版 日本国語大辞典 「卵」の意味・読み・例文・類語
たま‐ご【卵・玉子】
- 〘 名詞 〙
- ① 母体動物の生殖器内に生じ、発育して幼動物となることのできるもの。だいたい球形の細胞で、中に原形質、核、卵黄、脂肪球などがはいっている。その構造は動物によって異なる。外面にはさらに卵殻(鳥類)または、卵膜(昆虫類は厚い卵胞膜、蛙などはゼリー状物質、蛇などは柔らかいじょうぶな被膜)がある。卵子(らんし)。卵細胞。〔和漢三才図会(1712)〕
- ② 特に、鶏の卵のこと。鶏卵。
- [初出の実例]「碁石を十二かさねて、其上に九の卵子かさねんと云へり。〈略〉碁石十二に鶏の卵を九つかさぬるに、ちっともをちず」(出典:池辺本御成敗式目注(室町初か)四〇条)
- 「鶏卵(タマゴ)も三つ四つ持って来い」(出典:当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉九)
- ③ 物事の起こりはじめ。また、たね、もと。
- ④ 修業中の人。まだ、その事で一人前にならない人。
- [初出の実例]「この比の新造には出来物なり。〈略〉心もよし、御全盛の玉子とは此人の事にこそ」(出典:評判記・嶋原集(1655))
- ⑤ 和船の綱類を接続または留めるための便宜をはかって、綱の端を鶏卵状の輪にしたもの。用途により桁玉子、くくり玉子、蝉玉子などの名がある。〔今西氏家舶縄墨私記(1813)〕
卵の語誌
上代には「卵」を表わす語として「かひご(殻子)」があったが、中世において「蚕」が「かいご」とも呼ばれ、それによる同音衝突を避けるために「たまご」が用いられるようになり、近世に入って「たまご」が一般化した。
かいかひ【卵・稃・殻】
- 〘 名詞 〙 ( 「貝」と同語源 )
- ① たまご。また、その殻。かいご。
- [初出の実例]「然も国の危殆(あやふ)きこと、卵(カひ)を累(かさ)ぬるに過ぎたり」(出典:日本書紀(720)雄略八年二月(前田本訓))
- ② 穀米のから。もみがら。〔十巻本和名抄(934頃)〕
- ③ 虫などの、からだを覆っている外皮。〔色葉字類抄(1177‐81)〕
らん【卵】
- 〘 名詞 〙
- ① 配偶子の一つ。植物では卵細胞と呼び胚嚢、造卵器中にある大形の細胞。動物では後生動物の卵巣内にある卵子で、卵黄の含有量分布、卵黄の局在などにより種々の分類がなされている。精子を受精して卵割を開始し、一個の生命体を形成する。卵珠。
- ② たまごのこと。
- [初出の実例]「巣を作り卵(ラン)(〈注〉タマゴ)を育し」(出典:造化妙々奇談(1879‐80)〈宮崎柳条〉四)
改訂新版 世界大百科事典 「卵」の意味・わかりやすい解説
卵 (たまご)
egg
動物の雌が体外に産み出す卵子のこと。卵細胞は動物の諸細胞の中で最大で,とくに鳥類の卵は大きく,最小のハチドリの1種の卵でも1.2cm×0.8cm,最大のダチョウ卵に至っては16cm×12cmもの大きさがある。鳥類では,体の大きな鳥ほど大きな卵を産む傾向がある。ただし,体重に対する卵重の比は,大きな鳥ほど小さくなる傾向がある。体外に産み出される卵は,外敵からの保護や乾燥の防止などのために,膜membraneや殻shellによっておおわれていることが多い。昆虫卵は厚い卵胞膜で,カエルやイモリの卵はゼリー状の物質で,トカゲやヘビの卵は柔らかいがじょうぶな被膜でそれぞれ包まれ,鳥の卵は石灰質の固い殻でおおわれている。形は,鳥卵以外では一般に球形であるが,鳥卵では球形,卵形,楕円形,長楕円形,ヨウナシ形など変化に富んでいる。鳥卵におけるこの形の違いが何に基づくものかは必ずしも明らかではないが,穴の中に産みこまれる卵には球形に近いものが多い。また,岩棚にじかに産み落とされるウミガラスのヨウナシ形の卵は,転がるとき,とがったほうを中心にしてくるくる回るだけで落ちることがないので,そのような場所に産まれる卵として適した形をしているといえる。殻のついた鳥卵は,色もまた実に多様である。白,青,赤などの単色のものもあれば,それらにいろいろな模様のついたものもある。穴の中に産まれる卵には白いものが多く,地上に産まれる卵には褐色系のものが多いという傾向はあるが,それ以外の卵の色や模様にどういう意味があるのかはよくわかっていない。ただし,托卵をするホトトギス類の中には,托卵相手の鳥と同じ色や模様の卵を産むものが多い。これは,似た色の卵を産みこまないと,宿主の鳥に排除されてしまうためである。
1回の繁殖で産み落とされる卵の数は,動物グループによって著しく異なっている。魚類では一般にひじょうに多く,イワシやニシンで10万個前後,タラで300万個,マンボウでは2億~3億個にもなる。鳥類では一般に少なく,しかも変動幅も1~10数個とひじょうに限られている。こうした産卵数の違いは,卵を孵化(ふか)させるまでの方法と密接に関連している。すなわち,卵を産みっぱなしにする動物では産卵数は多く,産んだ卵をもち歩いたり暖めたりする動物では少ない。前者の代表が海洋魚であり,後者の代表が鳥である。魚でも,卵を安全な川底の石や水草の間に産みつけたり砂の中に埋めこんだりする淡水魚では,産卵数は数十個から数百個とかなり少ない。また,同じ系統内の動物では,産卵数は,気候や食物の季節的変動が著しいところにすむものほど多く,環境内に少しの食物しかないところにすむものほど少ないという傾向がある。この傾向は,同じ種内の異なる地域個体群の間にもあてはまることがある。例えば,ヨーロッパのロビンの産卵数は,季節変化の著しい北方にすむもののほうが多いし,日本のヤマガラの産卵数は,海洋性気候の影響下にある鳥のもののほうが本土のものより少ない。同じ系統内の動物では,産卵数と卵の大きさとの間には負の相関がある。すなわち,大きな卵を産むものほど産卵数は少ない。
→鶏卵 →産卵
執筆者:樋口 広芳
象徴,民俗
卵は西洋の象徴体系において,しばしば宇宙の原初状態を表現し,その場合は〈宇宙卵Cosmic egg〉と呼ばれる。錬金術では宇宙霊が封じこめられている混沌(カオス)を意味し,これをプリマ・マテリア(第1質料),すなわち宇宙創造の原物質とみなす。したがって,卵を隠喩とした宇宙開闢(かいびやく)論の影響は近世にまで及んでいる。これら卵生神話の例はおびただしいが,ギリシア神話には,豊饒(ほうじよう)の女神エウリュノメEurynomēが巨蛇の姿をとる神オフィオンOphiōnに犯され,ハトに身を変えて宇宙卵を産んだ話がある。この卵は後に巨蛇に抱かれ,そこから秩序宇宙(コスモス)が孵化したという。またギリシアのオルフェウス教による神話は,上天の神アイテルAithērがクロノスないしカオスと交わって巨大な銀色の卵をつくり,そこから最初の両性具有神プロトゴノスPrōtogonos(〈最初に生まれた者〉)あるいはファネスPhanēs(〈光明〉)が生まれたと説く。さらにエジプト神話では,ナイル川のガチョウが産んだ黄金の卵から太陽神ラーが誕生し,創造神クヌムKhnumも口から卵を吐きだしこれを言語の源としたと語られている。同様にヒンドゥー神話にも黄金の卵から創造神ブラフマー(梵天)が生まれ,二つに割れた殻が天と地に変じたという話がある。これらの神話は非生物的な卵から生物が生まれる創造の奇跡に由来すると考えられ,混沌から秩序への移行を象徴する。こうした〈宇宙卵〉の寓意はルネサンスのヘルメス思想家にも影響し,J.ディーやR.フラッドは卵に擬した神秘的な宇宙構造モデルを発想している。
また卵は生命とその再生を表す標章としても広く用いられた。すでにエジプトのミイラ棺には赤い太陽を思わせる卵が描かれており,再生を願う呪術(じゆじゆつ)的意味がこめられたものと思われる。キリスト教会,コプト教会,イスラムのモスクなどでも,ダチョウの卵をはじめ大型の卵を創造や再生の象徴として建物内部につり下げる習慣があった。このダチョウの卵はマリアの処女懐胎を表し,キリスト教美術の題材にされている。またユダヤ教徒は過越の祭に復活と来世を示す卵を食べたが,習俗としてキリスト教徒へも伝えられた。とくに復活祭には色を塗った卵〈イースター・エッグEaster egg〉を贈りあい,後には子どもの遊びになった。イギリスでは〈卵転がしEgg rolling〉や卵のスプーン運び競技,ドイツでは野原に隠したイースター・エッグを探す遊び,アメリカでは菓子やチョコレート製の卵を子どもたちに配ったり,卵を打ち合わせて割れないほうが相手の卵をもらえる遊びの〈ニッキングnicking〉などが行われる。
卵に関する俗信も多く,日没後これを屋外に持ちだしたり売り歩くのは不吉とされ,卵の夢は悪運の前兆と考えられた。また年取った雌鶏(めんどり)が最後に産む卵や聖金曜日に産まれた卵は,鶏小屋を守る護符にされる。イギリスにはかつて,目隠しをして,まきちらした卵を踏まぬように踊り回る〈エッグ・ダンスEgg dance〉が行われた。かなり難しい踊りであったため,現在では〈困難な事がら〉を意味する成句になっているが,これも生命の復活を祈願する古い信仰に由来する。民話や伝説に語られる金の卵を産むガチョウまたはニワトリの話は,これらの信仰に深くかかわっており,金の卵は太陽,銀の卵は月をも表すといわれている。またギリシア建築の装飾に〈卵鏃(らんぞく)飾りegg and dart〉と称する繰返し模様があり,卵と鏃(やじり)の組合せで女と男の生殖器,あるいは両性具有を象徴するといわれる。
執筆者:荒俣 宏
卵と日本人
玉子とも書くのは形が丸いところからきたと思われるが,魂(たま)の入ったものと考えたためとも解される。古語は〈カヒコ〉で,〈カヘルコ〉のつまったものとも,貝のような石灰質の殻に入った子という意味からきたとも解されよう。未成品ということから転じて,職業人の見習段階にある者を○○の卵と呼ぶ表現法もある。古代人は卵生について大きな神秘性を感じたであろう。貴人の系統には,一般民衆と異なるものがあることを説く,天から降った,海中から出現したなどという神話とならんで,卵から生まれた人が民族の祖となったという〈卵生神話〉の類型が,北・東アジアから北ヨーロッパの民族に認められる。日本でも《古事記》の天日槍(あめのひぼこ)の説話や《日本霊異記》などの卵状の肉団から人が生まれる話がみられる。
執筆者:千葉 徳爾
日本における食用の歴史
近世以前の日本人はあまり鶏卵を食べなかったようである。ニワトリのほうは天武天皇時代に牛馬犬猿とともに食用が禁止されているが,卵についてはそうした禁令は出されなかった。それにもかかわらず卵を食べることが少なかったのは,それを肉食同様の殺生とする感覚があり,《日本霊異記》や《沙石(しやせき)集》に見られる因果応報譚--卵を食べたために恐ろしい報いを受けるといった話が庶民の間に流布し,浸透していたためではないかと思われる。中世末期になって,いわゆる南蛮料理,南蛮菓子が伝えられ,ヨーロッパ人や中国人がまったく罪悪感をもたずに肉や卵を食べるのを実見してから,多くの日本人が卵に対して抱いていた観念は崩壊し始めた。そうした状況の中で,日本で初めて卵料理の作り方を書いた書が登場した。《料理物語》(1643)がそれで,〈みのに(美濃煮)〉〈玉子ふわふわ〉〈まきかまぼこ〉〈玉子はす〉〈玉子素麵(たまごそうめん)〉といったものが紹介されている。美濃煮は卵を金しゃくしに割り入れ,そのまま湯煮して固まらせ,吸物にする。玉子ふわふわは卵をとき,だし,たまり,煎酒(いりざけ)で調味して蒸す。まきかまぼこは薄焼卵に魚のすり身を塗り,それを巻いてゆでる。玉子はすは〈カラシれんこん〉のように,れんこんに卵黄を流し入れて蒸す。玉子素麵は,現在では鶏卵素麵と呼ばれて博多名物にもなっている菓子である。
食用に対する抵抗感,違和感が薄らぐにともない,卵は急速に食品としての重要性を増していった。栄養の豊富さや,さまざまな調理法を駆使しうる便利さからいっても,それは当然のなりゆきであった。しかも,《本朝食鑑》(1697)が陰萎不起に妙験ありとしているような強精効果も深く信じられていた。1785年(天明5)には《卵百珍》の別名で知られる《万宝料理秘密箱》前編が出版された。100種余の卵料理を紹介したもので,趣向を楽しませる読物としての性格が濃いが,卵料理の人気のほどを物語るものといえよう。ところで,卵を使った菓子の代表はカステラであり,卵料理のほうでは〈巨人,大鵬,卵焼き〉なる俗言のごとく,卵焼きが代表的なものである。しかるに《卵百珍》には卵焼きの作り方は書かれていないのである。それでいて,文中しばしば〈卵焼きなべ〉という語に出あう。天明(1781-89)初年,すでに卵焼きの調理法は常識であり,あらためて紹介する必要はなかったものと思われる。
執筆者:鈴木 晋一
卵料理
使用されるのは大部分が鶏卵であるが,ウズラやアヒルの卵も使われる。ウズラの卵は小型なので装飾的に用いられ,スープや吸物の実にしたり,そばつゆやこのわたに落としたりする。アヒルの卵は鶏卵より大きく,卵黄の色の濃いのが特徴で,中国では皮蛋(ピータン)などに加工されるほか,いろいろの料理に用いられる。
鶏卵を使う料理はひじょうに多いが,おもなものを挙げると次のようになる。(1)卵焼き 卵黄と卵白をかき混ぜて焼くものと,割ったままかき混ぜずに焼くものとがある。前者には薄焼きと厚焼きの和風の卵焼きのほか,西洋料理のオムレツなどがあり,後者には目玉焼きがある。薄焼卵はせん切りにして(金糸(きんし)卵と呼ぶ),五目ずしやめん類の具にしたり,焼き上げた大きさのまま酢飯を包んで茶巾(ちやきん)ずしにする。厚焼卵には関東風の厚焼きと関西風のだし巻とがある。前者は甘みをきかせた濃厚な味つけをし,表面に適度の焼色をつける。後者は甘みをひかえただしを加えて焼き,焼き上げたものを簀(す)で巻いて形をととのえる。厚焼きでウナギの蒲焼を巻いたものを〈う巻〉といい,魚のすり身を加えた厚焼きを巻いたのが伊達巻(だてまき)である。目玉焼きはフライパンにバターを入れ,熱したところへ割り入れて焼く。ハムやベーコンをいためてつけ合わせれば,ハムエッグ,ベーコンエッグである。(2)いり卵 鶏卵をといて砂糖,塩,しょうゆ,酒などで味をつけ,なべでいりつける。もみノリや煮つけたシイタケのせん切りを加えてもよい。中国風のものでは芙蓉蟹(フーロンシエ)があり,洋風のものにスクランブルドエッグがある。これはといた卵に牛乳,生クリームなどを加え,塩,コショウで調味し,バターをたっぷり使って半熟程度にする。野菜,ハム,ベーコンなどをいためてつけ合わせるとよい。(3)ゆで卵 ゆで方によって半熟から固ゆでまで,いろいろの固さのものが作れる。半熟卵は塩を振って食べるが,卵黄がとろりと流れるほどのものはきわめて美味なことがあり,これを名物の一つとする高級料亭もある。固ゆで卵は煮抜(にぬき)卵ともいい,かつては遠足や行楽に付物であった。そのまま食べるほか,おでん種にしたり,サラダに使ったりする。以上のゆで卵が殻のままゆでるのに対し,割った卵を静かに熱湯の中へ入れて加熱するものをポーチドエッグといい,いろいろの料理に用いられる。(4)蒸物 茶わん蒸し,卵豆腐などが代表的なもので,いずれも塩,しょうゆ,酒,みりんなどで調味しただしでときのばした卵汁を使う。卵とだしの割合は,茶わん蒸しで1対3,卵豆腐で1対1とする。卵豆腐はこの割合の卵汁を水囊でこして金属製の流し箱などに注ぎ,蒸器に入れて弱火で20~30分蒸す。これを冷やしたのち,大きめに切って器に盛り,やや濃いめに味つけしただしを少量かけ,おろしワサビやユズをのせて供する。冬はあんかけにしてもよい。(5)その他 卵とじやかきたまは,そばやうどんに用いられることが多い。前者は汁物や汁の多い煮物のでき上がりにとき卵を流しかけて半熟ほどにするもので,ドジョウの柳川なべや鶏肉を用いる親子煮などもこれに属する。かきたまは,とき卵に片栗粉などを加えて汁に流し入れる。月見と呼ぶものは,卵黄または卵をそのまま落としたもので,とろろいも,そば,うどんに使われる。変わったものには卵黄のみそ漬がある。弁当箱などにみそを詰めガーゼを敷いてくぼみをつけ,その中へ卵黄を入れ,ガーゼをかぶせ,みそでおおう。2日ほどでペースト状になり,さらに置くと固まって半透明になる。これを薄切りにすると〈からすみ〉に似ており,突出しに用いると好適である。
執筆者:橋本 寿子
卵 (らん)
egg
Ei[ドイツ]
œuf[フランス]
ovum[ラテン]
同一種の動植物において,生殖に関与する配偶子に形態学,生理学的な差が認められ,2種類以上のものが区別される場合に,それらを異型配偶子と呼ぶ。異型配偶子は形の大小にしたがって,それぞれ大配偶子,小配偶子と名づけられているが,大配偶子は一般に運動性をもたず,細胞質内には栄養物質を多量に有し,卵または卵子と呼ばれる。これに対して小配偶子は運動性に富み,細胞質はほとんどなく,細胞のほとんどすべてが細胞核成分と,運動のための小器官で占められていて,精子と呼ばれる。核相は単相。
動物の卵
卵あるいは卵子の語は厳密には配偶子に対して用いられるべきものであるが,実際には,胚や卵子の付属物もふくめて広く卵(たまご)の意味で用いられていることが多く,しばしば混乱の原因となっている。鳥の卵を例にとってみよう。鳥では受精は体内で起こるから,産卵時の卵の内部ではすでにかなりの程度胚発生が進んでいる(古い生物学の書物に,鳥は胎生であると記述してある場合があるのは,このためである)。さらに,孵卵(ふらん)をして胚が孵化直前に至るまで発生しても,外観は卵である。また哺乳類では,受精から着床期の胚盤胞に至る初期胚の時期すべてについて,卵を慣用語として当て,学術的にも用いられている。
本来の配偶子としての卵は,その周囲をいろいろな卵膜と呼ばれる無細胞性の膜構造や,卵形成に際して,その周囲を取り囲んで存在する濾胞(医学では卵胞と呼ぶ)細胞などさまざまな付属物とともに観察されることが多く,卵または卵子の語は,そのような複合構造全体に対して用いられていることが多い。一方,卵巣内にあって,いまだ成熟分裂を行っていない卵細胞は,配偶子ではなく,卵母細胞oocyte(医学では卵祖細胞と呼ぶ)の状態である。哺乳類では,卵巣内の第1次卵母細胞が排卵時に第1極体を放出して第2次卵母細胞(医学では卵娘細胞と呼ぶ)となり,受精と同時に第2極体を放出して減数分裂を完了する。したがって,配偶子としての意味で卵というべき時期は,第2極体放出後のひじょうに短時間存在するのみである。現状では,これらの用語の適・不適をいうのは困難であるが,精子に対応するものとして,卵子は配偶子に対して用い,より広義に用いる場合には卵,また細胞レベルで卵子や卵母細胞を含めて広義に呼ぶ場合には,卵細胞などの用語を用いるのが適当であると思われる。
これまでに知られている最大の卵は鳥類(ロック)のそれで,最小は外肛動物のコケムシの仲間のものであるという。前者は長径33cm,短径23cmの長円形で,後者は直径30~40μmの球形である。哺乳類の排卵時の卵母細胞の直径は70~140μmの範囲であるが,卵生哺乳類である単孔類(カモノハシ,ハリモグラ,ナガハシハリモグラ)の産卵時の卵の大きさは,12~15mmである。
卵子はその卵黄の量によって,無黄卵(棘皮(きよくひ)動物,哺乳類など),僅黄卵(きんおうらん)(昆虫類,甲殻類,斧足類など),中黄卵(両生類,頭足類など),多黄卵(爬虫類,鳥類など)に区別することもある。ただし,無黄卵といっても,卵黄物質がないわけではなく,また僅黄卵と中黄卵の区別も明確ではない。
脊椎動物の卵黄成分のタンパク質成分の主体は,水溶性リポタンパク質のリポビテレニン,不溶性リポタンパク質のリポビテリン,リンタンパク質のホスビチンから成る。無脊椎動物では昆虫の卵黄形成がよく研究されている。卵黄タンパク質の主成分は,マンノースを主体とする糖鎖,脂質,およびリンを含む複合タンパク質である。哺乳類卵子細胞質中には,電子顕微鏡で観察される盤状,繊維状など,種に特有の構造が認められる。これらの構造は,RNAとタンパク質の複合構造と考えられているが,その意味は不明である。
→卵(たまご) →排卵
執筆者:舘 鄰
植物の卵
植物の卵はふつう一つの雌性配偶子囊の中に1個つくられる。藻類や菌類では単細胞性の雌性配偶子囊である。生卵器oogoniumの中に,コケ植物や維管束植物では多細胞性の造卵器archegoniumの底部につくられるが,造卵器を欠く被子植物では,胚囊 embryo sacをつくるふつう8細胞のうちの一つが卵になり,助細胞を伴って胚囊の珠口側に位置する。卵は卵母細胞から体細胞分裂によってできるが,カサノリなどのように複相の植物体の場合は,減数分裂を経てできる。卵は精子と接合(受精)し,接合子(受精卵)になる。
→受精
執筆者:加藤 雅啓
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「卵」の意味・わかりやすい解説
卵(たまご)
たまご
egg
雌雄の配偶子で明確な差異が認められる場合に雌性配偶子をさす語であるが、生物学上は卵(らん)あるいは卵子(らんし)とよぶことが多く、卵細胞(らんさいぼう)ともいう。また、しばしば卵(らん)には卵巣から排卵されたのちに卵白のような養分や卵殻が付加されるが、卵(たまご)というときにはこれらの付加物を含めることが多い。
以上の生物学的な卵の詳細については「卵(らん)」の項を、また卵(たまご)のうちもっとも典型的で、広く利用される鶏卵(けいらん)については「鶏卵」の項をそれぞれ参照されたい。
[八杉貞雄]
文化史
世界のほとんどの民族にとって卵は食物だった。ただし、アフリカのサン系の人々にいまでもみられるように、西アジア、アフリカのダチョウの卵だけは先史時代から堅牢(けんろう)な殻を利用して、単に穿孔(せんこう)するか未加工のまま携帯用や据置き用の容器とし、あるいは加工して装飾品(ビーズなど)、楽器(がらがら)部品とするなどの技術を発達させた。
世界の多くの民族にとって卵は家禽(かきん)(実質的にはニワトリ)の卵を意味するが、蜂蜜(はちみつ)とともに採集した蜂の卵、漁獲した魚の卵の食用・加工などの随伴的利用の対象である卵があるほか、熱帯・亜熱帯的気候の大洋沿岸、アマゾン川流域のいくつかの民族ではウミガメなどの卵が特別な食糧とみなされ、哺乳(ほにゅう)動物相の貧弱な島の民族(とくにニュージーランドのマオリ)では、野鳥の卵を代替的に重要動物食にすることがあった。人々が卵を食用にする野鳥には、食用により生じる個体数減少を回復しやすい水鳥が多く、水産資源の豊富な寒流地帯ではウミガラス、ペンギンなどの卵を郷土食にすることもある。
人類を含む野生類人猿は野鳥の卵を食べていなかった可能性があり、人類の食域が拡大したのちでも、親鳥が隠すことの多い卵を発見するのはやや困難で、発見しても小形で採集労働に見合わない卵が多い。そのうえ、殻が薄くて運びにくいから、食用にしたとしても、偶然に発見した卵をその地点で採食するのにとどまりやすかった。特定の野鳥の卵を意図的に採食すると短期間にその鳥の密度が激減し、それ以後の食用は困難になりやすいから、家禽の出現以前には、比較的大きい卵を産み群生していて採集労働の効率的な一部の水鳥の卵を除けば、卵に関する文化複合が形成されるのはおろか、卵が一民族のメニューに恒常的にのることすら例外的だったとみてよい。
卵に特別な文化的意義を考えた最古の高度文化は、大形卵を産む群生水鳥(ガン)を家畜化した紀元前三千年紀のエジプトだった。第五王朝の浮彫りにガチョウの卵がみられ、太陽かガチョウの卵かを判断しがたい赤楕円(だえん)モチーフが一般的であるのに加え、原始混沌(こんとん)からの誕生神話などと並んでガチョウの卵から主神ラーが生まれたとの説話が残るなど、前二千年紀にかけてはガチョウの卵が特別な意味をもつ文化要素だった。
ニワトリ飼養の普及後にはニワトリの卵を主として利用した地域が広がったが、ニワトリの家畜化地域とされてきた南アジアの卵生説話はむしろ新しく、確認できる最古の例は、前9世紀以前に成立したとされる『シャタパトゥハ・ブラフマナ』だろう。宇宙を満たす水中に生じ、プラジャパーティが中から出てくる金の「宇宙卵」である。その後この卵生思想はウパニシャッドやプラーナ類にも散見し、南アジアの文化伝統になった。環地中海地域ではエジプト系の宇宙卵思想が発展し、トルコ半島から伝播(でんぱ)して前6世紀以降に整備されたオルフェウス教創世神話では、エーテルとカオス(またはクロノス)間にできた銀白色の宇宙卵からプロトゴノス(初生者)またはプハネース(光明)が生じるなどとした。この卵生神話を母体として、復活祭のイースター・エッグに連なるユダヤ、キリスト、イスラム教地域にみられる民間信仰的な卵の文化が展開したとみてよいだろう。錬金術には卵の黄色蒸留液を触媒に用いた試みがあり、近世神秘思想の宇宙卵につながる異端的卵生思想が西欧にあったことも確認できる。
東アジアの高度文化には、ツバメの卵を飲んだ母から殷(いん)王朝始祖が生まれた(『史記』)、揚子江(ようすこう)流域の卵生民族(『山海経大荒南経(せんがいきょうたいこうなんきょう)』)などがある程度で、年代的に遅れ、宇宙卵思想もないが、高句麗(こうくり)、新羅(しんら)、伽耶(かや)(加羅(から))の支配者が、それぞれ特異な卵から生まれたとの古代朝鮮の神話がやや目だつ。とくに新羅の王祖がウリに似た卵から生まれたとする説話は、果実からの誕生民話と卵の文化がつながる点で注目される。
19世紀の日本には、蚕種(さんしゅ)(養蚕用の蚕の卵)の生産輸出が地域経済上で重要な地域があった。
[佐々木明]
卵(らん)
らん
雌雄の配偶子が形態的にも機能的にも区別できるとき、雌の配偶子(雌性配偶子)を卵あるいは卵子という。これに対し、雄の配偶子(雄性配偶子)は精子とよぶ。動植物全般にわたって、精子が小形化し運動性を獲得するのに対し、卵は栄養分の蓄積により大形の球形あるいは楕円(だえん)球形をとることが多い。植物では、被子植物、裸子植物、シダ植物、コケ類などで卵細胞がみられる。動物ではほとんどすべてが卵をもつ。卵は雌性配偶子として卵巣内の原生殖細胞に由来し、卵原細胞、卵母細胞を経て、減数分裂により母側の半数の染色体を担う。この減数分裂の完了の時期は動物によって異なり、卵巣から体腔(たいこう)あるいは体外へ排出(排卵)されるときに、減数分裂を完了しているものから第一次減数分裂もしていないものまで種々の段階のものがある。いずれの場合にも、減数分裂の際はきわめて不均等な細胞分裂をし、半数の染色体からなる4個の核のうち、3個はごくわずかの細胞質を伴って放出され、1個の核が卵に残る。この小さな3個の細胞を極体と称し、極体が放出される部位を卵の動物極、その対極を植物極とする。ウニ卵などでは、この染色体による遺伝情報のほかに、母側の細胞の伝令RNA(リボ核酸)を受け取っていることが知られている。この減数分裂に先だって卵巣内で、濾胞(ろほう)細胞あるいは哺育(ほいく)細胞から栄養の供給を受けて、卵母細胞は卵黄を蓄積する。卵黄の蓄積は、ある種の昆虫、魚などにみられるように二十数時間で完了するものから、イモリなどのように3年近くかかるものまでいろいろある。卵黄の蓄積のようすも動物によって異なり、比較的少量の卵黄が卵内に均等するもの(等黄卵といい、ウニ卵など)、非常に大量の卵黄が蓄積され、細胞質は動物極側のほんのわずかな部分にしか存在しないもの(端黄卵といい、鳥類、爬虫(はちゅう)類の卵など)、あるいは卵の中心部に蓄積されるもの(中黄卵あるいは心黄卵といい、昆虫卵など)などがある。卵黄の蓄積と関連して卵の大きさも、ダチョウの卵のように最大長径15センチメートルに達する巨大なものから、10マイクロメートル程度のものまで多種多様である。動物によっては、卵黄蓄積とともに核は徐々に形を変え、核小体(仁)を多量に含む大きな不定形な核へと変化することがある。このような核を特別に卵核胞とよぶ。減数分裂はこの卵核胞の崩壊後におこる。卵黄蓄積の最後の段階で、卵を取り囲む濾胞細胞と卵の原形質膜の間隙(かんげき)に物質が蓄積し、卵黄膜をつくる。この卵原形質膜下の卵表層が精子に反応しうるような機能をもつようになったとき、卵が成熟したといい、ここまでの過程が卵形成である。成熟した卵は、動物のホルモンの作用により排卵される。
[竹内重夫]
卵
以上述べたような卵細胞のほか、これを包み保護している卵白、卵殻などを含めたものを「卵(たまご)」とよび、鶏卵は「卵」の典型的なものとされている。「卵」の中心にあるのは卵細胞で、極端に蓄積した卵黄のため黄色を呈し、黄身とよばれる。黄身の中心から卵表層の胚盤(はいばん)に通ずる細長いフラスコ様の通路には、色の薄い卵黄(白色卵黄)が満たされている。これはラテブラとよばれ、卵の成長に応じて胚盤が移動した跡だとされている。成熟した卵は体腔に排卵され、輸卵管上部に達し、ここで受精することになる。卵が輸卵管を下っていく間に卵白、いわゆる白身が取り囲む。白身はタンパク質で、水分の比較的少ない固い部分と水分の多い柔らかな部分が層をなしている。卵の両端にはねじれた紐(ひも)様の固いタンパク質が付着するが、これはカラザ(体)とよばれ、卵殻内での卵の位置を保つのに役だつと考えられている。白身は卵を機械的衝撃から保護するだけでなく、リゾチームという殺菌効果のある物質を含むことから外部からの細菌による汚染をも防護していると考えられる。また、卵への水の供給源として、また発生の際の栄養としても利用される。
卵白に包まれた卵が子宮に達すると、ここで卵殻が形成される。まず、繊維状の硬タンパク質からなる二層の緻密(ちみつ)な網が白身の外側を包み、卵殻膜となる。このしなやかで強靭(きょうじん)な膜の外側に方解石型の結晶構造をもつ炭酸カルシウムの粒子が沈着する。粒子と粒子の間隙は気体の通過を妨げない。かくして「卵」は完成し、産卵される。輸卵管の上部から産卵されるまで、二十数時間の過程である。受精している場合は、この間に卵割(細胞分裂)を繰り返し、上下二層からなる胚盤葉が形成された段階で産卵される。この胚の将来の頭の方向が、産卵前に子宮内に置かれた位置と関係しているといわれている。普通、「卵」のとがった側をわれわれの右に向くように置くと、この向きとは直角に、われわれより遠ざかる方向に胚頭が向く。これを「ベーアの法則」という。しかし、子宮内で「卵」を斜めにすると、その角度に応じて「ベーアの法則」からずれて胚の頭部が決められるという。つまり子宮内に置かれたときの重力がなんらかの影響を及ぼすと理解されている。
[竹内重夫]
普及版 字通 「卵」の読み・字形・画数・意味
卵
常用漢字 7画
[字訓] たまご
[説文解字]

[字形] 象形
卵の対生する形。〔説文〕十三下に「
 そ物、
そ物、 すること無きものは卵生なり。象形」とあり、〔段注〕に魚卵の形であろうという。〔礼記、内則〕「卵
すること無きものは卵生なり。象形」とあり、〔段注〕に魚卵の形であろうという。〔礼記、内則〕「卵 」の〔注〕に「讀んで鯤(こん)と爲す。鯤は魚子なり」とあって、魚卵のときは音が異なるようである。また〔五経文字〕等に〔説文〕を引いて、
」の〔注〕に「讀んで鯤(こん)と爲す。鯤は魚子なり」とあって、魚卵のときは音が異なるようである。また〔五経文字〕等に〔説文〕を引いて、 (こう)を卵の古文とするが、
(こう)を卵の古文とするが、 は礦の古文でその象形。声義ともに異なる。卵は卵の相対し、相連なる形である。
は礦の古文でその象形。声義ともに異なる。卵は卵の相対し、相連なる形である。[訓義]
1. たまご。
2. まるいもの、睾丸。
3. 大きい。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕卵 加比古(かひこ)〔名義抄〕卵 カヒコ 〔
 立〕卵 シケシ・カヒコ
立〕卵 シケシ・カヒコ[部首]
〔説文〕に一字、〔玉
 〕に四字を属する。空卵や孚化(ふか)に関する字がある。
〕に四字を属する。空卵や孚化(ふか)に関する字がある。[熟語]
卵育▶・卵殻▶・卵危▶・卵硯▶・卵
 ▶・卵息▶・卵胎▶・卵蛋▶・卵塔▶・卵白▶・卵養▶・卵翼▶
▶・卵息▶・卵胎▶・卵蛋▶・卵塔▶・卵白▶・卵養▶・卵翼▶[下接語]
危卵・魚卵・
 卵・蚕卵・産卵・生卵・胎卵・探卵・鳥卵・乳卵・排卵・孵卵・翼卵・累卵
卵・蚕卵・産卵・生卵・胎卵・探卵・鳥卵・乳卵・排卵・孵卵・翼卵・累卵出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「卵」の意味・わかりやすい解説
卵【らん】
→関連項目体外受精|卵|卵割|卵生
卵【たまご】
→関連項目性(生物)
卵【たまご】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「卵」の意味・わかりやすい解説
卵
たまご
ovum; egg
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「卵」の解説
卵
卵
世界大百科事典(旧版)内の卵の言及
【配偶子】より
…紅藻と他の藻類の一部および多くの菌類の配偶子は雌雄とも鞭毛を欠くので,不動配偶子aplanogameteと呼ばれる。また陸上植物,藻類の一部および動物では,大型の雌性配偶子は鞭毛をもたないので卵,小型の雄性配偶子は精子と呼ばれる。19世紀末にそれぞれ平瀬作五郎,池野成一郎によって精子が発見されたイチョウとソテツ類以外の裸子植物および被子植物の雄性配偶子は,鞭毛のない精細胞である。…
【養鶏】より
…鶏卵や鶏肉などニワトリの生産物を利用するためニワトリを飼養することをいう。飼い方により平飼い養鶏,ケージ養鶏,バタリー養鶏あるいは庭先養鶏などと区分することもあるが,生産目的によって分類すれば採卵養鶏とブロイラー養鶏とに大別され,それぞれはさらに種鶏生産と実用鶏飼育に区分される。…
【両性具有】より
… しかし,アンドロギュノスとしての原初的存在は,さらに古く世界各民族の宇宙創成神話に痕跡をとどめている。宇宙開闢(かいびやく)時には,世界は性的に未分化の〈卵〉であり,その潜勢的な産出力により神々と万物が分かれ出た。かくて始原にあるのは両性具有者なのである。…
【育児】より
…
〔育児の医学〕
【ヒトの成長・発達と育児】
人は,受胎後,胎内で約280日を過ごす。この間に,受精卵は細胞分裂を繰り返し,細胞分裂がある程度進むとそれに細胞の機能分化が加わって,身体を構成する諸器官が形成され,出生に備えてその機能も発達を続ける。視・聴・嗅(きゆろ)・味・触・圧覚などの感覚,哺乳,排出の能力は,胎内生活の末期にはほとんどその機能が完成する。…
※「卵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


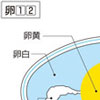
 〈ラン〉たまご。「
〈ラン〉たまご。「 〈たまご〉「
〈たまご〉「