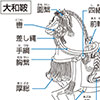関連語
精選版 日本国語大辞典 「取付」の意味・読み・例文・類語
とり‐つけ【取付】
- 〘 名詞 〙
- ① 取りつけること。作りつけること。
- [初出の実例]「列車内取附の洗面所の水タンクは小さいですから」(出典:旅‐昭和五年(1930)八月号・乗心地を聴く〈三輪真吉〉)
- ② 江戸時代、貢租の割付け方法。
- [初出の実例]「取付に少し宛様子替り有。高に幾つと割付ると、反別に取米を割付ると」(出典:県令須知(1752頃か)二)
- ③ 契約・了解などを獲得すること。
- [初出の実例]「各方面との折衝や了解のとりつけなどございますから」(出典:夢の浮橋(1970)〈倉橋由美子〉花野)
- ④ 一定の店を常に利用すること。
- ⑤ 預金者が預金を引き出すこと。特に、金融恐慌などで経済不安が生じたとき、預金者がいっせいに銀行に行き預金の引き出しをすること。
- [初出の実例]「若し甲銀行は乙に金壱万円の取付を要し、乙銀行は甲に金八千円の取付を為すべきに」(出典:銀行小言(1885)〈富田鉄之助〉下)
とっ‐つけ【取付】
とり‐つき【取付】
とっ‐つき【取付】
山川 日本史小辞典 改訂新版 「取付」の解説
取付
とりつけ
信用不安の発生時に預金者が預金引出しのために金融機関に殺到すること。連鎖的に波及し金融恐慌をひきおこす。日本では1927年(昭和2)3~4月のものを最大として頻発したが,銀行法の制定により中小銀行の集中・合併が進みほぼ例を絶った。第2次大戦後は,政策的に業界全体として保護していくとする護送船団方式や預金保険機構などの防止対策が確立した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...