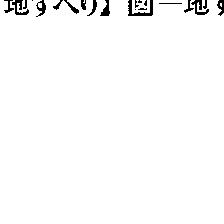地すべり
じすべり
土地の一部が重力の作用によってしだいに高所から低所へずり下がっていく現象。急な斜面が急激に崩れ落ちる現象を山崩れ、崖(がけ)崩れといい、1日に何ミリメートルから何センチメートルというように緩やかに移動するものを地すべりというが、両者を厳密に区別することはむずかしい。地盤の中に、水を含むと粘り気を失って糊(のり)状に変化するような軟弱な層(粘土(ねんど)層)があると、過剰な地下水が供給されたとき、その層に沿う摩擦力の減少と、層より上の土塊が水を吸って重くなることの二つの作用により地すべりがおこりやすい。このため、長雨や豪雨、急激な雪融(ゆきど)けなどのあとに地下水面が上昇すると地すべりがおこりやすい。こうした場所で地山の一部を切り取る工事などをすると均衡が崩れ、地すべりを誘発することもある。
地すべりは特定の地質または地質構造の所に多く発生する。第三紀(新・古)層の酸性白土や黒色頁岩(けつがん)などの分布している山形、新潟、富山、長崎、佐賀などの諸県は地すべりの多い地方である。そのほかに西南日本の中央構造線や中部日本の大地溝帯(フォッサマグナ)などのような地質構造線に沿って、断層などのために地質構造が細切れになっている所では集中的に生じている。徳島県吉野川(よしのがわ)流域、静岡県由比(ゆい)地方の地すべりはこの例である。地すべり地は特徴的な地形をしており、地形図や空中写真あるいは現地踏査で容易に判別できる場合が多い。すなわち、地すべりの頭部に急斜面または断崖(だんがい)があって、その直下に凹地または平坦(へいたん)地があり、それに続いて緩斜面があり、緩斜面の下方にふたたびやや急な斜面が続くという地形である。一度地すべり地形が形成されると、滑動土塊中にも2次、3次の地すべりが生じ、断崖と平坦面の数を増し、ついに階段状の地形となり、この地形を利用して千枚田(せんまいだ)、棚田(たなだ)などがつくられ、「田毎(たごと)の月」のような表現も生まれた。
地すべりが原因となって山崩れや土石流を誘発し、人命や財産に損傷を与えたり、鉄道・道路などの構造物が被害を受けることも少なくなく、その防止対策は社会的に重要な問題である。基本的な対策としては、地表水排除工(排水のために地表面に種々の排水施設を設置する工事・工法)により地すべり地内への雨水の浸透をできるだけ少なくすること、横井戸やボーリング孔などによってすべりに関与する地下水を排除することであり、そのほか、上部の切り取り、下部の押え盛土、杭工(くいこう)などがあるが、いずれも地すべり地の規模、すべり面の位置、地すべりの活動状況などに関して適確な把握が基礎となる。
[芦田和男・水山高久]
『小橋澄治著『地すべり・崩壊・土石流 予測と対策』(1980・鹿島出版会)』▽『山口真一著『地すべり・山崩れ 実態と対策』(1990・大明堂)』▽『藤田崇著『地すべり――山地災害の地質学』(1990・共立出版)』▽『古谷尊彦著『ランドスライド――地すべり災害の諸相』(1996・古今書院)』▽『中村三郎編著『地すべり研究の発展と未来』(1996・大明堂)』▽『申潤植著『地すべり工学――最新のトピックス』新版(2001・山海堂)』▽『藤田崇著『地すべりと地質学』(2002・古今書院)』
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
地すべり (じすべり)
landslide
地表を構成する土石の層が,塊のまま日々の変化を追える程度の速さで斜面下方へすべり動く現象。マス・ムーブメントの一形式であるが,現象が複雑で多様性に富むため,日本でも諸外国でもさまざまに定義されている。最も広い意味では,クリープとソリフラクションおよび凍結融解に関連する表層物質の緩慢な移動,それらを除いた他の様式による地表の物質移動すべてをさす。この場合,地表下および周囲の不動部分との間に生じたすべり面とよぶ明りょうな境界面によって区切られた斜面物質の一部が,ひと塊になって斜面をずり落ちる点でそれらと区別される。日本では,上記の内容からさらに泥流や土石流などのような流動現象と,岩石の落下や斜面の崩落など山崩れと総称される落下・崩落現象とを除いて,滑動現象のみをさすことが多い。地中の粘土が水を吸うと,一種の滑剤となってすべりを助長する。そのため地すべりを特殊な地すべり粘土の存在が原因となって滑動する現象に限定することもあるが,あまり一般的ではない。
典型的な地すべりは,地層中に重力によって生じた凹型のすべり面から上のブロックが,自重で下方へ押し出すようにずれ動き,斜面をすべり下り,緩斜地に達して止まる。地すべりの上部の動きはスランプとよばれる後方への回転をともなう滑動で,上端にはそれによってすべり面の一部が弧状の滑落崖となって現れる。上部では張力による割れ目が生じて,階段状の小ブロックに分かれる。ここまではもとの地表が低下する部分で,その下方ではほぼ一様な厚さを保って斜面に平行に滑動するが,周縁部の動きが中心部よりも遅くなるため,流向に平行な縦方向のしわと,それに斜交する凹凸や割れ目ができる。下端に近づくにつれて速度が衰えるとともに,動きの形成が滑動から流動に変わる。末端は舌状を呈し,背後からの圧力によってそれに平行なしわができる。このように一つの地すべりの中でも,部分ごとに動きの形式や速度が異なる。
地すべりは,巨視的にみた場合,土地の起伏が大きく,固結度の低い泥質の堆積岩類や変成岩類の広く分布する新期造山帯に多い。日本では特定の地質構造のところに集中しており,それにもとづいて,第三紀層地すべり,破砕帯地すべり,温泉地すべりが区別されている。第三紀層地すべりは,おもに第三紀の泥質堆積岩類からなる丘陵地に群発する。新潟,長野両県の信濃川流域の丘陵地帯にはとくに著しい。破砕帯地すべりは,おもに西日本の大きな構造線に沿って帯状に分布する。破砕帯そのものというよりも,それに沿う結晶片岩や蛇紋岩のところに多発している。温泉地すべりは,それらよりもはるかに狭く,温泉作用によって岩石が粘土化した温泉余土の分布地に限られる。いずれも粘土化しやすい岩石の分布地か,粘土ができやすい条件をそなえた場所である。多雨,多雪,地下水など水の供給の多いことも,地すべりの誘因として重要である。
地すべりは豪雨などに誘発されて突然発生することもあるが,上記のような特定の条件をそなえたところに,慢性的ないし長期間継続的に起こることが多い。一般に慢性的な地すべり地では,表土中に粘土分が多く礫が少ないことに加えて,斜面に地すべり地特有のしわや段ができているため,棚田や傾斜畑を作りやすく,山地斜面でありながら古くから農業的土地利用が進んでいる。地表の動きが一様でないため,棚田は不規則な形に小さく区画され,能登の千枚田,長野県姥捨山の田毎の月に代表される特徴的な耕作景観を作り出す。慢性的な地すべりは動きが遅いので,人命に危険が及ぶことはほとんどないが,山林や農地のほか,人家,道路,用水路,電線,電話線などに被害をもたらす。このような災害を防止するため,慢性的な地すべり群発地域は,地すべり等防止法にもとづき,動きを止めるための水ぬきなどの対策工事が施されている。この法の指定をうけているか,その資格をもつ土地は全国で約14万haに達するとみられている。
執筆者:小疇 尚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
じすべり
地すべり
landslide
かつては「地辷り」とも書いた。狭義には,斜面構成物質が地下のすべり面を境界として滑動する現象。広義にはマスムーブメントの運動形態の崩壊・流動・匍行の一部を含め,斜面運動の代名詞として使用される。特定の地質条件の所に集中して発生する傾向が強く,日本海側の新第三系泥岩地帯,四国の結晶片岩・蛇紋岩地帯はその代表である。小出博(1955)は地質条件をもとに日本の地すべりを大きく,第三紀層地すべり・破砕帯地すべり・温泉地すべりに三分したが,実態と合わないこともある。日本列島で現在活動する地すべりの大部分は,有史前に発生した古い大きな地すべりの一部からの再移動である。一般に大規模な地すべり地形の内部には,中・小規模の地すべり地形が多数含まれ,地すべり活動の階層性を示す。地すべり現象は,災害をもたらす破壊作用とともに山地農林業の基盤を形成した歴史をもち,小出博はこの「功罪」を「地すべり現象の両面性」と表現した。割れ目が発達した移動地塊は,山地での地下水貯留体の役割も果たしている。
執筆者:高浜 信行・山崎 孝成
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
Sponserd by 
地すべり
じすべり
landslide
土塊または岩塊が斜面上を下方へ徐々に移動する現象。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)では,土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象またはこれに伴って移動する自然現象と規定される。急激な崩壊をすることもある。地下水を含んだ粘土がある場合にすべり面ができて地すべりを起こしやすく,この粘土を地すべり粘土と呼ぶ。地すべりの原因となる地質的条件により,新第三紀層地すべり,破砕帯地すべり(断層などで岩石の崩れている部分に起こる地すべり。→断層破砕帯),温泉地すべりなどに分類される。地すべりが起こると,斜面上部には凹地,下部には高まりが生じ,断面形は階段状をなし,平面形は馬蹄形を呈する。日本では,新潟県の新第三紀の丘陵地帯や,吉野川,紀ノ川などの破砕帯の地域などに地すべり地形が多い。(→斜面崩壊,土石流)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
地すべり【じすべり】
緩斜面の土地の一部が徐々に下方に移動する現象。風化層の厚い緩斜面では雨水がよく地中に浸透し,未風化の岩盤より上の土層は雨水で飽和される。ここで土層中にすべり面が形成され,すべり面上の土層が徐々に下方へ移動,地すべりとなる。紀伊半島から四国,九州に連なる結晶片岩からなる地域,青森県から石川県に至る日本海側豪雪地帯の新第三紀層からなる地域などに地すべり地が多い。なお,地すべり等による被害を除去・軽減するため,地すべり等防止法(1958年)が定められている。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の地すべりの言及
【山崩れ】より
…山や丘陵などの斜面を構成している基盤岩や,地表を覆う岩屑層の一部が突然断裂して崩れ落ちる現象で,[マス・ムーブメント]の一種。崩れ落ちる部分と,その下の不動部分との境界は明瞭で,山崩れ発生後にその面が新しい地表面となって現れる。発生が突発的で物質の移動速度がきわめて速く,崩れ落ちた部分が原形をとどめないほど崩壊する,などの点で動きの緩慢な[地すべり]と異なる。 一般に山崩れと総称される斜面崩壊現象には,表層の岩屑が斜面をすべり落ちる岩屑すべり,基盤岩から岩盤が剝がれてすべり落ちる岩石すべり,岩盤や岩屑が一挙に崩れて高速で斜面をすべり下る岩屑なだれ,さらには火山活動による火山体の崩壊などを含んでいる。…
【地震災害】より
…(2)隆起・沈降 上下方向に生じる地盤の変位である。(3)地すべり,山崩れ,崖崩れ,山津波 地盤が徐々に崩れる現象が地すべりである。それが,傾斜地などで突然的に生じれば山崩れあるいは崖崩れとなり,さらに,谷間などでそれらが大規模に発生すれば山津波となる。…
【浸食作用】より
…
[その他の浸食作用]
特定の外作用によらないが,斜面上の風化層など未固結物質が重力によって移動されるタイプの浸食がマス・ウェースティングmass wasting([マス・ムーブメント])である。[地すべり],崩壊,岩屑なだれ,[クリープ](土壌匍行),[ソリフラクション]を含み,重力浸食とも呼べる。物質移動として浸食の範疇に考えない立場もあるが,浸食と運搬は結合したもので,河間地域に広く作用し地形に大きく影響するので,浸食営力としても取り扱える。…
【地形】より
…
[土地の性状と地形]
前述したように営力と地形との間には密接な対応関係があり,岩石と地形との間にもある程度まで対応関係がある。[地すべり]や崩壊は,斜面上の土塊や岩石が下方に移動する現象の一つであり,その結果地表に亀裂が生じ,地形は極端に変化させられる。これにより既存の土地利用や工作物が破壊され,土地保全上の由々しい問題をひき起こす。…
【乱堆積】より
…地層の形態研究の重要な課題の一つで,次のようなものが観察されている。(1)地すべりslumping 平行な地層にはさまれたある厚さの地層が,層内褶曲を示したり,層理がちぎれたりして,最終的には原形をとどめないほど混じりあってしまうもの。これは,地層が比較的急速に堆積し,地層の固結がまだ十分進んでいない状態で,堆積した斜面の傾斜が何らかの原因により増加したような場合に,斜面崩壊が原因で水中地すべりが生じたものである。…
※「地すべり」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by