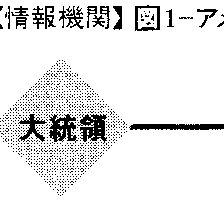精選版 日本国語大辞典 「情報機関」の意味・読み・例文・類語
じょうほう‐きかんジャウホウキクヮン【情報機関】
改訂新版 世界大百科事典 「情報機関」の意味・わかりやすい解説
情報機関 (じょうほうきかん)
intelligence agency
国家の安全保障や外交政策に資するため,(1)主として秘密裡に他国の情報を獲得し(情報活動あるいは諜報活動),(2)他国に自国の秘密がもれるのを防止し(対情報counterintelligence活動),(3)秘密裡の政治工作等により相手国の行動に影響を与える(謀略活動),などの活動に従事する組織をいう。
歴史
情報の重要性については中国最古の兵書《孫子》でも指摘しており,情報活動は古くから行われていた。中世のヨーロッパにおいては組織的な情報活動は行われていなかったが,ルネサンス期のイタリア都市国家は諸外国との通商にその基盤を置いており,情報活動を重視した。特にベネチアは情報入手を主目的として在外公館を設置するなど組織的な情報活動を行った(現在でも各国の在外公館は対外情報活動の拠点であり,各種情報機関員や駐在武官(日本では防衛駐在官)が情報収集に当たっている)。その後しだいに情報活動は活発化していき,19世紀末ころまでには各国の外務省,軍隊等は何らかの情報機関を持つにいたった。こうした情報活動はその後さらに強化され,軍事的にも重要な意味を持つようになる。例えば1941年秋に検挙されたソ連のスパイ,ゾルゲは,在日ドイツ大使館や尾崎秀実を通じ近衛文麿からドイツや日本の政策の最高機密を入手,これをソ連に通報するとともに,尾崎を通じ対ソ戦の回避を働きかけるなど,ソ連の勝利に大きな功績を果たしたとされる。現在では,戦争が総力戦化したこと,国際関係がより緊密になり複雑化したことなどによって,情報活動は一層重要視されている。
情報活動
必要とする情報のかなりの部分は新聞,雑誌,書籍,ラジオ放送,テレビ放送等のいわゆる公開(公刊)情報の分析によって得られる。秘匿されている情報は,航空機や人工衛星による偵察,通信電波やレーダー電波の傍受,およびスパイ等の活動によって得られる。収集される情報は政治,経済,人口,軍事力,科学技術,工業等の基礎的な資料から,首脳の人物,思想,私生活,人間関係等にいたる多方面なものである。近年,国内外の通信やレーダー電波等,電波の傍受が活発化している。これには,地上の傍受施設のほか,電子偵察機,情報収集艦,偵察衛星等が使用されており,コンピューターを使用して大量のデータが処理されている。
対情報活動
情報の収集をさまたげる活動で,(1)自国の秘密保全--政府機関等内部の不穏分子,あるいは秘密に近づくことのできる者などの監視と,秘密の管理保全のチェック,(2)相手国スパイの監視--外部から上記職員に働きかける者やスパイの可能性の高い者の監視,(3)自国スパイ網の監視,などの活動から構成されている。担当する機関は,任務上から秘密警察としての性格を持ち,司法権によらず被疑者を処断できる権力を持つ場合もある。
謀略活動
対情報活動に分類する場合もある。相手国内の反政府団体への資金援助や政治指導,暗殺や破壊工作等によって相手国の行動に影響を与える活動である。このほか自国の行動の意図をかくすため,偽情報を相手国に流し,相手国を別の解釈に導く欺瞞活動も謀略活動に分類される。
各国の情報機関
各国の情報機関はほとんど例外なく,公然活動のみならず非公然活動によって情報収集を行っていると見てよいであろう。情報機関は国家機構の中で最も秘密度の高い部門であり,失敗した情報活動の結果,亡命あるいは逮捕された情報員を通じてその一面をうかがいうるのみである。そのため第2次大戦における各国の情報活動の実態についても,一部は最近明らかとなっているが,多くの重要な部分は不明のままである。また各国の政府が自ら行う場合のほか,民間に委託して情報活動を行う場合もあり,実態は把握しにくい。
アメリカ
アメリカでの情報活動は1880年から1900年代の初めころまでは陸・海軍の情報部によっていた。その活動が国家の統制下に行われるようになったのは第2次大戦以後のことである。アメリカの情報機構の中心的役割を果たしている中央情報局(CIA)の萌芽は1942年初めに創設された情報統制局(COI)で,その後第2次大戦中に戦略業務部(OSS)と改称された。OSSは45年9月にいったん解散されたが,46年1月中央情報本部(CIG)として復活,47年9月にCIGに代えCIAが発足,ダレスA.Dullesが長官となり,CIAの名が世界中に知られるようになった。
アメリカの情報機構は大統領の下にある国家安全保障会議(NSC)を頂点とする膨大な組織からなっている。NSCはアメリカ国家政策の方針決定の最高機関で,大統領,副大統領,国務長官,国防長官,緊急計画局長,財務長官が常任のメンバーで,これに国家安全保障問題担当大統領特別補佐官と統合参謀本部議長が加わる。中でも特に重要な役割を果たすのが国家安全保障問題担当大統領特別補佐官とされている。対外活動の中枢はCIAで,情報部はおもに新聞雑誌など公刊された資料の分析を,科学技術部は外国の科学技術情報の収集・分析と情報収集技術の開発を,作戦部はスパイの運用,謀略活動などを担当する。軍事情報活動の中枢は国家安全保障局(NSA)で,偵察衛星の運用,無線の傍受と暗号解読などを担当する。また,軍事情報活動部門では,陸・海・空軍がそれぞれの情報部を持って情報の収集・分析に当たっている。陸軍情報部はその中に対情報活動に任ずる特別の部隊として陸軍対情報部隊(CIC)を持っている。対情報機関としては連邦検察局(FBI)や原子力委員会(AEC)が知られている。また,財務省も情報面では麻薬,密輸出入,通貨偽造などに関する経済情報の収集,および政府高官の護衛に当たる。大統領をはじめとする政府高官の護衛に当たる秘密警察部門はシークレット・サービスとして知られている。
ロシア
ロシアの主要な機関は旧ソ連時代の国家保安委員会(KGB(カーゲーベー))の機能を引き継ぐ4局および1機関,すなわち連邦保安局(FSB(エフエスベー)),連邦対外情報局(SVR(エスベーエル)),連邦国境局(FPS(エフペーエス)),連邦警備局(FSO(エフエスオー)),連邦大統領付属政府通信・情報機関(FAPSI(エフアーペーエスイ)),ならびに国防省の参謀本部情報総局(GRU(ゲーエルウー))である。
KGBは,革命直後の1917年12月に作られた反革命・サボタージュ取締り全ロシア非常委員会(チェーカーCheka)を前身とする。Chekaは22年に廃止され,内務人民委員部(NKVD(エヌカーベーデー))に国家保安部(GPU(ゲーペーウー))が設置された。ソビエト連邦の成立に伴いGPUは23年11月に合同国家保安部(OGPU(オーゲーペーウー))に変わるが,OGPUは34年に廃止され,NKVD内に国家保安総局(GUGB(ゲーウーゲーベー))が作られた。さらにNKVDは41年2月に国家保安人民委員部(NKGB(エヌカーゲーベー))とNKVDに分かれ,同年6月にNKVDに統合され,43年にはふたたび分離し,第2次大戦で活動した。46年には国家保安省(MGB(エムゲーベー))になった。KGBはスターリン死後の54年4月に設立されたが,91年のソ連の解体・ロシア連邦の成立に伴い,同年10月に解体された。
連邦保安局は,KGBの主要機能を継承した連邦執行権力機関であり,以下を任務とする。(1)連邦保安局の諸機関の指導。(2)大統領等の安全に対する脅威の通報。(3)安全保障の低下を任務とする外国の特務機関および組織,個人の諜報およびその他の行動の摘発,警告および阻止。(4)権限の範囲内での国家秘密たる情報の防護。(5)管轄する犯罪の摘発,警告,阻止および暴露。(6)テロ行為の摘発,警告,阻止。(7)他の国家機関と連携した組織犯罪,汚職,密輸,武器および麻薬の違法取引などの取締り,など。
参謀本部情報総局は,ロシア連邦軍参謀本部の数多い総局および局のうちの作戦総局等と並ぶ一つの総局である。ロシア連邦軍の行動に必要な戦略情報および戦術情報を収集・分析し,参謀総長に報告することを任務としている。同総局は1918年10月に設置された共和国革命軍事会議野戦参謀部記録部をその前身とする。創立当初からChekaによる粛清,スターリンのGRU弱化の策謀にあいつつも,赤軍時代からソ連軍を経て現在に至るまで,軍内各級部隊の情報組織を統括し,海外の工作員を含めその勢力を強化してきた。
イギリス
イギリスの情報機関の歴史は古く,エリザベス1世の時代(1558-1603)にはすでに近代的な情報機関が創設されている。情報機関の中で最も重視されたのは外務省の情報機関であるが,それはイギリスの植民地政策とそれに伴う紛争とが大きくかかわっているといえよう。イギリス情報機関の秘密性は非常に高く,情報機構,組織については正確にとらえにくいのが実情である。
イギリス情報機構の中心となっているのは秘密情報部(SIS),保安部(SS)の2組織である。SISは旧名MI6(MIはmilitary intelligence(軍事情報)の略)とも呼ばれる情報収集組織であり,SSは旧名MI5とも呼ばれる対情報組織である。イギリス情報機構の中での特色はロンドン警視庁特別局の存在で,保安部とともに対情報活動に当たっている。
ドイツ
1871年ドイツ帝国が生まれたが,その前後には宰相ビスマルクに重用されたシュティーバーW.Stieber(1818-82)の情報機関が活躍した。ドイツの近代的情報機関の原型はこのシュティーバーによって作られたといわれる。ただし,当時のドイツはユンカーを主体とする貴族政治で,情報活動に携わる者は軽視される風潮にあり,その後のドイツの情報活動の発展を阻害したと見られる。第1次大戦中にあってもこの傾向は強く,情報活動は低調であったが,大戦中,E.シュラグミュラーが心理学を応用した情報訓練の基礎を築き,後の情報活動に大きな影響を与えた。第2次大戦中は,党情報機関と国防軍の情報機関との対立,伝統的なユンカー出身将校とナチスとの深刻な対立がわざわいし,情報戦にも敗れた。
冷戦が本格化していく中で,1949年9月に西ドイツ,10月に東ドイツが成立した。西ドイツでは56年4月にゲーレン機関(戦後ゲーレンR.Gehlenが組織し,アメリカの情報活動に協力してきた)が連邦情報局(BND(ベーエヌデー))として初めて国家機関となった。一方,東ドイツでは,1950年ソ連のKGBを手本とする国家保安省(シュタージStasi)が設置された。1990年10月東西ドイツの統一に伴い,東ドイツの国家保安省は解体され,西ドイツの情報機関が統一ドイツの情報機関となった。
フランス
フランスの情報機関は17世紀のルイ13世時代のリシュリュー情報部,ルイ14世時代のパリ警視庁などにその原型が見られる。近代的な情報機関は,普仏戦争に敗れた1872年以降に設置されたといわれる。80年に参謀本部第2局ができており,後に第5局(情報,対情報),海・空軍情報部などが置かれた。しかし,第1次大戦,第2次大戦を通じてフランスの情報機関は十分な活躍を示していない。両大戦とも国土を戦場として損耗が著しかったという事情にもよるが,普仏戦争後の参謀本部第2局以来,軍主体の情報機構であったため,両大戦を通じてフランス軍の士気が必ずしも高くなかったということにも影響されているのであろう。第2次大戦後のインドシナ戦争やスエズ動乱などでも情報活動は十分でなかった。
現在でも主要な情報機関は軍の情報組織が主体になっており,中心組織は外国情報対情報本部(SDECE(エスデーエーセーエー))であり,情報収集,謀略活動,対情報活動を担当する。また国家警察の一機構である国土監視局(DST(デーエステー))は国内の防諜と破壊活動対策を主任務としている。同じ植民地主義国であったイギリスが外務省を中心とする対外情報活動を活発に展開してきたのとは対照的である。
イスラエル
イスラエルは1948年5月の独立戦争後,直ちに情報機関の設立に着手した。国の存立の特異性から,情報機関の必要性を非常に強く感じている。イスラエルの情報機関はモサドMossad(中央情報局),アガフ・モディーン(国防軍情報局。単にモディーンとも呼ぶが,通称はアマンAman),およびシャバクShabak(国家保安局)が中心である。さらに警察省の特別調査局や外務省の迫害国家在住ユダヤ人事務局というイスラエル独特の情報機関をも備えている。それらにとどまらず,準戦時態勢下にあるイスラエルでは各省ともそれぞれの職務分担に基づく情報任務を持っていると見られる。モサド長官を議長(メムネ=責任者)とする中央保安委員会がイスラエルの国家戦略情報の最高機関である。モサドの実態は高度の秘密が保たれていて推測の域を出ないが,本質的にはアメリカのCIAと同様な総合的情報機能を備えているものと見られる。
中国
中国は世界史上最初に体系的な情報理論を持ち,情報機関を持った国といわれている。前500年ころに著されたとされる《孫子》の中に情報が大きく取り扱われていることはそれを示している。中国の裏面史は謀略と情報活動の歴史でいろどられている。前30年代の合従の策,連衡の策,周時代の遠交近攻の策などは現在においても通用する謀略の基本ともいえよう。
中国共産党の創立期から中華人民共和国建国にかけては,情報・謀略活動は党直轄で盛んに行われた。1932年に党幹部,党組織の保全のための保衛総隊,38年には国民党の弾圧に対抗するための政治保衛局という組織が作られた。政治保衛局はその後42年に社会部と改称され,建国の49年に情報総処,56年には調査部となり党中央委員会に直属している。一方,保衛総隊は建国の時に公安部隊となり,国務院の公安部の下での実働部隊となっている。
現在では,中央政治局(党)の調査部,人民解放軍の情報部,国務院の公安部が,中国情報機構の三本柱である。調査部は,対内・対外の情報活動を総合管理し,党,政府,軍の各関係情報機関の行う工作の調整指導を任務とする,党中央委員会政治局直属の最高機関である。公安部の任務は反革命活動や反革命勢力の取締りによって体制を強化することにある。公安部はその性格上,党および政府の二重指導下に置かれるという特色を持っており,全国の各都市,農村にいたるまで治安保衛委員会を設置することを規定している。総参謀部の情報部は軍の唯一の対外情報機関で,外国軍事情報の収集を主任務としている。
日本
日本はCIAやKGBに当たる総合的な情報機関を持っていない。情報・謀略活動に関しては,古くは日露戦争に際しロシア,ポーランドなどの反体制派を支援して活動を行った明石元二郎陸軍大佐(当時。1864-1919)が有名である。その後シベリア出兵に際しシベリアや中国東北地区北部に特務機関の一変形としての情報収集・情報・謀略機関を設置,後に中国各地や東南アジアの占領地にも設けた。特務機関は日中戦争,太平洋戦争を通じさまざまな活動を行った。太平洋戦争開戦期におけるビルマ(現ミャンマー),インドの独立派への支援は著名である。1938年開校した後方勤務要員養成所は39年に陸軍中野学校となり,初期には情報・謀略活動を中心に,大戦末期には遊撃戦を中心にした教育を行い,多くの特務機関員を養成した。また陸軍登戸研究所は情報・謀略用機材の開発を担当した。電波傍受は陸軍参謀本部,海軍軍令部により行われ,連合国側の暗号の一部を解読していた。対情報活動は憲兵隊,特高警察の手によって行われた。
現在,日本の情報機関としては国内外の情報収集を担当する内閣情報調査室があり,防衛庁には1996年まで,調査および情報業務を担当する調査課,三自衛隊の調査部,無線傍受を担当する二部別室,情報関係の教育を行う調査学校があった。1997年1月に防衛庁の情報部門一元化のため,内局と統合幕僚会議,陸・海・空三自衛隊の調査部門を統合して情報本部が設けられた。業務の主体は電波傍受,レーダー監視,商業用衛星の画像分析などである。対情報関係では公安調査庁や警察の公安部などがある。国内の治安情報の能力は各国に比べ優れているが,対外情報を担当する機関は米英ロなどに比ぶべくもなく小規模なものであり,対外情報活動も非常に制限されている。吉田茂内閣当時に国家情報一元化の構想があったが,実現せず今日にいたっている。
→軍事情報
執筆者:寄村 武敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「情報機関」の意味・わかりやすい解説
情報機関
じょうほうきかん
国家の行政組織の一つ。その任務は、政府の意思決定や軍の作戦・戦闘、そのほかの国家組織の政策や運用に寄与するため、国の予算を使って情報を収集し、集めた情報を分析・評価して政府中枢をはじめとする関係機関に提供することである。ここでいう「情報」とは、国家の特定の目的のために収集および分析・評価されるもので、一般的には「インテリジェンス」とよばれる。そのため、情報機関はインテリジェンス機関とも呼称される。一般的には国内外での情報収集を専門とする組織や軍事情報収集を専門とする組織が複数存在しており、個々の組織を情報機関、情報機関の集合体をインテリジェンス・コミュニティーとよぶ場合もある。
各国の対外情報機関としては、アメリカの中央情報局(CIA)、イギリスの秘密情報部(SIS。MI6ともいう)、イスラエルのモサド、ロシアの対外情報庁(SVR)、中国の国家安全部、韓国の国家情報院などが存在する。日本には諸外国の対外情報機関に相当するような組織は存在しないが、外務省国際情報統括官組織(IAS)と同省の国際テロ情報収集ユニット(CTU-J)が限定的に海外での情報収集活動を行っている。なお、国内で情報活動や外国のインテリジェンス活動を監視する組織は、防諜(ぼうちょう)組織や保安・公安組織とよばれるのが一般的である。代表的な組織としては、アメリカの連邦捜査局(FBI)、イギリスの保安部(MI5)、イスラエルのシャバク(シンベトともいう)、ロシアの連邦保安庁(FSB)、中国の国家公安部、日本の警察庁警備局、法務省公安調査庁などがあげられる。国内といってもMI5は旧大英帝国諸国、FSBは旧ソ連邦諸国も担当することになっている。さらには、安全保障政策や軍事作戦のための情報を収集する軍事情報部があげられる。それらには、アメリカの国防情報局(DIA)、イギリスの国防情報部(DI)、イスラエルの参謀本部情報局(アマン)、ロシアの参謀本部情報総局(GRU)、中国の連合参謀部情報局、日本の防衛省情報本部(DIH)などがあげられる。多くの国では、軍事情報部が通信傍受情報(シギントSIGINT)を担当しているが、アメリカは国家安全保障局(NSA)、イギリスは政府通信本部(GCHQ)といった通信傍受に特化した組織を有しており、これらの組織はサイバー・セキュリティも担当している。
欧米のインテリジェンス・コミュニティーは、国防予算のおおよそ3~10%で運営されている。たとえば、2025年度のアメリカのインテリジェンス・コミュニティーの予算は約730億ドルで、これは同年度のアメリカ軍の予算8500億ドルのおよそ8.6%になる。同年度のイギリスのインテリジェンス予算は、約46億ポンド(国防情報部であるDIの予算は含まない)で、国防費(600億ポンド)の7.7%程度、ドイツのインテリジェンス予算は17億ユーロ程度と推定されているので、国防費(510億ユーロ)と比べると3.3%程度の規模となる。
[小谷 賢 2025年6月17日]
インテリジェンス・サイクル
情報機関のインテリジェンスは政策や軍事作戦を助けるものであることから、インテリジェンスを利用するまでの運用プロセスが重要となる。このプロセスはいくつかの段階に区分されて理解されているが、それらは、①政策・作戦サイド(情報を利用する側)が自らの利益や目的のための戦略を策定し、そのために必要な情報(インテリジェンス)を要求する(情報要求)、②情報サイド(インテリジェンスを作成する部門)は政策・作戦サイドからの情報要求を受けて情報収集を行う(情報収集)、③情報サイドは集めた情報を分析・評価しインテリジェンスを生産する(分析・評価)、④情報サイドは分析・評価した情報をインテリジェンスとして政策・作戦サイドに提出する(情報配布)、⑤政策・作戦サイドはインテリジェンスが役にたったかどうか情報サイドにフィードバックする、といった一連の流れでとらえられている。
情報要求から情報配布までの過程は、円を描くような一連の流れで説明されることが多く、これは一般に「インテリジェンス・サイクル」とよばれている。基本的にインテリジェンス・サイクルは、政策・作戦サイドと情報サイドの間でのやりとりといえるが、政策・作戦サイド内、情報サイド内でもさまざまなレベルでサイクルが成立していることも見落としてはならない。
どれほど優秀な情報機関が存在し、決定的な情報を入手していても、それをなんらかの目的につなげることができなければ、それは宝の持ち腐れとなる。インテリジェンス・サイクルの概念は、情報を収集、分析・評価、利用していく過程をわかりやすくモデル化したものである。
[小谷 賢 2025年6月17日]
機能と任務
情報機関の活動を機能別に分類すれば、①情報収集活動、②防諜活動(カウンターインテリジェンス、後述。敵の情報活動および破壊工作に対する防御や無害化)、③秘密工作活動(後述)などに大別される。
もっとも重要な任務は①で、公開あるいは非公開の情報を収集し、政府などが所要の決定をやりやすくし、かつ有効ならしめるために、その情報に専門的な知識、背景情報、あるいは科学的分析を加えることである。情報収集と諜報活動で集められた「生の情報」は情報資料(インフォーメーション)とよばれ、「生の情報」を情報源の信頼性、情報資料の正確度に基づいて分析した「分析・評価された情報」はインテリジェンスとよばれる。「分析・評価された情報」は外交・安全保障政策に活用されるほか、国内外の世論の形成、外国政府の政策決定に影響を与えるために、公式資料としてマスコミ、その他にタイミングよく配布、活用される場合もある。
非公開の情報収集活動によって得られた情報は、人的情報(ヒューミントHUMINT。「スパイ」の項目を参照)、技術情報(テキントTECHINT)に分類され、テキントはさらに通信傍受情報(シギントSIGINT)、地理空間情報(ジオイントGEOINT)などに分類される。なお、ヒューミントやシギントなどは、それぞれスパイ活動や通信傍受活動をさす場合もある。シギントは無線やサイバー空間での交信記録を傍受し、必要があれば暗号解読を行い、相手方の意図を察知するものである。有名な事例は、1942年(昭和17)6月のミッドウェー海戦の直前、アメリカ海軍の通信傍受班が日本海軍の通信を傍受したものである。アメリカ海軍は傍受した通信の暗号を解読し、日本海軍の攻撃目標がミッドウェー島にあることをつきとめ、日本海軍機動部隊を迎撃した。2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻においても、米英はロシア軍の無線を傍受し、ウクライナ軍に情報を提供しているものと考えられる。ウクライナ侵攻では、米英はウクライナ軍にジオイントも提供しているとされる。ジオイントは、かつては画像情報(イミントIMINT)ともよばれていた、写真や動画による情報である。現在では偵察衛星やドローンによって必要な地域の撮影を行い、その画像を分析している。最近の偵察衛星であれば、衛星軌道上から地上の数十センチメートルの物体を判別できるとされており、人間の数や車の種類を見極めることもできる。また、衛星リモート・センシングによって、夜間や雲の下の撮影も可能であり、さらに地上の物体が何から構成されているのかの判別もできる。
テレビや新聞、サイバー空間で得られる公開情報はオシントOSINTとよばれる。情報機関においても大部分の情報はオシントによって得られているが、その分析によっては情報の価値を高めることができる。近年ではネット上に拡散された画像や動画の真偽を判定し、正しい画像や動画から有益な情報を得ることもできる。このような活動は報道機関や非政府組織(NGO)といった民間組織にも可能であるが、これらの組織は国家の意思決定に寄与することはできないため、同じ公開情報を使用して情報収集活動などを行っていても、インテリジェンスとみなされないこともある。
国内では外国のスパイが国益に損害を与えないように監視し、必要があれば法執行機関によって拘束することもできる。そのような活動を防諜活動とよぶが、英語圏ではカウンターインテリジェンス(CI)とよばれる。CIは法執行機関自らが実施する場合もあれば、専門の調査組織が実施することもある。CIを担当する情報機関は、外交官の肩書をもつ者、もしくは民間人として赴任している外国の情報機関員を監視し、自国の秘密が漏洩(ろうえい)しないように対策を行う。スパイの外国での活動について規定する国際法等はないため、外国スパイへの対処はスパイ防止法といった国内法に準拠し、法律違反が認められれば法執行機関が逮捕することもできる。ただし日本はそのような法体系を整備していないため、基本的には監視に留まっている。
[小谷 賢 2025年6月17日]
秘密工作
情報機関は秘密工作活動Covert Operationも行う。これは外国に対するプロパガンダ活動から、破壊工作や暗殺工作まで含まれる。1970年代後半に東京で活動していたソ連の国家保安委員会(KGB)のスタニスラフ・レフチェンコStanislav Levchenko(1941― )は、情報収集に加え、日本国内でのプロパガンダ活動をも担っていた。その目的は日本の政財界、マスコミに働きかけ、日米関係を悪化させると同時に、日ソ関係を好転させることであった。そのための手段としては、マスコミの操作や支配、文書もしくは口頭による真実と逆の情報の流布などがあり、当時、日本のほとんどの新聞社内に協力者を抱えていたという。
暗殺工作については、ロシアやイスラエルの情報機関が行うことが多い。イスラエルのジャーナリストであり、インテリジェンス分野の研究者でもあるロネン・バーグマンRonen Bergman(1972― )によると、とくにイスラエルは暗殺工作の行政的手続が定められており、情報機関長官と首相の裁可によって暗殺が実行される。さらにイスラエルはモサドだけでなく、アマンやシャバクも暗殺を行うことができるため、これまで数千人規模の暗殺が行われてきたという。しかしイスラエルの情報機関も完璧(かんぺき)を期することはできないため、ときに暗殺に失敗したり、暗殺の証拠を残したりすることで、国際的なスキャンダルとなることもある。2010年にドバイでハマスの高官であるマブフーフMahmud al-Mabhuh(1960―2010)が暗殺された際には、ドバイ各地の監視カメラに実行犯とみられるモサドの要員が写っており、ドバイ警察はこれを証拠として取り上げ、当時のモサド長官とイスラエル首相を暗殺の責任者と断定し、指名手配した。現在もイスラエルのモサドは、イランの核開発を阻止するために核物理学者や技術者に対する暗殺や脅迫を繰り返しているといわれる。
[小谷 賢 2025年6月17日]
情報機関の監視
情報機関は大統領や首相に直結している国もあれば、各大臣の統制下にある場合もあるが、基本的には行政機関であるため、政治指導者の指示によって動く。しかしときには秘密工作活動も行うため、その存在は危険視されがちである。1970年代には、対外情報機関であるCIAがアメリカ国内で自国民を監視していたことが明るみに出て問題となった。これは、情報機関は自国内の自国民を監視対象としてはならない、との規則を破っていたことになる。そのため、アメリカでは議会も情報機関を監視すべきであるとの声が高まり、1980年代に与野党の政治家などからなる情報監視委員会が大統領のもとに設置され、議会の上院と下院それぞれに情報特別委員会が設置された。アメリカの情報機関は、情報収集活動や秘密工作活動について委員会に報告すべき義務を課され、これを軽んじた場合、委員会は情報機関が要望する予算や人事について拒否することができる。そのため、アメリカの情報機関は情報監視委員会や両院の情報特別委員会を無視して活動することはむずかしい。この制度は欧米諸国にも広まっており、2014年(平成26)には、日本でも特定秘密の運用を監視するための情報監視審査会が衆参両院に設置されている。
[小谷 賢 2025年6月17日]
『小林良樹著『インテリジェンスの基礎理論』第2版(2014・立花書房)』▽『ロネン・バーグマン著、小谷賢監訳、山田美明他訳『イスラエル諜報機関 暗殺作戦全史』上下(2020・早川書房)』▽『小谷賢著『インテリジェンス――国家・組織は情報をいかに扱うべきか』(ちくま学芸文庫)』▽『Christopher AndrewThe Secret World: A History of Intelligence(2019, Yale University Press, New Haven, U.S.A.)』▽『Mark LowenthalIntelligence: From Secrets to Policy, 9th Edition (2022, CQ Press, Washington, U.S.A.)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「情報機関」の意味・わかりやすい解説
情報機関
じょうほうきかん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...