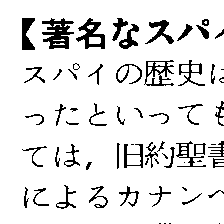翻訳|spy
精選版 日本国語大辞典 「スパイ」の意味・読み・例文・類語
スパイ
- 〘 名詞 〙 ( [英語] spy ) 敵国、敵軍や、競争相手などの機密の情報をひそかに調べ、探り出すこと。特に国家間での軍事的、政治的な意図を持って行なわれるものをさすことが多い。諜報活動。また、それをする人。間諜(かんちょう)。密偵(みってい)。
- [初出の実例]「同人はキリストを神が人間界へ送ったスパイだといふ」(出典:欧米印象記(1910)〈中村春雨〉大西洋航海日誌)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「スパイ」の意味・わかりやすい解説
スパイ
すぱい
spy
国家やその他の団体が秘密にしている情報を、ひそかにあるいは買収など不当な方法で探知、収集し、対立関係にあるほかの国家または団体の利用に供する者。スパイは国家間だけではなく、企業間でも産業スパイといった形で活動している。
スパイの語源は、13世紀の古フランス語の「espie」(監視)とされており、その後の中期英語で「espy」という形になった。古代中国ではスパイを「間(かん)」とよんでいたが、これはスパイが二つ折りにされた封書をのぞく行為に由来しており、日本でも「間諜(かんちょう)」ということばが定着することになった。現代ではスパイ活動によって得られた情報を、人的情報(ヒューミントHUMINT。Human Intelligenceの合成語)という。なおヒューミントは、スパイによる情報収集活動をさす場合もある。
[小谷 賢 2025年6月17日]
歴史上のスパイ
スパイの最古の記録については、古代エジプトやメソポタミアのものが残っており、旧約聖書でもモーセがカナーンの地に12人のスパイを派遣して調査を行ったという逸話が残っている。ただし古代社会においては、スパイの情報よりも神託や占いの結果を重視することもあった。時代が下るとスパイの有効性は認められ、外交や戦争の裏にはスパイの暗躍があった。16世紀にイギリスのエリザベス1世を支えた宰相フランシス・ウォルシンガムFrancis Walsingham(1532ころ―1590)や、独立戦争を率いたアメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンらは優れたスパイ・マスター(スパイ活動の統括者)でもあった。この時代のスパイの任務は、おもに相手の軍勢や侵攻ルートなど、戦場で軍事情報を収集し、それを軍事指導者に対して報告することであった。日本陸軍も日露戦争時には情報活動に力を入れ、明石元二郎(あかしもとじろう)や石光真清(いしみつまきよ)(1868―1942)のような今日でもその名が知られる諜報員が活躍し、日本海海戦の直前には、ロシアのバルチック艦隊が対馬(つしま)海峡を通るという貴重な情報が、上海(シャンハイ)でのスパイ活動によって得られた。
[小谷 賢 2025年6月17日]
スパイの手法
第二次世界大戦後には、アメリカの中央情報局(CIA)やイギリスの秘密情報部(SIS。MI6ともいう)、ドイツの連邦情報庁(BND)、ソ連の国家保安委員会(KGB)、イスラエルのモサドといった対外情報機関が設置され、冷戦は東西スパイ合戦の様相を呈した。すでに第二次世界大戦中から、アメリカはソ連側のスパイの浸透を許しており、これらスパイの活動によって、アメリカの最高機密である原子爆弾の製造方法がソ連側に漏れることになる。これに対してアメリカの情報機関は、ソ連の通信を傍受・解読するべノナ計画によって、アメリカ国内に浸透した100名以上のスパイを特定した。その一部が原子爆弾製造計画(マンハッタン計画)の秘密を盗み出した容疑で告発されたジュリアス・ローゼンバーグJulius Rosemberg(1918―1953)とその妻エセルEthel Rosemberg(1915―1953)であり、二人は司法取引に応じず死刑に処されている。その後もCIAやMI6はソ連のスパイの浸透に悩まされ続けた。ソ連は亡命ロシア人を使い、10年以上かけてアメリカの情報機関に潜り込ませるスパイ(「モグラ」とよばれる)と、金銭やイデオロギーで米英のスパイを寝返らせることによって(寝返ったスパイは「二重スパイ」とよばれる)、西側の情報機関内にスパイ網を張り巡らせた。相手側のスパイを寝返らせたり、協力者を募ったりする方法は「MICE(ネズミ)」とよばれており、これは「金銭Money」「思想信条Ideology」「妥協Compromiseと強要Coercion」「エゴEgo」といった人が組織を裏切る動機の頭文字をとった総称である。金銭と思想はイメージしやすいが、妥協は相手の弱みを握って協力を強要し、相手を屈服させることである。そのためには金銭を受け取らせたり、ハニートラップ(色仕掛け)を使用したりすることもある。
ハニートラップというと女性スパイが男性を誘惑するケースが想起されるが、逆のケースも存在する。とくに旧東ドイツの情報機関シュタージは、西ドイツの政治家の女性秘書や官庁の女性幹部をターゲットにした「ロミオ作戦」を実施し、成果をあげた。特異なケースとしては、1964年から20年近くスパイ活動が続けられた「時佩璞(じはいはく)事件」である。京劇の男性役者であった時佩璞(1938―2009)は中国の情報機関のため、女性に扮(ふん)してフランス人外交官、ベルナール・ブルシコBernard Boursicot(1944― )にハニートラップを仕掛ける。ブルシコは時佩璞が男性とは気づかないまま関係を続け、フランスの外交機密を提供し続けたのである。その後、1983年にパリで両者はフランス当局に逮捕され、ともにスパイ罪で禁錮6年の有罪判決を受けている。その裁判の過程で、ブルシコは初めて自分のパートナーが男性であったことに気づき、衝撃を受けたという。
エゴは秘密をもつ者の、抑圧された心理を利用するものである。戦前、日本で活動していたソ連軍参謀本部情報総局(GRU)のスパイ、リヒャルト・ゾルゲは、ドイツの新聞記者として日本の政治家や軍人に接触していたが、インタビューの最後にかならず「そんなことも知らないのですか」といったという。そういわれると多くの日本人は「そんなことはない」といって、秘密を話してくれたという。
スパイに求められる技法は、今も昔も外国語とコミュニケーションの能力である。秘密裏に外国に潜入して破壊工作を行うのは、映画やフィクションの世界の話である。現実のスパイのほとんどは、身分を偽装し、パーティーや国際会議の場で外国の要人や政府関係者から断片的な情報を得ている。情報を得るためにはできるだけ長く話す必要があるので、外国語によるコミュニケーション能力は必須(ひっす)であり、ジャーナリストのように相手の話をメモすることはできないので、記憶力も必要となる。
スパイ活動については国際法等で明確な取り決めはなく、グレーゾーンの領域とされている。したがって各国は国内法としてスパイ防止法を制定し、スパイを取り締まる。たとえば1917年に制定されたアメリカの防諜法では、国防や情報活動、暗号に関する情報を意図的に入手したり、外国政府への便宜を図った政府職員はスパイとみなし、10年以下の禁錮刑に処す、と規定されている。アメリカには量刑加重制度があるので、スパイ行為1件につき10年の禁錮刑ならば、5件で50年ということもありうる。冷戦期、ソ連に情報を売っていたCIAのオルドリッチ・エイムズAldrich Ames(1941― )や連邦捜査局(FBI)のロバート・ハンセンRobert Hanssen(1944―2023)らは終身刑に処されており、意図的な情報漏洩(ろうえい)や裏切り行為は、欧米諸国では重罪とみなされる。
[小谷 賢 2025年6月17日]
現代のスパイ
多くのスパイは、外交官の肩書で海外の大使館に勤務し、そこを拠点として情報収集活動を行う。このような身分偽装をオフィシャル・カバー(OC)という。他方、民間企業の従業員やジャーナリストの肩書で活動するスパイもおり、こちらはノン・オフィシャル・カバー(NOC)という。OCは大使館の決まったポストに配置されるため、赴任した国の監視対象になりやすいが、外交官特権があるので逮捕される心配は少ない。NOCは自由に動きやすいが、民間人なので逮捕されやすいというリスクが存在する。2010年6月に「美人過ぎるスパイ」として、アメリカの核弾頭開発計画に関するスパイ容疑で逮捕されたロシア人、アンナ・チャップマンAnna Chapman(1982― )はNOCに該当する。
現在でも必要があれば、暗殺がスパイ活動にまつわる手段として使われる。ロシアの情報機関であるロシア連邦保安庁(FSB)の元スパイ、アレクサンドル・リトビネンコAlexander V. Litvinenko(1962―2006)は、2006年11月にロンドンで放射性物質によって毒殺された。イギリス政府とヨーロッパ人権裁判所は、これをFSBによる犯行とみなしている。また、イスラエルのモサドは、2010年以降にハマスの指導者やイランの核物理学者を次々と暗殺しているとされる。
中国は世界各国の中国人留学生をスパイとして使い、その国の大学や研究機関から、先端技術情報の入手に努めていると指摘されている。2019年10月、オーストラリアに亡命を申請した王立強(おうりつきょう)(1993― )は、もともと、中国安徽(あんき)財経大学で油彩画を専攻する学生であったが、卒業後、中国人民解放軍総参謀部にリクルートされ、おもに香港(ホンコン)でスパイ活動に従事していた。しかし王は、スパイの任務に嫌気がさして亡命したとされる。
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻においては、CIAとMI6が協力してウクライナの情報機関の立て直しを図った。ウクライナ保安庁(SBU)はもともと、ロシア連邦保安庁(FSB)の下部組織だったこともあり、組織内には多くのロシア内通者が存在していたため、それらの排除が実施されたのである。ロシア側は侵攻と同時にSBU内の親ロシア派を動かす計画であったが、結果としてこれは未然に防がれ、ウクライナ大統領ゼレンスキーVolodymyr Zelensky(1978― )の暗殺計画もCIAからの情報提供を基にSBUが防いでいる。
2010年以降になると、スパイ活動のヒューミントと通信傍受活動であるシギントSIGINT(Signals Intelligenceの合成語)をあわせた「ヒュギントHUGINT」とよばれる活動も行われるようになった。これは情報収集の対象者がもつスマートフォンやパソコンにアクセスし、対象者のアクセスや検索履歴から、関心事や趣味、毎日の生活パターンを調べあげてから、スパイが接触するというものである。こうすることで話を合わせやすく、相手との関係構築がスムーズに進む。このように現代も日本を含む各国で、スパイが暗躍しているものとみられる。
[小谷 賢 2025年6月17日]
『小林良樹著『インテリジェンスの基礎理論』第2版(2014・立花書房)』▽『黒井文太郎著『工作・謀略の国際政治――世界の情報機関とインテリジェンス戦』(2024・ワニブックス)』▽『小谷賢著『インテリジェンス――国家・組織は情報をいかに扱うべきか』(ちくま学芸文庫)』▽『海野弘著『スパイの世界史』(文春文庫)』▽『Christopher AndrewThe Secret World: A History of Intelligence (2019, Yale University Press, New Haven, U.S.A.)』▽『Mark LowenthalIntelligence: From Secrets to Policy, 9th Edition (2022, CQ Press, Washington, U.S.A.)』
改訂新版 世界大百科事典 「スパイ」の意味・わかりやすい解説
スパイ
spy
スパイ(間諜ともいう)とは何かを正確に定義することは難しい。国際的な規定としては,1907年の〈陸戦の法規慣例に関する条約〉(ハーグ条約)の条約付属書,1948年の〈ジュネーブ条約並びに国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書〉がある。たとえば前者ではスパイを,作戦地帯内において相手交戦者に通報する意志をもって隠密または虚偽の口実のもとに情報を収集し,あるいは,しようとする者に限定している(同書29条)。これは制服を着用した軍人の情報収集活動を,各国で制定されたスパイ活動に関する処罰規定から除外するねらいをもったもので,各国間における最低限の合意事項にすぎない。
古典的な概念によれば,〈スパイとは軍事や政治に直接役立つ秘密情報を,秘密の手段で入手せんとする者〉という程度の,大まかな定義で十分であった。だが,近代,特に20世紀に入り,その内容は大きく変化せざるをえなくなっている。第1に,スパイ行為の目標が政治的・軍事的な情報のみならず,経済的・思想的・社会的あるいは科学技術的な情報にまで広がったこと,第2に,スパイの任務に単に情報の収集という知的で間接的に役立つものの入手に加えて,破壊,攪乱,宣伝などの,いわゆる〈謀略〉という直接的な攻撃が加わったこと,第3に,スパイ工作の主体が,通常〈国家〉または〈国家に準ずる組織〉であったものから,団体や企業,その他の結社など,より低次小規模の組織へと拡大されたことである。だが,そうした変化にもかかわらず,スパイの〈秘密性〉と〈非合法性〉は変化していない。〈秘密性〉は三つのカテゴリー,すなわち〈企図〉〈手段〉〈成果〉に分けて考えることができる。スパイは最小限その一つを,できればその全部を秘匿しなければならない。〈非合法〉はスパイにおける選択肢の一つであり,合法・非合法にこだわらず,〈目的と状況に最も適切な手段を選ぶ〉のが原則である。通念としてスパイに〈悪〉の印象が付きまとう主たる理由は,この〈容赦なき非合法性〉と〈秘密性〉の相乗効果によるといってよい。
以上をふまえてあえて一言で定義すれば,〈対立・敵対状況において,秘密裡に,ときに非合法手段によって,相手にマイナス,味方にプラスをもたらそうとする行為をスパイ行為といい,それに従事する者をスパイと称する〉となろう。
スパイ戦
現代のスパイ戦は以下の3部門に大別して考えることができる。(1)諜報工作 広い意味での情報活動の一部を形成するものであり,公然・合法の手段による情報活動を補完するための,秘密・非合法手段による情報活動。(2)謀略工作 秘密あるいは非合法の手段をもって破壊,暗殺,攪乱,偽計宣伝等々を実行し,相手に直接的な打撃を与えようとする活動。〈諜報〉が判断や決心の知的資料として味方の行動にいわば間接的に貢献するのに対して,その直接性はきわだって異質である。だが秘密と非合法の手段および組織によって遂行されるという一点において共通性をもつ部門である。(3)防諜 最近は対諜報活動ともいわれる。諜報,謀略がともに攻撃的な意味をもつのに対し,これを防衛する活動をいう。原則として,消極防諜と積極防諜とに分けられる。前者は市民が,それぞれの立場でスパイの企図に乗ぜられないように警戒の処置をとることであり,後者はスパイ組織または行為を積極的・直接的に防止し,力をもってその活動を封殺し,組織の壊滅を図ることである。通常,後者は官憲の任務に属し,そのためには非合法秘密活動を認めている国家も多い。以上の諜報,謀略,防諜を総括して〈秘密戦〉と呼ぶことがある。
近年,必要な情報のほとんど全部は,刊行物などの公開情報と偵察衛星や相手国の電波傍受などの科学技術を駆使することによって間にあうとし,スパイは不要であるとの議論が台頭しているが,スパイの機能は単に情報だけに限定されないし,往々にして〈公開情報の分析〉の欠落部分を埋める〈プラス・アルファ〉が決定的な意味をもつことがあるので,この論はスパイ工作の機能・効果を過小評価しているといえよう。
→企業秘密 →軍事秘密 →情報機関
執筆者:原田 統吉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スパイ」の意味・わかりやすい解説
スパイ
spy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「スパイ」の意味・わかりやすい解説
スパイ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル大辞泉プラス 「スパイ」の解説
スパイ
世界大百科事典(旧版)内のスパイの言及
【クーパー】より
…処女作《用心が肝要》(1820)から《現代の世相》(1850)に終わる30年の作家活動を通じて50にのぼる小説,評論,歴史,時評などを書いた。作家として有名となったのは第2作の《スパイ》(1821)によってで,独立後まのないアメリカの作家たちの関心事であり,かつ課題であった〈芸術の素材〉を,独立革命時のワシントン将軍とそのスパイに見いだした。その後同様の素材および17世紀の植民者とインディアンというアメリカの〈歴史〉を扱った《ライオネル・リンカン》(1825),《ウィッシュ・トン・ウィッシュの悲話》(1829),《ウィアンドテ》(1843)などを書いて新しい国の文学への道を開いた。…
【軍事情報】より
…たとえば電波の発信地,通信量などの分析により相手部隊の配置等が推定でき,暗号が解読できれば非常に確度の高い重要な情報を知ることができる。(7)スパイ。諜報(ちようほう)活動はきわめて古い歴史をもつ。…
※「スパイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...