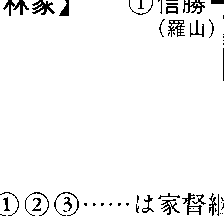精選版 日本国語大辞典 「林家」の意味・読み・例文・類語
りん‐け【林家】
りん‐か【林家】
- 〘 名詞 〙 林業を営む世帯。
改訂新版 世界大百科事典 「林家」の意味・わかりやすい解説
林家 (りんけ)
〈はやしけ〉の音読による呼称で,江戸時代,林羅山を初代として幕府の教学に関与すること12代に及んだ家。1607年(慶長12)羅山が徳川家康に登用され,諸法度の起草,外交文書の起案など枢機に参与し,側近者的役割を果たし,秀忠,家光にも出仕し,その忍岡(しのぶがおか)の家塾は幕府の学問所的役割を担い,江戸の漢学興隆の基を開いた。次の鵞峯(がほう)も治部卿法印,弘文院学士としてその役割を継承し,3代の鳳岡(ほうこう)は蓄髪して大学頭に任ぜられ,将軍綱吉の学問振興策に際会し教学の中心となった。正徳期(1711-16)には新井白石に押されたが,吉宗の享保期(1716-36)には回復し,多くの門人を諸藩に送り込んだ。家禄も1500石(述斎のときは3500石に増)に至り,儒官としては抜群の家格で,幕府崩壊まで続いた。また89年(元禄2)の湯島聖堂改築より祭酒,聖堂預りとなり,教育は八代洲河岸(やよすがし)と湯島で行われ,寛政年間(1789-1801)の学制改革で昌平坂学問所として幕府の学校整備が行われた後も一貫してその任に当たり,儒学界に占めた地位は大きかった。その間,歴代当主に学力の差,早世,時勢の変化があって盛衰があり,他学派の隆盛に押されることもあって,幕政参与は鵞峯以後漸次僅少となり,鳳岡,述斎を除いてはほとんど無力であった。林述斎は美濃岩村藩主の家から入って継承したが,老中松平定信ら幕閣に提言して,学校制度のみでなく編纂事業をも遂行した。林家は改元,法制,朝鮮通信使の応接,外交文書の起草,幕臣の教育などを初代から任務として当たり,幕府の諸事諮問を受ける家であるので,儒学界では終始重んぜられた。
執筆者:山本 武夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「林家」の意味・わかりやすい解説
林家
りんけ
「はやしけ」ともいう。林羅山(はやしらざん)を祖とする儒者の家系。代々江戸幕府の儒官として朱子(しゅし)学を奉じ、文教に携った。羅山は徳川家康以降4代の将軍に仕えて、和漢の古典の解読、故事の調査、歴史の編纂(へんさん)などに携り、上野忍ヶ岡(しのぶがおか)に学問所を建立して朱子学を講じ、幕政にも関与した。2代鵞峰(がほう)は経学・史学をよくして羅山の業を継承・発展させた。3代鳳岡(ほうこう)のとき、家塾は湯島へ移されて昌平坂(しょうへいざか)学問所となり、鳳岡は大学頭(だいがくのかみ)に任ぜられ、以後林家の当主が大学頭を継いだ。学問的には、鳳岡以後は徂徠(そらい)学ほかに押されぎみであった。18世紀末錦峰(きんぽう)のとき、幕府は朱子学不振の状況を打破すべく「寛政(かんせい)異学の禁」を令した。羅山の血統は錦峰で絶え、美濃(みの)岩村藩主松平乗蘊(のりもり)の子述斎(じゅっさい)が幕府の計らいで林家を継いだ。述斎のとき、昌平坂学問所は官学となり、朱子学の振興、学制の改革などの面で成果をあげた。その後の各代は、みるべき業績に乏しい。
[玉懸博之]
山川 日本史小辞典 改訂新版 「林家」の解説
林家
りんけ
「はやしけ」とも。江戸幕府の儒官として文書行政や教育をつかさどった家。初代羅山(らざん)は徳川家康以下,秀忠・家光・家綱と4代の将軍に仕えて朱子学を講じ,将軍や幕閣からの諮問に答え,武家諸法度,朝鮮使節への国書起草などを行い,弟永喜とともにその地位を高めた。1630年(寛永7)上野忍岡(しのぶがおか)の地に学寮を建設し,幕府学政への参与の道を開き,学者を養成した。2代鵞峰(がほう)・3代鳳岡(ほうこう)によって幕府内での地位が確立。林家の私塾は寛政期に官学昌平黌(しょうへいこう)へと発展した。鳳岡のときに大学頭の官号を得,儒者の剃髪・僧形も終焉させた。その後,代々の林家当主は幕府の諮問をうけ,幕臣の教育にも参与。また諸種の編纂事業も主導した。門弟を多く輩出したが,学問的な発展はみられない。家禄は徐々に加増され,述斎のとき3000石余を給された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「林家」の意味・わかりやすい解説
林家
りんけ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「林家」の解説
林家
りんけ
「はやしけ」とも読む。家祖の林羅山 (らざん) は徳川家康に登用され,4代将軍家綱の代までの侍講となり朱子学を講じ,江戸忍ケ岡に私塾を建て幕臣に儒学を教えた。5代将軍綱吉のとき,林家の私塾は湯島に移り聖堂に付属した学問所となり,3代鳳岡 (ほうこう) (信篤)は大学頭に任じられた。以後林家は大学頭を世襲し,儒学界の権威とされた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
林業関連用語 「林家」の解説
林家
農林水産関係用語集 「林家」の解説
林家
世界大百科事典(旧版)内の林家の言及
【林家】より
…林述斎は美濃岩村藩主の家から入って継承したが,老中松平定信ら幕閣に提言して,学校制度のみでなく編纂事業をも遂行した。林家は改元,法制,朝鮮通信使の応接,外交文書の起草,幕臣の教育などを初代から任務として当たり,幕府の諸事諮問を受ける家であるので,儒学界では終始重んぜられた。【山本 武夫】。…
【林業経営】より
…入会(いりあい)慣行の沿革を有する場所については,それら縁故者により経営されているものが多い。 私有林の所有者は林家(保有山林0.1ha以上の世帯),社寺,会社などで,林家数は250万(その3分の2は農家林家),林家以外の事業体は90万であるが,林家の9割以上は10ha未満の小規模経営である。農家が経営する小規模な森林は自家労働により植林,保育を行うものが多かったが,最近では自営による営林活動が減少し,森林組合の委託経営にゆだねる者が多くなった。…
【近世社会】より
…臨済宗僧侶としての経歴をもつ以心崇伝や林羅山が幕府に用いられたときは,文章練達の士として諸文書・法度類の起草のために用いられたのであろう。将軍の師として経典を講ずることはあっても,すべてを林家の朱子学の立場のみを強制するものではなかった。しかし林家が代々大学頭の地位にあったことによって,林家朱子学は武士のみならず,町人・百姓の間にも影響を与えた。…
※「林家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...