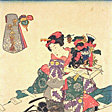精選版 日本国語大辞典 「節供」の意味・読み・例文・類語
せっ‐く【節供・節句】
- 〘 名詞 〙
- ① 人日(じんじつ)(=一月七日)・上巳(じょうし)(=三月三日)・端午(たんご)(=五月五日)・七夕(たなばた)(=七月七日)・重陽(ちょうよう)(=九月九日)などの式日をいう。祝いの行事があり、特別の食物を食べる風習があった。節日(せちにち)。
- [初出の実例]「御せつくいつものことし。ふしみとのも御しこうにて、御ひしひしとまいる」(出典:御湯殿上日記‐文明九年(1477)三月三日)
- ② =せちく(節供)
- [初出の実例]「御せつくはまいらす。御さか月ことさらまいる」(出典:御湯殿上日記‐文明一一年(1479)七月七日)
- ③ ( ①にあたる日は一般に休日としたところから ) 骨休め。楽しみ。
- [初出の実例]「ちる花のひとつひとつに小淋しく 鳩に節供をさする苣畑〈一茶〉」(出典:俳諧・迹祭(1816))
節供の語誌
( 1 )陰陽五行説においては、一・三・五・七・九の奇数を陽とする思想があり、それに基づき、月日共に奇数となる一月一日・三月三日・五月五日・七月七日・九月九日を、それぞれ人日(後に一月七日をさすようになる)・上巳・端午・七夕・重陽と称して、嘉祝の日とする俗信があった。
( 2 )一月一日は安楽の相で宜しく長久を祈り、三月三日は病患を除くことを念じ、五月五日は毒虫・悪鬼の攘却、七月七日は瘧鬼(ぎゃっき)を払い、九月九日は延命長寿を願うもので、それぞれ桃花・菖蒲・麦餠・菊酒などを供す。これらは朝廷において年中行事化されているが、民間においても、季節の変わり目を実感する五節供として、今日に伝わっている。「せっく」は、これら節日に供御を奉るのを例とするところから発した名称と思われる。
せち‐く【節供】
- 〘 名詞 〙 節日(せちにち)に供える供御(くご)。元日の膳、正月一五日(上元)の粥、三月三日(上巳)の草餠、五月五日(端午)の粽(ちまき)、七月七日(七夕)の索餠(さくべい)、十月初めの亥(い)の日の亥の子餠などの類。せく。せっく。おせち。
- [初出の実例]「東には正月の朔比(ついたちのころほひ)にて、梅の花糸
 (おもしろ)く栄(さ)き鶯糸花やかに、世の中に今めかしく、所々に節供参(まゐれ)り」(出典:今昔物語集(1120頃か)一九)
(おもしろ)く栄(さ)き鶯糸花やかに、世の中に今めかしく、所々に節供参(まゐれ)り」(出典:今昔物語集(1120頃か)一九)
- [初出の実例]「東には正月の朔比(ついたちのころほひ)にて、梅の花糸
せ‐く【節供】
- 〘 名詞 〙 ( 「せっく」の促音「っ」の無表記 ) =せちく(節供)
- [初出の実例]「日たくれば、せくまゐりなどすめる。こなたにもさやうになどして、十五日にも、例のごとして」(出典:蜻蛉日記(974頃)上)
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「節供」の意味・わかりやすい解説
節供
せっく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「節供」の意味・わかりやすい解説
節供
せっく
節句とも書く。年間の折り目となる年中行事をいう。古くは節日(せちにち)といった。節(せち)は竹の節(ふし)のように年間のところどころにあって、生活の句読点の役目を果たす。いまも、おせち料理などのことばが残っている。宮廷では節日に行う宴会を節会(せちえ)といい、元日節会(がんにちのせちえ)、白馬(あおうま)節会、踏歌(とうか)節会、端午(たんご)節会、重陽(ちょうよう)節会、豊明(とよのあかり)節会があって群臣が食事を頂いた。節供(せちく)は節日に供える供御(くご)(飲食物の敬語)の意で、節の日には特有の食べ物を伴うところから節日の意味にも使われ、近世の初めごろから節句とも書くようになった。節供は元来、年中行事の折々を示すことばであったから、各地に種々の節供の名称がある。1月7日の花かき節供、1月11日の田植節供・おから節供、1月14日の松立て節供、1月15日の粥(かゆ)節供・柴(しば)立て節供、1月20日の綱打ち節供、3月3日の船玉節供・野辺(のべ)節供・麦ほめ節供、4月8日の飴形(あめがた)節供、5月5日の田ほめ節供、6月1日の焼餅(やきもち)節供、7月27日の萱(かや)節供・酒(さけ)節供、8月1日の馬(うま)節供・姫瓜(ひめうり)の節供、9月9日のおかずら節供、12月1日の川渡り節供など数多くある。江戸幕府は徳川氏の出身地三河の習俗を取り入れて五節供を定めた。正月7日の人日(じんじつ)、3月3日の上巳(じょうし)、5月5日の端午、7月7日の七夕(しちせき)、9月9日の重陽である。これらはいまも七草、桃・菖蒲(しょうぶ)の節供、七夕(たなばた)、菊の節供ともいうが、3月と5月の節供だけを節供とよぶ人も多くなった。
[井之口章次]
改訂新版 世界大百科事典 「節供」の意味・わかりやすい解説
節供(句) (せっく)
年中行事を構成する日。年に何回かある重要な折りめのことで,基本的には神祭をする日である。迎えた神に神饌を供して侍座し,あとで神人共食することによってその霊力を身につけようとするもので,氏神祭や正月,盆も重要な節供といえよう。小豆粥を食べる正月15日を粥節供,稲刈り終了の日を刈上げ節供,年木伐りの日を柴節供などといって祝う地方があるのも,これらの日がハレの日と考えられているからである。正月7日(人日(じんじつ)),3月3日(上巳(じようし)),5月5日(端午(たんご)),7月7日(七夕),9月9日(重陽(ちようよう))の五節供(五節句)は中国から伝えられ,江戸時代に民間に普及したものであるが,現在みるこれらにもなんらかの神祭の意味を認めることができる。なお,節供の語は節の日の供え物がその日を代表するようになったとする考えがあり,おせち(御節)料理は正月に限らず本来は節の日一般の食べ物を指す語だったといわれている。
→雛祭
執筆者:田中 宣一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「節供」の意味・わかりやすい解説
節供【せっく】
→関連項目御節料理|雛祭
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「節供」の解説
節供
せっく
「せちく」とも。節句とも。
1節日などにおける天皇に対する供御(くご)。節会(せちえ)などの公的行事における饗饌(きょうせん)とは別に天皇に献上された食事。民間で行われていたものが宇多天皇の890年(寛平2)宮廷行事として整えられた。正月15日の七種粥(ななくさがゆ),3月3日の桃花餅,5月5日の五色粽(ちまき),7月7日の索麺(そうめん),10月初亥餅など。
2季節ごとの祝いの日。とくに人日(じんじつ)(正月7日)・上巳(じょうし)(3月3日)・端午(たんご)・七夕(たなばた)・重陽(ちょうよう)(9月9日)を五節供と称した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の節供の言及
【郷土玩具】より
…こうした信仰玩具が発達したのは,江戸時代に病苦や天災地変の厄からのがれるため神仏の加護にすがろうとする祈りと,それを目的とする神社詣や寺参りが盛んになり,信心がてらの物見遊山が流行したことが複合された結果でもある。さらに3月,5月の節供祭が盛んになったことや,あるいは土地の祭礼など年中行事にちなんだものが多く生まれ,季節感に富んでいる。ことに節供行事に付随してさまざまな人形類が各地で産出され,郷土玩具の中核ともなっている。…
【初節供】より
…生児がはじめて迎える節供の祝い。〈初子の初節供〉といって初子にかぎり,女児には三月節供,男児には五月節供を祝う風習が全国的にみられる。…
※「節供」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...