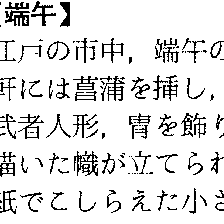精選版 日本国語大辞典 「端午」の意味・読み・例文・類語
たん‐ご【端午・端五】
- 〘 名詞 〙 ( 「端」は初めの意、「午」は「五」と同音 )
- ① 月の上旬の五日の日をいう。〔五雑俎‐天部〕
- ② 五節供の一つ。陰暦五月五日の男子の節供。邪気を払うために菖蒲(しょうぶ)や蓬(よもぎ)を軒にさし、粽(ちまき)・柏餠を食べる。江戸時代以降、男児のある家では鯉のぼりを立て、甲冑(かっちゅう)、刀、武者人形などを飾って将来を祝う。現在は「こどもの日」。端午の節。端午の節供。あやめの節供。重五(ちょうご)。端陽。《 季語・夏 》
 端午②〈大和耕作絵抄〉
端午②〈大和耕作絵抄〉- [初出の実例]「但毎レ臨二端五一、風樹驚レ心、設レ席行レ觴、所レ不レ忍レ為也。自レ今已後、率土公私、一准二重陽一、永停二此節一」(出典:続日本紀‐天平宝字二年(758)三月辛巳)
- 「五月には〈略〉五日は端午(タンゴ)の祭、薬玉の御節供、競馬、日吉の祭」(出典:太平記(14C後)二四)
- [その他の文献]〔資暇録‐中〕
- ③ 香木の名。分類は羅国(らこく)。百二十種名香の一つ。〔名香目録(1601)〕
改訂新版 世界大百科事典 「端午」の意味・わかりやすい解説
端午 (たんご)
中国にはじまり,朝鮮,日本でも行われる旧暦5月5日の節供。
中国
蒲節,端節,浴蘭節などともいう。〈端〉は〈初〉の意味で,元来は月の最初の午の日をいった。十二支の寅を正月とする夏暦では,5月は午の月にあたり,〈午〉が〈五〉に通じることや陽数の重なりを重んじたことなどから,3世紀,魏・晋以後,5月5日をとくに〈重五〉〈重午〉〈端陽〉などと呼び,この日に各種の祭礼を行うようになった。旧暦5月は高温多湿の盛夏であり,伝染病や毒虫の害がはなはだしく,悪月とされた。すでに戦国から漢にかけて,5月5日生れの子が長ずると自害するか,父母を殺すと信じられ,5月5日の誕生を忌む風習があり,唐・宋にまで及んでいるが,《礼記(らいき)》月令篇は〈是(こ)の月や日の長きこと至(きわ)まり,陰陽争い,死生分かる,君子斎戒し,処(お)るときは必ず身を掩(かく)して躁(さわ)ぐことなかれ〉と悪月を説明している。この解釈の当否はともあれ,この日にちなんでさまざまな避邪防病の俗信が生まれた。
この日,薬草を摘み,家の門には艾(よもぎ)で作った人形や虎,あるいは菖蒲(しようぶ)で作った剣をかけ,鍾馗(しようき)の絵や五毒(サソリ,ムカデ,ヤモリ,ガマ,ヘビ)を食っている虎の絵を貼って邪鬼の進入を防いだ。また菖蒲酒や雄黄酒(イオウを混ぜた酒)を飲み,無病息災を祈った。艾,菖蒲,雄黄などは,その香気や薬性によって邪気悪霊を払うことができると信じられたのである。子供たちには艾の葉や黒い桑の実を与えたり,雄黄酒で額に〈王〉の字を書いたり,朱砂を額や腹部に塗って魔除けとした。紅糸や五綵の紐をひじに結びつける長命縷も,元来はこの日の避邪の呪物であった。またこの日,湖南,湖北,江蘇,浙江,福建,広東などの南方の水郷地帯では,竜舟競渡(竜船競渡,ドラゴン・レース)が行われるが,これは,俗説では戦国時代の楚の詩人屈原が国を憂いながら汨羅(べきら)江に投身したのが,5月5日でその屍を救いあげる〈撈屍(ろうし)〉の行為が祭礼化したものとされる。竜舟は,船首に竜の彫刻や飾り物を施した舟で,競漕という娯楽としての要素のほかに,水死者の霊を慰め,同時に蛟竜水獣を鎮めて,水害を防ぎ,雨を乞い,五穀の豊穣を祈ったものである。粽(ちまき)を食べることの由来も屈原伝説に仮託されるが,同じく水神を祭り,豊穣を祈念したものであったと考えられる。
なお端午の起源・由来について明示する文献は,後漢以前にさかのぼるものはなく,古来さまざまな解釈がなされてきた。中国の神話学に独自な見解を示した聞一多は,端午に関する伝説・風俗の記載の多くが,竜舟競渡,粽など竜にかかわることの多いのに注目し,端午節を〈竜の節日〉とする見解を提出している。すなわち,端午ははるか古く竜をトーテム信仰する長江(揚子江)下流域の呉・越族の風俗として始まり,後漢以後,呉・越地域が開発されるにしたがい,中原文化との接触を通して長江上流域や北方の各地に広がっていったという。
執筆者:稲畑 耕一郎
朝鮮
旧暦5月5日は天中節ともいわれ,四大名節の一つである。朝鮮の端午の諸行事は二つのグループに大別できる。一つは中国の端午の行事が宮廷を中心に上層部に受容され,その一部が民衆に伝わったと考えられる辟邪の風俗である。朱書の辟邪文を書いた天中赤符(端午符)を門に貼りつけたり,菖蒲湯で髪を洗い,女子は菖蒲の簪(かんざし)を頭に挿す。艾の葉を混ぜた車輪形の餅を食べたり,艾や盆母草等の薬草を採る。宮廷ではこの日端午扇と災をはらう玉枢丹という薬を臣下に下賜した。一方,古く〈馬韓伝〉の五月下種後の国中祭天の記事が示すように,現在でもこの日には各地で朝鮮固有の部落祭であるソナンダン(城隍堂)祭や石戦(石合戦),相撲,鞦韆(しゆうせん)(ぶらんこ),嫁樹等の祈豊的農耕儀礼が行われている。南朝鮮では旧暦8月15日の中秋節(秋夕)が重要視されるのに対して北朝鮮では端午節が最も重要な名節であり,各地で男子の相撲(シルム)と女子の鞦韆の大会が盛大に行われている。朝鮮では元来この日が北方畑作文化圏の収穫儀礼であったことがわかる。
執筆者:依田 千百子
日本
5月5日の節会を〈端午の節会〉〈五月五日の節供〉という。中国行事の渡来したもの。日本のこの日の行事は邪気をはらう意味があり,薬猟(くすりがり)と称した。薬草を競い狩る風習が,不吉をはらうためのものとして,日本古代から行われており,《日本書紀》推古19年条に初めてみえる。邪気をはらうという意から,菖蒲を軒につるし,家の内にも飾り,菖蒲を飾った菖蒲輿(あやめのこし)などもあり,また,菖蒲縵(かずら)と称し,頭につけ,身につける風習があった。菖蒲はこの日ひろく用いられ,近世には菖蒲酒を飲み,菖蒲湯に浴すということも行われた。また,奇(くす)しく霊なる意味から薬の玉を室内に飾り,身につけ,邪気をはらう意があった薬玉(くすだま)は,寿命を延べることから続命縷(しよくめいる)と称し,五色の糸で作り季節の花を,それにつけて贈答する風もあった。平安時代には,天皇が武徳殿に出席して騎射(うまゆみ)と競馬が5日,6日の2日間にわたって行われ,のち宴が催された。武家時代には,印地打(いんじうち)(印地。石合戦のこと),菖蒲打など勇壮な行事が多く行われた。菖蒲が尚武に通じ,菖蒲縵が変化して,近世の菖蒲冑(かぶと)となった。その冑の前に人形を立て,その人形が武者人形となって,5月5日に飾り,五月人形と称せられるようになった。
執筆者:山中 裕 現行の5月5日の民俗としては,男児の初節供を祝う行事,菖蒲等で邪霊をはらおうとするもの,労働を避けて家に忌みこもろうとするもの,各種の競技等に大別できる。この中には中国に起源をもつものや,武家の時代になって強調された男児中心の行事が少なくないとはいえ,その背後には,本格的な農事(田植)を直後に控え,邪気をはらい慎みの生活を送ろうとする気持のうかがわれるものが多い。また,この日の食品には各地で特色あるものが作られる。
男児の初節供を祝い,前もって母親の実家や親戚から幟(のぼり)や鯉幟,武者人形,冑などを贈り,当日はそれらの人々を招いたりして返礼の行われることは全国的である。幟は両親の家紋がつけられ勇ましい鍾馗像等が描かれたもので,庭先に立てられたが,最近では屋内へ飾るものが多くなった。鯉幟は,吹流しよりも薫風を受けて泳ぐ鯉の姿が男児の好ましい姿を表すものとされ,近年いよいよ盛んに用いられるようになっている。しかしこれら幟類は,元来は忌みこもりしていることの標識か神の依代(よりしろ)に起源をもつものではないかとされている。幟竿の頂に髯籠(ひげこ)をつけたり杉の葉をつけるのはそのなごりであろう。冑は菖蒲縵の変化したものとされ,武者人形とともに武家時代に用いられはじめたという。
菖蒲(しようぶ)や蓬(よもぎ)を束ね,菖蒲屋根を葺(ふ)くといって母屋や倉・納屋などの入口の軒先に挿したり,菖蒲湯に入ったりして,邪魔の侵入を防ぎ身の穢(けが)れを払おうとすることも全国的である。そのためこの日を菖蒲節供という(4日夜にする所では宵節供などという)。薬効を期待して菖蒲酒を飲む風や,帯に通してキュウキュウ音をさせると腹の虫がおさまるとか,頭に巻くと頭痛が治るともいわれている。牛の角にまでつける所がある。菖蒲,蓬を枕や蒲団の下に入れて寝ると,病気にならないとかノミが出ないなどという所もある。新潟県新発田市には,宵節供に男の子が蓬,菖蒲を束ねた棒(これを菖蒲太刀という例がある)を持って各家を回り,〈菖蒲叩(たた)きの鉦(かね)叩き,どっちの音が強いか〉などといって地面を叩いて歩いたあと,川へ納める所がある。このような菖蒲叩きは東日本に多く,ときには子供同士で打ち合うこともあった。西日本にはこれで嫁の尻を叩いて〈大きくなーれ〉などといって回る例が多く,ともに菖蒲や蓬に呪力を認めて行うことであろう。臭気が強く刀剣のように形がするどい菖蒲には,とくに邪気をはらう力があると信じられ,古くからこの日には用いられていた。用いる理由として各地には,昔話の〈食わず女房〉や〈蛇婿(へびむこ)入り〉に類似する話が伝えられている。菖蒲,蓬だけではなく,香煎や粽(ちまき)のゆで汁を家の周囲にまいて蛇やムカデをのけるとしている所も多く,この日が邪霊の訪れる日として用心されていたことがわかる。
ことさら田仕事を忌む伝承も珍しくない。茨城県高萩市の旧高岡村では,節供として当然休むべき5月5日に田に入って働くと,棒足といって足がはれ,棒のように硬直して曲がらないようになるといったり,このときに植えた稲苗は赤くなって収穫不可能になるといって,田に入らないようにしていた。福島県飯坂町茂庭でも,この日田に入ると3里四方が不作になるといい,入った者を象った藁人形を作って皆で呪ったという。類似の伝承は北関東から東北各地にあるが,さらに山口県にも,〈代搔き(しろかき)の牛を出すな〉とか〈土に生金(なまがね)を立てるな〉といって田仕事を休む風がある。かつてこの日が,強い慎みの生活を必要としたことを物語るものであろう。慎みについては,近松門左衛門の《女殺油地獄》に〈五月五日の一夜さを女の家といふぞかし〉とあるので有名な,女の家の伝承がある。愛知県一宮市には,葺き籠りといって菖蒲で屋根を葺いたその夜を〈女の家〉といい,客となって訪れる男にフキやソラマメの五目飯を出してもてなす所があるという。男児の節供のごとくいわれるこの日の夜を,女の天下,女の家,女の夜,女の屋根などといって女性がいばる日とすることが,かつては全国に分布していた。これらの伝承は,後に控えた田植のときに早乙女としての重い役割を担う女性が,特定の家に忌みこもって精進の生活をし,田の神を迎えようとしたなごりではないかとされている。
武家時代の印地打は,近代になっても各地で行われていた。例えば茨城県新治郡出島村(現かすみがうら市,旧霞ヶ浦町)ではイシブシ(石投げ合戦)といい,菱木川をはさんで子供同士が口げんかから石投げとなり,大人や近隣の人々も応援にかけつけるありさまだったというが,石が当たっても菱木川で洗えば傷にならないといった。菖蒲叩きも二手に分かれて争う場合があったが,この日に競馬や綱引きをする所も多かった。鳥取県岩美町田河内では,子供が各家の屋根に挿してある菖蒲を集め,それに藁を加えて菖蒲綱という大綱を作って持ち歩いた後,二手に分かれて綱引きをしたという。また,瀬戸内や九州の沿岸部では競漕(ペーロン)をする所があり,鹿児島県大隅半島には蜘蛛(くも)合戦をする所がある。印地打をはじめ各種の競争は,この日を男児の節供として強く印象づけるものであった。
この日の食物としては,赤飯のほか柏餅や粽を作る所が全国的に多いが,東北地方には,餅や蒸した糯米(もちごめ)を笹の葉で包んだ笹巻餅を作る所が多い。朴の葉に飯を盛ったり餅を包む所もあり,ハレの日の食品を木の葉に入れることは,古い食器の形態を示すものであろうか。また,蓬餅やヤマゴボウの葉を入れた牛蒡(ごぼう)葉餅を作る所が全国に点々とあるし,鹿児島では糯米を竹の皮に包んで木灰(あく)汁で煮たアクマキを作っている。フキやたけのこ,山芋などを食べることにしている所も意外に多く,この日の食品は行事と同様に多様なものがある。
執筆者:田中 宣一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「端午」の読み・字形・画数・意味
【端午】たんご
 楚歳時記〕五
楚歳時記〕五 五日、之れを浴
五日、之れを浴
 と謂ふ。四民竝びに
と謂ふ。四民竝びに 百
百 の戲
の戲 り。
り。 (よもぎ)を
(よもぎ)を りて以て人を爲(つく)り、門
りて以て人を爲(つく)り、門 の上に懸け、以て毒氣を禳(はら)ふ。
の上に懸け、以て毒氣を禳(はら)ふ。
 を以て~酒に泛ぶ。〔杜公瞻注〕今、之れを浴
を以て~酒に泛ぶ。〔杜公瞻注〕今、之れを浴
 と謂ふ。
と謂ふ。 之れを端午と謂ふ。
之れを端午と謂ふ。字通「端」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「端午」の意味・わかりやすい解説
端午【たんご】
→関連項目柏餅|金太郎|屈原|鍾馗|ちまき(粽)|雛祭|武者人形
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「端午」の解説
端午
たんご
本来,月の初めの午(うま)の日または5日の意。漢代以来5月5日をさし,よもぎで作った人形を飾り,菖蒲酒を飲み,薬草を摘むなど邪気を払う行事が行われた。これが日本にも継承され,古くから薬猟(くすりがり)の行事があり,令制でも節日とされた。宮廷ではこの日,天皇に邪気を払う菖蒲が献上され,群臣は菖蒲縵(あやめのかずら)をつけて参上し,宴を張り騎射(うまゆみ)が行われた。江戸時代以降は鯉幟(こいのぼり)や甲冑(かっちゅう)を飾るなど,男児の成長を祈る行事が行われた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「端午」の意味・わかりやすい解説
端午
たんご
世界大百科事典(旧版)内の端午の言及
【薬猟】より
…翌年には羽田(奈良県高市郡高取町羽内(ほうち)付近),668年(天智7)には蒲生野(がもうの)(滋賀県近江八幡市から八日市市にかけての一帯)で薬猟が行われている。中国では《荆楚歳時記》によると,6世紀中葉ころ,揚子江中流域で,5月5日の端午の節句(夏至に近い)に,毒気を避けるため,香りの高いショウブやヨモギ,種々の薬草を摘む習俗があった。日本古代の薬猟は,百済を経由して伝えられたこの古代中国の民間習俗と,高句麗の宮廷で3月3日に行われていた鹿狩りの風習が併せて取り入れられ,推古朝に宮廷行事として成立したらしい。…
【鍾馗】より
…これは〈打夜胡〉〈跳鍾馗〉といい,清代まで残った。清代中ごろから端午にも鍾馗像を掛けるようになり,それが江戸時代の日本の武者人形に取り入れられた。鍾馗を魔除けとあがめる信仰は唐以前より存在し,南北朝時代,後魏の尭暄(ぎようけん)が本名を鍾葵(しようき),字を辟邪(へきじや)といった例や,あやかって鍾葵,鍾馗の名をつけた人物が多いことから,すでに六朝時代に鍾馗と辟邪との関連があったと思われる。…
【ショウブ】より
…昔話の〈食わず女房〉や〈蛇婿入り〉譚(たん)には,五月節供にショウブやヨモギを使う由来譚が伴っている。【飯島 吉晴】 中国では,日本において,その形状と芳香から,主として陰暦5月5日の端午節に邪気を払う呪物(じゆぶつ)とされた。〈水剣草〉の別名もあるように,葉が剣に似ているため,これを門に挿し,またヨモギを鞭(むち)に見立てて,ともに悪鬼を撃つの象とし,〈蒲剣蓬鞭〉と称した。…
※「端午」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...