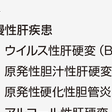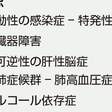関連語
内科学 第10版 「肝移植」の解説
肝移植(肝・胆道の疾患)
a.肝移植の分類
肝移植は進行性かつ不可逆的肝疾患に対する治療方法であり,肝移植以外の治療方法では患者を救命できない種々の肝疾患に適用される. 肝臓を提供するドナーの種類によって分類すれば,脳死者からの肝臓を用いる脳死(死体)肝移植と健常者ドナーの肝臓の一部を用いる生体肝移植に分けられる.また,肝臓のどの部分を使用するかによって分類すれば,肝臓の全部を使用する全肝移植と肝臓の一部を使用する部分肝移植に分類できる.あるいは,肝臓を移植する場所で分類すれば,本来肝臓が存在する場所に移植する(この場合にはレシピエントの病気の肝臓はすべて取り除かれる)同所性肝移植と,本来の場所でない部位に移植する(この場合にはレシピエントの病気の肝臓は全部あるいは一部残される)異所性肝移植に分類できる(図9-1-10).欧米をはじめ世界的に主流なのは脳死肝移植であり,健康なドナーにメスを入れる生体肝移植は脳死肝移植での臓器不足を補う補助的なものと考えるのは普通であるが,脳死肝移植が発達しないわが国ではいまでも生体肝移植が主流である.脳死肝移植では全肝移植が行われることが普通であるが,レシピエントが小児の場合には成人ドナーの部分肝を用いる部分肝が行われることも多い.さらに,臓器不足を補うために1つの脳死ドナーからの肝臓を2人のレシピエントに部分肝移植する分割肝移植も行われる.一方,生体肝移植の場合には部分肝移植しか有り得ない.異所性肝移植は滅多に行われることはなく,ほとんどが同所性肝移植である.
b.肝移植の歴史
はじめての肝移植は脳死肝移植として1963年にアメリカで胆道閉鎖症の小児患者に行われたが術中出血多量で死亡した.はじめての成功例(長期生存)はアメリカで1967年に得られた.しかしながらその後も生存率20%程度の成績であり,一般医療として発展するまでには至らなかったが,1978年に免疫抑制薬のシクロスポリンを使用することで生存率は劇的に改善し,欧米においては1980年代に肝不全患者に対する一般医療としての地位を確保することとなった.
一方,脳死肝移植が行われない1980年代のわが国では,海外に行って肝移植を受ける以外に方法がなかった.1989年に小児患者に対する生体肝移植が始まり,次第に成人患者へも応用されるようになった.一方,長年待ち望まれた脳死肝移植は1997年に脳死臓器移植を可能とする法律が制定されたことで可能となった.しかし,当初の法律では脳死ドナーからの臓器提供は生前に文書で意思表示がなされた脳死者に限定された特殊なものであり,脳死肝移植は年間に10件未満と少ない状況が続いた.2009年にこの臓器移植法が改正され,脳死者の家族の文書による承諾で脳死ドナーからの臓器提供ができるという世界標準の法律になり,脳死肝移植も増加したが,世界的にみると非常に少ない状況に変わりはない.現在は年間に500例前後の生体肝移植と60〜100例の脳死肝移植が行われている.
c.拒絶反応と免疫抑制療法
肝移植における拒絶反応は急性拒絶反応と慢性拒絶反応がある.急性拒絶反応はT細胞を主体とした細胞性免疫によって引き起こされ,門脈と肝静脈の血管内皮細胞,および小葉間胆管上皮が拒絶のターゲットとなる.移植後数日から1カ月以内に起こることから急性拒絶反応と命名されているが,移植後1年以降に起こっても同様のメカニズムによる拒絶反応であれば急性拒絶反応とよばれる.一卵性双児以外では免疫抑制薬を使用しなければ急性拒絶反応は必ず生じるものであるから,これをコントロールするために免疫抑制療法が必要となる.免疫抑制療法のキードラッグはシクロスポリンやタクロリムスなどのカルシニューリン阻害薬であり,T細胞におけるインターロイキン-2やインターフェロン-γの転写を阻害することで免疫抑制作用を発揮する.カルシニューリン阻害薬にステロイド薬,あるいは核酸合成阻害薬であるMMF(ミコフェノール酸モフェチル)を加えた併用療法が一般的に行われる.免疫抑制療法を行っても肝移植症例の30%前後には急性拒絶反応が起こる.急性拒絶反応の治療としてステロイドパルス療法が行われ,多くの症例での治療効果は良好である.
慢性拒絶反応の病態の主体は,腎臓や心臓などのほかの臓器移植と同様に慢性の動脈閉塞にあると考えられている.肝内の小動脈に閉塞が徐々に起こり,動脈血流不全から小葉間胆管の障害が引き起こされ,これらの胆管が消失することから進行性の閉塞性黄疸が出現する.移植後数年を経過してから発症することが多い.治療としては免疫抑制療法の強化を行うが,治療困難なことが多く再移植が必要となる.一方,小葉間胆管の消失を早期に診断し,早期に治療介入を行えば慢性拒絶反応の治療が可能な症例もあることがわかってきた.
血液型不適合間の肝移植は,血液型抗体による液性拒絶反応が生じ,そのコントロールが非常に困難であったので患者生存率が悪かった.近年,悪性リンパ腫などの治療に使用される抗CD20モノクローナル抗体であるリツキシマブを肝移植前に投与して,移植後の数カ月間にわたってB細胞の抗体産生能を低下させる治療方法の導入で成績は飛躍的に向上している.
(2)肝移植の適応
a.適応疾患
肝移植の適応疾患は,慢性肝疾患の末期状態,急性肝不全,腫瘍に大別され,脳死肝移植と生体肝移植で同じである.一方,成人と小児では疾患が異なる(表9-1-4).
成人の慢性肝疾患の多くはC型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスに起因するウイルス性肝硬変である.肝不全症状が進行したChild-Pugh分類(CP分類)におけるCが肝移植適応のタイミングとなる.原発性胆汁性肝硬変と原発性硬化性胆管炎における移植のタイミングもCP分類を参考にするが,原発性胆汁性肝硬変は日本肝移植適応研究会モデルでの死亡確率予測も参考にする.アルコール性肝硬変も肝硬変の適応疾患となるが,移植後のアルコール再飲酒は厳しく防止しなければならず,そのためのリスク評価が重要である.胆石手術など胆道系手術合併症に起因する続発性胆汁性肝硬変も肝移植の適応となる.代謝性肝疾患では,肝不全が進行して薬物療法が期待できないWilson病,意識障害発作を繰り返すシトルリン血症,全身の末梢神経障害が進行した家族性アミロイドポリニューロパチーなどが肝移植の適応となる.Budd-Chiari症候群はまずインターベンション治療を考慮するが,肝硬変に陥っている場合には通常の肝硬変と同様に肝移植適応を考える.先天性肝・胆道疾患としてはCaroli病と多発性囊胞肝がある.
急性肝不全は保存的治療の効果がない場合には肝性脳症が進行して不可逆性になる前に肝移植の適応を考える.特に,成因不明で亜急性型発症の場合には保存的治療での回復は困難であることが多く,肝性脳症が発症した場合には早期に適応を考える.肝移植適応時期の判定は厚生労働省研究班(難治性の肝・胆道疾患に関する研究)が2008年に作成した劇症肝炎の肝移植適応新ガイドラインが参考となる. 成人腫瘍の中で肝移植の適応となるのは肝細胞癌であり,多くはウイルス性肝硬変に合併する.ミラノ基準(腫瘍径5 cm以内で1個,あるいは腫瘍径3 cm以内で3個以内)などの比較的早期の肝細胞癌が適応となる.
小児の適応疾患の大部分は胆道閉鎖症である.
ほとんどの胆道閉鎖症には生後2〜3カ月以内に葛西手術が施行されるが,その後に黄疸が継続,腹水が出現,発育成長が不良な場合など,肝不全症状が出現した場合には肝移植の適応となる.小児の代謝性肝疾患にはWilson病,家族性進行性肝内胆汁うっ滞症,Crigler-Najjar病1型,高チロシン血症1型,糖原病などがある. 急性肝不全の肝移植の適応は成人と同様に考えるが,小児の場合には成人症例と比較して肝性脳症が急速に進行する場合が多いので,肝移植のタイミングを失わないように注意する必要がある. 小児の肝移植適応となる腫瘍性疾患の多くは切除不能の進行した肝芽腫である.肝芽腫治療の基本は肝切除と化学療法を併用した集学的治療である.切除不能の場合にも化学療法を先行させ腫瘍の縮小の後に切除の可能性を再評価し,集学的治療での根治性を追求する.しかし,上記の集学的治療で根治性が期待できない場合,遠隔転移がないことを確認して肝移植を考慮することができる.ほかに肝細胞癌やKasabach-Merritt症候群を伴った巨大血管腫も移植適応となる.
b.適応禁忌(表9-1-5)
肝不全状態が進行すると特発性細菌性腹膜炎や肺炎,さらには血液細菌培養が陽性となる敗血症などの感染症を合併する.これらの感染症が活動性の状態で肝移植を行っても成功率はきわめて低いので,肝移植の禁忌と考える.また,腎機能障害,ARDSによる呼吸障害,心機能低下などの多臓器障害を合併している場合には適応を慎重に判定する.腎機能障害は透析や持続濾過透析で乗り切ることができるが,心肺機能が低下した状態での肝移植実施は困難である.
肝性脳症が進行して不可逆性であると判定されれば肝移植の適応はない.対光反射などの脳幹機能が保たれていることが必要条件であるが,疼痛反応が不明瞭な場合の不可逆性の判定は難しい.単純CTで脳浮腫所見が明瞭であり脳波がフラットの場合には移植の適応はないが,そこまでは進行していない個々の症例での評価は難しい.
慢性肝疾患が進行すると肺高血圧症,あるいは低酸素血症という病態が徐々に進行することがあるので注意を要する.いわゆる肝肺症候群とよばれているものであるが,門脈圧亢進症が著明な症例に多い.肺高血圧症,低酸素血症ともにあるレベル以上に進行すると肝移植の適応はなくなる.
アルコール依存症は肝移植の適応禁忌である.6カ月以上の断酒を守れることが最低限の適応基準であるが,さらに患者の理解度,薬物療法のコンプライアンス状況やおかれた社会的環境の評価など,総合的な判断が必要とされる. 腫瘍性疾患のうち,肝細胞癌においては腫瘍の腹腔内破裂の既往,あるいは遠隔転移や血管浸潤(肝静脈や門脈)が画像上明らかな症例は肝移植の適応はない.一方,肝芽腫においては血管浸潤のある症例の移植適応は議論の分かれるところである.また,肝芽腫で肺転移のある症例においても化学療法で消失すれば移植の適応とする意見もあり,今後のエビデンスの蓄積による評価が待たれている.[上本伸二]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
家庭医学館 「肝移植」の解説
かんいしょく【肝移植】
肝移植とは、患者さんの肝臓が十分にはたらかなくなり、機能不全状態となって余命がほとんど期待できなくなったときに、他人の肝臓を生着(せいちゃく)させるために行なう手術です。
欧米では、脳死(のうし)状態の患者さんから臓器提供が行なわれるようになり、1980年代より急速に進歩し普及してきた技術です。
日本でも1997年、法律により脳死が死とされるようになりました。死の考え方に西欧社会とは文化的な相違もあり、脳死での移植は行なわれませんでしたが、1999年に初めて、脳死肝移植が実施されました。
この手術では、他者からの臓器を移植するため、移植後の臓器に対する免疫反応(めんえきはんのう)による拒絶反応が問題となります。そのために免疫抑制薬が使われますが、肝臓は比較的拒絶反応のおこりにくい臓器であり、ABOの血液型が一致していなくても移植が行なわれることもあります。日本で開発された新しい免疫抑制薬の臨床応用とともに、移植の成績が急速に改善してきました。
欧米での肝移植後の成績は、原因疾患にもよりますが、全体的には5年生存率が約75%です。1年生存さえむずかしいと予測される症例を対象にしていることを考えると、きわめてよい成績といえます。さらに、移植は肝硬変(かんこうへん)の進んだ高危険群となってから行なうよりも、比較的軽症の低危険群で行なったほうが成績がよく、たとえば原発性胆汁性肝硬変(げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん)の患者さんで、高危険群では1年生存率が60%であり、軽症の低危険群の80%に比べてかなり低いため、移植の適応も徐々に軽症の肝硬変へと広がってきています。
◎生体肝移植(せいたいかんいしょく)が中心
日本における肝移植は、脳死を死と認めるか否かの問題が解決しなかったために、欧米に比べて普及が遅れていました。
生体肝移植とは、他人の肝臓の一部を生きたままとり、患者さんに移植するものですが、他人の死を前提とはしていません。脳死肝移植が不可能だった日本で普及しはじめ、脳死肝移植と同等、もしくはそれ以上の治療成績をあげています。提供できる臓器が一部であるため、その大きさに限界があり、子どもを対象に、母親などから臓器の提供が主として行なわれてきています。提供者の生命の危険がまったくないわけではなく、提供者の選択や安全性などの問題が残されています。
肝移植の対象疾患は、小児では胆道閉鎖症(たんどうへいさしょう)、代謝性肝疾患(たいしゃせいかんしっかん)など、おとなでは原発性硬化性胆管炎(げんぱつせいこうかせいたんかんえん)、原発性胆汁性肝硬変、劇症肝炎(げきしょうかんえん)、代謝疾患、ウイルス疾患(B型、C型肝硬変)、アルコール性肝硬変、肝細胞がんなどです。
臓器の提供数(供給)に限界があるために、欧米では移植を受けるための優先順位がつけられます。ウイルス性肝疾患では移植後のウイルスのコントロールがむずかしいこと、肝細胞がんでは移植後の再発が問題となることなどから、優先順位は低くなっています。しかし、肝移植後に抗ウイルス薬を併用することなどにより、移植後もウイルスをコントロールし、長期の生存を得ようとする試みがなされ、よい成績をあげてきています。
アルコール性肝硬変では、移植後に飲酒を再開し、再び肝硬変に進展する例も多くみられるため、移植肝の供給数の少ない現在では、欧米においても断酒がある一定の期間守られていることが確認されたうえでないと、移植の対象にはなりません。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肝移植」の意味・わかりやすい解説
肝移植
かんいしょく
liver transplantation
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「肝移植」の意味・わかりやすい解説
肝移植【かんいしょく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「肝移植」の意味・わかりやすい解説
肝移植
かんいしょく
→肝臓移植
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...