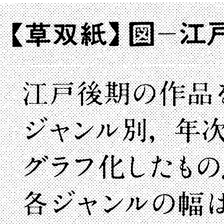精選版 日本国語大辞典 「草双紙」の意味・読み・例文・類語
くさ‐ぞうし‥ザウシ【草双紙】
- 〘 名詞 〙 ( 草仮名で書かれた草紙の意とも、また、薄手の浅草紙を用いたので一種の悪臭があったところからの名ともいう ) 江戸時代の絵入り短編小説の一様式。広義には、赤本、黒本、青本、黄表紙、合巻(ごうかん)の総称。狭義には、合巻だけをさす。江戸で発生、展開したもので、江戸初期から婦女子向きの簡単な説明入り絵本として出はじめたが、次第に小説界や演劇界の動きに刺激されて複雑なものとなった。安永四年(一七七五)黄表紙の出現で、滑稽本、洒落本とともに大人向きの軽妙な小説となったが、その後、読本(よみほん)の影響で合巻となり、内容は再び婦女童幼向きのものとなった。装丁は、すきがえし紙の美濃紙四つ折五丁目を単位とし、五丁またはその倍数を一冊としてその冊数を重ね、表紙には絵を主にした外題をつけ、数冊を袋入りにして売り出すのが常である。草本(くさほん)。仮名の草子。
- [初出の実例]「うき名とらるる内裏(だいり)上臈 大方は恋路をかける草双紙(クサザウシ)」(出典:俳諧・正章千句(1648)三)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「草双紙」の意味・わかりやすい解説
草双紙
くさぞうし
江戸時代の小説の一ジャンル。江戸特有の挿絵入り仮名書き小説で、寛文(かんぶん)末年(17世紀後半)ごろに刊行され始めた幼童向けの絵本である赤本を初めとして、黒本、青本、黄表紙、合巻(ごうかん)という順序で展開し、明治10年代(1877~1886)まで出版され続けた絵双紙の総称。江戸時代のもっとも通俗的な小説の一つで、「草」は似て非なるもの、本格的でないものというほどの意を表す卑称である。判型の多くは中本型(四六判。縦約18センチメートル、横13センチメートル)で、1冊5丁(10ページ)よりなり、1~3冊からなるが、合巻には100冊に及ぶ大部なものも数多い。赤本、青本、黄表紙などの呼び名は表紙の色によるもので、合巻はそれらが長編化し、数冊が合綴(がってつ)されるようになったがための呼び名であったが、またそれらはそれぞれに独自の内容的特徴をもっていたので、今日ではそれらの文芸のもつ特質をもその名でよんでいる。
[宇田敏彦]
赤本・黒本・青本
赤本は最初期の草双紙で、1662年(寛文2)ごろ発生した幼童向けの絵本である。素朴な絵と簡単な書き入れとからなり、表紙は丹色(にいろ)で絵題簽(えだいせん)を張り、判型は四六判と赤小本とよばれる小型のものがあったが、出版の商業化とともに四六判に統一され、以後この判型が草双紙のみならず、近代の小説本の大きさの原型となった。よく知られた前代からのおとぎ話や怪異譚(たん)を内容とし、叙述はきわめて簡潔なものであったが、しだいに歌舞伎(かぶき)や浄瑠璃(じょうるり)の素材を題材とするようになって複雑化するとともに、大人の、とくに青少年向けの読み物へと脱皮していった。延享(えんきょう)(1744~1747)初年ごろ、染料の値段の関係から表紙が黒色にかわって黒本が、また同じころ萌黄色(もえぎいろ)表紙の青本が誕生し、ともに演劇の演目に取材した史伝、伝説、神仏の霊験譚などを内容とした。初期は作者、画工とも不明の作が多いが、しだいに浮世絵創生期の代表的画家の奥村政信(まさのぶ)、鳥居清満(きよみつ)、富川房信(とみかわふさのぶ)らが作者を兼ねて活躍し、やがて専業の作者丈阿(じょうあ)などが出て草双紙の世界も大きくさま変わりして、滑稽洒脱(こっけいしゃだつ)な叙述で現実世界の世態人情をも写すようになり、次代の黄表紙を生み出す母体を醸成することとなった。
[宇田敏彦]
黄表紙・合巻
1775年(安永4)恋川春町(こいかわはるまち)が『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』を自画作で発表し、草双紙の世界は大転換期を迎える。この作は、そのころの江戸で成人の読み物としてもてはやされていた洒落本(しゃれぼん)の世界の絵解き、戯画化ともいうべきもので、精緻(せいち)な現実描写、知的で滑稽洒脱な視点と筆致が注目される。ちょうどこのころ、表紙も退色しやすい萌黄色から、値段も安く色もあせない黄色に変わって定着し、ここに黄表紙の誕生となった。以後黄表紙は、自由主義的な田沼時代を背景に、春町、朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)らの武家作者や山東(さんとう)京伝、芝全交らの町人作者、北尾重政(しげまさ)、鳥居清長、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)ら当代第一級の浮世絵師を中核とし、安永(あんえい)末年から天明(てんめい)年間(1780年代)にかけて、狂歌壇を中心とする天明文壇の隆盛とともに全盛期を招来し、軽妙な風刺性、奇想天外なパロディー(戯画化)を駆使した、内容よりもその表現に意義を認めざるをえない独特の文学形態を生み出した。
しかし田沼意次(おきつぐ)の失脚、保守派の松平定信(さだのぶ)による寛政(かんせい)の改革(1787~1793)により、その軽い風刺性すらもとがめられ、武家作者の総退場や、作風の転換を迫られる結果となった。心学を取り入れた教訓性の強いものや敵討物(かたきうちもの)の流行がそれで、しだいに筋(すじ)も複雑化し、長編化して、1807年(文化4)ごろには装丁を変えた合巻へと移行していった。末期には、のちに小説の世界に新ジャンルを開拓する曲亭馬琴(きょくていばきん)、式亭三馬(しきていさんば)、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)らがあり、画工には歌川豊国(とよくに)・国貞(くにさだ)らの活躍が著しい。合巻の特徴は、複雑でグロテスクな筋立てと、挿絵が役者の似顔で描かれる点など演劇との結び付きが密接なところにあり、京伝、柳亭種彦(りゅうていたねひこ)らを代表作者として、初期には短編物であったが、しだいに長編化して『白縫譚(しらぬいものがたり)』のように90編・各4冊という長大な作も出るに至った。血みどろなグロテスクさはその題材による点が多いが、時代の要求および天明期の知的で滑稽洒脱な戯作(げさく)精神の裏返しであったところにも注目したい。
[宇田敏彦]
『石田元季著『草双紙のいろいろ』(1928・南宋書院)』▽『『草双紙と読本の研究』(『水谷不倒著作集2』所収・1973・中央公論社)』▽『『草双紙』(『岩崎文庫貴重本叢刊』所収・1974・同書刊行会)』
改訂新版 世界大百科事典 「草双紙」の意味・わかりやすい解説
草双紙 (くさぞうし)
江戸中・後期に江戸で刊行された庶民的絵入小説の一体。毎ページ挿絵が主体となり,その周囲を埋めるほとんどひらがな書きの本文と画文が有機的な関連を保って筋を運ぶのが特色。美濃紙半截二つ折り,5丁1冊単位で,2,3冊で1編を成す様式が通例。しだいに冊数を増し,短編から中編様式へ,そして後には年々継続の長編へと発展する。表紙色と内容の変化とがほぼ呼応し,赤本,黒本あるいは青本(黒本・青本),黄表紙と進展し,装丁変革を経て合巻(ごうかん)に定着,明治中期まで行われる。草双紙の称は上述5様式の総称だが狭くは合巻を呼ぶ。本格的ではないという意の称呼で,赤本は童幼教化的,黒・青本で調子を高め,黄表紙は写実的な諧謔み,合巻は伝奇色が濃厚になる。
→草双紙物
執筆者:鈴木 重三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「草双紙」の意味・わかりやすい解説
草双紙【くさぞうし】
→関連項目江戸文学|偐紫田舎源氏|読本
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「草双紙」の意味・わかりやすい解説
草双紙
くさぞうし
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「草双紙」の解説
草双紙
くさぞうし
近世中期~明治初期,主として江戸(東京)で行われた,絵を主体とする小説の一様式。赤本,黒本・青本,黄表紙,合巻(ごうかん)の順序で展開する本来的に幼童むけを建前とした絵本形式の文芸の総称。書型は中本(美濃判半截の二つ折り)を基本とし,5丁を1冊とする。寛文末頃には発生していたと思われる赤本は,ほとんどが1冊完結で,御伽噺(おとぎばなし)などの簡略な絵解きである。演劇的要素の摂取,それにともなう筋の複雑化から,黒本とよばれる2~3冊の黒表紙のものがうまれ,ついで萌黄(もえぎ)色表紙の青本が発生し黒本と同時期に行われる。1775~1806年(安永4~文化3)の青本を黄表紙と称し,それ以降の草双紙を合巻とよぶ。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「草双紙」の解説
草双紙
くさぞうし
挿絵を主とする通俗・大衆的読み物の総称で,赤本・黒本・青本・黄表紙・合巻の順に変遷。寛文(1661〜73)ころより明治初期まで約200年間行われた。10ページ単位で1冊とし,1〜3冊程度でまとまる短編。ページごとに挿絵があり,仮名書きで女性・子供を対象として出発し,のちに成人向きとなった。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の草双紙の言及
【イラストレーション】より
…1930年代から登場してくるSFのイラストレーション,さらにそれに使われるエア・ブラシなどの手法などについても,美術の問題として取り上げていくべきであろう。【海野 弘】
【日本の挿絵】
文章に挿入された絵画としては,古く経巻装飾,絵巻などが数えられるが,現在の新聞,雑誌,書籍の挿絵に通じる形式と性格をそなえるものは,複製技術が発達した江戸時代の草双紙にたどることができよう。江戸中期から後期にかけて大衆文学の主流をしめた草双紙(赤本,黒本,青本,黄表紙,合巻の総称)は,半紙半裁二つ折りの各ページごとに挿絵が入り,絵と文が有機的に連係していた。…
【絵本】より
…下って歌川国芳(くによし)とその門下によって,切って折れば物語絵本となる連続こま絵などの一枚絵が盛んに描かれ,〈手遊び絵〉(今日ではおもちゃ絵ともいう)と呼ばれた。赤本の系統は,庶民の草双紙となり,各ページに絵を入れて文字を散らし書きに刷りこんだ絵本が一般的になった。
[明治以後]
明治維新後早くも1872年(明治5)に学制がしかれ,アメリカの読本によった国語読本が翌年に出るが,その体裁と版式は江戸時代と異ならず,民間ではやはり草双紙本が作られていた。…
【黒本・青本】より
…江戸で刊行された初期草双紙の一類。赤本に次いで現れ,体裁もほぼ踏襲している。…
※「草双紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...