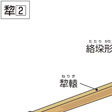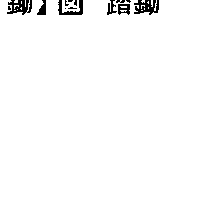鋤(読み)スキ(その他表記)spade
改訂新版 世界大百科事典 「鋤」の意味・わかりやすい解説
鋤 (すき)
spade
bêche[フランス]
やや幅広い刃床から柄が垂直ないしは鈍角状にのびる人力用農具で,耕起,土の掘りあげ,溝掘り,塊根類の掘りとりなどに使用される。中国では耒耜(らいし)ともいわれ,耒は柄,耜は刃を意味する。鋤は掘棒から発展したもので,典型的な掘棒が木棒の先端をとがらせただけで刃床を欠くのに対して,鋤は柄よりも広幅の長方形ないしは半月状の有肩刃床が柄の下端にある点で異なる。柄と刃床との関係はさまざまで,柄の下端の同じ木部を幅広い板状に加工したもの,石や木製などの板状の刃を柄に結びつけたもの,鉄製の刃床の上端中央に円筒形のさし込み穴があり,そこに柄を装着したものなどがある。最初のタイプは掘棒に最も近い鋤であり,スコップ(シャベル)は最後のタイプに属する。刃床が幅広になっているのは掘りおこす土の量を大にするためであると同時に,刃床の肩に足をかけて力を加え,鋤を土中に押し込むのを容易にするためである。この作業をさらに効率よくするため,柄の下部に足かけ用の横木を取り付けたものもある。同じ人力用耕具であっても,鍬(くわ)が手に依存するのに対して,鋤は手足をともに用いて作業する耕具である。また柄の上端には取っ手が取り付けられ,手のにぎりを容易にしているものもある。さらに刃床の両肩あるいは柄の下端部にロープを取り付け,一人が鋤を土中に押し込むと,向かい合う他の一人がそのロープを引いて土の掘りおこしを効率的に行うようにする場合もある。これは乾燥地帯のオアシス農業,また園芸農業でよくみられる。鋤は掘棒を主要農具とする湿潤熱帯の根栽農耕地帯では広く使用されているが,それ以外の地帯では耕起は主として犂(すき)や鍬によってなされるため,犂や鍬の使用が困難なところで用いられる補助的な農具にとどまっている場合が多い(鋤と犂の分布圏等については〈犂〉の項目を参照されたい)。
→農具 →農耕文化
執筆者:応地 利明
考古学から見た鋤
中国の新石器時代では石鏟と呼ぶ,刃先がU字形の扁平な石器があり,鍬あるいは鋤の刃と考えられる。これとともに耒(らい)と呼ぶ,刃先が二股に分かれた木製耕具も使用されたことが,殷代の遺跡での耕具痕や画像石から知り得る。同種のものは朝鮮初期金属器時代の青銅器絵画にも認められる。青銅や鉄の普及とともに各種の鏟が作られた。刃全体を金属で作り,着柄用の袋部を有する型式,あるいは木製の台部の先に着装する凹字形の鏟もあった。なお中国では〈鋤〉は除草用のクワを意味する。
日本では弥生時代の開始期に,すでに大陸で発達を遂げた耕具が伝わったが,各種の鍬とともに刃先が円形あるいは尖がった形のスコップ型の鋤が含まれていた。これらは刃先まで木製であるが,弥生時代後期から中国の鏟の流れをくむ青銅製品や,鉄板の両端を折り返した形の鉄器が鋤にも着装された。また,5世紀中葉に朝鮮半島から伝わったU字形鉄刃先の技術によって,刃先の着装法は改良された。なお,弥生時代後期から古墳時代にかけて認められる〈ナスビ型木器〉を着柄鋤と見なす説があるが,鍬先とも考え得る。
執筆者:都出 比呂志
日本の鋤
鋤と犂はともに〈すき〉と読まれる耕具である。そこで牛馬の力を利用する犂を中国から来たという意味で〈唐犂(からすき)〉といい,手と足で,ことに刃床部の肩に足をかけて土に押し込む鋤を〈踏鋤(ふみすき)〉,なまって〈ふんずき〉と呼んで区別することもある。西洋のシャベルも鋤の一種であるが,日本の在来型は鍬の刃床部と同じように,風呂と呼ばれる木製のブロックに鉄を鍛造してつくった刃先をはめこんだものである。鋤の使用は古く,稲作の伝来からまもなくと考えられるが,これは刃先も木製であった。機能や形態が分化・発達してくるのは,江戸時代中期以降である。土を起こす道具として鍬と並びあげられることが多いが,実際は耕起がもっぱら鍬でなされたのに対し,鋤の用途は限られており,排水溝をつくるというように,ただ掘るだけでなく土を持ちあげる作業に使われた。畑のうね底の土をさらうにも便利であるが,江州鋤は柄の付け根が少し湾曲しており,そのため柄と刃が同一面になく,土をすくいあげるのに便利で,江州地方の一部(現在の琵琶湖東岸)に独特の型である。鋤は農耕用だけでなく,水路や池を掘ったり,植木職人などにも広く用いられた。なお,畑地帯や焼畑では耕起にも鋤が用いられたが,柄と刃に角度をつけてつくられ,踏鍬などと呼ばれる。
執筆者:堀尾 尚志
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「鋤」の意味・わかりやすい解説
鋤
すき
農具の一種で、鍬(くわ)よりも古くから土壌を耕うんする道具として使用されていた。鍬は主として手の運動を利用して刃床部を土壌に打ち込みまたは引き込む作用をするが、鋤は手の力あるいは足の踏力により鋤先を土壌中に刺し込み、次に土壌をすくい上げる作用をするものである。深く耕す作業、根菜類の掘り取り作業、溝掘り作業などに適する。鋤の名は、土をすくい上げる働きをする器具を意味してつけられたともいわれる。構造は刃床部と柄部(えぶ)からなり、柄角(えかく)は150~180度の範囲内にある。普通、柄の端には取っ手がついている。
[小林 正]
種類
種類は数多く、使用法ならびに構造上から分類される。使用法からは普通鋤と踏鋤(ふみずき)に大別され、構造上からは風呂(ふろ)鋤と金(かな)鋤に分けられる。
普通鋤は柄角が180度で、使用法は手力により鋤先を土壌中に押し込み、柄をてこにして土壌をすくい上げ耕うんする後退耕法である。踏鋤は普通鋤と比較し長大な柄を有し、柄角は小さく150度内外である。使用法は土壌中に刃床部を斜めに片足で踏み込み、ついで柄を両手で前方に押し倒しながら土塊を側方に反転する後側退耕法である。反転方向は左右いずれでも可能で作業能率も大であるが、操作には熟練を要する。
風呂鋤の構造は、普通鋤では風呂と柄部とは一体としてカシなどの堅い木でつくられている。全長は120センチメートルくらいの長さのものが多い。刃部は練鉄製でその形状は多岐にわたる。江戸鋤の刃床部は平面形であり、京鋤、江州(ごうしゅう)鋤には反りがある。踏鋤の風呂鋤では板状の風呂に踏み木と鋳鉄製の刃がついた関東型、風呂と柄が自然木を利用して一体としてつくられた南部型、肉厚の風呂に柄を取り付けた信州型などがある。金鋤は刃床部がすべて練鉄製であって風呂がなく、柄は受け口に挿し込まれている。全長、刃床部の大きさはいずれも風呂鋤より小さく、穴掘り、根切りなどの作業に使用される。刃の形状は作業目的により変形され、ヤマイモ掘りなどに使用される鉈(なた)鋤、重粘土質用の股金(またがね)鋤などがある。
鋤に類するものは諸外国でも多く使用されているが、その形態は金鋤に相当するもので、スペード、ショベル、スコップ、フォークなどはその代表的なものである。現在日本では、在来の鋤は特殊なもの以外はほとんど使用されず、かわりにショベル、フォークなどが使用されている。
[小林 正]
歴史
農耕具のなかでももっとも原始的な掘棒は、棒の先端をとがらせただけの道具で、いまなお世界の広い地域で使用され、メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアなどのタロイモ、ヤムイモ栽培民の間では唯一の農具となっている。掘棒から発達した鋤(踏鋤)は、土すくいに適するように刃の幅を広くし、足かけをつくったもので、手だけでなく、足で踏む力を利用して刃先を深く土中に挿し、土を掘り起こし、すくいとる道具である。中国古代の耒(らい)は、重粘土地帯に生まれた木をたわめた二股(ふたまた)鋤であるとされている。世界の高文化の地域では、鉄の刃先を取り付けた鋤が発達する。中国では殷(いん)代に青銅製の鏟(さん)が、また先秦(せんしん)代には鉄製の鑱(さん)が鋤先に用いられた。
日本では弥生(やよい)時代に、刃先まで木製であるが一木造りの鋤、鋤身に柄(え)を枘差(ほぞさ)しにした鋤、二股鋤など多様な形態の鋤がみられる。5~6世紀のころ、鉄製の鋤先が大陸から導入されて以後、風呂鋤(ふろすき)が用いられた。江戸後期の『農具便利論』には京鋤、江州鋤、関東鋤のほか、踏鍬(ふみぐわ)、鋳鍬(いぐわ)と称する関東以北の畑作地帯で用いられる、鋤身に鈍角に柄を取り付けた踏鋤を示している。
[木下 忠]
『E・ヴェルト著、藪内芳彦・飯沼二郎訳『農業文化の起源』(1968・岩波書店)』▽『天野元之助著『中国農業史研究』(1962・御茶の水書房)』▽『「農具便利論」(『日本農書全集15』所収・1977・農山漁村文化協会)』
普及版 字通 「鋤」の読み・字形・画数・意味
鋤
15画
(異体字)
13画
[字訓] すき
[字形] 形声
声符は助(じょ)。助は
 (すき)と力(耒(すき))とを合わせた字。助が多義化して鋤・耡が作られた。鋤は名詞、耡は動詞的な字である。
(すき)と力(耒(すき))とを合わせた字。助が多義化して鋤・耡が作られた。鋤は名詞、耡は動詞的な字である。[訓義]
1. すき、すく。
2. のぞく、悪類をのぞく。
[古辞書の訓]
〔新
 字鏡〕鋤 須
字鏡〕鋤 須 (すき)〔和名抄〕鋤 須
(すき)〔和名抄〕鋤 須 (すき)〔名義抄〕鋤 クハ・スキ・スク・サラヒ 〔
(すき)〔名義抄〕鋤 クハ・スキ・スク・サラヒ 〔 立〕鋤 スカセ・ケヅリ・スキ・トラセ 〔字鏡集〕鋤 ヤブル・キカム・スキ
立〕鋤 スカセ・ケヅリ・スキ・トラセ 〔字鏡集〕鋤 ヤブル・キカム・スキ[語系]
鋤・助・耡dzhiaは同声。鋤・耡は助から分岐した字。鋤は名詞的、耡は動詞的な字である。
[熟語]
鋤耘▶・鋤禾▶・鋤穀▶・鋤社▶・鋤除▶・鋤治▶・鋤抜▶・鋤
 ▶・鋤
▶・鋤 ▶・鋤犂▶・鋤理▶・鋤笠▶
▶・鋤犂▶・鋤理▶・鋤笠▶[下接語]
耘鋤・耕鋤・
 鋤・
鋤・ 鋤・春鋤・稷鋤・耨鋤・誅鋤・把鋤・負鋤・
鋤・春鋤・稷鋤・耨鋤・誅鋤・把鋤・負鋤・ 鋤・犂鋤
鋤・犂鋤出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「鋤」の意味・わかりやすい解説
鋤【すき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鋤」の意味・わかりやすい解説
鋤
すき
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...