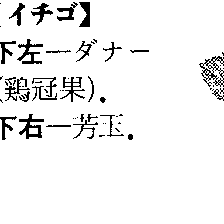日本大百科全書(ニッポニカ) 「イチゴ」の意味・わかりやすい解説
イチゴ
いちご / 苺
strawberry
[学] Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozier
Fragaria grandiflora Ehrh.
バラ科(APG分類:バラ科)の多年草。葉は3小葉からなる複葉で、長柄があり、葉柄や葉の裏面には毛がある。各小葉は長さ3~6センチメートル、幅2~5センチメートル、縁(へり)に鋸歯(きょし)がある。5~6月、径3センチメートルほどの白色花をつける。花期後に花托(かたく)が肥大して多肉質円錐(えんすい)形になり、その表面に痩果(そうか)が配列している偽果を形成する。果実は紅色から赤く熟し、芳香が強く、甘酸味がよく調和する。多くの栽培品種があり、果実の大きさや形はさまざまである。主茎は伸びないが、結実終了後に走出枝(ランナー)を伸ばし、その各節から発芽・発根して殖える。
南アメリカ原産で、現在の栽培種の大部分はペルーからパタゴニアに野生しているチリイチゴF. chiloensis (L.) Mill.(染色体数2n=56)と、北アメリカ東部に野生するF. virginiana Mill.(染色体数2n=56)との雑種起源と考えられている。このほかにも他種との交雑に由来するものが若干あるといわれる。イチゴと人類とのかかわり合いは古く、野生イチゴの利用は石器時代までさかのぼる。栽培化された初期のころは薬用であったというが、14世紀以降、ヨーロッパでF. vesca、F. moschataなどが栽培され始めた。新大陸発見に伴って、北アメリカや南アメリカの大果の野生種が導入され、17世紀の中ごろから品種改良が始まり、現在のイチゴがつくりだされた。日本へは江戸時代の末期に南蛮船によってもたらされ、オランダイチゴとよばれるようになった。現在の栽培品種はこれとは別で、明治以降新たに導入された品種およびその子孫である。普通栽培では3~6月が収穫期であるが、栽培法と品種との組合せで、ほぼ一年中供給されるようになった。
[星川清親]
促成栽培
8月上旬~9月上旬の約1か月間、苗を高冷地の低温条件にさらして花芽分化を促す(山上げという)。株ごと冷蔵する方法もある。これをビニルハウスや温室で促成栽培し、10月中旬から翌年3月にかけて収穫する。著名な品種に福羽(ふくば)があり、これは日本初のイチゴの品種である。1898年(明治31)福羽逸人(はやと)(1856―1921)の育成になる品種で、第二次世界大戦前の石垣イチゴはこの品種を用いた。
[星川清親]
準促成栽培
12月から翌年4月にかけて収穫する。かつてこの時期は、静岡県久能山(くのうざん)の石垣イチゴの独壇場であったが、現在はビニルハウスと石油暖房により、東北地方でも栽培可能となった。
[星川清親]
普通栽培
3~6月に収穫する。その有力品種はダナーと宝交早生(ほうこうわせ)であった。ダナーは第二次世界大戦後導入されたアメリカの品種で、濃赤色で、その香味は関東地方で好まれた。宝交早生は兵庫県宝塚で育成された品種で、明赤色、果肉がやや軟らかく、関西地方でより好まれた。イチゴは品種の移り変わりが激しく、2016年(平成28)時点で、とちおとめ、あまおう、とよのかなど多くのの品種がある。普通栽培に類する方法として、自然の低温で花芽形成したのち、ビニルをかけて生育をすこし早める半促成栽培や、苗を冷蔵庫に入れて低温で花芽分化させ、次に電照栽培を行い、さらに10日ほど結実を早めることもある。
[星川清親]
抑制栽培
2月に掘り上げた株を冷蔵庫に入れ、8月に花が咲くばかりになったころ取り出して植え付けると、すぐに開花し、9月から10月にかけて収穫できる。7~8月はイチゴの少ないときで、高冷地産のイチゴでつないでいくが、それでも8月どりは困難とされる。現在この時期のイチゴはアメリカからの空輸に頼っている。なお、ジャムなど加工用の品種には、御牧ヶ原、ふじさきなどがある。
栽培は、果実の収穫の終わった親株を肥料をやって育て、発生したランナーにできた新苗をとって定植する。イチゴの主要病害であるウイルス病を防ぐため、成長点培養(メリクロン)によってウイルス・フリーの苗を増殖する技術が実用化されている。
現在、イチゴの国内収穫量は年約15万9000トン、作付面積は5370ヘクタール(2016)、主要な生産県は栃木、福岡、熊本、静岡、長崎などである。
[星川清親]
利用
イチゴは冬期のビニル被覆栽培、石垣栽培などをはじめとして、陽光のよく当たる畑地や、水田の転換利用などに取り入れられ、主として12月上旬から6月上旬まで新鮮な果実が出回る。果実は100グラム中に35キロカロリーをもち、炭水化物8.3グラム、カルシウム17ミリグラム、リン28ミリグラム、ナトリウム1ミリグラムを含み、ビタミンはカロチン6マイクログラム、ビタミンC80ミリグラム、B1とB2で0.05ミリグラムなどを含み、かならずしもこれら成分に富んでいるとはいえないが、新鮮な果実は食味をそそる。
生果利用としては、水洗後そのまま食し、また砂糖や牛乳を加えてもよい。ケーキやアイスクリームなど、菓子やデザートに使われることが多い。冷凍利用は、水洗後、零下1℃で1日予冷し、これに砂糖30~40%を加えて凍結させ、零下20℃で貯蔵する。これはそのまま利用できるし、また加工原料にもよい。冷凍輸送にも適す。ジャム、プリザーブとしても需要が多く、果実に含まれる可溶性ペクチンは、製品の粘度を保つのに好都合である。家庭でつくるには、水洗し、萼(がく)を除いて水切りし、果実の60~80%の砂糖を加え、ほうろう引きかガラス鍋(なべ)で加熱濃縮する。果形をそのまま保つとプリザーブで、つぶすとジャムになる。酸味の強い品種が適す。ジュースとしてもよく、貯蔵用には果実を80~100℃で急速に加熱、搾汁し、そのまま、または50%程度の加糖をしてシロップとする。いちご酒をつくるには、果実1キログラムに等量または半量の砂糖を加え、焼酎(しょうちゅう)1.8リットルに漬けて2~3か月熟成する。この際1、2個のライムやレモンの輪切りを加えるとよい。アイスクリームにも利用する。
[飯塚宗夫]
民俗
近代的なオランダイチゴが誕生する17世紀以前には、同属のエゾヘビイチゴFragaria vescaなどの野イチゴが食用にされていた。属名のフラガリアは、北欧神話の光の神の母親フラグ(フリッグ)にちなむ。ヨーロッパにキリスト教が広まると、フラグは聖母マリアに置き換えられ、イチゴは聖母の実とされた。また中世のイギリスでは正義の実とされ、貴族たちは好んで冠にイチゴの葉の飾りを付けた。このことから、イチゴの葉を得ること(to win the strawberry leaves)は、爵位を授かることを意味するようになった。
[湯浅浩史]
『矢部和則著『イチゴ――NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月』(2001・日本放送出版協会)』▽『松田照男編著『イチゴQ&A栽培技術早わかり』(2003・全国農業改良普及支援協会)』▽『谷本雄治著『バケツ畑で野菜づくり4――イチゴ』(2003・フレーベル館)』▽『農山漁村文化協会編『野菜園芸大百科3――イチゴ 第2版』(2004・農山漁村文化協会)』

イチゴ(とよのか)

イチゴ(女峰)

イチゴ(章姫)

イチゴ(ダナー系)

イチゴ(あまおう)

イチゴ(初恋の香り)

イチゴの果実

イチゴの花

イチゴの栽培

イチゴのおもな歴史的品種〔標本画〕

野生イチゴ(エゾヘビイチゴ)

野生イチゴ(エゾヘビイチゴ)の花