スズメ (雀)
tree sparrow
sparrow
Passer montanus
スズメ目ハタオリドリ科の鳥。全長約15cm。雌雄同色。背面は茶褐色で黒い縦斑があり,腹面は淡い。眼からほおにかけて暗色の巴紋があり,のどは黒い。ユーラシア大陸の中緯度地方に広く分布し,南はヒマラヤ山ろくから東南アジア,ボルネオ島,ジャワ島,バリ島にまで生息する。また北アメリカ,オーストラリア,フィリピン,セレベス島などに移入されたものが繁殖している。日本ではもっとも一般的な鳥で,人家,農耕地にすみ,とくに水田に接する人里に多い。雌雄ひとつがいで繁殖し,建築物の穴に巣をつくる。ときには樹木の茂みの中に枯草を集めて球形の粗雑な巣をつくる。1腹4~6個の卵を産む。雌雄で抱卵し,12~14日で孵化(ふか)する。雛には青虫など昆虫を与えるが,のちにヒエなどの草の種子に切り替える。主食は種子や穀物である。夏の終りころには木の茂みに,さわがしい幼鳥のねぐら集合が目だつようになる。イネの実るころに大群で現れ,胚乳をつぶして食べるためイネに大害を与える。秋から冬にかけて水田地帯に数百羽になる大群が見られ,松林やヨシ原などをねぐらにするが,人家の穴にねむるつがいもある。
近縁種のニュウナイスズメP.rutilans(英名russet sparrow)はスズメによく似ているがやや小さく,全長約14cm。アジア南東部,台湾,日本,サハリンなどに分布し,日本では本州中部以北の林で繁殖し,秋にスズメの群れに混じって水田や畑に飛来する。なお,ヨーロッパやインドで人家にすみついているのは近縁種のイエスズメP.domesticusで,スズメは樹林地にいる。
スズメ目
スズメ目Passeriformes(英名passerine)は全世界の鳥類約8600種のうちの約6割を含む大きいグループで,かつては燕雀目(えんじやくもく)とも呼ばれた。鳥の中ではもっとも進化した仲間と考えられ,全長8~110cmの幅があるが,一般に小型の鳥が多く,すべて陸上にすんでいる。あしゆびは三前趾足で,ゆびを器用に使いこなし,細枝をつかむことができる。採食行動に伴ってあしゆびを使うものがあり,エナガのように餌を握ってくちばしでつついて食べるものさえある。鳴管がよく発達し,鳴管を動かす筋肉の数が多く,よい声でさえずるものが多い。とくにスズメ亜目のものは,さえずりが発達していて鳴禽(めいきん)類とも呼ばれる。雛は孵化したときにはまだ眼が開いておらず,巣にはある期間いて両親か一方の親の保育を受ける。
執筆者:中村 登流
象徴,民俗
スズメはアフロディテの聖鳥で,愛,とくに夫婦仲のむつまじさを象徴し,ときには好色の代名詞にもされる。そのために卵は媚薬(びやく)に使用された。また海の泡から生まれたアフロディテとの結びつきにより,海に関連づけられることがある。例えば,船の航行を助ける順風のあとにはスズメの群れがついてくるという言い伝えなどである。どこにでもいるので,卑近なもの,子ども,民衆などに言及する際はよく引合いに出される。他方,この鳥の雄が翌春まで生きのびないという俗信が根強いのは,雄の黒い前胸部が冬季に淡色に変わってしまうことによる。キリスト教美術においては,原野に好んで住みつき孤独を愛すると考えられたことから,〈憂鬱(ゆううつ)〉〈孤絶〉の寓意として使われたりする。半面スズメは個体数が多く,穀物やサクランボなどを食う害鳥という面をも有するので,ときには悪魔の手先と認められ,イギリスの童謡《だれが殺したか,コック・ロビン》でも弓と矢でロビンを殺す犯人にされている。
執筆者:荒俣 宏 〈スズメ〉という語は,古くは小鳥類一般を総称していたらしい。四季を通じて人里近くによく見られる。口達者によくさえずる小鳥だというので,ノキバノオバサン,ユムンドゥリ,イタクラ(いたこまたはいたかのようによく物をいう小鳥)などの方言で呼ばれる。害虫を捕食する反面,農作物に群がって甚大な被害を与え,農民生活を脅かす害鳥でもある。その一種のニュウナイスズメは終生蔵人頭になれずに遠流の地で死んだ摂関家出身の歌人藤原実方(?-998)の亡魂が化したものとする俗説がある。農民はスズメを駆除するために田畑にかかし,鳴子などを備えつけ,小正月の〈鳥追〉の行事でその一掃を願った。だが一方,こうしたスズメの穀物をついばむ習性を善意に解釈して,穀霊神的な見方をして〈スズメが田をつくる〉といったり,昔話でもスズメが米をついばむのは親孝行の報いであると説いたりした。スズメの色彩はじみで,人々に注目されることは少なかったが,喉部(こうぶ)の黒色模様が特徴的なので,昔話の〈雀孝行〉では親の臨終の知らせにあわてたスズメが御歯黒をつけそこない,それが模様になったとする由来譚が語られている。白いスズメは来福の兆しと考えられたが,昔話でも〈舌切雀〉のように,スズメは人間に富を与える鳥としても語られた。《宇治拾遺物語》にも,腰を折られたスズメを老婆が助けたところ,そのスズメがヒョウタンの種子をもたらし,成長したヒョウタンの中から白米が生じたとするスズメの報恩譚が見える。スズメをとると火事になる,夜盲症になるとする俗信は多く,スズメを保護しようとする思想のあったことが知られるが,かつてはスズメを飼うことも行われた。《枕草子》にスズメの子飼いの記事があり,スズメの両足をそろえてとんで歩く姿をユーモラスなものとして愛玩したらしい。また,スズメの歩く姿を踊りに見たて,これを芸能化したものに雀踊がある。なお,スズメの肉は食用にされ,その黒焼きは夜盲症,百日咳などの民間薬として利用された。
執筆者:佐々木 清光
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
スズメ
すずめ / 雀
tree sparrow
[学] Passer montanus
鳥綱スズメ目ハタオリドリ科の鳥。同科スズメ属19種中の1種。全長約13.8センチメートル。雌雄同色で、頭は栗(くり)褐色、上面は赤褐色に黒の縦斑(じゅうはん)があり、顔と頸側(けいそく)は灰白色、耳羽の後半とのどの黒斑が顕著である。シベリアの北部とインド半島を除いたユーラシアのほとんど全土、日本、台湾、海南島、大スンダ列島などに分布する。オーストラリア、セレベス島、フィリピン、アメリカ合衆国などにも生息するが、これは輸入されたものである。同属で大形のイエスズメP. domesticusのほうが勢力が強く、イエスズメの分布する地域では、その優勢におされてスズメは少なく、かつ人家から遠ざけられている。しかしアジアではいまのところイエスズメの侵入はまだ西部地域のみで、スズメが人間の身近に存在している。日本では南千島から琉球(りゅうきゅう)諸島まで全国に普通であるが、近年すこしずつ減少の傾向がみえる。
スズメは本来樹上に営巣する鳥で、地上2~10メートルの樹上に膨大な草の茎葉を使って丸い横型の巣をつくる。隣どうしの巣が連なって集団営巣のようになることもある。松の木であることもあれば、ツゲや貝塚を利用することもあるが、けっしてじょうずな巣づくりとはいえず、むしろ乱雑にさえみえる。長い年月、人間とかかわり合って、人間の改良した穀物の味を覚えたからか、人家のある所かならずスズメがいると思わせるまでになり、巣づくりも樹上から人家の構造物に移動するようになった。人間の去った廃村には家屋が残ってもスズメは残らないほど、人間とのかかわり合いが深い。早春から夏にかけてが営巣期で、この時期は雑草の種子もとるが、昆虫などの動物食も多くとり、冬季の雑草駆除と相まって春夏季の害虫駆除の効果は大きい。秋になると農耕地に集まり、夜は葦原(あしはら)、竹やぶなどを集団のねぐらとするが、稲穂を食害するので、近縁種でヒマラヤ、中国、本州以北などで繁殖するやや小形のニュウナイスズメP. rutilansとともに農家から嫌われ、古くから焼きとりとして賞味される。冬季は人家付近に帰る。
[坂根 干]
鎌倉時代の『十訓抄(じっきんしょう)』には、人の霊がスズメに化した話がみられる。奥州へ流された藤原実方(さねかた)は、都へ戻ることを願いながらかの地で死に、その霊は化してスズメとなり、宮中へきて台所の飯をついばんだとある。貝原益軒の『大和(やまと)本草附録』などにみえる江戸時代の俗伝では、これをニュウナイスズメの起源説話に結び付け、そのスズメが内裏(だいり)へ入ったことから入内雀(にゅうないすずめ)とよぶとあるが、ニュウナイは「新嘗(にいなえ)」と同語で、「新穀を食うスズメ」という意味であろう。
スズメは実ったイネなどの穀物を食う害鳥として知られ、日本の案山子(かかし)(鳥おどし)の大半は、このスズメを追うために仕組まれている。秋田県大仙(だいせん)市内小友(うちおとも)の加茂神社は「スズメの神様」とよばれ、「加茂神社鳥虫除守護符」の立札を田に立て、スズメ除けの祈祷(きとう)をしてもらうと、どんなにスズメがきてもその田の稲穂だけはついばむことがないという。ルーマニアの北西部地方には、穀物をスズメから守るために、播(ま)き始めに「これはスズメのため」といって、一握りの種を頭越しに後方へ投げる習慣があった。
アイヌでは、神が天地をつくったときにスズメは人間といっしょに地上へ降ろされたので、人間が穀物を搗(つ)くとかならずスズメがきてその穀物を食べると伝える。スズメが酒を醸して他の動物をもてなしたという物語もある。中部地方でも、晩秋の夕暮れにスズメが大木に群がって騒ぐのを「スズメが酒倉をつくる」という。穀物を食うスズメが、穀物で酒をつくるとみなしたもので、イラムシ(イラガ科の幼虫)の繭が壺(つぼ)のような形をしていることから、これを「スズメの壺」「スズメの酒桶(おけ)」「スズメの担桶(たご)」「スズメの据え風呂(ぶろ)」などとよぶ。中国にも「スズメの甕(かめ)」などの称がある。
[小島瓔 ]
]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
スズメ
Passer montanus; Eurasian tree sparrow
スズメ目スズメ科。全長 12.5~14cm。背面は茶褐色で,背と肩には黒色の縦斑があり,耳羽,腮(さい。あご),喉,上胸は黒色,胸以下の下面は白色である。ユーラシア大陸に広く分布するが,北部の寒冷地や南アジアから西アジアには生息しない。また,北アメリカの一部やオーストラリアには人為的に輸入されたものが分布を広げている。日本では留鳥として全国の都会や農村の人家近くにすみ,屋根瓦の下,建物のすきま,鉄柱の中,巣箱などに営巣している。非繁殖期には群れをなして生活し,雑木林や竹藪にねぐらをとるが,特に夏から秋にはたくさんの鳥が集まる。イネ科を主とする種子食であるが,昆虫類も食べる。農村ではイネの害鳥とされてきたが,近年では対策が講じられ被害が少なくなっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
スズメ(雀)【スズメ】
ハタオリドリ科の鳥。翼長7cm。雌雄同色で頭部は赤茶色,背は褐色で黒斑がある。ユーラシア大陸の中・南部に広く分布。日本では留鳥として全国の人家付近に見られる。軒下,瓦の下などに巣を作るが,時には木の穴や巣箱にも営巣する。秋〜冬には竹やぶ等に大群ですむ。収穫期には米も食べるが,春〜夏の繁殖期には大量の昆虫,秋〜冬には雑草の種子等を食べる。近縁種にニュウナイスズメがある。またヨーロッパではイエスズメのほうが人家周辺には多い。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
スズメ
学名:Passer montanus
種名 / スズメ
目名科名 / スズメ科
解説 / 人が住んでいる場所に生息していて、人がいなくなると、その場所をはなれます。近年、生息数がへってきているという研究もあります。
全長 / 15cm
食物 / 種子、昆虫
分布 / 留鳥
環境 / 人家周辺、農耕地
鳴声 / チュン、ジップ
出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報
Sponserd by 
すずめ
日本のポピュラー音楽。歌は女性歌手、増田恵子。1981年発売。作詞・作曲:中島みゆき。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のスズメの言及
【鳥】より
…農民生活と鳥との関係は深く,害虫を捕食するツバメなどの益鳥は,これを捕ると火事になる,盲目になるなどといって積極的に保護が加えられた。一方,スズメやガン・カモ類は田畑を荒らす害鳥としての側面が大きかったので,小正月の〈[鳥追]〉では憎み嫌われる鳥の代表例となっている。鳥は食用としての利用価値も大きい。…
※「スズメ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 

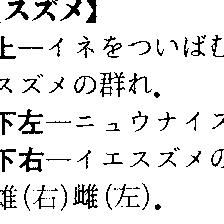

 ]
]
