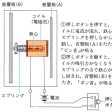翻訳|chime
関連語
精選版 日本国語大辞典 「チャイム」の意味・読み・例文・類語
チャイム
日本大百科全書(ニッポニカ) 「チャイム」の意味・わかりやすい解説
チャイム(鐘)
ちゃいむ
chime
いくつかの音高に調律されたベル(鐘)のセット。本来椀(わん)形で大型のものも多く、古くから教会の塔などに備え付けられてきたが、中世末期以後は鍵盤(けんばん)演奏あるいは機械仕掛けの自動装置を用いて鳴らす方向へと発展してきた。一般に規模の大きなものはカリヨンcarillon(フランス語)、小さなものはベル・チャイムあるいはチャイムとよばれている。また、椀形ベルが半音階に調律したチューブ管に変わって音楽に導入されたものがチューブラー・ベルtubular bellsで、オーケストラでチャイムというとこれをさし、ムソルグスキー作曲の『禿山(はげやま)の一夜』(1881~83)などで効果的に用いられている。
[川口明子]
音楽用語ダス 「チャイム」の解説
チャイム
出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「チャイム」の意味・わかりやすい解説
チャイム
chime
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「チャイム」の意味・わかりやすい解説
チャイム
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...