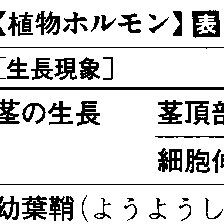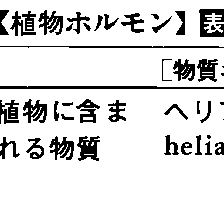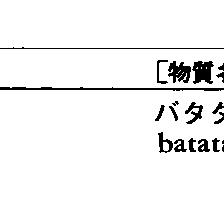精選版 日本国語大辞典 「植物ホルモン」の意味・読み・例文・類語
しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「植物ホルモン」の意味・わかりやすい解説
植物ホルモン
しょくぶつほるもん
plant hormone
phytohormone
植物ホルモンはおおよそ次のように定義される。「植物自らが天然に生産する有機化合物で、通常、それが生成される場所から植物体内の他の場所(標的部域)に運搬され、微量(低濃度)で植物の成長・分化の諸過程や諸生理機能を調節するもの」。
植物でホルモンということばを最初に用いたのはドイツのフィッティングH. Fittingで、彼はランの花粉の中に花粉ホルモンがあると考えた(1910)。その後、ドイツのハーバーラントG. Haberlandtが傷組織から癒傷(ゆしょう)ホルモンが分泌されると主張した(1918)。しかし、「植物ホルモン」ということばを使ったのはハンガリーのパールPaál Árpád(1889―1943)が最初であり、彼は、屈光性の刺激伝達物質に対して植物ホルモンということばを使っている(1916)。この物質は、のちにオーキシンと名づけられたものである。
植物ホルモンは、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、エチレン、アブシシン酸、ブラシノライド、ジャスモン酸の7種類があげられるが、ほかにもシステミン、フィトスルフォカインなどのペプチド性物質もホルモンに入れる場合もある。合成された化合物のなかには、植物ホルモンと同じような作用を有するものも多く、このような物質を植物ホルモンに含めた場合は、植物(成長)調節物質、あるいは植物(成長)調節剤plant (growth) regulator, plant (growth) regulating substanceとよんでいる。
植物ホルモンは動物ホルモンと異なって、それぞれのホルモンを生産する特定の場所(腺(せん))がなく、一般に若い組織でつくられる。ホルモンの種類は種を超えて共通であり、一つのホルモンが多様な効果(作用)をもつ。また、ホルモン間で相互作用をもつことが多い。
[勝見允行]
『トマス・アンソニー・ヒル著、勝見允行訳『植物ホルモン』(1981・朝倉書店)』▽『増田芳雄著『植物の生理』(1986・岩波書店)』▽『C・ダーウィン著、渡辺仁訳『植物の運動力』(1987・森北出版)』▽『太田保夫著『植物ホルモンを生かす――生長調節剤の使い方』(1987・農山漁村文化協会)』▽『下川敬之著『エチレン』(1988・東京大学出版会)』▽『E・ビュンニング著、田沢仁ほか訳『分子生理学の先駆者ヴィルヘルム・ペッファー――現代に生きるその研究と洞察』(1988・学会出版センター)』▽『増田芳雄著『植物生理学』(1988・培風館)』▽『倉石晋著『植物ホルモン』(1988・東京大学出版会)』▽『日本比較内分泌学会編『ホルモンハンドブック』(1988・南江堂)』▽『桜井英博・柴岡弘郎・清水碩著『植物生理学入門』(1989・培風館)』▽『柴岡弘郎編『現代植物生理学3 生長と分化』(1990・朝倉書店)』▽『勝見允行著『植物のホルモン』(1991・裳華房)』▽『増田芳雄著『植物ホルモン研究法』(1991・学会出版センター)』▽『神阪盛一郎ほか著『植物の生命科学入門』(1991・培風館)』▽『増田芳雄編著『絵とき 植物ホルモン入門』(1992・オーム社)』▽『ハルトムート・ギムラー著、田沢仁ほか訳『植物生理学・栄養学の創始者ユリウス・ザックス――今日に生きる苦闘と栄光』(1992・学会出版センター)』▽『増田芳雄著『植物学史――19世紀における植物生理学確立期を中心に』(1992・培風館)』▽『清水碩著『植物生理学』(1993・裳華房)』▽『高橋信孝・増田芳雄編『植物ホルモンハンドブック』上下(1994・培風館)』▽『長田敏行ほか編『植物の遺伝子発現』(1995・講談社)』▽『板倉聖宣編『自然界の発明発見物語』(1998・仮説社)』▽『今関英雅・柴岡弘郎編『植物ホルモンと細胞の形』(1998・学会出版センター)』▽『ハンス・モーア、ペーター・ショップァー著、網野真一・駒嶺穆監訳『植物生理学』(1998・シュプリンガー・フェアラーク東京)』▽『酒井敏雄著『評伝 三好学――日本近代植物学の開拓者』(1998・八坂書房)』▽『宮地重遠・大森正之編『植物生理工学』(1998・丸善)』▽『東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻編『実験生産環境生物学』(1999・朝倉書店)』▽『横田明穂編、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科植物系全教員著『植物分子生理学入門』(1999・学会出版センター)』▽『増田芳雄著『植物ホルモンと私――戦後研究の国際的発展の中で』(2000・学会出版センター)』▽『ハンス・ワルター・ヘルト著、金井龍二訳『植物生化学』(2000・シュプリンガー・フェアラーク東京)』▽『大森正之・渡辺雄一郎編著『新しい植物生命科学』(2001・講談社)』▽『駒嶺穆総編集、福田裕穂編『朝倉植物生理学講座4 成長と分化』(2001・朝倉書店)』▽『増田芳雄著『植物生理学講義――古典から現代』(2002・培風館)』▽『小柴共一・神谷勇治編『新しい植物ホルモンの科学』(2002・講談社)』▽『柴岡弘郎著『植物は形を変える――生存の戦力のミクロを探る』(2003・共立出版)』
改訂新版 世界大百科事典 「植物ホルモン」の意味・わかりやすい解説
植物ホルモン (しょくぶつホルモン)
phytohormone
plant hormone
高等植物の体内で合成される有機化合物で,低濃度で植物の生長,分化およびこれに関連する生理学的過程を調節する物質。通常,生産された部域から移動して,作用すべき部域へ到達して働く。現在,天然に見いだされる植物ホルモンと同じ作用をもつ合成物質が多数知られている。これら合成物質,および微量で植物ホルモン様活性を示す物質ではあっても必ずしも植物界に普遍的でないものをも含めた場合には,植物調節物質plant regulatorという名称が使われる。植物の生長に影響を与える物質という意味に力点を置いた場合には,同義語としてそれぞれ植物生長ホルモンplant growth hormoneおよび植物生長調節物質plant growth regulatorまたは植物生長物質plant growth substanceという言葉が用いられる。植物学の世界でホルモンという言葉が最初に使われたのは1909年のことで,ドイツのフィッティングH.Fittingがランの花粉の抽出物が子房の拡大生長(単為結実)を引き起こすことを見いだし,この抽出物中に作用物質が存在すると考え,ホルモンと名付けた。しかし,現在のオーキシンなどの物質を指すものとして植物ホルモンという言葉が用いられたのは,1937年にウェントF.W.WentとティマンK.V.Thimannが《植物ホルモンPhytohormones》という書物を出版したときに始まる。
現在,植物ホルモンとしてはオーキシン,ジベレリン,サイトカイニン,アブシジン酸,エチレンの5種類が知られている。それぞれの生理作用をまとめると表1のようになる。このほかに花成ホルモンの存在が示唆されているが,物質としてはまだ同定されていない。上記5種類の植物ホルモンのほかに,近年多くの天然の植物調節物質が見いだされている(表2)。ただし,これらの化合物は微生物の生成物で,まだ高等植物自身には見いだされていなかったり,あるいは特定の植物のみに含まれているにすぎないので,植物ホルモンとは認められていない。植物界での分布も広く,かつ植物組織に与えたとき一定の生理作用を示す物質として,トランス-桂皮酸,p-クマル酸,コーヒー酸,クロロゲン酸などのフェニルプロパノイド,およびクマリン類がある。単独では活性を示さないが,ホルモンと共力作用を示す物質として,ジヒドロコニフェリルアルコールがあり,これはジベレリンと共力的に働きレタス芽生え下胚軸の伸長を,インドール酢酸と共力的に働きキュウリ下胚軸切片の伸長を促進する。
植物の生長,分化の調節は,単独のホルモンによって行われるのではなく,幾種類かのホルモンの相互作用によっている場合が多い。また,作用時の相互作用とは別に,高濃度のオーキシンによるエチレン生合成の誘導のように,一つのホルモンが他のホルモンの合成に影響を与える場合もある。外からホルモンを与えたときに起こる変化は,植物の置かれている環境や植物の齢によって異なる。これらの要因によって,当該ホルモンや相互作用するホルモンの組織内の量および当該ホルモンに対する感度が異なり,このことにより外から与えたホルモンの効果が異なって現れることとなる。
植物体内の各ホルモンの量はその合成と分解の速度で決まり,植物体内におけるホルモンの分布はホルモンの移動の調節によって決まるが,これらの過程は光,温度,湿度などの環境要因により大きく影響される。したがって,環境要因→ホルモン→生長・分化という図式で植物の生長・分化の制御が行われている場合が多い。
どのホルモンの研究にも一般に次の三つの段階がある。(1)ある特定の生理学的現象が,何かある特定の微量な物質(のちにホルモンと判定される)によって引き起こされることが確認される。(2)その物質の単離と同定が行われる。(3)その物質がどのような作用機構で,生理学的変化を引き起こすかが調べられる。(1)の判断規準として1959年にジェーコブズW.P.Jacobsが6項目を提案し,これは各項の頭文字をとりPESIGSの法則と呼ばれる。(a)平行関係parallelism その生理学的現象と,その組織中に存在するホルモンの量との間に平行関係があるか。(b)除去excision そのホルモンが組織から取り除かれると,その生理作用も消失するか。(c)置換substitution (b)の組織に対し外からホルモンを与えると,生理作用が再び回復するか。(d)単離isolation 反応にあずかる組織を植物体から切り離した状態でも,もとの状態のときとほぼ同じ反応が起こるか。(e)一般化generalization 上記(a)~(d)の点について違った組織,違った植物でも同じことが認められるか。(f)特異性specificity 他の物質ではなく,問題としているホルモンを与えたとき,初めてその生理作用が現れるか。さきに述べた研究段階(3)は,現在どのホルモンについてもまだ完成されていない。ホルモン分子が最初に行うことがらを知るために,ホルモン受容分子を追い求める研究が現在盛んに行われている。
→植物生長調節剤
執筆者:辻 英夫+前田 靖男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「植物ホルモン」の意味・わかりやすい解説
植物ホルモン【しょくぶつホルモン】
→関連項目アブシジン酸|植物生長調節剤|成長ホルモン|ホルモン
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「植物ホルモン」の意味・わかりやすい解説
植物ホルモン
しょくぶつホルモン
plant hormone
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
化学辞典 第2版 「植物ホルモン」の解説
植物ホルモン
ショクブツホルモン
plant hormone, phytohormone
植物がみずからつくりだし,ほかの部分へ移動し,そこで特殊な生理作用を示す化学物質.きわめて低濃度で作用し,植物の生長(発芽,生育,開花など)を調整する.エテン(果実の成熟促進),オーキシン類(茎の伸長,花芽形成,発根),ジベレリン(茎や葉の伸長),サイトカイニン類,(細胞分裂の促進,芽・葉の生長促進),アブシシン酸(生長抑制,休眠),ジャスモン酸(生長抑制,老化促進)などがある.ジベレリンは種なしブドウの作製や果物の肥大化にも使われている.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
栄養・生化学辞典 「植物ホルモン」の解説
植物ホルモン
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...