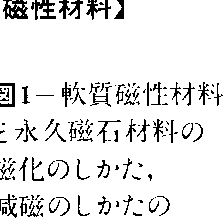改訂新版 世界大百科事典 「磁性材料」の意味・わかりやすい解説
磁性材料 (じせいざいりょう)
magnetic material
磁気的な性質を利用する金属材料の総称。録音用の磁気テープや磁気ディスク,永久磁石が身近な例である。電気を流して熱や光を発生させるヒーターや電球は,電気抵抗体に電気を流すと熱に変わるという原理の応用であって,磁性とは関係がないが,電気を流すと力の出るモーター,力を加えて回転すると電気が発生する発電機,電圧を変える変圧器,テープへの録音などは電気と磁気の作用の応用であって,このような機器には必ず磁性材料が使用されている。これらは家庭用電気機器から発電所まで,あるいは通信・計測・制御やコンピューター,また各種の産業機械などほとんどあらゆる分野で利用されている。コイルに電流を流すとその中に磁場ができる。磁場とは,そこに物質をおいたときに磁気的な作用を生じるような状況のことである。磁場に対する物質の反応としては,実際上ほとんど影響のないものもあり,これは常磁性あるいは反磁性といわれる性質である。いいかえると磁石に吸いつかない材料がある。たとえばアルミニウムのサッシュや銅の電線,18-8ステンレス鋼の流しは磁石に吸いつかない。このような材料は磁性材料にはならないが,一方では磁性材料の応用が広がるにつれて磁性があっては困る用途もふえており,とくにその点に注目した材料に非磁性材料がある。磁場の作用によって強く磁化するものが強磁性体であって,鉄が最も基本的な材料である(磁性については〈磁性〉の項参照)。
磁性材料として利用されるのは強磁性体であるが,その磁気的性質は材料によって大幅に違い,それぞれの特徴によって応用が違ってくる。コイルに流す電流によって磁場の強さHが変わる。また,そこにおかれた材料が磁化される程度を磁束密度Bで表し,磁場の強さを変化させたときのBの変化を図1に示すと図の右上のような曲線になる。この曲線は磁気履歴曲線といわれ,材料の磁性の特徴をよく表している。Hが増したときのBの増し方を表す透磁率の大きいことに重点がある材料を高透磁率材料という。また,一度一方向に強く磁化して着磁した状態で使用されるものは永久磁石材料あるいは硬質磁性材料と呼ばれる。ある程度保磁力が大きくて,使用中に一つの方向に磁化されたり,また反対方向に磁化されたり,履歴曲線の全域にわたって動作するように使用されるものを半硬質磁性材料という。交流磁場のなかにおくと,材料のなかに渦電流と呼ばれる電流が流れ,これがまた磁場を発生する。この現象は磁性材料の特性を悪くするので,これが少なくなるように電気抵抗が高いことが望ましい。
高透磁率材料
磁場の変化につれて容易に磁化されることが特徴で,その原理は,磁区の壁の移動と磁化の方向の変化が容易なことである。この性質は材料中の不純物,結晶粒組成,加工ひずみにきわめて敏感に影響される。そのために製造の際には,不純物の少ない原料を真空溶解などで不純物が入らないようにしたり,溶解するときに不純物を除く処理を行ったりし,また,使用形状に加工した後で加工ひずみを除くために焼きなましをするなどの注意が必要である。また,結晶の方向によって磁化のされ方は違うので,使用するときの磁場の方向に結晶の容易磁化軸がそろうように加工と焼きなましによって結晶方向をそろえることも行われる。形状としては多く薄板とし,互いに電流が流れないように絶縁して積み重ねて使用されることが多い。
電力用の変圧器,発電機,モーターでは最大透磁率と飽和磁束密度の大きい材料が必要となる。これは強い磁場においたときに強く磁化し,しかもその限度が高いのが良く,また商用周波数で磁場が変化したときに履歴損失が少なく,また,そのとき発生する渦電流による損失が少ないように電気抵抗が高いのが良い。このような条件に合うものは低炭素鋼板とケイ素鋼板であって,電気鉄板と総称される。これらは製鉄所で他の鉄鋼製品と同様な方法で大量生産され比較的安価でもある。とくに,鋼にケイ素を添加すると磁気特性が改善されることが20世紀の初めに発見されて以来,製造方法の改良を通じて不純物や内部の組織の影響が研究され,ケイ素鋼の特性が改善・発展してきた。圧延と焼きなましによって結晶の方向をそろえた方向性ケイ素鋼板もある。一方,通信機用の変圧器の磁心などでは,弱い電場で使用されるので,とくに初透磁率が重要となる。この材料として代表的なものは35~90%Niの鉄合金でパーマロイと呼ばれる。磁性はNiの量によって変化し,用途によって選択される。9.5%Si,5.5%Alの鉄合金はセンダストと呼ばれ透磁率が非常に高い。しかしきわめてもろく加工ができないという欠点をもち,粉末として固めたもの,鋳造のままのものが使われてきた。最近この材料の加工の研究が進み,磁気ヘッド材料として使われている。テレビの電波のような高い周波数で使う磁心材料はとくに電気抵抗が高くないと渦電流による損失が大きくなる。この分野で活躍するのは金属ではなく,ソフトフェライトと呼ばれる鉄の酸化物Fe2O3にさらに他の酸化物が加えられた複合酸化物である。また,最近発展してきている非晶質合金にも高透磁率材料として期待されるものがある。
永久磁石材料
硬質磁性材料とも呼ばれる。この材料は保磁力が大きいこと,(BH)maxの大きいことで特徴づけられ,FeとCoを中心とした合金磁石と化合物磁石に大別される。古くは焼入れした高炭素鋼が磁石として使われたが,やがてW,Cr,Coなどの添加が磁性を改善することがわかってきた。重要な発見は本多光太郎によるKS鋼(Co-Cr-Wを含む高炭素鋼)であり,それ以前の磁石鋼よりもHcと(BH)maxが2倍に向上した。次いで,三島徳七は1931年にFe-Ni-Al3元系の合金磁石MK鋼を発見した。その保磁力はKS鋼の2倍である。この合金はその後の研究によりFe-Co-Ni-Al-Cu5元系のアルニコ系の磁石へと発展し,現在にいたっている。合金磁石の原理はFeあるいはFe-Coの合金をきわめて細く,長い粒子としたときに,その長手の方向に磁化し,磁化の方向がきわめて反転しにくいということである。この粒子を非磁性の物質のなかに分散させることによって優れた磁石材料となる。したがってこの材料の特性は成分だけできまるのではなく,特性を出すように製造工程において内部の組織を都合よくつくり出すことがたいせつであり,そのため鋳造法,熱処理法,ものによっては加工法にいろいろなくふうがある。合金磁石としてはほかにCu-Ni-Fe合金,Fe-Cr-Co合金がある。
化合物磁石はその物質が本来もっている高い磁気異方性を利用するものであり,とくにBaフェライトなどのフェライト磁石,希土類コバルト磁石の発展が著しい。ほかにMnAl磁石などがある。
半硬質磁性材料
ある程度の保磁力があって,残留磁束密度が高く履歴曲線は角形であって,一つの方向へ磁化された状態と反対方向に磁化された状態とがはっきり区別できるものが望ましい。この性質を示すのは永久磁石材料と似た合金である。用途としてはヒステリシスモーターの回転子,継電器やスイッチなどである。また磁気記憶材料も同様の特性を利用する材料である。
磁気記録材料
磁気記録はオーディオカセットテープ,VTR,コンピューターのディスクやテープ,キャッシュ・カードなどに広く応用されているが,小さいものに大量の情報を記録でき,記録と再生が両方とも電気的に比較的容易であり,また記録が不要になれば消してまた別の情報を記録できるといった特徴がある。特性としては保磁力,飽和磁束密度ともに高く,角形の履歴を示すものが良い。磁性粉をテープなどに一様に付けて使用される。材料としてはγFe2O3,二酸化クロム,コバルトを添加した酸化鉄の粉末が広く使われてきたが,最近メタルと称される金属鉄を主成分とする鉄合金の1μm程度の粉末が保磁力,残留磁束密度ともに高く注目され,オーディオテープに使用されるようになった。コンピューターの記憶素子として磁気バブル材料があるが,これは強磁性体の薄膜のなかでの特殊な磁区構造を利用するものである。
磁歪材料
強磁性体には磁化されたときに微小な寸法変化を生じるという性質(磁歪(じわい))がある。この性質の応用としては電気信号を音に変える変換器があり,磁歪振動子と呼ばれる。材料としてはニッケルを含む合金またはフェライトなどが用いられる。
その他の磁性材料
磁性材料は大部分固体であるが,磁性流体と呼ばれる流体がある。これは流体のなかに100Å程度のきわめて細かいマグネタイトの微粒子を分散させたもので,粒子をこのように細かくするとコロイド状態になり,液体と粒子がほとんど分離せず,粒子は浮遊しつづけるようになる。磁性流体は流体自身が磁性をもっているのではないが,強磁性体の粒子のためにあたかも液体が磁性をおびたようにふるまう。その他,光と磁性の相互作用を利用する光磁気記録(MO)の材料など,磁気を利用した電子デバイスが新しい物質の発見とともに発達しつつある。
執筆者:大久保 忠恒
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報