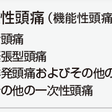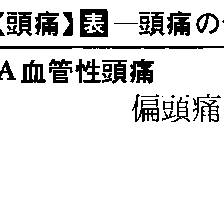精選版 日本国語大辞典 「頭痛」の意味・読み・例文・類語
ず‐つうヅ‥【頭痛】
- 〘 名詞 〙
- ① 頭が痛むこと。また、その痛み。種々の疾患にともなって頭の一部、または全体に痛みを感じる症状。
- [初出の実例]「頭痛すと云て聊に悩む」(出典:今昔物語集(1120頃か)一五)
- 「後白河法皇頭痛(ヅツウ)の御労(おいたはり)」(出典:雑談集(1305)一〇)
- [その他の文献]〔史記‐倉公伝〕
- ② なやんで頭を痛めること。また、そのなやみ。苦労。心配事。
- [初出の実例]「浄土坊主が目には日蓮のあたまが頭痛にさはりていやなも、ただ身がたてたさの事也」(出典:随筆・独寝(1724頃)上)
- 「其を今から頭痛(ヅツウ)に病むでゐるのです」(出典:続珍太郎日記(1921)〈佐々木邦〉六)
とう‐つう【頭痛】
- 〘 名詞 〙 頭の痛いこと。また、その痛み。ずつう。
内科学 第10版 「頭痛」の解説
頭痛(発作性神経疾患)
頭痛
について
頭痛は,「国際頭痛学会頭痛分類第2版」(ICHD-Ⅱ)(日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会,2007)により一次性頭痛と二次性頭痛に分類される【⇨2-48】.二次性頭痛の原因となる疾患については,他項で解説されており,ここでは一次性頭痛を中心に説明する.
(2)片頭痛
(migraine
)
概念
片側性,拍動性の頭痛で,随伴症状として悪心や光過敏・音過敏を伴う症例が多い.発作急性期の治療には,セロトニン受容体アゴニストであるトリプタンを用いることが多い.
分類
さまざまなタイプがあるが大きく「前兆のない片頭痛」と「前兆のある片頭痛」に二分される.
疫学
わが国における15歳以上の片頭痛の有病率は約8.4%(男性3.6%,女性13.0%)であり,その傾向は欧米諸国でも同様で女性が男性に対し約3倍多いと報告されている.
病因・病態生理
片頭痛の病因および病態はいまだに明らかにされていない.片頭痛における前兆には,cortical spreading depression(皮質拡延性抑制)とよばれる現象が関与していると考えられている.頭痛は三叉神経血管系の活性化による脳血管および脳硬膜動脈の拡張や脳硬膜の神経原性炎症に起因するとされている(図15-17-5).
臨床症状
片頭痛は,片側性・拍動性で,中等度から重度の強さをもち,4~72時間持続する頭痛である.また動作による増悪を認め,随伴症状として悪心や光過敏・音過敏を有する.
前兆は5~20分にわたり徐々に進展し,かつ持続時間が60分未満の可逆性脳局在神経症状と定義される.前兆のある片頭痛のなかで視覚症状,感覚症状あるいは言語症状のいずれか1つ以上からなる片頭痛は「典型的前兆に片頭痛を伴うもの」に分類される.視覚性の前兆は最も一般的な前兆で,閃輝暗点として出現する場合が多く,患者は「眼前のチカチカ」と表現することが多い.なお片頭痛に特徴的な他覚症状はない.
診断・鑑別診断
前兆のない片頭痛のICHD-Ⅱの診断基準を表15-17-3に記す.項目B〜Dには発作時間,頭痛の性状および随伴症状などが列挙され,項目Eには二次性頭痛の可能性を鑑別することが記載されている.その他の片頭痛の診断基準についてはICHD-Ⅱ(日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会,2007)を参照されたい.
経過・予後
片頭痛発作頻度の多い症例では,慢性片頭痛への移行が報告されている.慢性片頭痛は,片頭痛の特徴とされる光・音過敏や悪心・嘔吐などが減少し,拍動性の要素はあるがその他は緊張型頭痛に類似した性質の頭痛が月の半分以上かつ3カ月以上の頻度で出現するものである.
治療
片頭痛の薬物療法は,急性期治療と予防療法に分けられる.急性期治療薬としてセロトニン受容体アゴニストであるトリプタン,エルゴタミン製剤および鎮痛薬などが用いられる(日本頭痛学会,2006).わが国で使用可能なトリプタンはスマトリプタン,ゾルミトリプタン,エレトリプタン,リザトリプタンおよびナラトリプタンの5種類である.スマトリプタンは錠剤のほか皮下注射薬(在宅自己注射が可能)および点鼻薬としての投与も可能である.なお「前兆のない片頭痛」および「典型的前兆に片頭痛を伴うもの」では通常トリプタンが第一選択薬となるが,片麻痺性片頭痛や脳底型片頭痛では,トリプタンは禁忌とされている.
予防療法としてカルシウム拮抗薬であるロメリジンおよび抗てんかん薬のバルプロ酸が保険適用となっているが, β遮断薬,抗うつ薬,アンジオテンシン変換酵素阻害薬,アンジオテンシンⅡ受容体阻害薬なども投与されることがある.
(3)緊張型頭痛
(tension-type headache)
概念
圧迫感または締めつけ感を呈する頭痛で,頭頸部筋肉における緊張が関係するとされている.
分類
発作の出現頻度により稀発反復性緊張型頭痛,頻発反復性緊張型頭痛,慢性緊張型頭痛および緊張型頭痛の疑いの4型に分類される.
疫学
わが国での有病率は22.3%(男性18.1%,女性26.4%)とされている.
病因・病態生理
緊張型頭痛の発生機序については不明な部分が多いが,精神的,社会的ストレスが誘因といわれている.その他,不安,抑うつ,神経症などの精神的な因子,姿勢異常,頸椎病変,顎関節異常,眼科疾患など頭頸部の筋肉に緊張を与える病態が影響し緊張型頭痛を引き起こすと考えられている.
臨床症状・診断
両側性に出現する圧迫感または締めつけられる感じをもつ軽度~中等度の頭痛で,日常的な動作による増悪はない.悪心はないが,光過敏または音過敏を呈することがある.緊張型頭痛においても片頭痛と同様に特徴的な他覚症状はない.頻発反復性緊張型頭痛のICHD-Ⅱによる診断基準を表15-17-4に記す.
治療
薬物療法として鎮痛薬(アセトアミノフェン,NSAIDs),筋弛緩薬(塩酸エペゾリン,塩酸チザニジン)および抗不安薬(ジアゼパム)などが用いられる.非薬物療法として頸部指圧,鍼灸,タイガーバーム,催眠療法,頭痛体操などがある.
(4)群発頭痛
(cluster headache
)
概念
片側の眼窩周囲や眼窩に生じる疼痛で群発期と寛解期をもつ.頭痛と同側に流涙・結膜充血・鼻閉・鼻汁などの自律神経症状を伴うことが特徴である.
疫学
群発頭痛の有病率は約0.07〜0.09%とされており片頭痛と比べると少ない.
病因・病態生理
疼痛部位がおもに三叉神経第1枝領域を中心とすることや自律神経症状を呈することから,病変として内頸動脈分岐部遠位から海綿静脈洞付近が想定されている.このような末梢性の病変を視床下部が時間的な調節を行い頭痛が発生するのではないかと考えられている.
臨床症状・診断
片側の眼窩周囲や眼窩など三叉神経第1枝領域を中心に1時間程度続く激しい疼痛で,就寝直後に認められることが多く,毎日のように頭痛が生じる群発期と,頭痛を認めない寛解期がある.激痛のため頭痛発作中はじっとしていることができず,落ち着きなく動き回る症例が多い.これは同様部位に痛みを生じるが,痛みのために安静を保つ三叉神経痛の症例と対照的である.頭痛と同側に流涙,結膜充血,鼻閉,鼻漏,前額部の発汗亢進,縮瞳,眼瞼下垂などの副交感神経機能亢進を示す自律神経症状が出現するため,ICHD-Ⅱ では群発頭痛およびその近縁疾患について,三叉神経・自律神経性頭痛として分類している.表15-17-5
に「群発頭痛」の診断基準を記す.
治療
急性期治療としては,スマトリプタンの皮下注射,純酸素投与(7 L/分で15〜20分間)が有効である.スマトリプタン点鼻薬やゾルミトリプタン経口投与の有効性も報告されており選択肢に考慮してもよい.群発頭痛の発作回数が多い場合予防療法として,カルシウム拮抗薬を用いる場合もある.
(5)
三叉神経痛(trigeminal neuralgia)
概念
三叉神経第2枝および第3枝支配領域に出現する短時間の電撃痛である.
分類
ICHD-Ⅱでは,舌咽神経痛などとともに「頭部神経痛および中枢性顔面痛」に含まれる.血管性圧迫以外の器質的病変が原因となる場合は症候性三叉神経痛,それ以外は典型的三叉神経痛に分類される.
疫学
10万人あたりの年間発症数は4.3人で,男女比は1:1.73と女性に多い.年齢が進むにつれ発症者が増加する.
病因・病態生理
典型的三叉神経痛の原因は,三叉神経のroot entry zoneでの血管による圧迫とされている.
臨床症状・診断
三叉神経支配領域の第2枝および第3枝領域に好発する一側性電撃様あるいは穿刺様の疼痛である.持続時間は数分の1秒〜2分と短い.多くの症例で,顔面の特定の部位に触れると神経痛が誘発されるトリガー域といわれる部位を有する.トリガー域は,口唇・鼻翼・鼻唇溝・頬・歯肉などに認められる.診断はICHD-Ⅱの診断基準に従う(表15-17-6).症候性三叉神経痛の原因には,多発性硬化症や類上皮腫・髄膜腫・神経鞘腫などの腫瘍がありこれらを鑑別する必要がある.
治療
薬物療法が試みられ,不応例に対して神経血管減圧術などの外科的治療が考慮される.第一選択薬はカルバマゼピンであり,その他の選択薬としてはバクロフェン,クロナゼパム,フェニトイン,バルプロ酸などがある.[清水利彦・鈴木則宏]
■文献
日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会訳:国際頭痛分類第2版 新訂増補日本語版,医学書院,東京,2007.
日本頭痛学会編:慢性頭痛の診療ガイドライン,医学書院,東京,2006.
頭痛(症候学)
頭痛は,神経内科のみならず一般内科・総合内科診療において最も頻度の多い主訴の1つである.頭痛の分類は,「国際頭痛学会頭痛分類第2版」(ICHD-Ⅱ)に基づき一次性頭痛,二次性頭痛および頭部神経痛,中枢性・一次性顔面痛の3部に分けられる(表2-48-1)(日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会,2007).
病態生理
頭蓋内において痛みに対し感受性を有する部位は硬膜および血管(内頸動脈,中大脳動脈,前大脳動脈,椎骨脳底動脈,硬膜動脈および静脈洞など)とされている.これらの部位の圧迫および炎症などにより頭痛が生じると考えられている.
鑑別診断
頭痛の診断において大切なことは,表2-48-1に記載されているような二次性頭痛の原因となる疾患を鑑別することである.特に,突然発症した頭痛,いままで経験したことのないような激しい頭痛,50歳以上ではじめて自覚された頭痛,癌や免疫不全など基礎疾患のある患者の頭痛,熱,髄膜刺激症状およびその他神経症状を伴う頭痛などでは生命に影響を及ぼす二次性頭痛が存在している可能性がある.このため,頭痛の性状,部位,発症のしかた,持続時間,頻度,出現する時間,随伴症状などについて詳細な病歴を聴取するとともに,頭部画像検査を施行し鑑別診断をすすめる.症例によっては髄液検査の施行についても検討する.【⇨15-17-2)】[清水利彦・鈴木則宏]
■文献
日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会訳:国際頭痛分類第2版 新訂増補日本語版,医学書院:東京,2007.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「頭痛」の意味・わかりやすい解説
頭痛 (ずつう)
headache
頭痛は臨床上最も頻度の高い訴えで,医師に治療を求める患者の半数以上において認められる。頭痛があっても受診しない患者を考慮に入れると,さらに多くの人がなんらかの頭痛を経験していると思われる。頭痛は頭蓋内外の器質的疾患や感染などさまざまな全身性疾患の部分症状としても起こり,また頭痛そのものが疾患の主要症状であるいわゆる機能性の慢性頭痛も多い。前者には適切な治療を欠くと生命の危険のある疾患もあり,他方後者では遺伝素因が大きく関与したり,不安,緊張などの精神的要因によって起こるものもある。したがって頭痛はつねに注意深い鑑別診断を要し,それを訴える患者の診療にあたっては,医学的診察のみならず,生活環境をも含んだ全人格的立場から接しなければならない。
病態生理
頭痛は頭蓋内外の組織の刺激によって生ずる。頭部における頭蓋外の痛覚感受性組織は,頭蓋の皮膚,頭蓋外の動脈,鼻腔・副鼻腔粘膜,外耳・中耳,歯,頭蓋・顔面・頸部の筋肉などである。これらの障害による疼痛は通常限局しているが,ときにはかなり広範囲のこともある。頭蓋内の痛覚感受性組織は,頭蓋内の静脈洞とそれに注ぐ大静脈,頭蓋底部の硬膜,硬膜動脈,脳底部の動脈とその大分枝,第2・第3頸髄神経,第5・第9・第10脳神経などから成る。
頭蓋内疾患における頭痛の基本的発症機序は,痛覚感受性組織の直接的あるいは間接的牽引,頭蓋内血管の拡張,痛覚感受性組織そのものあるいは近傍の炎症,脳室内圧の上昇による痛覚感受性領域のゆがみ,あるいは腫瘍による脳神経,脊髄神経への直接的圧迫などである。これらの一つあるいはいくつかが組み合わさって作用していると考えられる。頭蓋外疾患における頭痛の機序は,頭皮の血管の拡張,持続的筋収縮および痛覚感受性組織あるいはその近傍の炎症である。
小脳天幕上の組織からの痛みは,第5脳神経を介して前頭部および側頭・頭頂部前方の頭痛として感ずる。天幕下および後頭蓋窩(か)の組織からの痛覚は,舌咽・迷走神経および第2・第3頸髄神経を介して後頭部に頭痛として感ずる。
診断
頭痛が頭蓋内外の器質的疾患による部分症状であるか,あるいは頭痛を主症状とする機能性の頭痛であるかの鑑別は,家族歴や既往歴を含む患者の病歴,頭痛の性状,神経学的検査により比較的容易であるが,頭痛の原因を明らかにすることはしばしば困難である。しかし片頭痛の各型と三叉(さんさ)神経痛は問診だけでほぼ診断がつく。すなわち頭痛についての問診としては以下の項目が必要である。(1)1日のうちいつ頭痛が起こりやすいか,(2)頭痛は持続性か発作性かまたは周期性か,(3)頭痛の強さと性質(ずきずき痛む拍動性,ずーんと痛む圧迫性,きりきり痛む乱切性など),(4)頭痛の部位,(5)頭痛の誘因(疲労,不眠,月経,天候,職業など),(6)薬物の効果,(7)随伴症状(吐き気,嘔吐,閃輝暗点,半盲,視力低下,複視,流涙,鼻汁,角膜や顔面の潮紅など)の有無と頭痛との時間的関係,(8)患者の生活歴,(9)合併症の有無,(10)家系内の類症者など。
発症のしかたについては,突発性の強い頭痛はとくに意識障害や局所的神経症状を伴う場合や,脳出血や髄膜炎などにみられる。高齢者で初発した再発性あるいは持続性の頭痛は,頭蓋の動脈炎,緑内障,頸動脈などの循環不全あるいは高血圧によることが多い。
頭痛の生ずる時間的関係については,高血圧や腫瘍あるいは前頭洞の炎症などによる頭痛は,覚醒時や早朝に多い。これに対して上顎洞の炎症による頭痛はふつう午後に始まり,群発性頭痛は夜間,とくに就眠後間もないころに多い。一般に緊張性頭痛にはこのような関係はなく,朝,覚醒時からあるいはやや遅れて始まることもあるが就眠まで続くことが多い。
部位については,片頭痛はふつう前頭部に多く,2/3は片側性で,患側が一側から他側へと変わる傾向がある。一側に限局した繰り返す頭痛のときは脳腫瘍を考慮しなければならないが,進行して頭蓋内圧が亢進してくると両側性となる。副鼻腔,歯,眼,上部頸椎などの疾患による頭痛は,その病変のある領域に感じられることが多い。
頭痛の性状については,拍動性頭痛は片頭痛,高血圧あるいは発熱などに伴う血管拡張による。神経痛では,一過性のショック様の刺すような激しい疼痛が生ずる。脳腫瘍ではふつう持続的なうずくような痛みであるが,初期には間欠的であることもある。筋収縮性頭痛は,一定の圧迫性あるいは締めつけられるような痛みである。
頭蓋内疾患による頭痛は,なんらかの神経症状を伴うことが普通である。髄膜腫のような腫瘤形成性の病変は頭痛を訴える前に局所症状を呈しやすいが,浸潤性の神経膠腫(こうしゆ)などは大脳半球全体を占めるほどになっても頭痛を訴えないことがある。転移性脳腫瘍もよく頭痛を伴うが,必ずしも激しいものでなく,また一定したものでもない。髄膜癌腫症も頭痛を伴いやすく,何ヵ月も他の症状に先行することすらある。結核菌,真菌あるいは寄生虫などによる慢性の髄膜炎では,頭痛はふつう早期症状である。
日常の生活様式との関係も重要で,頭蓋内の血管の障害に随伴する頭痛は,その原因が二日酔であれ脳腫瘍であれ,頭を急に動かしたり,咳をしたり,いきんだりすることで増悪する。性交は緊張性頭痛および血管性頭痛をもたらすことがあり,ときにくも膜下出血のきっかけとなることも知られている。多くの頭痛は,精神的なあるいは生活環境からのストレス要因によって増悪する。
診察は,頭頸部のみならず全身について行われなければならない。とくに詳細な神経学的検査が重要である。そして必要に応じてX線写真,CTスキャン,MRI,脳波等の特殊検査も行って,正確な診断をつけることが適切な治療のために最もたいせつである。
分類
頭痛は表のように分類される。偏頭痛は,繰り返し起きる拍動性頭痛を特徴とする。機序としては,発作性に生ずる脳動脈の攣縮(れんしゆく)に引き続く外頸動脈系の拡張(血管説),あるいは三叉神経と血管の両動障害が考えられている。最近は神経伝達物質のセロトニンや遺伝子異常などが注目されている。臨床的には閃輝暗点などの前兆が頭痛発作に先行するものと,そうでないものとに大別されるが,後者が多い。随伴症状として悪心,嘔吐などを伴い,数時間持続したのちに,睡眠とともに消失することが多い。緊張性頭痛は,頭部および頸部の諸筋肉の持続的な収縮によって生ずるが,精神的緊張を背景としていることが多い。日常最も頻度が高い頭痛で,慢性の頭痛には多かれ少なかれこの頭痛が関与する。
治療
脳腫瘍,髄膜炎,脳出血,高血圧,眼・耳・鼻・歯・頸椎の疾患など,原因が明らかな場合はその治療を行う。対症的には消炎鎮痛剤や精神安定剤などを用いるが,その頭痛の発症機序を考慮しつつ対応することが必要である。
片頭痛発作に対しては,外頸動脈系の選択的収縮剤のエルゴタミン製剤が用いられる。これは発作の前兆期あるいはごく初期に用いることが重要である。また一般の鎮痛剤や精神安定剤も補助的に使用する。発作間欠期には精神的緊張を避け,過労や不安などの誘因を除去することがたいせつで,このために鎮静剤を用いることもある。
筋収縮性頭痛に対しては,まず精神的緊張をとるようにし,加えて筋弛緩剤,精神安定剤,消炎鎮痛剤などを用いる。頸部のマッサージや温熱療法などの理学療法が有効なこともある。
執筆者:水沢 英洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
家庭医学館 「頭痛」の解説
ずつう【頭痛 Headache】
人間、頭、頭痛――誰もが自然に連想することでしょう。
人間には、頭痛をおこす条件が整いすぎているとさえいえるのです。その条件をあげてみましょう。
私たちは、てっぺんに頭という大きなコンピュータを載せています。その重さを支えるくび(頸)、肩の骨と筋肉の負担は、ほかの動物とは比較にならないほど過重なものです。この過重な負担が、頭痛を誘発することがあります。頭部には、4本の太い血管から大量の血液が送られてきています。この血液をまんべんなく配るために、頭部には、末梢血管(まっしょうけっかん)、毛細血管(もうさいけっかん)の網が緻密(ちみつ)に張り巡らされているので、頭を打ったりすると、そこに多量の血液やリンパ液が集まり、こぶやあざができます。感情が高まると、毛細血管が拡張したり収縮したりして、流れる血液の量が変化し、顔がまっ赤になったり、青くなったりします。この激しい血管の変化が痛みを誘発します(血管性頭痛)。目、耳、鼻、口は、感覚器として反応が鋭敏ですし、粘膜(ねんまく)が直接、外気と接するので、その保護のために知覚神経(ちかくしんけい)がきわめて敏感になっています。このため、ちょっとした刺激で痛みを感じ、頭痛になることもあります。
脳そのものには知覚神経がありませんが、脳を包む髄膜(ずいまく)には知覚神経があって、脳圧の変化、脳の血管の拡張、炎症の発生などの刺激や圧迫に対して敏感に反応します。その結果、頭痛がおこってきます。
まさに、人間に頭痛の種は尽きないのです。
◎医師の診察が必要な頭痛
多くの人が、医師の診察を受けることもなく、経験から自己診断、自己治療でしのいでいます。自分にあった常用薬を準備している人もいます。
しかし、医師の診察が必要な頭痛もあります。
つぎのような状態がみられたときは、医師の診察を受け、原因をはっきりさせて適切な治療を受けるべきです。
●突然おこった激しい頭痛
嘔吐(おうと)があり、助けを求めるほどの危機感をともなう場合、救急車で脳神経外科のある病院へ(救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし)の判断も重要)。
●いつもとようすが異なる頭痛
安静にしていてもおさまらず、常用薬も無効な場合、できれば神経内科へ。
●くり返し、いつまでも続く頭痛
しかも、しだいにひどくなる場合、なるべく神経内科へ。
●目、耳、鼻、歯の症状がはっきり出ている頭痛
それぞれの専門科へ。
●女性特有の頭痛
月経障害(げっけいしょうがい)、性器出血(せいきしゅっけつ)にともなう貧血などによると思われる女性の頭痛の場合、婦人科へ。
◎受診するときの心得
医師は、問診でほぼ決定的な診断が下せます。問診には正しく、はっきりと答えてください。とくにつぎのような事項は重要な情報です。あらかじめメモにして持参するとよいでしょう。
●いつから頭痛がおこったか
何月何日、何時におこったか。または、おこり始めたのは何日前か、何週間前か。
●頭痛のおこり方は
急におこったか、徐々におこったか。
●痛みの強さと経過は
頭が割れるほどひどいのか、軽いのか。だんだん強くなるのか、軽くなるのか。痛み方に波があるか。
●持続時間と頻度は
痛みはどのくらい続いているか。何回もくり返すか。
●痛む部位は
痛むのは、頭の前か後ろか、右か左か、全体か。くびや、うなじにも痛みがあるか。
●どんな性質の痛みか
ずっきんずっきん、がんがんなどと拍動性(はくどうせい)の痛みか。きりきりと鋭い痛みか。じーんと鈍い持続性の痛みか。
●痛む時間帯は
朝と夕方、どちらが痛むか(朝の頭痛は、高血圧、二日酔(ふつかよ)い、てんかん、肺気腫(はいきしゅ)、うつ状態などが原因のことが多い。夕方の頭痛は、緊張型頭痛(きんちょうがたずつう)、眼精疲労(がんせいひろう)などが原因のことが多い)。
●ほかに、どんな症状をともなうか
①発熱(はつねつ)、②鼻汁(びじゅう)、くしゃみ、せき、③めまい、耳鳴り、④吐(は)き気(け)、嘔吐、⑤涙、汗、顔面紅潮(がんめんこうちょう)、⑥手足のしびれ、まひ、⑦けいれん、⑧くびや肩のこり、⑨目のかすみ、複視(ふくし)(物が二重に見える)、⑩まぶしい、⑪意識障害、⑫目の前がちかちか光る、⑬せきや排便(はいべん)の力みで痛みが増強、などのうちのどれかをともなっていないか。
●生活環境、家庭環境は
悩みごとや環境の変化はないか。血のつながった家族のなかに同じような頭痛もちの人はいないか。
●これまでに経験したけが、病気は
頭部外傷(とうぶがいしょう)、脳卒中(のうそっちゅう)、梅毒(ばいどく)、リウマチ性の病気のうちのどれかを、これまでに患ったことはないか。
●持病(じびょう)はないか
とくに高血圧、糖尿病、アルコール依存症、不眠症(ふみんしょう)、神経症(しんけいしょう)、うつ状態のほか、目(とくに緑内障(りょくないしょう))、耳、鼻、歯の病気(コラム「頭痛を誘発する目、耳、鼻、のど、歯の病気」)などの病気にかかっていないか。
●服用中の薬は
現在、服用している薬はないか。あれば申告。また、頭痛薬を使用していれば名称と効果も報告。
◎重症別、頭痛の原因
●緊急入院が必要な頭痛
くも膜下出血(まくかしゅっけつ)、脳出血(のうしゅっけつ)、髄膜炎(ずいまくえん)など。いずれも突発的または急性に頭痛がおこり、嘔吐、意識障害などをともない、重症感がある。髄膜炎(ずいまくえん)は熱が高い。
●入院・検査・治療が必要な頭痛
脳腫瘍(のうしゅよう)、慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)、頸椎(けいつい)の病気など。運動障害や意識障害をともない、比較的慢性的、進行性に経過。その他、目(緑内障)、耳、鼻、歯の病気。
●通院で治療できる頭痛
緊張型頭痛(きんちょうがたずつう)、片頭痛(へんずつう)、群発頭痛(ぐんぱつずつう)、側頭動脈炎(そくとうどうみゃくえん)、心因性(しんいんせい)・精神性頭痛(せいしんせいずつう)(神経症、うつ状態など)。いずれもその症状に特徴があり、問診で診断できる。有効な薬もあるので、痛みを抑えることが可能。
ときに特別な検査や安静、医学的観察のために入院が必要になることも。
●生活習慣の見直しが有効な頭痛
高血圧、糖尿病、睡眠障害、過労、不摂生(ふせっせい)など。
◎慢性頭痛
頭痛がおこりますが、常用薬を飲んだりしてじーっと耐えているうちに痛まなくなります。
しかし、いつの日か、また、同じ頭痛がおこってきます。
頭痛のおこっていない時期は元気で、ふつうの人と同じように支障なく生活できます。
このようなことをくり返す頭痛を慢性頭痛といいます。
かつては、原因不明とされるケースが多く、本人も「自分は頭痛もち」と考えてあきらめている人が多かったのですが、診断技術の進歩によって原因のわかる慢性頭痛が増えてきました。
慢性頭痛で悩まされている人は、神経内科か脳神経外科を受診し、原因を探索してもらいましょう。原因さえはっきりすれば、薬剤の使用など治療によって頭痛から解放されることも夢ではありません。
慢性頭痛には、緊張型頭痛(きんちょうがたずつう)、片頭痛(へんずつう)、群発頭痛(ぐんぱつずつう)の3つがあります。
食の医学館 「頭痛」の解説
ずつう【頭痛】
《どんな病気か?》
〈ストレスや過労、不眠、雨天や飲酒もきっかけに〉
頭痛(ずつう)の原因はさまざまですが、突然嘔吐(おうと)をともなうはげしい頭痛が起こったり、常用薬が効かないような場合には、脳出血(のうしゅっけつ)など重大な病気が隠れていることもあるので、医師の診断が必要です。
頭痛がシグナルになる大病には次のようなものがあります。
(1)くも膜下出血
動脈瘤が大きくなり血管を破ると大量の血液がくも膜下腔に流れ、髄膜を刺激。はげしい痛みに失神することもあります。
(2)脳梗塞
脳の血管がつまり、脳が部分的に機能しなくなる。おもな症状は頭痛、手足などのまひ、言語障害や視力障害などがあげらます。
(3)脳腫瘍
腫瘍が頭蓋内を圧迫するため頭痛が起こる。くしゃみや、頭を振ったり下げたりすると痛むのが特徴。意識障害がでることもあります。
(4)髄膜炎
発熱時にはげしい頭痛が起こる。かぜっぽい症状のほか、嘔吐、けいれん、意識障害などの症状がでることもあります。
(5)脳出血
頭痛の傾向はくも膜下出血と類似しているが、めまいや耳鳴りが多いのが特徴。ときに失神を起こすこともあります。
このような場合には、すぐに病院へ行きましょう。
そうではなく、頭痛の起こっていないときは元気で、起こっても薬を飲んで安静にしているといつしかおさまる、といった状態がくり返し起こることを慢性頭痛と呼びます。
慢性頭痛には筋肉が収縮し、首筋から後頭部にかけてズーンと鈍い痛みが起こる緊張型(きんちょうがた)(筋緊張性)頭痛(ずつう)、脳の血管がいったん収縮して、そのあと過度に拡張するために起こる片頭痛(へんずつう)、季節の変わり目などに集中的に頭痛発作(ほっさ)が起こる群発頭痛(ぐんぱつずつう)などがあります。
また、これらが混在して起こる混合性頭痛(こんごうせいずつう)もあります。
いずれの頭痛も、仕事や対人関係の悩み、不安といった精神的ストレスや過労、不眠などが発作の起こるきっかけとなるほか、雨天などの天候や、飲酒が誘因となることもあります。
《関連する食品》
〈ビタミンEやIPAで脳内の血液循環をよくする〉
○栄養成分としての働きから
慢性頭痛の多くは、血液循環の改善で緩和されることが多いようです。血液循環の改善には、ビタミンEや不飽和脂肪酸のIPA(イコサペンタエン酸)が効果的です。
ビタミンEを多く含む食品には、サバやイワシなどの青背の魚、アーモンドなどのナッツ類、アボカド、カボチャ、そしてホウレンソウなどの青菜類があります。ヒマワリ油、綿実油(めんじつゆ)、サフラワー油、米ぬか油、コーン油などの油にも、ビタミンEが多く含まれています。調理をするときに、これらの油を使うといいでしょう。
IPAは血栓(けっせん)(血液のかたまり)ができるのを予防したり、また脳を活性化する作用もあるといわれ、魚類、とくにカツオやイワシ、サバ、アジなど、青背の魚に多く含まれています。
〈神経伝達物質をつくるトリプトファンをとる〉
神経伝達物質、セロトニンを脳内でふやすことも、頭痛をやわらげるのに役立つのではないかと考えられています。
セロトニンは、必須アミノ酸の1つであるトリプトファンがビタミンB6、ナイアシン、マグネシウムと結びついてつくられます。これらの成分を含む食品をじょうずに組み合わせてとるといいでしょう。
トリプトファンを含む牛乳やチーズ、ビタミンB6を含むマグロ、サンマ、サケ、レバー、緑黄色野菜、ナイアシンを含むカツオ、サバ、ブリ、レバー、マグネシウムを含むアーモンド、ダイズ、ヒジキ、納豆などをバランスよくとりましょう。
トリプトファンからは、ドーパミンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質もつくられます。
また、ナイアシンには片頭痛を軽くする働きがあるので、前述のカツオ、サバ、ブリ、レバーや豆類、ナッツ類などをとるといいでしょう。
〈鎮痛作用のあるミントなども有効〉
頭が痛いときは同時に気分もすぐれないものです。鎮痛作用のあるカモミール、ラベンダー、オレガノ、レモンバームなどのハーブを料理やお茶として摂取すると頭も気分もスッキリします。
スーっとするメントールの香りでおなじみのミントもその1つ。乾燥したミントの葉に熱湯をそそぎ、3分ほど蒸らしたミントティーなどを飲むといいでしょう。
スペイン料理の「パエリア」に使われるサフランも頭痛に効果があります。サフランはアヤメ科の多年草で、雌(め)しべの花柱を乾燥させたものに、鎮痛・鎮静効果があるとされています。ハーブティーとして入手できるほか、料理用のスパイスとしても市販されていますから、頭痛には、これを熱湯にひたして、お湯ごと飲むようにします。
人によってはチョコレートやアルコール類が頭痛の引き金になるので、避けたほうが無難でしょう。
○注意すべきこと
解熱鎮痛剤(げねつちんつうざい)のアスピリン製剤は、ビタミンC強化食品(ジュースやイチゴ、レモンなど)と併用すると、消化管から出血(吐血(とけつ))したり、鼻血がでて止まらないなど、出血しやすくなることがあります。
また、鎮痛剤のなかには、アルコール飲料と同時に飲むと薬の効果が増強されるものがありますので、鎮痛剤を使用中は飲酒しないようにしましょう。
○漢方的な働きから
種を取り除いたウメ干しをこめかみに貼ると頭痛を緩和するといわれ、昔からよく行われています。
葛根湯(かっこんとう)の主薬であるクズ湯にショウガとシナモンを加えて飲むとたいへんよく効きます。
そのほか、長ネギとショウガのスープも効果があります。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「頭痛」の意味・わかりやすい解説
頭痛
ずつう
headache
頭の中に感じる痛みを頭痛といい、頭皮の表面に感じる痛みは頭痛とはいわない。しかし実際には、頭蓋(とうがい)骨の外側にある筋肉・筋膜・動脈・神経などの軟部組織に起因する投射痛を頭の中の痛みとして感じている場合が多く、頭の中には痛みを感受する場所はごくわずかしかない。
頭痛の原因としては、頭蓋内外の血管の異常な拡張および頭蓋筋の持続性収縮によるものが多い。前者による頭痛は血管性頭痛とよばれ、片(へん)頭痛がその代表である。後者による頭痛は筋収縮性頭痛である。これらは機能障害性頭痛ともよばれ、頭痛はそれ自体が一つの疾患とみなされる。頭痛は繰り返しおこり、慢性に経過するのが特徴で、種々の精密検査をしても身体的な原因はみいだしえない。このような頭痛の治療としては、単に鎮痛剤が用いられるだけでなく、片頭痛に対しては発作時には血管を収縮させる作用のあるトリプタン系薬剤やエルゴタミン製剤を用いることが多い。予防には、カルシウム拮抗(きっこう)薬の塩酸ロメリジン、β(ベータ)遮断薬、精神安定剤などが用いられ、また筋収縮性頭痛に対しては筋弛緩(しかん)作用をもった精神安定剤や抗うつ剤などが用いられる。日常生活では精神的な緊張を避け、過労にならないよう注意する。筋収縮性頭痛では軽い体操、頸部(けいぶ)筋のマッサージ、入浴などが効果がある。また、かぜ、高熱、二日酔い、血圧異常などの際みられる急性頭痛も血管が拡張するためにおこり、機能障害性頭痛に含まれる。
このほか、頭痛の原因には、頭蓋内の器質的な病気、眼・耳・鼻・歯疾患など頭蓋外の病気などがある。頭蓋内の器質的な病気のうち、脳腫瘍(しゅよう)や脳出血のように頭蓋内の一定の空間を占拠するような病気による頭痛は、頭蓋内にある血管、神経、硬膜の一部など痛覚感受部位が圧迫、牽引(けんいん)されておこり、牽引性頭痛とよばれる。これに対して髄膜炎など炎症による頭痛は炎症性頭痛といい、頭蓋内外の痛覚感受部位が刺激を受けておこる。一方、眼・耳・鼻・歯疾患による頭痛は、三叉(さんさ)神経、舌咽(ぜついん)神経、迷走神経などを介する投射痛となるが、頭蓋筋の持続的収縮も関与する。このようななんらかの病気の際にその症状の一つとして現れる頭痛では、治療の対象となるのは頭痛の原因疾患で、それが治れば頭痛も消失する。とくに「脳腫瘍」「脳出血」「くも膜下出血」「髄膜炎」「硬膜下血腫」など生命にかかわる原因疾患は重要である。関連する疾患の項目を参照されたい。
[海老原進一郎]
百科事典マイペディア 「頭痛」の意味・わかりやすい解説
頭痛【ずつう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「頭痛」の意味・わかりやすい解説
頭痛
ずつう
headache
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「頭痛」の読み・字形・画数・意味
【頭痛】とうつう・ずつう
字通「頭」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
栄養・生化学辞典 「頭痛」の解説
頭痛
世界大百科事典(旧版)内の頭痛の言及
【頭】より
…〈首〉の項目を参照。 頭痛は脳または脳膜の症状であるが,英語でheadache,ドイツ語でKopfschmerz,フランス語でmal à la têteとすべて頭で代用する。ケルススもcapitis doloresとラテン語の頭の語を使った(《医術について》)。…
【頭】より
…〈首〉の項目を参照。 頭痛は脳または脳膜の症状であるが,英語でheadache,ドイツ語でKopfschmerz,フランス語でmal à la têteとすべて頭で代用する。ケルススもcapitis doloresとラテン語の頭の語を使った(《医術について》)。…
※「頭痛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...