改訂新版 世界大百科事典 「アヘン」の意味・わかりやすい解説
アヘン(阿片) (あへん)
opium
ケシPapaver somniferum L.の未熟の果実に傷をつけ,浸出してくる白色乳液が空気に触れ,乾燥して黒色をおび,固形となったもの。産地によって形状が異なり,300~700gくらいの重量のもち状,球円状,円錐状の形にして商品にされる。
作用の本体となるのは全量の約25%を占める20種以上のアルカロイドであるが,これらは化学的には次のように二つに大別される。一つはフェナントレン骨格をもつモルヒネ(10~16%),コデイン(0.8~2%),テバインthebaine(0.5~2%)であり,他の一つはイソキノリン骨格をもつパパベリンpapaverine(0.5~2.5%),ノスカピンnoscapine(ナルコチンともいう。5~7%)で,これ以外のアルカロイドの含量はきわめて低く,ほとんどが0.01%以下である。アヘンの作用の主体はモルヒネで,一般に中枢神経系に対する抑制作用の結果としての鎮痛・鎮静・鎮咳(ちんがい)のほか,消化管の蠕動(ぜんどう)運動抑制による止瀉(ししや)(下痢止め)作用が臨床的に応用されている。モルヒネ単独よりも含有されている各種アルカロイド類の協力作用があることと,副作用が比較的少ない点で賞用される。副作用としては,個人差が大きいが,頭痛,めまい,便秘,皮膚疾患,排尿障害などがある。日本薬局方には,アヘン末,塩酸アヘンアルカロイド,アヘンチンキのほか,去痰薬のトコン末と配合した鎮咳去痰薬として用いるアヘン・トコン散,気管支・唾液などの分泌を抑制し,心臓・胃腸などの機能も抑制するアトロピンあるいはスコポラミンを併用し,薬効の相乗作用を期するとともに副作用の軽減をねらったアヘンアルカロイド・アトロピンおよびアヘンアルカロイド・スコポラミン注射液などが記載されている。これら抗コリン作用薬の併用は,外科手術時の麻酔薬の量を減らし,精神的な安静,新陳代謝の抑制,分泌抑制による手術の安全と術後合併症の予防などを目的としている。アヘン製剤はいずれも麻薬で,依存性を有するため,激痛に対する応急処置や頑固な下痢や咳に用いるほかは,連用を避けることが望ましい。
執筆者:金戸 洋+新田 あや
アヘンの東漸
英語のopiumの語源はギリシア語で〈汁〉〈ケシの液〉を意味するopionで,現在の欧米語はこれに起源する。プリニウスの《博物誌》では,催眠・鎮痛の作用にふれ,習慣性があるから〈倦怠をともない,ついには短命に終わらせる〉とある。アラビア語ではアフユーンafyūnと称し,13世紀のアラブ系植物学者イブン・アルバイタールは〈アフユーンはオリエントでも西洋でも知られず,ただエジプトに産するのみで,ここから各地に送られる〉と述べている。
このアフユーンが,16世紀以降,ポルトガル人などの東方貿易によってアジアにもたらされたことは,アルブケルケ,リンスホーテン,バレンティンらの記録にある。アフユーンは漢字では〈阿芙蓉〉(《本草綱目》穀部第23巻)と音訳されるが,やがて〈阿片ā piàn〉〈鴉片yā piàn〉の表記が主流になるのは,主要産地インドではopiumと呼ばれ,そのpの音が残ったものと思われる。なお鴉片の鴉は,黒褐色(ボール状になったアヘンの色は黒砂糖に似ている)の色からとられたものであろう。
東インド会社とアヘン貿易
薬用に限定されていたアヘンが,大規模に商品として生産・販売されるようになり,麻薬と化すようになったのは,18世紀後半,イギリス東インド会社が植民地インドでケシ栽培,アヘン生産の専売制を開始し,これを中国向けに輸出しはじめてからのことである。こうしてアヘンは,中国からイギリスへの茶,イギリスからインドへの機械製綿製品という輸出商品とともに,19世紀のアジア三角貿易における不可欠の商品となった。
イギリス東インド会社は,1600年に特許商社として生まれたが,1773年の特許(チャーター)更新に際して,イギリス政府の監督権が規定され,インドにおける総督制が発足したことによって,商社とともに植民地インドの公権力という二つの性格をもつようになった(1858年,東インド会社の廃止にともない,商社活動は終わり,植民地の公権力はインド政庁に継承された)。
総督制の発足と同時に,塩,硝石とならんでアヘンも専売制とし,国内消費を禁止して,もっぱら輸出にあてた。1897年には専売制を強化して,ベンガル大管区のビハール,ベナレス(ワーラーナシー)の2州にケシ栽培を制限,東インド会社(以下,会社と略称)直営の精製工場を一つずつ建てて混ぜ物を防ぎ,ここで乾燥・梱包(1箱に約64kg)をし,ガンジス川を船で運搬して,カルカッタの会社倉庫に収めた。会社は輸出に関与しないという政策をとったため,カルカッタにおいて輸出業者に競売によって売り渡した。これが専売制によるベンガル・アヘンで,産地名をとってベナレス・アヘン(中国名は喇荘土)とパトナ・アヘン(公班土)に大別される。
特定の認可農民にケシ栽培をやらせた会社は,作付けの前に半分の前渡金を渡し,ジュースを採取し,ボール状(小児の頭ほどの大きさ)に固めて会社に納品させたときに,残金を農民に支払った。1箱分に換算すると,会社が農民に支払う金額が300ルピー,カルカッタの競売の値が1200~1500ルピーであるから,その差額から倉庫代,梱包代,運送費など若干の経費と人件費を除き,残りがすべてアヘン専売収入となる。アヘン専売収入は,19世紀を平均して,植民地インドの歳入の約17%と高い比率を占めた。
ベンガル地方のほかに,直轄領に入らない中央インドの藩王国でアヘン生産が盛んになったのは,19世紀に入ってからである。これはマルワ・アヘン(中国名は白波土)と呼ばれ,輸出港はカルカッタではなく西海岸(初めポルトガル領のディウ,やがてイギリス領のボンベイ)であった。マルワ・アヘンに対して会社は専売制をとることができず,内陸運搬ルートの安全を確保することによって〈通過税〉のみを歳入として確保した。地味のやせた中央インドでは最良地を使ったため(ケシは地力収奪型の作物で,高度の施肥と灌漑によって連作が可能となる),生産費は1箱あたり約600ルピーであったが,これに通過税を加算した輸出価格は800ルピー前後で,ベンガル・アヘンよりはるかに安く,中国市場ではマルワ・アヘンの割合が高くなった。
アヘン戦争
インドから輸出されたアヘンの約85%は中国へ,あとの15%はペナン,シンガポールを経てオランダ植民地インドネシアなどへ転売された。これらの植民地で輸入されたアヘンは,いちど植民地政府の手に入り,それが特定の請負人に売却され(ライセンスが発行される),両者の差額が植民地政府の大きな財源となった。中国への輸出は,清朝の禁令のため,広州に陸揚げできず,広州湾の金星門や伶仃島に躉船(とんせん)(アヘンを貯蔵する船)を浮かべ,そこで中国人商人とおもに銀で取引を行って輸出した。ジャーディン・マセソン商会,デント商会が二大商社であった。
アヘン輸入に反対する欽差大臣林則徐は,外商のアヘンを没収,これが原因でアヘン戦争(1840-42)となり,戦勝国イギリスは南京条約を結ばせたが,このなかにアヘン輸出を明記しえなかったため,アヘンは依然として公然たる密輸商品であった。1844年のアメリカ・清朝間の望厦条約ではアヘン禁輸条項を明記したが,イギリスが認めず,アメリカ商人も均等待遇を主張して,禁輸の拘束をまぬがれ,貿易量は急増した。南京条約で香港がイギリスに割譲され,ここが大きなアヘン輸入基地となり,さらに開港した5港の近くに南墺(ナモア)や呉淞(ウースン)などの輸入基地が作られたことも,輸入急増の大きな要因となった。
第2次アヘン戦争(1856-60)の中間で結ばれた天津条約(1858)の税則で,アヘンに1箱あたり30テールの関税を課すことが決められ,これによってアヘン貿易は〈合法化〉され,アヘンの名は〈洋薬〉と改名された。インド産アヘンの中国輸出のピークは,価格でみると1880年であり,20世紀に入って国際的な反対が強まるまで続いた。日本へは長崎出島の会所貿易で薬用として少量入っていたが,開港を決めた日米修好通商条約(1858)の4条に〈アヘン禁輸〉がアメリカ側の主張で明記されたために,アヘン禍をまぬがれることができた。
→アヘン戦争
アヘン禍とその対応
アヘンはまた19世紀のイギリス,フランスなどでも大流行した。中国では吸煙がおもな形態であったが,イギリスでは液体のアヘンチンキがおもな形態で,規制の法律(毒性薬物法Dangerous Drug Act)ができる1920年まで,おもにトルコから輸入されたアヘンを原料として全国に出回っていた。T.ド・クインシー《阿片常用者の告白》(1822)やC.ボードレール《人工の楽園》(1860)ではアヘンよりアルコールのほうが害が大きいとし,アヘンは空想力を高めると述べている。
アヘンの害毒が認識され,アヘン生産および貿易を国際的に禁止,制限しようという運動がおこり,1909年,アメリカ大統領の提案にもとづいて上海で国際アヘン会議(参加13ヵ国)が開かれ,勧告が出された。この勧告は,12年のハーグ会議における第1回アヘン条約の基礎となったが,これはアヘンの生産にふれず,貿易のみを禁止したもので,そのうえ批准国が少なかった。第1次大戦後のパリ講和会議の議決によって,27年には批准国がやっと50ヵ国に達した。
ついで31年,国際連盟の規約にもとづいて国際アヘン条約が作られ,ここにおいてアヘン生産の制限,利用は医療・学術面に限定すること,年間のアヘン必要量の概算義務制度が盛り込まれた。ただし日本は批准しておらず,中国東北地方(旧満州)では相当量のアヘンを密造していた。
第2次大戦後,国連が国際的なアヘン制限の仕事を継承し,麻薬委員会を発足させて,61年には,アヘンを含む麻薬取締りの単一条約Single Convention on Narcotic Drugが採択された。67年,世界のアヘン合法生産量は778tまで減少したが,その後は毎年の増減が激しく,78年には約1800t,80年には約1100tである。ちなみに19世紀中葉においては,インド産アヘンのみの輸出量が年間約4000tであった。これには東南アジアの一部など非合法生産分は含まれていない。おもな合法生産国はインド,イランなどで,おもな消費国はアメリカ,旧ソ連などである。消費量は生産量より少ないので,在庫が増えている。
執筆者:加藤 祐三
アヘン中毒
中毒とは毒物によって引き起こされた病的状態をいい,アヘンの場合も,その摂取によって起こる急性と慢性の中毒がある。急性中毒では,呼吸抑制,縮瞳,チアノーゼ状態となり,昏睡から呼吸麻痺の結果死に至る。しかし,アヘン中毒といえば,一般には慢性的なアヘン使用の結果として形成される依存のため,その摂取をやめられず,生理的機能が障害された状態,すなわち慢性中毒をさす。アヘンは本来,胃痙攣(けいれん),胆石のほか負傷など,他の鎮痛薬では抑えられないような激しい痛みに対して,鎮痛の目的で用いられるが,この薬のもつ不快感・不安感を除き,陶酔的で多幸性の気分をまねく作用も加わり,しだいに用量が増え,習慣になり,1日量1~2gにも達し,いわゆる耐性・依存の状態に陥る。この状態ではその摂取を中止すると,不快な禁断症状をきたすため,摂取がやめられなくなる。また,意志もいちじるしく弱くなり,高等感情も低下する。全身的に栄養状態が悪くなり,食欲・性欲も減退する。治療としては,病院に隔離して摂取を中止させ,持続睡眠(長時間眠らせる療法)や依存性の弱い薬物に代えて徐々に離脱させる方法などがとられる。中毒者の母親から生まれる新生児が中毒で,出生後禁断症状が発現する例が報告されている。
→薬物依存
執筆者:金戸 洋
アヘンについての法的規制
日本の法的規制は,主として〈あへん法〉(1954公布)によって行われている。〈あへん法〉は,医療・学術研究用のアヘンを確保するとともにアヘンの乱用を取り締まるため,(1)許可制のもとで,ケシの栽培,アヘンの採取・所持を認め,(2)アヘンの輸出入・買取り・売渡しを国の専属権限としている。それ以外の,ケシの栽培,アヘンの輸出入・採取・譲渡・譲受け・所持・吸食は禁止され,その違反に対しては最高15年の懲役刑が科される。〈あへん法〉の対象には,生アヘンとその加工物であるアヘン煙膏が含まれるが,医薬用加工アヘンは麻薬取締法(麻薬)の規制対象とされている。他方,刑法は阿片煙および阿片煙吸食器具の輸入・製造・販売・所持等を処罰しているが(136~141条),〈あへん法〉のほうが法定刑が重いため,吸食器具に関する罪を除いてほとんど適用の余地がなくなっている。〈あへん法〉の違反は,観賞目的によるケシの不法栽培を除くと,ごく少数にとどまっているのが現状である。
→薬物犯罪
執筆者:佐伯 仁志
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報


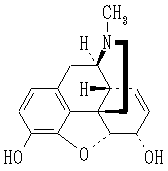 モルフィンともいう。アヘンの主成分で,産地によって異なるがアヘンに9~14%含まれる。モルヒネは1805年ドイツの薬剤師
モルフィンともいう。アヘンの主成分で,産地によって異なるがアヘンに9~14%含まれる。モルヒネは1805年ドイツの薬剤師