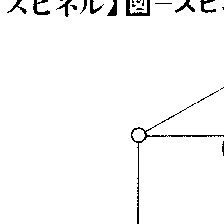翻訳|spinel
精選版 日本国語大辞典 「スピネル」の意味・読み・例文・類語
スピネル
改訂新版 世界大百科事典 「スピネル」の意味・わかりやすい解説
スピネル
spinel
尖晶石ともいう。化学組成MgAl2O4の鉱物。立方晶系に属する。八面体結晶が最も一般的で,まれに六面体や十二面体結晶も存在する。赤,青,緑,茶色の透明結晶,また不透明結晶も産する。赤色の美麗なものはスピネルルビーという宝石になる。{111}を双晶面とするスピネル双晶をしばしば示す。へき開はないが裂開が見られる。モース硬度7.5~8,比重3.581。結晶質石灰岩,片麻岩,蛇紋岩,カンラン岩中に産出する。RM2X4のスピネル型構造をもつ鉱物や化合物は図に示すように,単位胞中に32個の陰イオンがほぼ立方最密充てんをしている。その隙間に64個の四面体と32個の八面体が存在し,前者の1/8,後者の1/2に陽イオンが存在する。化合物としてR2⁺M23⁺X42⁻,R4⁺M22⁺X42⁻,R6⁺M21⁺X42⁻,R2⁺M21⁺X41⁻など多種の電荷をもつイオンが存在する。またR[M2]X4の正スピネル型,M[R,M]X4の逆スピネル型,その中間型など,陽イオンの分布により多種多様な化合物がある。陰イオンにより,酸化物以外に硫化物のチオスピネル,ハロゲンスピネル,カルコゲンスピネルが存在し,30種以上の鉱物が記載報告されている。また磁性体をはじめ,多くの工業材料となり,250種ほどの合成化合物が報告されている。
執筆者:山中 高光
宝石
スピネルはミャンマー,スリランカなどの主要産地において,ルビーやサファイアとともに産し,古い時代には区別することなく取り扱われていた。そのため,スピネルがルビー,サファイアの名で著名な古い財宝の中に入り込んでいる例は数多い。たとえば,イギリス王室の第1公式王冠の正面に世界第2位の大きさのダイヤモンド(カリナン第2石,317カラット)と肩を並べてセットされている歴史的に有名な〈黒太子のルビー〉や同王室所蔵の〈ティムール・ルビー〉は,実はレッド・スピネルである。スピネルの名の由来は棘(とげ)を意味するラテン語のspinaが起源であろうといわれる。またスパーク(閃光)の意味のギリシア語スピンタリスspintharisから由来したともいわれる。色は豊富で,赤,ピンク,赤紫,青,緑,紫,橙色,褐色,無色(微色を帯びる)などがあり,ときにスター効果を示すスター・スピネルの産出もある。合成スピネルは,ルビー,サファイアと同様,フランスのベルヌーイA.V.L.Verneuilによって発明された火炎溶融法によって製造されている。
執筆者:近山 晶
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「スピネル」の意味・わかりやすい解説
スピネル
すぴねる
spinel
尖晶石(せんしょうせき)という名称も同義語として用いられる。スピネル系鉱物の総称をさす場合と、その一員である狭義の単一鉱物種スピネルをさす場合とがある。混乱を防ぐ場合には、後者を苦土スピネルあるいは苦土尖晶石という。スピネルは、熱変成を受けた苦灰岩、ケイ酸分に乏しい粘土質の堆積(たいせき)岩、超塩基性岩、塩基性岩中などに産する。自形は正八面体を基本としたもので、これを基体とした反覆双晶(スピネル双晶)をつくることがある。日本の産地としては、岐阜県揖斐川(いびがわ)町春日(かすが)鉱山(閉山)、大分県宇目(うめ)町(現、佐伯(さいき)市宇目)木浦(きうら)鉱山(閉山)などが有名。透明なものは研磨して宝石として用いられることもある。とくに赤色のものはルビーの代用品として用いられる。語源は、ラテン語の「小さなとげ」を意味するスピネラに由来する。
[加藤 昭 2017年8月21日]
スピネル(データノート)
すぴねるでーたのーと
スピネル
英名 spinel
化学式 MgAl2O4
少量成分 Fe2+,Mn,Zn,Fe3+,Ti,V3+,Cr
結晶系 等軸
硬度 7.5~8
比重 3.58
色 灰,淡紫,紅,緑,淡褐
光沢 ガラス
条痕 白
劈開 無
(「劈開」の項目を参照)
化学辞典 第2版 「スピネル」の解説
スピネル
スピネル
spinel
尖晶石ともいう.狭義には,アルミン酸マグネシウムMgAl2O4をさす.鉱物として広く変成岩中に産出する.ラテン語のspina(イバラ)から命名されたという.立方晶系に属し,天然産で純粋に近いものは格子定数 a = 0.8080~0.8086 nm.密度約3.55 g cm-3.融点約2135 ℃.MgOとAl2O3の粉末を混合し,1500 ℃ 程度で加熱すれば容易に焼結体として合成される.広義には,Mg2+ あるいは Al3+ を種々の金属が置換した酸化物固溶体の一般名として用いられる.[別用語参照]スピネル型構造
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スピネル」の意味・わかりやすい解説
スピネル
spinel
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「スピネル」の意味・わかりやすい解説
スピネル
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新