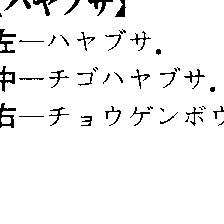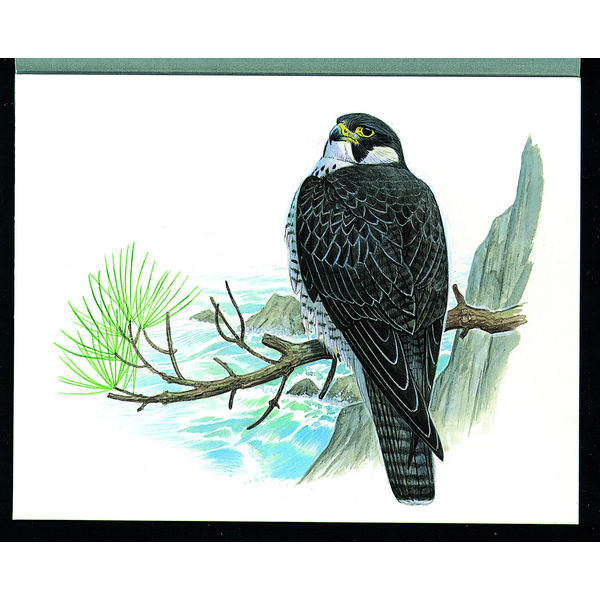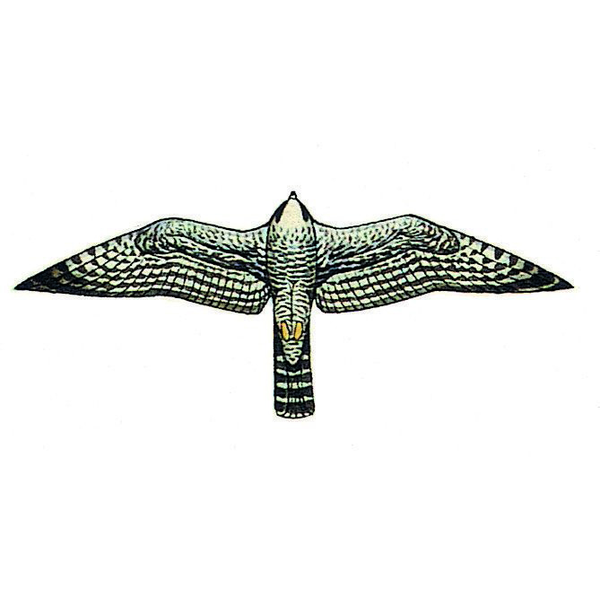月惑星探査に必要なイオンエンジンと自律航法の技術実証、および小惑星探査と表面物質の地球への持ち帰りを目的とした日本の小惑星探査機の小惑星探査技術実証機。大きさは1メートル×1.6メートル×2メートルほどで、質量は510キログラム(含燃料)。宇宙航空研究開発機構(JAXA(ジャクサ))の開発による。
「はやぶさ」(プロジェクト名MUSES-C)は、2003年5月9日に打ち上げられ、新開発のイオンエンジンによる微小な加速を蓄積して航行し、2005年9月に目標の小惑星イトカワに到達した。そして小惑星の形状、表面状態などの近接撮影、重力場測定などを行い、科学データを地球へ送信した。同機は2005年11月、世界で初めて小惑星への着陸および離陸に成功した。接地時における表面物質採取装置の稼働は確認できなかったが、離陸後、地球への帰還軌道への投入と軌道制御に成功した。2010年6月13日に地球大気圏に再突入し、資料回収カプセルをオーストラリアの計画地点へ軟着陸させた。11月にはカプセル内の微粒子がイトカワ由来のものであることが明らかになった。
「はやぶさ」は、世界初の小惑星サンプルリターンを目指す探査機として打ち上げられ、革新技術によるイオンエンジンを使う高効率飛行で小惑星の軌道に到達し、イトカワと並行して公転しながら観測および着陸接地を行った。同機により、イオンエンジンの長期運用、および、電波指令が大きく遅延する超長距離にある自動航法システムの複雑な作動が成功したことで、惑星空間での探査機の長期にわたる複雑かつ柔軟な運航が可能であることが実証された。太陽を背にして小惑星の表面に映った自機の影を写し込んだ写真は有名である。
「はやぶさ」の7年間にわたる小惑星往復航行の経過は以下の通り。
2003年5月9日 内之浦宇宙空間観測所からM-Ⅴロケットによって打ち上げられる。
2004年5月 地球スイングバイ(天体の重力を利用した軌道変更)に成功。
2005年9月12日 小惑星イトカワに到達。イトカワからの距離が20キロメートルの空間に静止。
9月30日 イトカワから7キロメートルの距離まで降下。
11月20日 「はやぶさ」第1回目のイトカワ着陸。後のデータ解析により、6時10分ごろ「はやぶさ」が着陸していたことがわかる。「はやぶさ」は2回のバウンド(接地)を経て、約30分間イトカワ表面に着陸。世界初の小惑星への軟着陸に成功。その後、地上からの指令でガスジェットを噴かして上昇。
11月25日 第2回目の着陸。3回目の接地に成功。その後、地表面に鉛直上方に離陸上昇。
12月8日 再度の燃料漏れが発生。燃料等のガス噴出によると思われる外乱により、探査機の姿勢を喪失。地上の管制センターと探査機の交信がとだえる。「はやぶさ」は姿勢喪失のため、太陽電池発生電力が極端に低下し、いったん電源が完全に落ちたもよう。
2006年3~4月 探査機内に漏洩(ろうえい)した揮発性ガスの排出を行う。
5月 イオンエンジンの起動試験に成功。
7~9月 放電してしまったリチウムイオン電池の再充電を行う。リチウムイオン電池は帰還カプセルの外蓋(そとぶた)を閉めるのに必要。
2007年1月 探査機内の試料採取容器を地球帰還カプセルに搬送収納し、帰還カプセルの外蓋を閉める。
2月 イオンエンジンの運転のための新しい姿勢制御方式を採用、試験を実施。
3月 イオンエンジンの試験運転を行う。
4月 地球への帰還に向けたイオンエンジンの巡航運転を開始。イトカワの軌道を離脱。
2010年6月13日 地球に帰還。地球大気圏に再突入し、オーストラリアの砂漠への軟着陸に成功。資料回収カプセルが回収された。
11月 回収された約1500個の微粒子(ほとんどが大きさ10マイクロメートル以下)を調べた結果、微粒子の鉱物種と成分割合が隕石(いんせき)の特徴と一致し地球の岩石とは合わない、「はやぶさ」が観測したイトカワ表面の鉱物成分のデータと一致した、回収された資料容器内に地球上の一般的な岩石は見つからなかったことから、帰還カプセルに入っていた微粒子はイトカワ由来のものと判明した。小惑星の粒子の採集は世界初の快挙である。なお、「はやぶさ」のサンプル採取装置は故障して作動しなかったが、着陸の衝撃でイトカワの表面物質を飛散させた結果、帰還カプセル容器内部に微粒子を付着させることができた。
[岩田 勉]