関連語
精選版 日本国語大辞典 「兎」の意味・読み・例文・類語
うさぎ【兎・兔】
- 〘 名詞 〙
- ① ウサギ科の哺乳類の総称。また、イエウサギの呼称。耳が長く、後ろ足は前足より長い。口には長いひげがあり、上唇は縦に裂けている。草食性で繁殖力が強い。アンゴラ、チンチラ、日本白色種などのイエウサギは、ヨーロッパ原産のアナウサギを家畜化したもの。野生のものにノウサギ、ユキウサギ、アマミノクロウサギなど一一属四二種がある。肉は食用に、毛は羊毛とまぜたり筆の材料にしたりする。う(兎)。おさぎ。《 季語・冬 》
- [初出の実例]「菟頭骨菟竅〈略〉和名宇佐岐」(出典:本草和名(918頃))
- 「くすしも女もうさぎの血を師子の血とまうして」(出典:法華修法一百座聞書抄(1110)六月一九日)
- ② 紋所の名。兎の形を模様にする。マムキウサギ、ミツコウリンウサギなど種々ある。
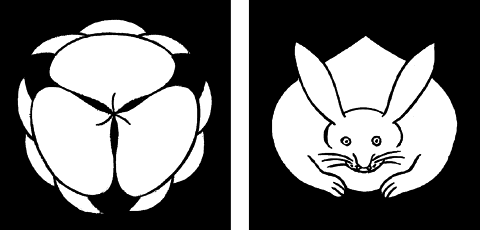 三つ尻合わせ兎@真向き兎
三つ尻合わせ兎@真向き兎
- ③ 寝すごして約束の時間に遅れる者。〔東京語辞典(1917)〕
兎の語誌
「古事記‐上」「因幡風土記逸文」には、鰐を騙す狡猾な側面と、騙した相手に報復される無力な姿とが対照的に描かれる。仏典に典拠を持つ「今昔‐五・一三」には、帝釈が化した老人をもてなすために、兎が我が身を焼いて供する説話が見える。死後兎はその誠実さをたたえられ月に住むことになるが、この説話は講経談義の場においてさかんに語られ、「月の中で兎が餠をついている」という伝説はこれらを通じて流布されたらしい。
う【兎・菟】
- 〘 名詞 〙 「うさぎ(兎)」の古いいい方。
- [初出の実例]「露を待つうの毛のいかにしをるらん月の桂の影を頼みて」(出典:拾遺愚草(1216‐33頃)上)
兎の補助注記
「書紀‐斉明五年三月」に「問菟、此をば塗毗宇(トヒウ)と云ふ。菟穂名、此をば宇保那(ウホナ)と云ふ」とあって、「菟」字は「ウ」と訓んでいる。
おさぎをさぎ【兎】
- 〘 名詞 〙 ( もとは「うさぎ(兎)」の上代東国方言か ) =うさぎ(兎)
- [初出の実例]「等夜(とや)の野に乎佐芸(ヲサギ)窺(ねら)はりをさをさも寝なへ児ゆゑに母に嘖(ころ)はえ」(出典:万葉集(8C後)一四・三五二九)
うさ【兎】
- 〘 名詞 〙 うさぎ。
- [初出の実例]「何が故ぞ、菟(ウサ)の角を生ぜざる」(出典:大般涅槃経治安四年点(1024)八)
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

 〈ト〉
〈ト〉 〈うさぎ〉「
〈うさぎ〉「

