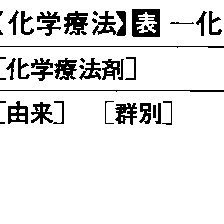翻訳|chemotherapy
精選版 日本国語大辞典 「化学療法」の意味・読み・例文・類語
かがく‐りょうほうクヮガクレウハフ【化学療法】
- 〘 名詞 〙 化学的な薬品や抗生物質を用い、病原微生物などを殺滅、抑制する治療法。
- [初出の実例]「化学療法で治して肺を生かしたほうがいい」(出典:蟹(1963)〈河野多恵子〉)
改訂新版 世界大百科事典 「化学療法」の意味・わかりやすい解説
化学療法 (かがくりょうほう)
chemotherapy
化学療法とは,創始者P.エールリヒによれば,化学物質を用いて人体や動物体内に侵入した病原体を殺す原因療法と定義される。そして,そのような物質(化学療法剤)は,人体には無害で病原体にのみ選択的に毒性を発揮するものであり,消毒薬のように,いずれにも有害であるため,体外での使用しかできない薬剤とは根本的に異なる。化学療法はL.パスツールやR.コッホによって確立された病原微生物学の上に発展したものであり,エールリヒの選択的毒性の概念は,彼自身の研究経験である細菌の色素親和性や免疫現象における特異性の問題にそのヒントを得ている。しかし現在では,癌に対しても化学療法が試みられ,この言葉の適用範囲は必ずしも感染症にとどまらなくなった。また,感染の可能性のあるとき,予防のために前もって化学療法剤を投与することがあるが,これは予防内服とか化学予防と呼ばれている。化学療法は,20世紀における医学の最大の成果であって,各種急性伝染病のみならず,結核症,性病など長年人類を苦しめてきた感染症を急速に制圧した。
化学療法剤の開発史
上記のような考え方で研究を開始したエールリヒは1904年,まずトリパン赤というアニリン色素でトリパノソーマ(アフリカの睡眠病の病原虫)に感染したマウスの治療に成功した。ついで彼と秦佐八郎は多数の有機ヒ素化合物を系統的に合成し,それらの実験梅毒に対する効果を一つずつしらべた。606番目の合成品に至って,これが最も毒性が弱く効果の高いことが発見され(1910),サルバルサンと命名されて臨床にも使用されることになった。こうした方法によって,原虫や梅毒トレポネマに対する化学療法はその後も発展した。しかし細菌に対する有効物質は,ドイツのG.ドーマクがスルファニルアミドクリソイジン(商品名プロントジル)を用いて溶血性連鎖球菌によるマウスの敗血症の治療に成功する(1935)までは得られなかった。まもなく,このプロントジルの有効成分は体内で分解されて生ずるスルファニルアミドであることがわかり,以後今日まで,その誘導体は数千種以上も合成され,そのうちサルファ剤の総称で各種細菌性疾患の治療に用いられてきたものも多数に及ぶ。このドーマクの発見に先だつ1929年,イギリスのA.フレミングは,たまたま寒天培地上の黄色ブドウ球菌の集落が,その周辺にできたアオカビの集落によって溶けることを観察し,アオカビの培養濾液の中に各種細菌の発育を阻止する物質(ペニシリン)のあることを報告した。10年後,この報告から出発してイギリスのチェーンErnst B.Chain(1906-79)とフローリーHoward W.Florey(1898-1968)は,ペニシリンの再検討と実用化にのり出し,さらにアメリカの協力を得て工業生産にも成功した(1941)。たまたま重症の肺炎にかかった当時のイギリス首相チャーチルが,ペニシリンによって生命を救われたのは有名なエピソードとなった。一方,このころ土壌微生物間の拮抗現象(生存競争)の研究に従事していたアメリカのS.A.ワクスマンは,ペニシリン発見の報にも刺激され,土壌放線菌の代謝産物を材料として化学療法剤の開発研究を開始した。44年,結核菌を含めた広い範囲の細菌種に有効なストレプトマイシンが発見された。抗生物質antibioticsと呼ばれることになったこれら微生物由来の抗菌物質は,その後主として大きな製薬会社の手に移って開発がすすめられ,クロラムフェニコール,クロルテトラサイクリン,オキシテトラサイクリン,エリスロマイシンをはじめとして数多くの有効物質が発見されることになった。すぐれた発酵工業技術の伝統のある日本は,この分野でもアメリカとならんで世界の最先端の地位を築き,梅沢浜夫のカナマイシンをはじめとして各種の有用抗生物質を発見してきた。60年以後になると,土から新しい放線菌を分離し,それから新有効物質を発見する成功の確率はしだいに減少した。しかし,抗生物質の作用機序や,菌の薬剤耐性のしくみがしだいに明らかになったので,そのため既知の抗生物質の化学構造を人工変換する半合成手段によって,有効物質をつくる計画的な方向がとられるようになった。その主流となっているものがβ-ラクタム抗生物質と総称されるペニシリンやセファロスポリンの誘導体で,これらは今日先進国で使用される化学療法剤のかなりの部分を占めている。なお,有機合成,分析化学の急速な技術的進歩に伴って,純合成化学療法剤の開発も効率的にすすめられ,さらに今後は遺伝子組換技術の導入による抗生物質の開発も期待されている。
化学療法剤の種類とその抗菌域
化学療法剤は病原体にのみ選択的毒性を有するべきものであるが,すべての製剤がその理想を完全に満足しているわけではなく(たとえば副作用),また病原体の種類も多様であって,薬剤によって効果を発揮する範囲は異なる(これを抗菌域という)。さらには薬剤耐性菌の発現によって既存の薬剤が使用価値を減じ,あるいはこれまで非病原菌と考えられていた微生物による新たな感染症(菌交代症,日和見感染)が化学療法の結果として発生するので,新しい抗菌物質の開発は絶えず必要となる。そうした努力のなかで多くの薬剤が発見され,合成されてきたが,これらは大別すると抗生物質,その半合成誘導体,化学的合成品となる(表)。細菌に対する薬剤にしても,その作用域はテトラサイクリンのようにきわめて広いものや,ポリミキシンのように狭いものもあり,また広くても特定の感染症にのみ使用するリファンピシン(結核)やスペクチノマイシン(淋病)のような薬剤もある。結核菌や真菌(カビ)に対する化学療法剤は一般にこれらに特異的に働くものが多く,原虫・寄生虫に対する化学療法剤はほとんど他とは共通性のない合成品である。癌に対する化学療法剤は,選択的毒性において抗菌物質より開発に困難な面があり,副作用が強く免疫抑制的な作用を伴う場合が多い。ウイルスに対する化学療法はいちばん遅れており,チオセミカルバゾン誘導体(マルボラン),ハロゲン化ヌクレオシド,ホスホノ酢酸,ベンズイミダゾール誘導体などがそれぞれ特定のウイルス疾患に用いられるが,いずれも試験的段階のもので,本格的な開発は今後に残されている。
作用機序
化学療法剤には,その種類や濃度に応じて菌を殺す場合(殺菌効果)と,単にその分裂増殖を阻止する場合(静菌効果)とがある。いずれにせよ,薬剤は菌の代謝過程の微妙な点に作用して上記の効果をもたらす。その作用点で大別すると,細菌の細胞壁合成を阻害するもの(例,ペニシリン系,セファロスポリン系,サイクロセリン),細胞膜に障害を与えるもの(例,ポリミキシンB,アムホテリシンB),タンパク質合成を阻害するもの(例,ストレプトマイシン,クロラムフェニコール,テトラサイクリン系,マクロライド系),核酸合成を阻害するもの(例,リファンピシン,ノボビオシン),また菌の中間代謝産物と類似の化学構造をもつため代謝拮抗剤として働くもの(例,サルファ剤)などがある。消毒薬がパーセントの濃度で使用され,体外の菌を非特異的なタンパク質凝固などで殺菌するのに反し,現在使用されている化学療法剤は,1㏄あたりマイクログラム,あるいはそれ以下の濃度で作用しうるものが多い。また,一般に菌の分裂速度が速く旺盛な発育をしている場合に薬剤効果が著しい。
薬剤投与方法
皮膚,粘膜等の感染局所に直接化学療法剤を外用する場合以外は,注射(皮下,筋肉内,静脈内),点滴,あるいは内服する。いずれを選ぶかは主として薬剤の性質により,消化管内で分解されたり不活化される薬剤,あるいは吸収されにくいものなどは注射による。しかし注射によって局所障害の強いものは経口投与によらざるをえない。投与法,投与量をきめる目安として,患者体内の感染菌に対して有効濃度が維持されるよう血中の薬剤濃度の消長を重視するのが普通である。殺菌効果のためには最高濃度が重要であるし,静菌効果を考慮する場合には,むしろ有効濃度の維持が必要である。そのため,最初にできるだけ大量を投与し,そのあと必要量を一定時間間隔でつづけるのが一般的であるが,結核症のようにきわめて慢性の感染の場合には,複数薬剤の組合せを含めて投与法にさまざまなくふうがなされる。
副作用
人体には害がなく,病原体にのみ毒性を発揮するのが,エールリヒが理想とした化学療法剤であった。事実,現在では,その開発にあたっては有効性の検討に加えて,実験動物に対する急性毒性(50%致死量など)や長期投与による慢性毒性,さらに催奇形性までも試験して安全性を確認し,そのうえで臨床試験に入る。しかし,無数の被験物質の中からこうして選ばれぬいてきた化学療法剤であっても,その多くは多少なりとも副作用をもつものである。副作用は薬剤の種類,投与量,投与経路に応じて異なるが,主要な化学療法剤の副作用としては,神経障害,腎臓障害(アミノ配糖体抗生物質,ポリミキシンB,イソニコチン酸ヒドラジド,エタンブトールなど),痙攣(けいれん)(ペニシリン系,セファロスポリン系),肝臓障害(テトラサイクリン系,エリスロマイシン,ピラジナマイドなど),造血器障害(クロラムフェニコール),胃腸障害(リンコマイシン系,テトラサイクリン系,経口ペニシリン系,パスなど)がある。
化学療法の限界
化学療法は原因療法であるから,その理想は患者体内の感染菌を根絶することである(細菌学的治癒)。しかし亜急性,慢性感染症においては,この目的達成が時として困難であり,感染菌は潜在化して不顕性あるいは休眠感染の形をとり,それが将来における再発の原因となることもある(例,結核)。また,治療中に使用薬剤に対する耐性菌が出現し,これが薬剤投与下に選択されて感染菌の主役となると化学療法はもはや効かない。一方,薬剤投与によって腸管内,気道内等の正常細菌叢(フローラ)の均衡がやぶれ,特定の菌の異常な増殖がおこると,菌交代症と呼ばれる臨床症状(例,カンジダ症)を招来する。これは,免疫抑制剤の使用によって発生する平素無害な菌による日和見感染とともに,医学の進歩に伴う暗い面で,いわゆる医療性疾患の一つである。
化学療法の成果
各種抗生物質が登場し,さらに従来のサルファ剤の進歩を含め,化学合成品についても急速な開発のつづいた1950年以後,化学療法が日本の疾病構造に及ぼした成果はまことにめざましいものがある。例を腸チフス,赤痢といった法定伝染病にとれば,患者数においては現在は第2次大戦直後の1/100にも減少し,数千から1万もあったその死者は今日ではほとんどみられない。長年,日本の死亡率の1位を占めた結核症は,この間死亡率において1/40にもなり,死因順位においては10位以下におちた。そのほか数多くの伝染病,性病の制圧のみならず,化膿のような日常的な疾患の処置,外科手術における感染予防対策など,化学療法の医学全般に及ぼした成果は計り知れない。日本の平均寿命の急速な延長は,化学療法の進歩に負うところがきわめて大きい。
また,化学療法剤は多くの場合,アカデミックな基礎研究のなかから発想が生まれ,その応用研究として発展してきたが,化学療法剤の作用機構や薬剤耐性機序という現実的な問題を介して,生物化学,遺伝学をはじめ,今日生命科学(ライフサイエンス)と呼ばれる分野の中に重要な研究テーマと研究手段を提供してきた。化学療法剤は基礎研究と応用研究との循環のなかで発展した学問の最もよい例であるといえよう。
執筆者:金井 興美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「化学療法」の意味・わかりやすい解説
化学療法
かがくりょうほう
化学物質を用いて生体内の病原寄生体に対し直接その増殖を阻害したり殺菌することによって疾患を治療する方法をいう。薬物療法の一種であるが、対症療法ではなく、原因療法の一つである。
[柳下徳雄]
沿革
化学療法はドイツの細菌学者エールリヒによって創始された。1899年、新設の国立実験治療研究所の所長となったエールリヒは、数百に及ぶ化学物質を動物実験に用い、化学物質と抗菌作用の関連を追究していたが、留学中の秦(はた)佐八郎が同研究所で梅毒をイエウサギに感染させることに成功すると、ただちに前述の化学物質を投与して効果をみることを命じ、1909年、606番目の化学物質サルバルサンによってようやく梅毒の治療に成功、翌年これを発表した。また、エールリヒは化学療法を学問的に体系づけたことでも知られ、薬効係数や化学物質の作用機序などの理論は現在もなお認められている。
1932年に、殺菌性染料を研究中のドイツのドーマクは、発見されたばかりの赤色染料プロントジルを、溶血性連鎖球菌によって敗血症をおこさせたハツカネズミに投与して卓効のあることを確認し、35年に発表した。その後、プロントジルの作用の本態が、生体内でアゾ結合が分解して生ずるスルファニルアミドであることがわかり、36年には合成されたスルファミンに抗菌性のあることが確認された。さらに37年、イギリスでスルファピリジンが肺炎の治療に用いられて成功するに及んで、次々に多数のスルファミン誘導体が合成され、多くのサルファ剤が出現した。しかし、実際に使われているサルファ剤は、その数に比べてきわめて少ない。
ついで抗生物質が登場したが、その発見は1928年である。イギリスのフレミングはインフルエンザウイルスの研究中に、実験室内で空中から落下したアオカビがブドウ球菌の培養器内で増殖し、その周囲が無菌状態になっているのを偶然発見、アオカビの培養物のエキスをつくり、これを800倍に薄めてもブドウ球菌の増殖を抑制することをつきとめ、この物質をペニシリンと名づけた。しかし、このエキスは物質として純粋なものでなかったこともあり、治療効果の面では評価されないまま10年を経過した。39~40年、イギリスのフローリーとチェインらは共同研究の結果、ペニシリンを純粋な物質として抽出することに成功し、動物の連鎖球菌感染症を治療した。このペニシリンが注目されたのは44年、当時のイギリス首相チャーチルの肺炎を治し、奇跡の薬として全世界に報道されてからである。
また、1943年にはアメリカのワックスマンがストレプトマイシンを発見し、45年から結核の化学療法が始まった。以来、多くの抗生物質の研究開発が行われて、多くの感染症の原因療法が容易となったが、一方、化学療法剤に対する耐性菌も出現した。そして、この耐性菌にも有効な新しい化学療法剤の開発、それに対する耐性菌の出現、という繰り返しが現在まで続けられている。また、化学療法の対象は病原寄生体にとどまらず、近年は抗悪性腫瘍(しゅよう)剤(制癌(せいがん)剤)の開発も盛んに行われている。
一般に、化学療法史上では、サルバルサンの発見を第1期とし、サルファ剤時代を第2期、抗生物質時代を第3期と称している。
[柳下徳雄]
化学療法剤
化学療法に用いられる化学物質をいう。狭義には、微生物が産生する物質である抗生物質を別にして、あくまで合成された化学物質をもって化学療法剤とするが、抗生物質にも合成されるものが出現して、この区別があいまいになり、現在では広義に抗生物質を含んでよばれることが多い。
化学療法剤は、生体に寄生する病原体を目標として投与されるのが特徴で、一般の薬物療法に用いられる薬剤が生体に対する薬理作用を利用しているのと異なる。化学療法剤では、生体そのものに対する作用は、副作用となる。また、病原体に対する親和性は効果であり、生体の組織細胞に対する親和性は毒性とみられ、両者の比を化学療法係数という。
化学療法剤には、その薬物に感受性のある病原体が決まっており、選択毒性という。これは効果の有効範囲を示すもので、グラム陽性菌のみに有効とか、グラム陽性菌と陰性菌の両方に有効といったことが選択毒性で、化学療法剤にはかならず有効な菌種や無効な菌種などの程度を示す抗菌スペクトルが示されている。また、化学療法剤の耐性は病原体そのものが耐性をもつことを意味し、生体がその薬物に対して耐性をもってくるのではない。その機序については、病原体の遺伝子の細胞融合や酵素系に関連するといわれる。
化学療法剤の作用には、病原体の発育を抑制するだけの静菌作用と、殺菌してしまう殺菌作用の二つがある。静菌作用は発育を阻害するだけであり、病原体は増殖しないが死んではいないので、環境の変化があれば増殖することがある。したがって、化学療法剤の種類やその濃度に留意すべきで、投与間隔が問題にされる。静菌性のものは投与間隔を短く、頻回に投与する必要があるが、殺菌性のものは再増殖を始めるまでに時間がかかるので、投与間隔は長くてもよい。また、作用機序については、(1)病原体の細胞壁の合成阻害、(2)細胞壁の透過性を変える、(3)増殖に必要なタンパク質の合成阻害、(4)核酸の合成阻害、(5)代謝拮抗(きっこう)、などがあげられている。(1)と(2)は溶菌をきたし、殺菌作用を示す。(3)~(5)の場合は増殖阻害作用であり、静菌作用を示す。
[柳下徳雄]
『『臨床医』7巻1号「化学療法――基礎と臨床」(1981・中外医学社)』▽『ガリル著、塚田隆訳『化学療法』(白水社・文庫クセジュ)』▽『真下啓明他著『臨床薬理学大系10 化学療法薬』(1964・中山書店)』
百科事典マイペディア 「化学療法」の意味・わかりやすい解説
化学療法【かがくりょうほう】
→関連項目感受性検査|抗菌スペクトル|造血幹細胞移植|伝染病|ドーマク
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「化学療法」の意味・わかりやすい解説
化学療法
かがくりょうほう
chemotherapy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
PET検査用語集 「化学療法」の解説
化学療法
栄養・生化学辞典 「化学療法」の解説
化学療法
世界大百科事典(旧版)内の化学療法の言及
【医学】より
…このような治療血清やワクチンは,細菌学の技法を用いているとはいえ,基本的にはE.ジェンナーの牛痘接種による痘瘡(とうそう)予防と同じく,生体自身がもっている免疫能力を利用したものである。ところが同じくコッホの門人であったP.エールリヒは,細菌には染料によって着色されやすいものとそうでないもののあることから,細菌のみに作用して動物や人体には影響のない物質を発見できる理論的可能性に着目し,秦佐八郎とともに梅毒の病原体にのみ特異的に結合し,その発育を阻止する物質サルバルサンを開発,化学療法の基礎をきずいた(1909)。このような開発研究は,アイデアはともかくとして,実験が多大の資材や人員を要し,いかに政府によって設立され,経常費を支出されている研究室でも,その限界を上まわる。…
【癌】より
… 末期の患者では,治療による副作用も無視できないものがある。化学療法は骨髄抑制をきたし,感染や出血の原因をつくる。肝臓や腎臓に高度の障害をきたす場合もある。…
【肺結核】より
…それは有力な肺結核の治療薬が出現しないためでもあった。 しかし,44年に至ってアメリカのS.A.ワクスマンが,土壌の中の放線菌の1種から抗生物質であるストレプトマイシンを発見し,結核化学療法の輝かしい第一歩をふみだした。同年,パラアミノサリチル酸(パス,PAS)が人体に用いられ,46年スウェーデンのO.レーマンによって,その臨床効果が発表された。…
※「化学療法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...