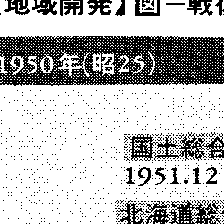精選版 日本国語大辞典 「地域開発」の意味・読み・例文・類語
ちいき‐かいはつチヰキ‥【地域開発】
- 〘 名詞 〙 特定の地域社会を対象とし、その特性に応じて資源の開発や国土保全をすること。国土開発や総合開発と同じような意味に用いられる。
改訂新版 世界大百科事典 「地域開発」の意味・わかりやすい解説
地域開発 (ちいきかいはつ)
地域開発は経済計画の地域版として,生産・生活の社会化や地域問題に対応して,国や自治体が地域の経済・社会を管理し,あるいは改造しようとする政策である。現代経済の下では生産の社会化が進み,企業は操業にあたって事業用地,用水や交通,通信手段などの産業基盤を計画的に整備する必要がある。他方,生活の社会化にともなって,国民は生活環境,教育施設などの生活基盤を必要としている。これらの施設やサービスは民間の手で供給される場合もあるが,多くは地域計画の一環として公共団体の手で供給されている。この生産と生活の社会化が,地域開発が行われる第1の根拠である。市場経済の下では企業や個人が最大限の利益をあげようとして立地をし,空間を利用する。このため,大都市圏では集積利益を求めて企業が過度集中し,これにともなって人口も過剰に集中する。その結果,交通混雑や公害などの集積不利益が生まれ,共同住宅,保育所,学校などの社会的共同消費の不足という都市問題が発生する。他方,農村では人口とくに若年労働力人口の過度流出によって過疎問題が生まれる(過疎・過密問題)。国土全体として,資源の適正配分を欠き,地域間の経済的,教育・文化的な格差が拡大し,自然破壊やアメニティ(生活環境の快適さ)の喪失などが発生する。このような地域問題は貧困問題と重なって,政治的不安を生むので,そのために,国家や自治体がそれを解決しようとして,地域開発を行うのである。このような地域問題の深刻化が地域開発が行われる第2の根拠である。
形態
地域開発は各国の歴史的発展段階や社会状況によって,その具体的な形態が異なっている。日本の場合,国家による経済の近代化が進められたので,資本主義の初期から地域開発が行われた。明治期の北海道開拓や官営八幡製鉄所の経営を中心とした北九州開発は,地域開発のはしりといわれている。しかし,世界史的にいえば地域開発は1920年代以降,国家が経済過程に介入するようになった現代社会の産物である。第2次大戦前においては,イギリスの特定地域計画に始まるニュータウン計画(ニュータウン),アメリカのTVA,日本の時局匡救事業(高橋是清蔵相による大規模な農村土木事業)が地域開発の世界史的な出発点といってよく,また不況対策をかねた地域格差是正を目的としていたといってよい。第2次大戦後,福祉国家の成立にともなって,各国とも福祉政策の一環として都市・農村問題の解決と地域格差是正を目ざす地域開発が行われるようになった。他方,後進資本主義国の日本やイタリアでは経済成長のための工場立地政策が地域開発として進められた。この経済成長のための地域開発は,発展途上国や社会主義国でも進められている。またECのように国際的な地域開発も現代の特徴である。
第2次大戦後の日本の地域開発
第2次大戦後,日本では大都市化という有史以来の地理的変化が進んだこともあって,地域開発は経済政策の中心となった。歴史的にみれば,それは以下のように四つに分類できる。
(1)多目的ダムを中心とする河川総合開発方式 この方式は戦前から行われ,戦後1950年代にTVAを模範として行われた。1950年〈国土総合開発法〉が立法されたが,これに基づく全国総合開発計画の策定は62年まで進まなかったので,当時の戦災による産業の荒廃,植民地の喪失と引揚者,兵士の大量の引揚げによる失業の増大による地域問題に対処するために,同法による特定地域総合開発計画が行われた。この計画には42都府県から総計51の候補地が立候補したが,次の21地域を指定した。阿仁田沢,最上,北上,只見,利根,飛越,能登,天竜東三河,木曾,吉野熊野,大山出雲,芸北,錦川,那賀川,四国西南,北九州,阿蘇,南九州(以上1951年決定),十和田岩木川,北奥羽,仙塩(以上1957年決定)。
この地域をみてもわかるように,大部分は後進農村地域であり,河川総合開発であった。この方式での政府の目的は,多目的ダムによって電源開発,農産物増産,治山治水を行い,後進農村地域の住民の所得水準を引き上げ,電化によって生活を改善し,同時に日本経済の復興の基盤をつくり,地域格差の是正を図ろうというのであった。アメリカのTVAは資本主義国の地域開発では数少ない成功例であるが,それは開発の目的を特定産業に偏せず総合的なものとし,責任を明確にするために一元化し,さらに開発計画への住民参加=草の根民主主義を確立したことにある。ところが日本の場合には,開発の結果をみると総合開発というよりは電力資本の復興に特定化した。それによって国際的にみて安い料金の産業用電力の供給をうけた大都市地域の重化学工業の発展に寄与したが,農村の工業化や農民の生活の向上にはつながらなかった。現在,当時の特定地域のほとんどは過疎地域になっている。実行機関は各府県であったが,実際には各省のばらばらの補助金事業で行われたために計画性がなく,これらの地域ではダム災害など災害が多発した。これらの失敗に対する責任の所在も不明であった。とりわけ問題なのは住民参加が行われず,官僚主導型になったことであろう。TVAの模倣はその方法にかぎられ,理念に学ぶことが少なかったことが似て非なる結果をまねいたといってよい。この方式は全国的には60年代にあらわれた次の重化学工業化を目的とした開発の前に姿を消すが,個別的には今なお続けられている。
(2)拠点開発方式 1955年以降の高度成長時代に登場した日本独自の開発方式である。拠点という意味は,まず第1に地域的には全国をおしなべて開発するのでなく,重化学工業(とくに臨海コンビナート)の立地可能地点で,将来中枢主導的役割を果たす地方都市を拠点として開発するものである。第2にすべての産業を総合的に開発するのでなく,素材を供給する重化学工業(とくに臨海性の鉄鋼,石油精製,石油化学)や発電所を拠点産業として重点的に開発しようというものであった。拠点開発の論理を図式化すると次のようになる。産業基盤の公共投資集中→素材供給型重化学工業の誘致→関連産業の発展→都市化・食生活など生活様式の変化→周辺農村の農漁業の近代化→地域全体の財産(土地)価値・所得水準の上昇→財政収入の増大→生活基盤への公共投資,社会政策による住民福祉の向上(→企業・人口分散による国土の均衡ある発展)。この論理では,地域開発というピストルの弾丸が最終目標の住民福祉に的中するかどうかは,工場進出というひきがねがひけるかどうかにかかっている。このため空前の工場誘致合戦が行われた。
拠点開発は当初,四日市市や京葉地域など太平洋ベルト地帯で行われていたが,やがて政府は62年第1次全国総合開発計画を発表し,〈拠点地域〉を新産業都市と工業整備特別地域と名づけて,全国に指定をすることとした。このため全国から44地域が立候補し,史上空前といわれる陳情合戦が行われ,結局,次の地域が指定された。新産業都市--道央,八戸,仙台湾,常磐郡山,新潟,富山高岡,松本諏訪,岡山県南,徳島,東予,大分,日向延岡,有明不知火大牟田,秋田臨海,中海の15ヵ所。工業整備特別地域--鹿島,駿河湾,東三河,播磨,備後,周南の6ヵ所。このように多くなったのは政治的妥協の産物である。現実にコンビナートの誘致に成功したのは,新産業都市のうち岡山県南と大分にすぎなかった。このため,全国的に工場団地が売れ残り,地方財政が危機におちいるなどの問題が残った。また拠点開発の進んだ地域では,その結果として,先の論理には明らかにされていない重大な社会問題を生んだ。それは四日市公害に始まる公害や災害の増大である。このため三島,沼津,清水地域では,コンビナート誘致反対運動が63年以来1年近く続き,ついに地元自治体は〈四日市の二の舞をするな〉ということでコンビナート誘致をやめた。以後,拠点開発に反対する運動は全国にひろがった。拠点開発の問題点は公害だけではない。コンビナートは地元の産業と連関がなく,地域の雇用,付加価値や租税などへの貢献度が小さく,地域開発の経済効果が資源消費や環境破壊の大きさに比べて乏しいことが明らかとなっている。にもかかわらず後進地域では,拠点産業を原子力発電所や先端産業にかえて原発基地やテクノポリスとして,この方式は続けられている。また発展途上国ではコンビナート中心の拠点開発方式が進められている。
(3)巨大開発方式 1969年〈新全国総合開発計画〉(第二次全国総合開発計画,以下〈二全総〉と略す)が発表された。この計画は85年を最終目標年次とし,20年計画で国民総生産を1965年の約5倍増の130兆~150兆円とするもので,このために明治以来の累積投資の約3~4倍を一挙につぎこむというのであった。二全総は田中角栄の〈日本列島改造論〉と似ており,国土を一つの都市のごとく考え,3地域に分割した。太平洋ベルト地域の中央地帯は巨大都市地域とし,北東・南西両地域は巨大産業・観光基地として特化し,これらの地域を〈一日行動圏〉として短時間で結ぶために,新幹線,高速道路,マイクロウエーブ網などの巨大交通通信ネットワークで結ぼうというものであった。すべてが巨大なプロジェクトなので巨大開発方式とよばれた。巨大開発方式は高度成長時代の最後の到達点といってよい。産業からみて日本列島を最大限に効率よく利用し,国民が国土を忙しくかけまわって働く計画であった。しかし,国民はこのように地域が分業化して中央集権によって管理され,大量の資源浪費と環境破壊が予測される国土の未来像に不安をもった。公害反対を中心とする住民運動,地価高騰そして石油ショックが,この巨大開発の進行を止めた。
(4)定住圏開発方式 過密過疎問題の深刻化や公害の多発は,国民の目的意識を成長から福祉へとかえた。〈地方の時代〉や〈文化の時代〉といわれるように,人口の地方への定着が始まり,自然や歴史的環境と共存する経済の発展が求められるようになった。政府は1977年第三次全国総合開発計画によって,〈定住圏〉を水系ごとに確立する構想を発表した。これは成長型から福祉型へという重大な転換であったが,必ずしも徹底したものでなく,むつ小川原・志布志などの二全総で計画した巨大産業基地の開発も進めるものであった。最終目標の経済規模が大きすぎ,人口の伸びや高齢化の進行も予測に反し,財政危機による公共投資の停滞などもあって,定住圏構想は現実化していない。87年策定の第4次全国総合開発計画では,定住圏構想は継続するが,〈多極分散型国土の形成〉を掲げた。
展望
世界的にみれば,先進工業国の地域開発は大きな曲り角にきている。1970年代にはいって,ニューヨークやロンドンなどの古い大都市の衰退現象があらわれ,〈再農村化現象〉といわれるように,大都市圏から企業や人口の地方あるいは他国への分散がみられるようになっている。このため,イギリスのようにニュータウン政策などの地方分散政策をやめて,大都市再開発が重視されるようになっている。財政危機の深刻化とともに福祉国家の破産が問題となり,今後は〈小さな政府〉を目ざし,地域開発の主体は政府・自治体から民間あるいは公私混合の第三セクターにし,民間活力を生かすべきだという意見が強くなっている。他方,住民のニーズの変化から開発の目標に文化の向上が求められ,コミュニティレベルの〈小さな開発〉,そして地元産業を主体とした〈内発的な発展〉が始まっている。成長型開発が公害を発生させ,中央集権型管理社会を生んだ反省から,環境アセスメントという事前調査や行財政への住民参加が欧米では制度化されるに至った。
多国籍企業の発展とともに,地域開発は国際化しつつある。いまや日本企業の動向が,オーストラリアや東南アジアの地域開発のあり方を決めている。また,日本の産業配置は,今後の企業の海外立地に大きく影響をうけるといってよい。OECD(国際経済協力開発機構)はあるが,これは国際的な地域開発をコントロールする権限も経済力ももたない。したがって国際的な規模での地域問題が予測される。これらの新しい課題が相互に影響しながら,21世紀の地域開発は動いていくといってよい。
→国土計画 →国土総合開発
執筆者:宮本 憲一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域開発」の意味・わかりやすい解説
地域開発
ちいきかいはつ
regional development
地域の潜在的可能性を開くことを掲げる社会的計画。その先駆的な例としては、アメリカの大恐慌を救ったとされるニューディール政策の一環としてのTVAなどがあげられる。開発や計画の主体や推進力としては、行政や企業体が中心となることが多く、とりわけ日本では住民の関与や参加は少ない。
[園田恭一]
資源開発中心主義の段階
日本において地域開発ということが本格的に取り組まれるようになったのは、第二次世界大戦後の経済再建の過程、とりわけ1950年(昭和25)の国土総合開発法の制定以降の時期であった。それは、敗戦による植民地の喪失、領土の縮小という現実を前にして、その経済的復興の道が国内市場の発展や後進地域の開発に求められたからでもあった。
[園田恭一]
工業開発中心主義の段階
しかし、日本の経済復興が進むなかで、とりわけ1950年代の後半以降となると、地域開発政策の重点も、大企業の経済活動に、より直接の関係をもつ道路、港湾、工業用水の確保や拡充といった産業基盤の整備に向けられるようになってきた。
[園田恭一]
地域格差是正主義の段階
1960年に池田勇人(はやと)内閣が国民所得倍増計画を前面に掲げ、高度経済成長政策を打ち出すに及んで、それは一方での企業の設備投資ブームをよんで、既存の工業地帯の過密や人口集中の激化による都市問題を生み、他方では農山村地帯での人口の急減や所得の低下などの、いわゆる地域格差の問題をさらに激しいものとすることとなった。過密地域の工場抑制と地方都市の開発を重点とした全国総合開発計画が62年に策定されるようになったのは、このような背景があったからであり、その目玉として打ち出されたのが、既存の工業地帯以外の地域に政策的に新しい産業都市を建設するという新産業都市建設促進法であった。
[園田恭一]
過密・過疎対策の段階
しかしながら、そこで地域格差を是正するためにとられた方策は、農漁業とか地場産業などといった生産力の低い産業を引き上げるというのではなく、石油や鉄鋼などのいわゆる成長産業をさらに育成強化し、それを分散させ、そこに人口を吸収したり、あるいは、それらを通して地域格差の是正と産業の過度集中の排除を進めようとするものであった。そのため、採算や効率や競争などを第一とする大企業や財界などの協力が得られず、企業とりわけ成長企業の大都市周辺の臨海工業地帯への集中はさらに進行した。そしてそれらの地域での環境問題などの事態は、ますます深刻化する方向に進んだのである。
[園田恭一]
大規模プロジェクト主義の段階
新産業都市政策の挫折(ざせつ)した後を受けての地域開発政策の新しい動向は、企業や人口のよりいっそうの大都市への集中を前提としたうえでの大都市の再開発であり、大都市圏の整備への転換であった。そしてこれらの総仕上げともいえるのが、1969年の新全国総合開発計画(新全総)であった。この計画は、三大都市圏への人や産業の集中を前提として、そこに都市機能を集中させ、そして他方、交通・通信手段を確立し、大規模化することによって、日本の各地方を大都市に結び付けていこうとするものであり、それは拠点開発方式にかわるネットワーク方式の計画であるといわれた。
[園田恭一]
安定政策主義の段階
しかし、経済の高度成長のひずみはさらに大きなものとなり、またその後の低成長経済時代を迎えて、1979年には、人口の地方定住化、限られた資源の活用、自然との調和のとれた環境づくりを目ざした第三次全国総合開発計画(三全総)が策定された。さらに、人口の高齢化、都市化、国際化に対応するということで、21世紀を展望した国土づくりの指針とするという第四次全国総合開発計画(四全総)の策定が現在進められている。
[園田恭一]
『園田恭一著『地域社会論』(1969・日本評論社)』▽『宮本憲一著『社会資本論』改訂版(1976・有斐閣)』
百科事典マイペディア 「地域開発」の意味・わかりやすい解説
地域開発【ちいきかいはつ】
→関連項目第三セクター
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地域開発」の意味・わかりやすい解説
地域開発
ちいきかいはつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の地域開発の言及
【国土総合開発】より
…国や地方自治体が,その時代に直面する課題を解決し,国民生活の向上と安定に寄与するために,地域の資源や土地,労働力を有効に活用して地域の生産力や所得・雇用を増大させる政策をとることを地域開発と呼ぶ。それゆえ,地域開発は経済政策の一分野ということができる。…
※「地域開発」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...