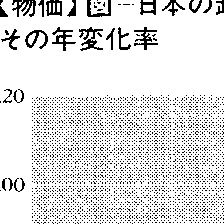精選版 日本国語大辞典 「物価」の意味・読み・例文・類語
ぶっ‐か【物価】
- 〘 名詞 〙 諸商品の価格を総合的にみたもの。売買する品物の値段。
- [初出の実例]「価長二人。〈掌下平二物価一市易上、〉」(出典:令義解(718)職員)
- 「物価騰踊して、上下ともに困窮して」(出典:太平策(1719‐22))
改訂新版 世界大百科事典 「物価」の意味・わかりやすい解説
物価 (ぶっか)
物価とは文字どおり物の価格であるが,経済学で単に物価というとき,あるいは物価問題というように用いられるときには通常個々の財の価格ではなく,経済全体での一般的な物価水準を指す。もちろん現実経済に一般的な物価というものが存在するわけではなく,それは統計的な指数(多くの財の価格の平均)によってとらえられるものである。たとえばどのような財の価格を指数に取り入れるかによって,消費者物価指数,卸売物価指数(現,企業物価指数),GNPデフレーター等があり,これらはそれぞれ目的に応じて使い分けられている。
さて一般物価水準の変動(その上昇がインフレーションにほかならない)にわれわれが関心をもつのはどのような理由によってであろうか。もしすべての財の価格(労働サービスの価格である賃金等も当然含む)が比例的に上昇し,しかもそれが人々によって完全に予見されていたとしたら,一般物価水準の変動は経済活動の実質面にあまり大きな影響を与えないであろう。たとえば賃金20万円,パン100円,家賃4万円という状態が,それぞれ40万円,200円,8万円というように変化したとしても,人々の実質的な経済状態に変りはなく,それはちょうど計算単位の変化のようなものにすぎない。将来まで影響を及ぼすような長期契約(一定期間にわたる賃金契約,金銭の貸借契約等)についても,もし物価の変動が完全に予見されているのであれば,それはあらかじめ契約に織り込まれるであろうから実質的影響は比較的小さなものになろう。しかしながら以上述べたようなことは,すべての財の価格が比例的に変動し,しかもそれが完全に予見されているような一般物価水準の変化のもとでのみ成り立つことである。実はこのような一般物価水準の変化(あるいはインフレーション)が現実経済ではほとんど存在しないところに問題があるわけである。いいかえれば現実経済において物価水準が変化するときには必ずもろもろの財の価格が不均等に変化し,しかもそのかなりの部分が予想されないものなのである。そしてこのような物価の上昇は,企業や家計の将来計画を困難にし,また社会の各グループ間で恣意(しい)的な所得再分配を生み出す。ここにわれわれが一般物価水準の変化に重大な関心を寄せる理由があるわけである。
一般物価水準の決り方
それでは次に一般物価水準はどのようにして決定されるのかについてみることにしよう。この点について経済学には大別して二つの考え方がある。
マネタリズムの考え方
まず第1の考え方は,一般物価水準は貨幣で計った財の(集合の)価格であるから,いいかえればそれは財で計った貨幣の価格の逆数にほかならないという事実に注目する。さて(財で計った)貨幣の価格は,その供給量が増大すれば下落するというのは,ある財(たとえばパン)の価格がその供給量の上昇に伴って下落するのと同じであるから,結局一般物価水準(貨幣の価格の逆数)は貨幣の供給量が増加すれば上昇するということになる。すなわちこの考え方によれば一般物価水準を決定するのはなによりも貨幣供給量であり,後者の変動に応じて前者は上下するのである。こうした考え方がマネタリズムと呼ばれる立場である。なおマネタリズムによれば,物価上昇を沈静化するための方策は当然貨幣供給量(あるいはその変化率)を減少させることということになる。さてマネタリズムの考え方は明快であるが,貨幣供給量すなわちマネー・サプライ(これは中央銀行によって決定される)が一般物価水準(これは各企業が決定する個別価格の平均)に対していかなる経路を通して影響を与えるのかについては必ずしも明らかでない。
ケインズ学派の考え方
この点マネタリズムとは対立する立場にあるケインズ学派の人々によって主張される第2の考え方は,企業による価格決定から出発するのである。現代経済において多くの財の価格はその財を生産,供給する企業によって決定される。もちろん原材料,食料品の価格は一部を除いて古典的な市場の需給関係によって決定される(とくに銅,スズ,亜鉛等の金属,小麦,綿花,羊毛,コーヒー,ゴム等には国際的にきわめて競争的な市場が成立しており,これらの財の価格はロイター指数と呼ばれる価格指数によってとらえられている)が,工業製品の価格は供給者である企業によって決定されるのが通常である。そこで企業がどのような価格決定方式にとっているかが問題となるが,典型的なものとして挙げられるのがマーク・アップ方式と呼ばれるものである。これは企業が,製品1単位当りの労賃を中心とするコストに一定の利潤を確保するような比率(マーク・アップ率)をかけて価格決定を行うというものである。すなわち,いま企業がLだけの労働者を雇ってQだけの製品を生み出したとすると,賃金率がWなら総労働コストはWL,製品1単位当りの労働コストはWL/Qとなる。労働以外のコストを簡単のために無視すれば製品価格Pはマーク・アップ率をmとしてmWL/Q=P(m>1)として決定されるわけである。こうしたマーク・アップ方式による価格決定は,長期的にみた場合,利潤を最大化するという企業の合理的行動と矛盾するものではない。
さてP=mWL/Qというマーク・アップの式をみればわかるように,価格Pは三つの要因に依存している。マーク・アップ率m,賃金水準W,それに労働の生産性Q/L(上の式には直接的には労働生産性の逆数が入っている)である。このうちマーク・アップ率mは経済全体の平均をとった場合短期的には比較的安定していると考えられるので,結局一般的物価水準(個別価格の平均)は平均賃金Wおよび平均的労働生産性Q/Lという二つの要因によって主として決定されることになる。したがって,この二つの要因に影響を与えるものはすべて物価にも影響を与えると考えられる。とくに経済全体の活動水準(景気)や期待物価上昇率は賃金決定の動向に大きな影響を与える(いわゆるフィリップス曲線の考え方)ものである。先にマネタリズムが貨幣供給量を物価決定の唯一の要因として挙げることを述べたが,このケインズ派的な考え方によれば,貨幣供給量は総需要→景気動向→賃金→物価という経路を通して,なるほど物価に影響を与えるのではあるが,それは物価に影響を与える数多くの要因の一つにすぎないということになる。
為替レートの影響
この点に関連して国内の物価水準に為替レートが与える影響についても述べておく。これは1970年代に入り,世界経済が戦後長く続いた固定相場制(IMF体制)から変動相場制に移行したことにより生じてきた問題である。周知のように日本の輸入品の大半は原材料品であるが,先に述べたように,こうした原材料品の国際価格(ドル価格)は世界市場で成立している。そこでもし円の為替レートが切り下がったとしたら(たとえば1ドル220円から280円というように),ドル価格が与えられている輸入原材料品の国内価格(円価格)は当然上昇することになる。この結果,マーク・アップ率,労働生産性に大きな変化がないかぎり国内の物価水準も上昇することになる。為替レート(円レート)の下落は,輸入原材料品の国内価格を引き上げることにより物価水準を上昇させるのである。
戦後日本の物価の動き
以上物価がどのようにして決定されるかについてみたわけであるが,次に第2次大戦後の日本における物価の動きを卸売物価と消費者物価という二つの指数の動きを中心にみてみることにしよう。ここで,消費者物価は最終的消費財の価格であり,とくに約1/3はサービスを含むのに対し,卸売物価は主として(約3/4)企業相互間で取引される生産財,資本財の価格であるという点に注意されたい。
さて第2次大戦直後日本はまず激しい戦後インフレに見舞われた。たとえば1947年から48年にかけては卸売物価は実に年率300%に及ぶ率で上昇し,また消費者物価の上昇も100%を超えた。その後50年にかけていったん沈静化した物価は,朝鮮戦争による特需ブームの影響で再び51年には卸売物価50%強,消費者物価20%強という高率の上昇を経験した。その後73年第1次石油危機時に至るまで日本経済はこれほど高率の物価上昇を経験しなかった。
1950年代末から72年に至る期間の日本の物価の動きは,卸売物価がきわめて安定していたのに対し,消費者物価が持続して上昇した時期として特徴づけることができる。図には1960から80年に至る日本の卸売・消費者物価指数と,それぞれの年変化率が示してあるが,これら(1960-72年の期間について)からもこうした特徴を読み取ることができる。この事実は,先に述べたように卸売価格が主として製造工業部門の価格であるのに対し,消費者価格はこれに加えてサービス部門,流通部門を大幅に含む価格指数であるということから説明される。すなわち1950年代末から72年に至るいわゆる高度成長期に,製造工業部門ではきわめて高率の労働生産性の上昇が実現された(家庭電気製品,カメラ等ある種の個別製品についてはそのため価格が下落したことはわれわれが日常経験したところである)のに対し,消費者物価に影響を与えるサービス,農業,流通等の部門での生産性の上昇率は低率にとどまった。再びマーク・アップの式をみればわかるように,経済の各部門でほぼ同率で賃金が上昇するかぎり消費者物価は卸売物価に比べて相対的に上昇しなければならないのである。こうした部門間の生産性上昇率格差が卸売物価と消費者物価上昇の乖離(かいり)を生み出したといえる。
さて1970年代に入ると世界経済はOPEC(オペツク)による一方的な石油価格値上げ,いわゆる石油危機に見舞われた。73年から74年のいわゆる第1次石油危機は単に石油価格が4倍化したのみならず,また世界的な凶作による一次産品の大幅な価格上昇に重なっていた。先にふれたロイター指数は長期間安定していたが,この時期にほぼ3倍になった。こうした状況を背景に,将来資源制約から供給が不足するのではないかと恐れる企業,家計による仮需が発生し,これが企業による相乗的な価格引上げを招いた。図にみられるとおり,この時期,卸売・消費者物価指数はともに朝鮮戦争以来の20%を超える高率で上昇した。いわゆる狂乱物価である。ただし図を注意深くみればわかるように,物価は1973年すでに大幅に上昇しているのであり,これを73年秋から始まった石油危機(第1次)にすべて帰することはできない。むしろ73年から74年に至る狂乱物価は,1973年を中心とする期に貨幣供給量が過大となったことにより発生し,それに石油危機が重なったものとして説明されることも多い。これは先に述べたマネタリズムによる説明に近い。
こうした第1次石油危機と対照的に,79年からの第2次石油危機においては,石油価格の急騰により原材料,生産財を多く含む卸売価格が急上昇したにもかかわらず,消費者価格の上昇は比較的小幅にとどまった(図)。これはこの時期,貨幣供給量の増加が抑制されたこと,インフレ期待が沈静していたこと,また賃金上昇率も比較的小さかったこと等に帰せられるが,アメリカ等諸外国における同時期のパフォーマンスと比べてもきわめて良好なものであった。
執筆者:吉川 洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「物価」の意味・わかりやすい解説
物価
ぶっか
prices (of commodities)
種々の商品やサービスの価格を、ある一定の方法で総合した平均値のことであり、物価指数として示される。いいかえれば、商品・サービスが貨幣に対してもつ交換価値のことであり、貨幣の購買力とは逆数の関係となる。
物価は、どのような経済活動の側面についての商品・サービス価格を総合して示すかによって、卸売物価・小売物価、国内物価・国際物価(輸出物価・輸入物価)、都市物価・農村物価などに分けて示される。
日本の物価は、長期的にみて、戦争による生産能力の著しい低下、急速な経済成長に伴う有効需要の拡大、さらには輸入物価の急騰などのさまざまな局面を通して、それぞれに、物価変動に関する諸理論によっても説明しうる経過をたどってきたが、第二次世界大戦前平時の1934~1936年(昭和9~11)当時と比較するとき、それからおよそ75年を経た2010年(平成22)の物価水準は、卸売物価(企業物価)でおよそ668倍、小売物価(消費者物価=東京)ではおよそ1767倍となっている。
物価の形成・変動に関する理論については、貨幣数量説がもっとも古い。この理論は、物価上昇が通貨の発行量の拡大によってもたらされることが多いという経験的事実に根ざすものであり、I・フィッシャーによって
PT=MV
として定式化された。ここで、Pは一般物価水準、Tは取引数量、Mは通貨の量、そしてVは通貨の流通速度を表す。この式は、通貨の流通速度(貨幣が一定期間内に人の手に渡る回数)と取引数量(したがって財貨の生産量)が大きく変動しないと考えられる限り、物価水準は通貨数量に応じて変動するという内容のものであり、一般に「フィッシャーの交換方程式」とよばれている。この基本的な考え方については、マネタリスト(貨幣主義者)の代表であるM・フリードマンによって、より精緻な解釈の下で支持されてきた。
ついでA・マーシャルは、この交換方程式を、経済主体による主体的行動を含む形に改変し、「マーシャルの残高方程式」とよばれる次の関係式を提示した。
M=kPY
ここで、M、Pはそれぞれ通貨数量および物価水準であり、Yは1年間の実質所得、kはそのうち貨幣の形で保有しようとする割合である。このkは、形のうえでは先の交換方程式の流通速度Vの逆数に対応するものであるが、社会的慣習や制度的要因によって規定されるものではなく、経済主体の貨幣保有に関する主体的判断に依存するものであり、「マーシャルのk」とよばれる。
物価理論にさらに深い内容を与えたのはJ・M・ケインズである。彼は、一般的に社会的有効需要が生産量と物価水準の積で示されるところから、有効需要に関する生産の弾力性(有効需要が1%増加した時、生産が何%増加するか)eoと物価の弾力性epとの間には
eo+ep=1
なる関係のあることを示し、生産能力が完全利用の状態における有効需要の増大は、物価の上昇に吸収されることを説明した。この状況は、ケインズがtrue inflation(真正インフレーション)とよんだものであるが、それ以前の物価理論が需要面を強調したデマンド・プル型であったのに対して、ケインズの考え方は、供給側の要因を重視するコスト・プッシュ型であるところに新局面がある。
このような物価理論の展開は、次の段階として、需要・供給の両側面を総合する方向が考えられるが、人々の将来に対する物価上昇の期待形成が社会の総需要と総供給に与える影響を理論的に考察することなどは、そのような試みの一つである。
[高島 忠]
普及版 字通 「物価」の読み・字形・画数・意味
【物価】ぶつか
字通「物」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の物価の言及
【貨幣数量説】より
…貨幣量と物価の関係についての古典派の学説で,〈ある国の物価水準は,その国に流通している貨幣の量に比例して決まる〉というものである。すなわち,貨幣の量が2倍になれば物価もほぼ2倍になると考える。…
【津留】より
…62年(寛文2)仙台藩は他領出禁制品を増しているが,禁制は絶対的なものでなく,それぞれの品目によって,藩主の印判あるいは奉行・出入司・御算用奉行・御割奉行の手形をもつ品目の移出入を認めるようにした。津留は物価調節策の一手段としても実施された。1672年福岡藩は博多湊からの生魚・酒の津出しを禁ずるとともに,他浦からの生魚の迎買(むかえがい)をも禁じている。…
※「物価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...