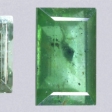翻訳|beryl
精選版 日本国語大辞典 「緑柱石」の意味・読み・例文・類語
りょくちゅう‐せき【緑柱石】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「緑柱石」の意味・わかりやすい解説
緑柱石
りょくちゅうせき
beryl
シクロ珪酸(けいさん)塩鉱物の一つ。ベリルともいい、透明ないし半透明で縦に条線のある六角の長柱状、まれに短柱状結晶をすることがある。ベリリウムのもっとも重要な鉱石となるほか、良質な結晶は宝石として利用される。宝石種として価値が高いのは、濃緑色のエメラルド、青緑色のアクアマリン、桃色のモルガナイトなどである。おもに花崗(かこう)岩質ペグマタイト中に産し、石英、曹長(そうちょう)石、白雲母(しろうんも)などを伴う。日本では、福島県石川地方、茨城県筑波(つくば)地方、山梨県甲府市黒平(くろべら)、岐阜県苗木地方、佐賀県富士町杉山などが有名な産地であるが、良結晶はほとんどなく、黒平や苗木地方からわずかにアクアマリン種が出たことがある。ほかに、グライゼンや気成鉱脈から石英、白雲母とともに産し、岐阜県中津川市福岡鉱山(閉山)では、かつてベリリウム鉱石として採掘されていたことがある。アメリカ合衆国ユタ州では流紋岩の晶洞から、石英、黄玉、ビクスビ鉱を伴って赤色の結晶が産する。コロンビア、ロシア、オーストリアなどのエメラルドは、片麻(へんま)岩、千枚岩、黒雲母片岩、泥灰岩中またはそれらを切る脈に産する。アクアマリンはブラジル、マダガスカル、パキスタン産が有名。普通の緑柱石は世界中に広く産する。ギリシア語のベリロスberyllosに由来するが、大昔この名前は一種以上の緑色をした鉱物に対して使われたらしい。しかし、その本来の意味は不明。
[松原 聰]
緑柱石(データノート)
りょくちゅうせきでーたのーと
緑柱石
英名 beryl
化学式 Be3Al2Si6O18
少量成分 Cs,Li,Na
結晶系 六方
硬度 7.5~8
比重 2.6~2.9
色 緑,青,白,桃,黄赤
光沢 ガラス
条痕 白
劈開 なし
(「劈開」の項目を参照)
改訂新版 世界大百科事典 「緑柱石」の意味・わかりやすい解説
緑柱石 (りょくちゅうせき)
beryl
ベリリウムの主要な鉱石鉱物の一つで,美しいものは宝石としても用いられる。成分Be3Al2Si6O18。少量のナトリウム,カリウム,リチウム,セシウムなどを含む。六方晶系に属し,六角柱状結晶として産する。透明~半透明でガラス光沢がある。色は緑色であるが,無色,青色,黄色,淡紅色の場合もある。へき開は不明りょうで,貝殻状断口を示し,もろい。モース硬度7.5~8。比重2.6~2.9。色と形とから緑柱石と名づけられた。英名のベリルberylはギリシア語のbēryllosに由来する。花コウ岩,ペグマタイトおよび変成岩中に産する。世界のおもな産地はコロンビア,ブラジル,旧ソ連。日本では福島県石川,茨城県山尾,福岡県長垂(ながたれ),佐賀県杉山などに産する。なお宝石については〈ベリル〉の項目を参照されたい。
執筆者:青木 義和
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
最新 地学事典 「緑柱石」の解説
りょくちゅうせき
緑柱石
beryl
化学組成Be3Al2Si6O18の鉱物。ベリルとも。六方晶系,空間群P6/mcc, 格子定数a0.9215nm, c0.9192, 単位格子中2分子含む。六角短ないし長柱状結晶。ふつう淡青~緑~鮮緑色,ほか白・黄・ピンク・無色,透明~半透明,ガラス光沢。劈開{0001}に不明瞭。硬度7.5~8,比重2.64。薄片では無色,屈折率ω1.568~1.602, ε1.563~1.594, 一軸性負。Sc>Alのものがバッツイーアイトで同構造。Li, Na, K, Rbなどを含むことがある。主に花崗岩質ペグマタイト,結晶片岩,片麻岩,熱水鉱脈中に広く産する。宝石として,青緑色透明種のアクアマリン,鮮緑色透明種のエメラルド,ピンク色透明種のモルガナイトなどがある。名称は古代ギリシアで緑色の鉱物の何種類かをberyllosと呼んでいたことに由来するが,本来の意味は不明。
執筆者:青木 義和・松原 聰
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
化学辞典 第2版 「緑柱石」の解説
緑柱石
リョクチュウセキ
beryl
Be3Al2Si6O18.花こう岩,ペグマタイト,雲母片岩中に産出する.六方晶系,空間群 P 6/mcc,格子定数 a0 = 0.920,c0 = 0.919 nm.単位胞中に二つの基本組成を含む.透明ないし半透明,ガラス光沢ないし樹脂光沢,エメラルド緑色,淡青,淡緑,黄,白,無色など.もろく断口は貝殻状ないし不規則.六角の長柱状結晶をなすことが多く,柱面に縦の条線がある.密度2.63~2.91 g cm-3.硬度7.5~8.緑色の透明のものをエメラルド,淡青色の透明のものをアクアマリンと称し,宝石として用いられる.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「緑柱石」の意味・わかりやすい解説
緑柱石
りょくちゅうせき
beryl
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「緑柱石」の意味・わかりやすい解説
緑柱石【りょくちゅうせき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...