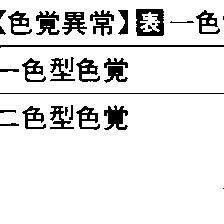精選版 日本国語大辞典 「色覚異常」の意味・読み・例文・類語
しきかく‐いじょう‥イジャウ【色覚異常】
最新 心理学事典 「色覚異常」の解説
しきかくいじょう
色覚異常
color vision deficiency
【色覚の生理学的基礎と分類】 網膜の視細胞には視物質とよばれる光受容タンパク質が発現している。視細胞はその形態から錐体と桿体に分類されるが,分光的に前者は長波長(558nm)に吸収極大波長をもつ視物質を含むL錐体,中波長(531nm)に吸収極大波長をもつ視物質を含むM錐体,短波長(419nm)に吸収極大波長をもつ視物質を含むS錐体の三つに分かれる。これらはそれぞれ,赤錐体,緑錐体,青錐体ともよばれる。一方,桿体に発現する視物質はロドプシン(吸収極大波長500nm)1種類である。
ヒトは3種類の錐体の興奮の相対比によって色を区別している。正常色覚者のこのような色覚を正常3色型色覚normal trichromacyという。3種類の錐体機能が存在するが,L・M・S錐体のいずれかの働きが正常と異なるのが異常3色型色覚anomalous trichromacyである。L・M・S錐体のいずれかの機能が欠けているのが2色型色覚dichromacyで,錐体機能が1種類しか存在しないか全錐体の機能を失い桿体のみが働いているのが1色型色覚monochromacyである。異常3色型色覚と2色型色覚において,L・M・S錐体機能の異常をそれぞれ第1異常,第2異常,第3異常という。
先天色覚異常の大多数を占めるのが3色型第1異常および第2異常と2色型第1異常および第2異常である(264ページ表)。L・M錐体の視物質の吸収スペクトルの重複が大きいためこれらは似た色の見え方をし,赤,橙,黄,緑の間で色の違いを感じにくくなる。そのためこれらは赤緑色覚異常red-green color vision deficiencyと総称され,白人男性の約8%,黒人男性の約4%,日本人男性の約5%,日本人女性の約0.2%がこの種の色覚を有している。
【色覚異常の遺伝学】 桿体のロドプシンをコードする遺伝子は第3染色体に,S錐体の視物質タンパク質をコードする遺伝子は第7染色体に存在する。これに対してL錐体とM錐体の視物質タンパク質をコードする遺伝子(以下,L遺伝子,M遺伝子と表記)はどちらもX染色体長腕qの28(Xq28)に存在し,L遺伝子の下流に1個から数個のM遺伝子が結合しているが,これらの遺伝子のうち発現するのは上流の二つのうちのどちらかである。したがってこの遺伝子座において不等交叉による遺伝子欠失やハイブリッド遺伝子の形成が生じると,赤緑色覚異常を生じさせる原因となる。
X染色体上にL・M遺伝子が複数並んでいるにもかかわらず二つの遺伝子だけが色覚にかかわるので,遺伝子型と表現型が一致しないことがある。たとえばL・L・M遺伝子の順で並んでいる場合は,L・M遺伝子ともに染色体上にあっても色覚検査では2色型第2異常を示す。逆にL・M・ハイブリッド遺伝子の順に並んでいる場合は,遺伝子検査でハイブリッド遺伝子が検出されるにもかかわらず色覚検査では正常3色型色覚を示す。L・M遺伝子の180番目のアミノ酸はセリンであるが,これがアラニンになると吸収極大波長が8nm変化する。このような者の割合が日本人の場合それぞれ22%および10%いる。このため正常3色型色覚といえども,ハイブリッド型遺伝子をもっている可能性を含め遺伝子的に多型,色覚も多様である。
赤緑色覚異常は伴性劣性遺伝をする。男性に赤緑色覚異常が多いのはX染色体が一つだからであり,女性に少ないのは二つあって片方のX染色体に変異があってももう一方の正常型遺伝子が補うからである。変異のあるX染色体をもつのに正常色覚の表現型を示す女性を保因者carrierとよぶ。これに対し,異常3色型色覚および2色型第3異常は常染色体優性遺伝をする。
先天色覚異常の原因が遺伝子にある以上,もしこれが病気なら根本的な治療法は遺伝子治療である。近年サルの色覚異常の遺伝子治療に成功したとの報告があり,この成果は錐体より先の神経回路の形成が生得的か後天的かという興味深い問題を提起するとともに,ヒトへの応用の可能性を開くものである。しかし治療の必要性やコストの面から,遺伝子治療は現実的ではないであろう。
【色覚検査】 仮性同色表isochromatic plateは色覚検査表plate testともよばれ,数字などの形と背景とが色覚異常者にとって見分けにくい色の組み合わせから構成されている。短時間で多人数の集団から色覚異常の疑いのある者を抽出するスクリーニングを目的としている。現在までに多数の仮性同色表が考案されていて,なかでも石原式色覚検査表Ishihara testは国内外で最も定評のある検査表の一つである。パネルD-15テストpanel D-15 testは色相環配列検査の一つで,色相環から抽出された16個の色のついたキャップからなり,被検者は基準の色に近い順に残りの15個のキャップを並べる。色覚異常の程度を強度と中程度以下に判定することを目的としていて,典型的なパターンを示す場合は第1異常と第2異常の診断が可能である。アノマロスコープanomaloscopeは色合わせ法(等色法)を行なって赤緑色覚異常を確定診断することを目的とした検査器である。円の下半分に基準となる黄色(589.3nm)の光が呈示され,上半分に赤色(671nm)の光と緑色(546nm)の光が重ねて呈示される。被検者は上半分の二つの光の混合比を変化させて下半分と同じ色にする。混合比が正常と異なるのが異常3色型色覚で,第1異常と第2異常の判定をすることができる一方,強度の異常3色型色覚と2色型色覚の区別は困難である。
【職業・資格の制限】 1850年代から色覚異常をもつ蒸気機関車運転士や船舶操縦士が信号を見誤って事故を起こす可能性が主張され始め,のちに各国で鉄道業や海運業への従事において色覚による制限が設けられた。この制限は軍人,警察官,消防士,医師,教員等にも広がっただけでなく,これらの職業に通じる教育機関への入学資格の制限ももたらした。日本では1980年代まで色覚異常をもつ者に入学制限を設ける大学が多数あったが,現在では一部に残るだけである。カラーバリアフリーやユニバーサルデザインの思想が普及し,色覚による職業制限も近年なくなりつつある。 →色 →視覚 →進路指導
〔鈴木 聡志〕
出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「色覚異常」の意味・わかりやすい解説
色覚異常 (しきかくいじょう)
色の区別ができないか,困難な状態をいう。一般には色盲color blindnessあるいは色弱color weaknessとして知られるが,最近は色覚異常としてまとめることが多い。先天性と後天性のものがあるが,大部分は先天性のもので,これは色覚の機能不全による。
先天性の色覚異常
一色型色覚,二色型色覚および異常三色型色覚に分類される。一色型色覚は1色しか判別できないもので,いわゆる全色盲,全色弱がこれにあたり,二色型色覚は部分色盲ともいわれ,赤緑色盲および青黄色盲が含まれる。異常三色型色覚は,いわゆる色弱のことで,赤緑色弱と青黄色弱とがある。さらに,二色型色覚と異常三色型色覚については,表のように分類される。しかし,赤緑色盲と赤緑色弱との境界は,日常生活のうえでは画然としてはいないので,赤緑色覚異常とまとめて呼ぶことがある。この赤緑色覚異常が先天性色覚異常の大部分を占めており,青黄色覚異常はきわめてまれである。赤緑色覚異常には赤色盲と緑色盲が含まれ,ともに赤緑色覚が不完全であり,赤色盲は赤色とその補色の帯青緑色との区別がつかず,緑色盲は緑色とその補色の帯紫赤色との区別がつかない。しかし,色盲の人が色をどのように感じているかは,ほんとうのところはわかっていない。赤緑色覚の異常のほかは異常なく,視力やそのほかの機能の障害もない。色弱は色盲より程度が軽いといわれているが,両者の区別は明確ではなく,日常生活のうえでは,第1と第2,色盲と色弱の区別ができないとされている。また,日常生活で第三者が色覚異常と気づくことは少ない。まれに,図画を描かせたとき木の葉の色をまちがえたり,靴下や箸(はし)の色を誤って異なった色のものを同じ色のものと思って使っていることで気づくことがある。
一色型色覚である全色盲および全色弱は,赤緑色覚異常とはまったく異なったものである。全色盲は杆体一色型色覚と呼ばれ,錐体の機能のまったく欠如しているものである。したがって,色覚をまったく感じないほか,視力が通常0.1以下で,明るいところでは見えない,いわゆる昼盲があり,非常にまぶしがり,眼振がある。全色弱は,錐体一色型色覚と呼ばれ,色覚はまったく感じないが,視力そのほかの異常はない。しかし,全色弱は非常にまれとされている。
色覚異常と遺伝
先天性の色覚異常は遺伝によるものが大部分で,全色盲は常染色体劣性遺伝とされており,両親が血族結婚のものに多くみられる。赤緑色覚異常はX染色体劣性遺伝であり,伴性劣性遺伝といわれるように,男と女とでは色覚異常発現の頻度が異なる。日本人では,男子は4~5%,女子はその1/10以下の頻度で赤緑色覚異常の先天性色覚異常者が発現している。これはX染色体劣性遺伝では,X染色体に色覚異常の遺伝子があった場合,男子ではX染色体が1本しかないので,すべて色覚異常となるが,女子ではX染色体が2本あるため,そのうち1本のみに色覚異常の遺伝子があっても発現しないで,保因者となるためである。したがって,女子が色覚異常となるためには,父親が色覚異常で,母親は色覚異常か保因者でなければならないが,男子では父親が正常であっても,母親が色覚異常であればすべてが,保因者であれば2人に1人が色覚異常となる。全色弱および青黄色覚異常については,非常にまれなもので,遺伝形式もわかっていない。
後天性の色覚異常
後天性の色覚異常は,網膜や視神経の疾患によって起こり,もとの疾患によってさまざまな色覚異常が起こる。この場合,色覚ばかりでなく視力も障害されるのが通常である。
色覚異常の診断と日常の生活
臨床上は色盲表およびアノマロスコープanomaloscopeによって,赤緑色覚異常の分類が行われるが,この分類は日常生活での不便さとは必ずしも一致しない。そこで,職業の適性検査などでは,ランターン試験や色相配列検査を併せて行う。ランターン試験は赤,緑,黄などの色を答えさせる検査で,色相配列検査は少しずつ異なる色を見せて,似た色の順番に並べさせる検査である。これらの結果は日常生活との関連が少しわかるものと思われる。
色覚異常の最初の記載は1777年とされているが,1800年代に色覚異常の研究がはじめられた動機は,交通事故を起こした鉄道員が色覚異常であったことによるとされている。色覚異常では,現在確実な治療法がないことから,職業適性の問題が指摘されてきた。交通関係の仕事をはじめ,染色や化学関係など,色を多く使う仕事などは色覚異常の人に適さない。色盲であっても画家として大成している人もいるが,色に対する感覚が正常な人と異なっている点を考えると,無理に色を多く使う職業をえらぶ必要はないと思われる。進学や就職にあたって,一部の学校や職場ではまだ色覚異常者を不当に制限するところがあるが,日常生活ではさほどの不自由はないので,正しい医学知識にもとづいて判断することが必要である。
執筆者:久保田 伸枝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「色覚異常」の意味・わかりやすい解説
色覚異常
しきかくいじょう
色覚が通常の場合と違い、すべての色、あるいはある色の識別ができないか、困難な状態をいう。人間の網膜の視細胞には錐状体(すいじょうたい)(錐体)と桿状体(かんじょうたい)(桿体)とがあるが、錐体は明るい所で働いて色の情報を感じるが、桿体は暗い所で働いて色を感じない。したがって、ある程度以上の明るさがなければ人間の目は色を感じない。網膜には赤・緑・青に対する感受性を有する3種の錐体受容器があり、色を伝える信号に変えて脳に送り、色の感覚が生じる。色覚異常は大きく先天性の色覚異常と後天性の色覚異常に分けられる。また、色盲ということばは、かつては色覚異常全般をさす一般的な呼び名として用いられたが、学術的には色盲と色弱は明確に分類されている。なお、「色盲(しきもう)」「色弱(しきじゃく)」という表現は、現在はほとんど用いられない。
後天色覚異常は網膜や視神経疾患によっておこるもので、先天性を除いたすべての色覚異常をさし、ヒステリーなどによっておこる心因性のものも含まれる。
先天色覚異常は一色覚(いちしきかく)(旧称は全色盲)、二色覚(にしきかく)(旧称は赤色盲(せきしきもう)、緑色盲(りょくしきもう)、青黄色盲(せいおうしきもう)、青色盲)、異常三色覚(さんしきかく)(旧称は色弱)に大別される。
[太田安雄]
一色覚
外界の事物を白黒写真のようにただ明暗と濃淡を感じる状態で、桿体(かんたい)一色覚(旧称は桿体一色型色覚)と錐体一色覚(旧称は錐体一色型色覚)がある。桿体一色覚は、視力が0.1以下で、明所でまぶしく、眼球振盪(しんとう)(眼球の律動的運動で、眼振ともいう)があり、錐体機能が欠け、桿体機能だけが存在する。緑(通常では黄)をもっとも明るく感じ、赤は暗く感じる。錐体一色覚は、錐体の機能をもち、一色覚でありながら視力は正常か正常に近いものが多く、まぶしさや眼振がない。
二色覚
網膜に存在する3錐体のうち、赤錐体(正式名称は長波長感受性錐体またはL-錐体)の欠損したものを1型二色覚(旧称は赤色盲、第1色盲)、緑錐体(中波長感受性錐体またはM-錐体)の欠損したものを2型二色覚(旧称は緑色盲、第2色盲)、青錐体(短波長感受性錐体またはS-錐体)の欠損したものを3型二色覚(旧称は青黄色盲、青色盲、第3色盲)とよんでいる。1型二色覚は赤とその補色の青緑が灰色に見え、2型二色覚は緑とその補色の赤紫が灰色に見える。3型二色覚は赤と緑は感じるが、青と黄を灰色に感じる。
異常三色覚
赤・緑・青の3種の色光の混色により、すべての色光と等色できるが、それぞれの錐体に異常あるいは減弱があり、この錐体異常が赤錐体にあれば1型三色覚(旧称は赤色弱、第1色弱)、緑錐体にあれば2型三色覚(旧称は緑色弱、第2色弱)、青錐体にあれば3型三色覚(旧称は青黄色弱、青色弱、第3色弱)を呈する。異常三色覚は、通常と変わらない軽度のものから、二色覚に近いものまで、その範囲は広く存在している。異常三色覚は、異常三色型色覚ともよばれた。
色覚異常の遺伝形式
赤緑色覚異常(1型二色覚と2型二色覚)は、日本では男性の20人に一人にみられ、女性の500人に一人にみられる。その遺伝形式は伴性潜性遺伝(X染色体潜性遺伝)で、女性では性染色体が1対あるので、二つの染色体がともにその遺伝質をもたない限り症状として発現せず、男性では1個あるだけなので遺伝質があれば症状は発現する。したがって、女子には出現率が低く、保因子をもつ母親を介して子の男子に遺伝する。
3型二色覚(青黄色覚異常)の遺伝形式は常染色体顕性遺伝であり、その出現率の頻度は1万人ないし5万人に1人といわれている。
[太田安雄]
治療・予後
色覚異常は先天性の場合がほとんどであるから、自分では認識しておらず、自分なりに緑あるいは赤を認知しているので、日常生活にはあまり支障はない。現在、先天性の色覚異常に対する治療法はいずれも確立されていない。後天性のものでは原病の治療が第一で、通常は疾患の治癒とともに色覚も改善する。
後天的な色覚異常は疾患や障害によって二次的におこり、色覚異常の程度は症状の増悪(ぞうあく)や軽快に並行している。この異常は、しばしば種々の症状より先に現れ、疾患が治癒したと考えられる時期にも残っていて、完全に通常の状態に戻るまでにはかなり時間を要する。疾患の際の色覚検査は、予後の判定や診断に役だつので臨床的検査として用いられる。
[太田安雄]
家庭医学館 「色覚異常」の解説
しきかくいじょうしきもうしきじゃく【色覚異常(色盲/色弱) Color Blindness】
色覚異常とは、色に対する感覚が正常とは異なるものです。その程度によって色の識別がまったくできない色盲(しきもう)から、まぎらわしい色の識別だけができない色弱(しきじゃく)まであります。
色覚異常は先天性と後天性に大きく分けられます。
■先天色覚異常
健常人では、すべての色は赤(長波長光)、緑(中波長光)、青(短波長光)の3種類によってつくられていますが、先天色覚異常はこれらに問題があり、すべての色の知覚をつくり出すために必要とする色の数によって分類されています。つまり3種類のうち1種類が正常でない異常三色型色覚(いじょうさんしょくがたしきかく)、2種類だけで色が成立する二色型色覚(にしょくがたしきかく)、1種類だけの一色型色覚(いっしょくがたしきかく)に分けられます。
また、色覚検査での色のまちがいの性質により、先天赤緑異常(せんてんせきりょくいじょう)、先天青黄異常(せんてんせいおういじょう)、先天全色盲(せんてんぜんしきもう)などに分類されます。
これらのうちでいちばん多く、問題になるのは先天赤緑異常です。こうした異常には、本人は気づかないままで、色覚検査などで初めて発見されることが多いものです。
■後天色覚異常
生まれたときは正常の色覚であった人が、なんらかの病気にかかり、その症状として色覚の異常をきたしたものをいいます。
[原因]
先天性の色覚異常は、伴性劣性遺伝(ばんせいれっせいいでん)をすることがわかっています。発生頻度は男性に多く、全人口の約5%であるのに対して、女性は約0.2%にしかみられません。
後天性の色覚異常の原因には、眼底、視神経、脳などの視覚に関係する部位の障害によるものや、心因性のものなどがあります。この場合、色覚の異常だけでなく、視力の低下や、違和感のあるものの見え方などの症状を同時に自覚することがあります。
[治療]
先天色覚異常には、治療法はありませんが、生涯のある時期に正確な検査をして色覚異常の病型と程度を診断してもらい、的確な指導を受けることはたいせつです。
たいていの人は、代償能力と訓練によって問題なく日常生活を送り、ほとんどの職業につくことができますが、色覚の異常の程度によっては職業適正があって、色彩を直接取り扱う職業などでは制限が加わることもあります。色覚異常を理由に就職などを不必要に制限するような風潮がなくなってきたのは、たいへん好ましいことです。
色覚異常といっても、色に対する感覚が、色覚の正常な人とやや異なっているだけで、特別な配慮はいらないことが多いのですが、程度もさまざまなので、医師に相談して早めに状態を把握し、その後の対処を決めていくことが必要です。
後天色覚異常では、原因になっているものを治すことがたいせつで、治療法は原因によって異なります。
目の病気が原因である場合には、視力、視野、眼底などの眼科的検査が必要です。また、心因性のものでも眼科的検査を行ない、器質的な変化がないことを調べなくてはいけません。
したがって、ものの色が以前とはちがって見える、なんとなく見にくいなどの症状を自覚した場合には、眼科を受診して詳しい検査をしてもらうことがたいせつです。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「色覚異常」の意味・わかりやすい解説
色覚異常
しきかくいじょう
colour deficiency; defective colour vision
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「色覚異常」の意味・わかりやすい解説
色覚異常【しきかくいじょう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...