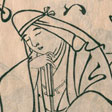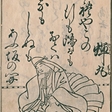精選版 日本国語大辞典 「蝉丸」の意味・読み・例文・類語
せみまる【蝉丸】
- [ 1 ]
- [ 一 ] 平安初期の歌人。伝説的人物で、宇多天皇の第八皇子敦実親王に仕えた雑色(ぞうしき)とも、醍醐天皇の第四皇子ともいう。盲目で琵琶に長じ、逢坂(おうさか)の関に庵を結び隠遁生活をしたと伝えられる。生没年不詳。
- [ 二 ] 謡曲。四番目物。各流。作者不詳。古名「逆髪(さかがみ)」。延喜帝の第四皇子蝉丸の宮は幼少から盲目だったので、帝は清貫(きよつら)に命じて逢坂山に捨てさせる。蝉丸は頭を剃り、琵琶をだいて泣き沈む。一方、髪がさか立つ病気を持つ姉の逆髪の宮は、狂乱の体でさまよい歩いて逢坂山に至り、蝉丸の琵琶の音にひかれて弟と再会する。二人は互いの身の不幸を嘆き、やがて名残りを惜しみながら別れる。
- [ 三 ] 浄瑠璃。時代物。五段。近松門左衛門作。元祿一四年(一七〇一)大坂竹本座での上演は、竹本義太夫が筑後掾(ちくごのじょう)を受領した祝儀として再演されたもので、初演は元祿六年二月以前と推定。謡曲「蝉丸」に題材をとる。琵琶の名手蝉丸の宮は直姫を恋し、北の方の怨念で盲目となり、逢坂山へ捨てられるが、姉宮逆髪の祈祷で開眼する。
- [ 四 ] 横笛の名器の名。
- [初出の実例]「蝉丸 或記云く、保延四年十一月廿四日夜半許、土御門内裏炎上のとき焼失」(出典:続教訓鈔(14C前か))
- [ 2 ] 〘 名詞 〙
- ① ( [ 一 ][ 一 ]が琵琶に秀でていたところから ) 琵琶法師をいう。
- [初出の実例]「蝉丸に似た人をよぶ大法事」(出典:雑俳・柳多留‐二四(1791))
- ② 蝉のこと。
- [初出の実例]「晴天の蝉丸は声ども惜しまずぞ叫びける」(出典:御伽草子・貴船の本地(室町時代物語大成所収)(室町末))
- ① ( [ 一 ][ 一 ]が琵琶に秀でていたところから ) 琵琶法師をいう。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「蝉丸」の意味・わかりやすい解説
蝉丸(能)
せみまる
能の曲目。四番目物。五流現行曲。世阿弥(ぜあみ)作か。古くは『逆髪(さかがみ)』ともよばれた。盲目に生まれついた皇子蝉丸(ツレ)は、父の帝(みかど)の命令で逢坂(おうさか)山に捨てられる。護送していく臣下の者(ワキ)は嘆き悲しむが、蝉丸は前世の業(ごう)をこの世で果たさせる親の慈悲と、あきらめを語る。剃髪(ていはつ)させられ、ひとり山に取り残されると、さすがに蝉丸も泣き伏すが、博雅三位(はくがのさんみ)(アイ狂言)が庵(いおり)をしつらえて保護にあたる。姉宮の逆髪(シテ)は、狂気の放浪の途中に、この逢坂山に来かかり、蝉丸の弾く澄んだ琵琶(びわ)の音を聞きつけ、弟との対面となる。幸薄い姉弟のはかない逢瀬(おうせ)。やがて姉宮は、またあてどない旅に別れていく。悲痛な宿命を描きながら、舞台に流れるむしろ甘美な叙情性で人気曲の一つ。第二次世界大戦中は、皇室に対する不敬な能として、上演が禁止されていた。典拠は『今昔物語』『平家物語』など。
[増田正造]
蝉丸(歌人)
せみまる
生没年不詳。平安初期の歌人。「これやこの行くも帰るも……」の歌で知られる伝説的人物で、その出生も宇多(うだ)天皇第八皇子敦実(あつざね)親王に仕えた雑色(ぞうしき)とも、醍醐(だいご)天皇の第四皇子とも伝える。盲目で琵琶(びわ)に長じ、逢坂山(おうさかやま)の関に庵(いおり)を結び、隠遁(いんとん)生活をした。源博雅(ひろまさ)はその琵琶に3年間師事をした、と伝える。盲目の琵琶法師たちの座である当道では、その職業の起源を語る蝉丸の伝説は長く重んじられてきた。謡曲『蝉丸』は、盲目のため帝(みかど)から逢坂山に捨てられた蝉丸と、狂い出た姉の逆髪宮(さかがみのみや)の琵琶の音にひかれての再会の物語である。蝉丸伝説は『今昔物語集』巻24や『平家物語』巻10にも記されている。
[渡邊昭五]
百科事典マイペディア 「蝉丸」の意味・わかりやすい解説
蝉丸【せみまる】
→関連項目狂乱物
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蝉丸」の意味・わかりやすい解説
蝉丸
せみまる
蝉丸
せみまる
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「蝉丸」の解説
蝉丸 せみまる
「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」(「小倉百人一首」)で知られる伝説的人物。宇多天皇の皇子につかえた雑色(ぞうしき)とも,醍醐(だいご)天皇の第4皇子ともいう。「今昔物語集」では琵琶(びわ)の名手とされる。謡曲に「蝉丸」がある。
歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「蝉丸」の解説
蝉丸
(通称)
せみまる
- 元の外題
- 蝉丸女模様
- 初演
- 享保10.11(江戸・市村座)
蝉丸
せみまる
- 初演
- 元禄11.11(大坂・岩井半四郎座)
出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...

 平安前期の伝説的
平安前期の伝説的