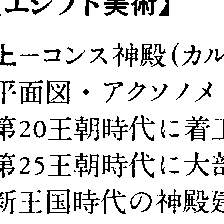改訂新版 世界大百科事典 「エジプト美術」の意味・わかりやすい解説
エジプト美術 (エジプトびじゅつ)
広義には,先史時代から現代に至る,エジプトおよびその影響下にあった地域の美術活動を総称するが,一般には,王朝時代を中心とする古代エジプト美術を指す。王朝の終末以後の美術については,コプト美術,イスラム美術などの一環として考察される場合が多い。本稿の記述も,王朝時代を中心とする。
エジプト美術は,古代エジプト人の,きわめて特色のある世界観,宗教観から生まれた。この世界観,宗教観を育てたものは,おそらく,その特異な自然環境,風土であろう。長い先史時代を経て後,上・下(南・北)両エジプトを唯一の君主が支配する統一国家が形成され,王朝時代に入るが,この段階で,美術は飛躍的に発展し,エジプト特有の表現形式も確立された。第3王朝以後,王権の拡大,国力の増進に伴って,美術は,ファラオ(エジプト全土の王)の権威と富を象徴する有効な手段として重要性を増し,神々の体系の整備,厚葬の風習の確立とあいまって,特色のある宗教的宮廷芸術の性格を強めていくのである。
とくに美術の性格に決定的な影響を与えたのは,エジプト人の強固な来世観である。彼らは霊魂の不滅を信じ,いったん肉体を離れた魂は,その肉体が亡びない限り,再び戻って,死者は永遠の生を享受すると信じられた。これは,放置された死体がミイラ化し,永くその形をとどめていることなどから発した信念であろうが,このために,極端な厚葬の習俗が生じ,壮麗な墳墓や莫大な量の副葬品がつくりだされることとなった。今日残るエジプト美術の遺例は,ほとんどすべて,この種の,葬祭に関連のある作品である。
表現形式の上から見れば,エジプト美術は,いくつかの顕著な特色をもっている。まず抽象的形態への強い指向があり,ある理念を単純な幾何学形態に託することが珍しくない。その最も代表的な例が正四角錐(横から見れば三角形)の形をとるピラミッドである。また,大きな特色として,形態の記号化,象徴化が挙げられる。その傾向の極限を示すものがヒエログリフであろうが,たとえば円が太陽を,蓮が下エジプトを,禿鷹が上エジプトを象徴するなど,造形の基本に常に象徴性があると言っても過言ではない。また,事物の描写に当たって,目に映る光景をそのまま描かず,個々の物象をいったん観念像としてとらえ,それを集積して,一つの全体像を構築する。たとえば人体を描く場合,体の諸部分の像は観念上定型化しており,それを配置することによって一つの人体をまとめるのである。エジプト美術の多くが,一見してエジプトのものとわかるのは,この観念表象的性格による。これは一面において,エジプト美術をきわめて類型的かつ反自然主義的なものとしたが,同時に,そこに他に類を見ない,簡潔で明晰な表現力を与える結果となったのである。
執筆者:友部 直
建築
先王朝時代
先王朝時代のエジプトの人々は木,草を編んだマットなどを使ってテントのような住居を建てていたらしい。これらの原始的な住居に由来する形が様式化されて後代のエジプト建築の細部に残っている。壁の角や上部につけられる丸い繰形(くりかた)や,エジプト風コーニスと呼ばれる湾曲した軒蛇腹(のきじやばら)などがそれである。木や草で編んだ壁を土で塗り固めたり,壁土や日乾煉瓦や粗石で壁を造ることもあった。後世の建築に見られる外壁面の傾斜はこのような土壁のなごりと解釈されている。古い住居の平面は円い形が多かったが,矩形平面の家も造られた。墓も円い竪穴から矩形の竪穴に変化し,竪穴の側面を日乾煉瓦で固め,内部に間仕切りが造られ,材木で天井が造られ,墓室の壁に壁画を描くものも現れた。
初期王朝時代
統一王朝の現れた前3000年ころには建築も急速に発展した。住宅の遺構そのものは乏しいが,有名な《蛇王の碑》などに描かれる〈宮殿正面〉は,規則的に設けられた角塔と1対の入口,壁面につけられた装飾的なニッチ(壁龕(へきがん))やバットレス(控壁)など,当時の宮殿の外観をよく示している。〈宮殿正面〉のモティーフは石棺や王墓の外壁面にもしばしば用いられた。墓,特に王墓はしだいに壮大さを増し,地下の墓室は煉瓦ばかりでなく輸入された木材のパネルで仕上げられたものもある。墓室は大きく深くなり,やがて地下の岩盤深く掘りこまれ,埋葬のために設けられた階段や斜路は埋葬後落としこみの石扉で密閉されるようになった。墓の上には煉瓦づくりの擁壁をめぐらし,その中に土砂をつめて,ゆるく湾曲した上面をもつ墳丘が造られた。このような長方形の台形の墓をマスタバと呼ぶ。アビドスの王墓では単純なマスタバの前面に1対の石碑と供物台が置かれ,全体を取り囲む周壁がめぐらされていた。マスタバの壁面に二つのニッチが設けられ,あるいはそこに〈偽扉false door〉がつけられることもある。さらにマスタバの外壁全面に複雑なニッチのある宮殿正面の装飾をつけ,生前の宮殿のダミーとするものもある。アビドスで発見された当時の神殿の内陣部は,共通の前室である横長の広間の奥に,三つの神室が並列する形式をもっていた。
古王国時代
古王国時代になると王墓は飛躍的に大規模になり,建物全体が石造になった。第3王朝のジェセル王の墓(サッカラ)は最初マスタバとして建造が始まったが,数度の計画変更によって,マスタバを6段に積み重ねた〈階段状ピラミッド〉になった。その後王墓は正四角錐の形をしたピラミッドに移行したと思われる。その形を完全に保っている遺構としてはダフシュールにある第4王朝のスネフル王のピラミッドが最も古い。ギーザのクフ王の第1ピラミッドを頂点として,ピラミッドは古王国時代最大の建造物であったので,古王国時代は〈ピラミッド時代〉とも呼ばれる。ジェセル王の墓は,階段状ピラミッドを中心にして,葬祭神殿,宮殿,神殿,倉庫など多くの建物があり,東西277m,南北544mの長方形の墓地全体に高さ10.5mの石造周壁をめぐらしていた。それはメンフィスにあった生前の王の宮殿となんらかの類似性をもっていたと想像されている。建築は石造であるが,煉瓦や木や草の建物に由来する技術や形が随所に認められる。たとえばフルーティング(溝彫)や胡麻殻決(ごまがらじやくり)をつけた柱も,多くはナイル流域に育つ植物の形を模していた。ギーザの第1ピラミッド(底辺230.4m,高さ146m)は,ピラミッド前面の葬祭神殿と,ナイルの谷にのぞむ〈流域神殿〉を長い廊下でつないでおり,墓所の性格を最も明確に示している。柱は単純な角柱となり,すべての建物は単純で抽象的な形の部材で構成されていた。第5王朝に入ると,ピラミッドはむしろ小さくなって祭儀用神殿の比重が大きくなり,再びヤシやパピルスなどの形をもつ柱が使われる。また第5王朝時代にはいくつかの太陽神殿(エジプトの最高神,太陽神ラーの神殿)が建てられた。首都メンフィスの北西郊のアブー・グラーブAbū Ghurābにある太陽神殿はナイルの谷にのぞむ門から廊下を通って神殿に達する。神殿は中庭に建てられた巨大なオベリスクとその前面にある祭壇が中心となっていた。住宅としては,ジェセル王の墓にある〈王のパビリオン〉(第3王朝)がある。これは長方形の建物が縦に二分され,一方が玄関,広間,居間などに,他方が私生活空間にあてられていた住居が石造化されたものと見られている。ギーザにある第4王朝の住宅では,正方形に近い平面で,中央部の中庭の周りに広間や居室が非対称的に配置されていた。
中王国時代
古王国末期から力を増した封建勢力である州侯たちは,ベニ・ハサンBeni Ḥasanやアスワンなど各地の岩山の斜面に掘りこまれた横穴式の岩窟墓を造った。前面は建築物の正面のように整形され,しばしば柱廊玄関が造られた。内部には一つまたは二つの広間があり,広間の間に長い廊下を造って奥行きを深くするもの,広間に列柱を造るものもある。墓室は普通奥の広間の床に掘られた竪穴の底にある。また墓の前面に葬祭神殿,廊下,〈流域神殿〉を備えた古王国時代の王墓の形式を再現しようとするものもある。テーベの州侯であった第11王朝初期の王の墓もこのような岩窟墓であったが,同王朝のメンチュヘテプ2世はディール・アルバフリーDīr al-Baḥrīに,高い基壇の上に柱廊に取り囲まれた小ピラミッドと,その奥にある列柱中庭と,半ば岩山に掘りこまれた葬祭神殿から成る画期的な神殿を建てた。都をメンフィス近郊に移した第12王朝の諸王は再びピラミッドを建てた。中王国時代のピラミッドは底辺およそ100mほどで,石は重要な部分にしか使われず,芯積みは煉瓦であった。しかし,墓室および廊下には,盗賊に備えて密閉のための巧妙な装置が発達したことや,葬祭神殿などの付属施設が大規模になったことなどに特色がある。ヘロドトスの伝えるラビュリントスは,ハワーラHawāraにあるアメンエムハト3世の葬祭神殿であった。葬祭神殿以外の神殿では,横長広間の前室の奥に三つ,七つ等の小神室が並列するものや,横長広間に列柱を建て,その奥に,前後に開口部をもつ神室を独立に設け,神室を取り巻く廊下に多くの小室を開く形式が見られる。カルナック大神殿第3ピュロン(塔門)の用材に転用されていたセンウセルト1世の即位30年祭典用の小神殿は,前後に階段つき斜路をもつ基壇上に合計20本の角柱で支えられた吹き放しの小祠堂であった。
センウセルト2世がラーフーンal-Lāhūnのピラミッド建設のために造った職人の町(ピラミッド都市)は,多くの住宅と共に,直交道路をもつ計画都市の遺跡としてよく知られている。職人の住宅は95~170m2の大きさで,中庭式の平面であった。町の北辺には工事監督官の住宅など,数軒の大邸宅があった。約2400m2を占める大邸宅は,居間,寝室,浴室などから成る主人用の続き部屋を中心に,婦人用の部屋,事務所,倉庫部分などが多くの中庭と組み合わせてまとめられていた。また,この時代エジプトの支配は第2急湍(たん)の上流セムナSemna付近まで及び,辺境防衛のための要塞がナイルの岸や川中の島に残っている。これは防御用の塔をつけたがんじょうな城壁や空濠で守られ,内部は直線のメーン・ストリートを軸に司令部,神殿,兵舎,倉庫などが整然と配置されていた。
新王国時代
第18王朝から王墓はテーベ西岸の山中にある〈王家の谷〉の岩山の中にひそかに掘りこまれ,葬儀や供養は山を隔てて別に建てられた葬祭神殿で行われた。王墓はいくつかの広間をへて地底深くのびる廊下の奥にあり,石棺や副葬品を納める諸室があった。葬祭神殿は基本的にはアメン(およびムートとコンス)の神殿で,それらの神室群の左側に王の葬祭用神室群,右手にラー・ハラクティの祭壇のある中庭があるのが普通である。この内陣部の前には多柱室,中庭,ピュロンなどがあって,一般の神殿と同様の構成になっている。しかし,ディール・アルバフリーのハトシェプスト女王の神殿のように階段テラス状の配置をもつユニークな例,マディーナト・ハーブーMadīnat-Hābūのラメセス3世神殿のように神殿の周囲に宮殿,管理事務所,倉庫群,兵舎などを配置し,その全体を城壁と濠で囲んで要塞のようになったものもある。一般に神殿の正面には,入口の両脇に傾斜した壁面をもつ二つの塔をつけたピュロン(塔門)を建てる。入口を入ると柱廊つきの中庭,前玄関をへて多柱室がある。多柱室は中央3スパン部分の天井が高い横長列柱広間で,高窓を備えている。その奥は聖所で,中央には前後に入口をもつ聖舟室と,最奥に神像を納めた厨子を安置する神室があり,聖舟室の左右には多くの小室がある。カルナックのコンス神殿(カルナック神殿)はこの典型的な実例である。カルナックの大神殿やルクソルの神殿のような巨大な神殿は,これらの基本的要素を繰り返し重複して建て増しされたものである。神殿の壁面は一面に浮彫やヒエログリフが彫刻され,華麗に彩色されていた。またアブ・シンベルの二つの神殿のように,神殿全体が岩山の中に掘りこまれているものもある。テル・エルアマルナで出土した大邸宅の主屋は,ほぼ正方形の平面の一隅に玄関が突出していた。内部はほぼ3等分され,列柱のある横長のホールと中央広間,そして居間,寝室,浴室,便所などのある私室部分にあてられていた。中央広間には壁に接して一段高い壇が主人の座としてあり,反対側に設けられた壇には手を洗う水がめが置かれていた。マルカタに発見された宮殿も,居室部分の構成はこれと似ている。ディール・アルマディーナなどの職人の町にはもっと簡素な住宅が知られている。
王朝末期
プトレマイオス王朝からローマ時代にかけてはデンデラ,エドフ,フィラエなどに重要な神殿が建てられた。建築の基本構成や様式はほぼ新王国時代のそれを踏襲しているが,多柱室前面は解放的になって,中庭との境に柱の半分ほどの高さの間仕切り壁が建てられるようになった。また諸種の植物を浮き彫りした〈混合式〉柱頭が発展した。
執筆者:堀内 清治
彫刻
初期王朝時代にすでに丸彫で写実的表現を目指し,浮彫では国王の威徳を物語る叙事的表現を試みた。〈パレット〉と仮称される石の浮彫は後者の例で,構図は画趣的だが表現技巧はまだ原始的である。しかし聖動物を取り扱った浮彫に第1王朝の《蛇王の碑》(ルーブル美術館)があって,構図は単純だが,正確な自然観察と洗練された彫技と厳粛な効果とを見せており,別系統の工房もあったことが知られる。丸彫は象牙のものには軽妙なものがあるが,石の肖像彫刻は猪首で,両腕も胴に密着し,両脚も離れていない。
この鈍重な原始性からの脱却は古王国の第3王朝に始まり,第4王朝にはそれをみごとに達成し,写実的洗練と彫刻的量感の安定とをもって大型の肖像彫刻に成功した。エジプト人は,肉体と〈死者の霊〉カーとが不離の一体となってこの世に生き,この両体の分離が死であると考えたが,絶対永遠の分離ではなく,死者の霊は墳墓内に永くとどまり,ミイラとなって玄室に存する肉体との神秘的合体によって,墓の内外を自由に往来し,現世におけると同じように供物を飲食し舞楽を享楽する神通力を得ると信じた。また死者の生前のおもかげを彫像として墓内の密室に安置し,死者の霊はこの肖像に宿ることによっても神通力を得ると信ぜられた。肖像彫刻はまた供養儀式を行う礼拝堂にも安置された。これらの彫刻は死者の生前の最も元気で栄えたころのおもかげを写した。これが古代に他に先んじてエジプトが肖像彫刻を発達させた原因であった。エジプトは多神教国であったから神像彫刻も制作した。オシリスやアメンは人間態に表現されたが,人間の理想的肉体美を追求する情熱はなかった。頭部だけ動物になっている神像,女神ハトホルのように牝牛の耳をもつ神像,スフィンクスのように人頭で獅子身の精霊像,または全身動物になっている神像や精霊像のあることは,エジプト彫刻の特徴である。神々にはホルスの鷹,アメンの牡羊,ハトホルの牝牛,女神バステートの牝ネコというように,それぞれの聖動物があって彫刻で表現されたので,これが動物彫刻の発達を促した。神殿には神に最も近いものとしてファラオの肖像も安置された。
彫像の材料には,セン緑岩,花コウ岩,アラバスター,石灰岩,玄武岩,片岩,石英,粘板岩などのほか,シリア方面から輸入されたシーダー(レバノン杉),サイプレス(糸杉)などの木も用いられた。金属像の大きなものは少ない。石灰石像や木像は塗色して仕上げた。男性像,女性像の肌は塗色を異にした。塗色はすべて平らで,色の対照は強い。目の実感を求めてしばしば玉眼が用いられた。角膜に乳白色の石英,虹彩に水晶,瞳子に黒檀の微粒,眼縁に黒くした銅を用いたものが多い。眼縁がとくに太いのが特殊な印象を与えるが,これは眼病よけに黒い目ばりを入れた習俗を表したものである。彫像には立像と座像とがあり,男性の立像は原則として左足を一歩踏み出している。座像には腰かけているものと,あぐらをかくものとがある。神殿に安置されたファラオの像にはアジア風に座したものや,腹ばいになったものもあって,謙譲な情操を表している。すべて動勢を抑制し,安定した正面性(正面に正しく向いている姿勢)の法則を固守している。この法則を長く破らなかったところにエジプト彫刻の保守性がある。
代表的彫刻(丸彫)を歴史的に見ていけば,古王国の最高の傑作には,第4王朝の《カフラー王の座像》(セン緑岩,高さ1.68m。カイロ博物館)がある。硬質の石の硬度と色沢とを生かして堂々たる量感を現出し,顔形は王者の威厳と慈悲とを兼ねそなえ,体勢は力にみちてしかも安定している。《王族ラーヘテプ夫妻像》(石灰石。カイロ博)は男女の相異なる骨相の表現に成功し,また夫のだいだい色,妻の淡黄色の肌色は鮮明に保たれている。これらは宮廷御用の工房で制作された。夫婦や親子のむつまじく並んでいる肖像はしばしば作られ,左に寄り添う妻が右手を夫の背にまわして胴を抱いている姿も見られる。家臣の像としては,《村長立像》(木,高さ1.10m。カイロ博)や第5王朝の《書記胡座像》(石灰石,高さ0.53m。ルーブル美)がすぐれている。前者はサッカラのマスタバの礼拝堂に安置されたもので,肥満した中年男の肉体の特徴を,後者は耳を澄ましている緊張した表情を,的確に表現している。第4,第5の両王朝はエジプト彫刻の力感ある伝統を確立し,第5王朝の高位の《神官ラーネフェル立像》(石灰石。カイロ博)にも,ヒロイックな力感のきびしさがある。第6王朝の《ペピ1世立像》(カイロ博)は胴体と四肢は槌起(つちおこし)銅板の鋲止め,頭部と手は蠟型の鋳物で,目にはエナメルが嵌装(かんそう)されている。このような技法の肖像彫刻は珍しいが,第6王朝は芸術の衰退期で,ついで80年余の空白の後に中王国が起こる。
中王国は都を北のメンフィスから南のテーベに移し,第11,第12の両王朝に芸術活動が復活し,古王国の伝統を学んだが,むしろ伝統にとらわれない顔つきの個性表出や異邦的要素と思われるものに特色を出し,地方的工房の存在を想像せしめる。《センウセルト3世の頭部》(カイロ博)や《タニスのスフィンクス》(黒花コウ岩,長さ2.20m。カイロ博)がその例である。墓の主の幽界生活に奉仕すると信ぜられた種々の労務姿の人形を副葬した古王国の習俗をうけて,中王国でも雑多の風俗人形を作ったが,木彫が多くなった。遺品では木彫を白しっくいでおおい,さらに彩色して着衣の文様を細かに描いた《供物を運ぶ女》(ルーブル美)が最も美しい。
前1552年ころにテーベを都として新王国の第18王朝が樹立され,外征勝利による財宝獲得やアジアの奢侈の移入によって,彫刻は優雅になり,婦人の顔のやさしみの表出が巧みになり,服飾美に興味が注がれ,かつらの取扱いが細密になった。動物彫刻のすぐれたものも現れた。イクナートンが宗教改革を断行して,テル・エルアマルナに遷都してから作風は一変し,弱々しい感傷味やおかしいほどのデフォルマシヨンを特徴とした。しかし,《王妃ネフェルティティの胸像》(ペンガモン美術館)は肉づけが優雅で,着色も鮮麗である。王の没後アマルナ派は没落し,テーベ派の伝統に復帰したが,アマルナ派のなごりは後を引いた(アマルナ美術)。第19王朝にはテーベ派が活動したが,力感と威厳とに優雅味を加えた。ラメセス2世は,富強とはで好みとを反映して巨大な岩窟神殿を営み,アブ・シンベルのそれには,正面に高さ20mの王の座像4体を彫出した。第20~25王朝には国運衰微し,芸術も堕落したが,青銅像は発達し,《王妃カロママ立像》(高さ35cm。ルーブル美)のごときは金銀線の象嵌で服飾の豪華を表現して工芸美を誇った。第26王朝に始まるサイス時代には都が北方に移ったため古王国の伝統に親しんだが,作品は気迫を欠いた。しかしメンフィス出土の《神官頭部》(ペルガモン美)に見るような,顔つきの自然主義的追求の行われた例もある。プトレマイオス朝にはギリシアの影響を受けて折衷様式が生まれた。新王国では奉仕人形よりもウシャブティを多数墓室に納めた。これは墓の主の分身を意味するミイラ形の人形で,死者の霊魂バーがオシリスの楽園で農耕に従事するとき霊魂に代わって働くものと信ぜられた。カーよりもバーが重視されるように信仰が変わったのである。薄肉の浮彫はマスタバの煉瓦壁をおおう木の板や墓室および神殿の石面に施された。石面の浮彫は目的も様式も絵画と同じであった。原図を画家が描き,彫工が石面に彫り,画家が彩色して仕上げた。石面にしっくいを塗ってから彫ることもあった。古王国と中王国の浮彫は地の空間に余裕をもたせ,人物をあたかも縦の平行線に順応させたかのように繰り返して秩序よく並べた。中王国にいくぶん新しいくふうが試みられたが,新王国になると構図が緊密になり,群集の重なりや動勢の実感も追求され,彫技も精巧となって優美な線で細部を仕上げた。アメンヘテプ3世の宰相ラーモセの墓の浮彫人物はその優雅精巧を代表している。襞(ひだ)をそろえた亜麻布の薄衣を着ることが流行し,その衣をすかして見える肉体が巧みに表された。代表作は第19王朝の《ハトホル女神とセティ1世》(ルーブル美)である。サイス時代には浮彫も復古的であった。神殿や葬祭殿の壁や柱が聖なる主題や象形文字の浮彫でおおわれたばかりでなく,民衆の目に触れる中庭,ピュロン,外壁などはファラオの威徳や勇武を誇示する浮彫で飾られた。セティ1世とラメセス2世とは,外征の成功を記念して戦勝場面を表現させた。第20王朝のラメセス3世は,野牛狩りの勇姿を表現させた。いずれもおそらくアジアの影響によるものであろう。
絵画
先王朝時代のヒエラコンポリスの墳墓壁画の原始性は古王国になって超克されたが,ある情景を物語ろうとする叙事的性質は保持された。墳墓壁画の目的は功利的で,描かれた神々は恩恵を,人物はそれぞれの奉仕を,動植物は芳香や栄養を,墓の主に与えると信ぜられ,この目的で,ある情景が絵筆を用いて物語られたのであるから,むしろ呪術的であった。壁面は石灰石,しっくい,わらを刻み入れた練土の3種。画面構成は高さ30~50cmの水平帯の層を設けてその中に描いた。農耕の過程を描いたものは,最下層から最上層へと順序をたどったが,主題によってはそうでないものもある。神々,ファラオ,神々を礼拝する墓の主,狩猟人物などはとくに方形の区を設けて大きく描いたが,高さ1.5mを超すことはほとんどない。描く順序は,まず壁面に朱の方眼線を引き,それを見当にして下がきの線描をなし,ついで地を塗り,物象を彩色し,最後に輪郭線を描き起こした。描き起こしは赤系統の色であったが,黒線を用いることもあった。技法はテンペラである。描法はほとんどが鉤勒(こうろく)法(線描でアウトラインを描き,その中を色で埋める方法)であるが,植物などはしばしば没骨(もつこつ)法(筆触だけで描く方法)で描かれた。メイドゥームの墓の日乾煉瓦壁面にしっくいを塗り,そのフリーズ(高さ24cm)に描いた《カモの図》(第4王朝。カイロ博)は最古の傑作であるが,カモはきびしい鉤勒法と平らな塗色とで様式化されており,地上の草花は没骨で単純化されている。鳥の生態はよく観察され,効果は明晰,気品もある。
人物の顔と足は側面向き,目と肩は正面向きという独特の表現法も長く守られた。しかし新王国時代には側面向きの肩や若い娘のうしろ向きの立姿さえも描かれることがあった。彩色は平らで,色の対照は強い。男女は肌色を異にし,また並び重なる裸人や動物には濃淡の差をつけた。彩色した上に透明なワニスをかけた例もある。構図においても,第三次元を平面化し,前後にあるものを上下にあるかのように描く方法を踏襲しており,これが画面を装飾的にした。つまり,与えられた面に物象を装飾的に展開させるために奥行きの感じを無視したのである。植物も装飾文様のように人工的調整に服従した。物象の平面図と立面図とを混在させて画面の装飾的配分を行った例も珍しくない。たとえば川は平面図に,その岸の植物は立面図に描くの類である。群集は定型化されたが,そのポーズは現世のいろいろの労務に応じて多様である。画技が進んで,簡明な線と平らな塗色とで若い女性の肉体のしなやかさを出すようにもなった。第18王朝中期のメンナの墓(テーベ)の《カモシカを肩にかついだ少年》は緊張した表情をもち,ナクトの墓(テーベ)の《盲人弾琴》は,胴がまったくの側面向きであり,盲人の顔も特色がよくとらえられている。動物の描写はもとから得意であったが,中王国から鳥獣の群の表現が巧みになり,それが新王国でいっそう活気を増し,草木の間に群がる鳥類やチョウ,それをねらうネコ,スイレンの間をおよぐ魚類などが狩猟漁労の場面を多彩ににぎわしている。
中王国以後テーベ付近の岩山をうがって墓をつくるようになってから,石質の関係上,浮彫よりも絵画が多く採用された。壁画はメイドゥームの《カモ図》の簡明と気品は失ったが,地をひろやかにして,物象をあたかも縦の平行線に順応させたかのように配置した整然たる構図は,中王国をへて第18王朝前期まで保持された。中王国に新しいくふうが加わり,第18王朝中期のアメンヘテプ2世やトトメス4世の時代になると構図が自由になり,人物のポーズは優美となり,淡い灰青を地として色合いが複雑になった。家畜や野獣の表現は元来巧みであったが,この時代の宮廷書記ウセルハトの墓(テーベ)の壁画の逃げるウサギやひん死のキツネは,硬い機械的な線をやめて,活気ある自由な線をふるって日本画の筆技を思わせる。この奔放な線とは反対に,同じ墓の気品ある婦人像は,繊細な線で顔の細部や白衣の襞を仕上げているが,この絵は時代が百数十年も下る。ジェセルカラー・セネブの墓(テーベ)の化粧図では若い女の肉体のしなやかさが感ぜられ,その中の1人は全くの側面向きである。
第18王朝後期のアメンヘテプ3世時代には,厳粛と優美とを調和させ,均衡を重んじて構図が合理的となり,白っぽい地に対して色合いがいっそう洗練された。宰相ラモーセの墓(テーベ)の〈泣女(なきおんな)〉の群は,群団の行動や衣襞の流れの取扱いが複雑になって,しかも知的な均衡を失っていない。この均衡を捨てたのはアマルナ派であった。アマルナ美術は《幼い両王女》の図(アシュモリアン博物館)に見るように,肉体のデフォルマシヨン,肌の柔らかさ,家庭的親和感などを特色とした。このデフォルマシヨンは第19王朝まであとを引いた。テル・エルアマルナの宮殿には,自然愛を反映した優美な装飾画が描かれた。壁画はやがてテーベの伝統に復帰し,第19王朝には技巧が繊細となり,構図がきちんと整い,襞をそろえた亜麻布の薄衣の美しさがいよいよ発揮された。前出のウセルハトの墓にはこの時代の壁画もあって,その中の《シコモール(イチジクの一種)の前の婦人たち》は時代の特色顕著で,こまやかな服飾美と画趣的な華やかさとで統一され,あごからのどにかけての曲線もかっきりと引かれている。前出の気品ある婦人像の細部表出がここではいっそう繊細になっているのである。ラメセス2世の妃ネフェルタリの墓の壁画では,妃の肌は黄色の伝統を破って淡紅色に彩色され,ほおには紅をさしている。この化粧法は当時アジアの風を移入したものであった。白の薄衣をすかして見える淡紅の肌色も美妙である。これらは第19王朝の富強と豪奢とを反映している。これ以後は伝統的形式がただ惰性的に保持された。第18王朝後期から葬儀行列や神々礼拝の図が多くなって庶民労役図は少なくなった。第19王朝のディール・アルマディーナDīr al-Madīna(テーベ墓地の片隅)の庶民の墓群には,民画化された伝統画技によって黄色の地に活気ある庶民風俗が描かれた。新王国には陶片や石灰石の断片にさまざまのものが線描された。これはオストラカと呼ばれ,スケッチでもあり,壁画の原図や習作でもあった。第20王朝以後には,パピルスに,《死者の書》の審判図や風刺的な動物漫画が描かれた。線描を主とする絵で,前者は宗教的用途によるものであり,後者はなにか政治的意味のものであろう。工芸品に描かれた絵の代表作は,第18王朝後期の《ツタンカーメンの櫃(ひつ)》(カイロ博)である。義父のイクナートンが排斥した武勇伝を復興して戦争と狩猟の図を描き,細密描写ながらアジア人の顔の特徴をよく表している。若い王の勇姿にはアマルナ美術のなごりが認められる。グレコ・ロマン時代には,板に死者生前の顔を蠟画で描いてミイラの顔に当てたが,描法はまったくギリシア風である。
執筆者:森口 多里
工芸
古代エジプト工芸の遺品はことごとく墳墓からの出土品で,それらには宗教関係のものも単なる実用的用途のものもあるが,これによってエジプト人の審美感,宗教理念がうかがえるばかりでなく,彼らの日常生活のありさまを知り,その物質文明がいかに高度の発達を遂げていたかを理解することができる。このようなエジプト工芸の発達の背後には,ごく少数の例外を除いて,たいていの工芸材料はナイルの流域や砂漠から産出するという,恵まれた自然的条件があったことを忘れてはならない。
石器
無機物を素材とする工芸品には,まず石器がある。石製の武器や利器の製作は,太古から始まりローマ時代までつづいたが,先王朝時代後期には,フレーキング(剝片)の技法で精巧優美なフリントの小刀がつくられた。石製容器は先王朝時代前期から見られ,初めは硬い石が多く用いられ,同時代後期になると軟らかい石が好まれるようになった。最も入念に石製容器がつくられたのは王朝時代直前で,轆轤(ろくろ)も回転砥石も使わず,薄く正確に成形し,金剛砂でみがきをかけて生地の美しさを出している。王朝時代に入ると一般に石製容器の製作はむしろ退化し,とくに硬い石の使用は少なくなったが,その中で,半透明で,ときとして美しい縞目のあるアラバスターがおもな材料になった。とくに意匠をこらした石製品としては,ツタンカーメン王墳墓出土のアラバスター製のつぼやランプなどである。
土器
土器は石器についで古くから行われたが,先王朝時代には作品の種類も多く,装飾方法も変化に富み,おそらく最も興味のある時代であったといえよう。また,第18王朝ころにつくられた,赤,黒,青で水平の縞を描いたつぼや,以上の色に緑,白をまじえて蓮の花などを描きつけたものは,優雅である。轆轤の起源については定説がないが,古王国時代に存在していたことは,第5王朝時代の墳墓の彫刻に表われているので明らかである。
陶器
釉(うわぐすり)の発明は古代世界における重要な発明の一つであって,すでに先王朝時代よりも古いバダーリ時代から,凍石に釉をかけてビーズがつくられた。先王朝時代の末から王朝時代を通じて,人工的に準備したケイ酸質の胎に釉をかけて,器物のほか,人形や動物像,ウシャブティ,護符,装身具などをつくり,またタイルや煉瓦にも釉をかけるようになった。陶製品は第18王朝,第26王朝に進歩の頂点があったといえる。釉は青緑色,藍色などで,いずれも金属塩で着色されていたが,質は純ガラス質であるために粘土の胎にはかからず,この点がエジプト陶器の発達をはばむことになった。
ガラス
ガラスの起源は明らかでないが,釉が胎にかけられないで単独に加工されたものと見れば,釉の発明の古さから推して,エジプトを発祥の地と考えることも必ずしも不自然ではない。ただガラスと確認される第18王朝以前の遺品がなく,この王朝の時代になり忽然として遺物や製造所の跡が見いだされることは,他地方から伝えられたと考える理由にならないでもない。一般にエジプトのガラスは,貴金属や美麗な縞のある石の模造品としてまず用いられたようで,したがって着色不透明にして細工された。吹きガラスの技法によって,透明性というガラスの大きな特徴に目ざめたのは,前1世紀ころのことであった。
金工
銅はバダーリ時代に使われはじめ,王朝時代にはいってもかなり長く主要金属の地位を占めていた。鎚打,鋳造がおもな製作技法で,武器,工具,装身具,容器類につくられた。青銅は銅より硬く,鋳物にも適していたので,中王国時代から普及し,道具や器物とともに彫像の製作に用いられた。貴金属宝石細工はエジプトでとくに発達した技術で,優品も数多くある。金はアマルガムによるいわゆる消しめっきなどは別として,今日知られているたいていの技法を用いて,加工および仕上げが行われた。第12王朝時代には,種々の宝石を透し彫のある金の台にはめこんだ装身具がつくられたが,とくにセンウセルト2世の胸飾は傑作である。第18王朝の遺品には,ツタンカーメン王の墳墓からの出土品が多数あるが,中でも人体形の三つの棺のうち最奥のものは,金の延べ板でつくられ,重さ60kg以上におよび,細かい条彫(すじぼり)が施してある。同種の他の二つの棺は,木でつくられており,それに金箔をはった上に,さらに色ガラスがはめられている。
木工
工作に適した木材がエジプトにはあまり産しないので,木工には,西アジアやシチリアあたりからの輸入材を利用せねばならなかった。家具では,たとえばいすなど,神聖動物や象徴を浮彫や透し彫で施し,金箔をはって仕上げをした玉座のような装飾的なものもある一方,実用本位の簡素なものもある。後者はもちろん,前者も座部にくぼみをつけ,背部を傾斜させるなど,使用者の安楽を考慮した合理的な構成をとっており,また工作にも細かい注意が払われている。なお,さまざまなものがあるが,小型の木工品としては,蓮,パピルスなどの植物や人物を装飾として彫り出した匙(さじ)の形をした化粧料入れなどがある。
織物
エジプト産の亜麻布は,古代世界において,とくに有名であるが,古い遺物としてはファイユーム出土の新石器時代のものがある。第1王朝の遺物に,1インチ(約2.5cm)四方に経(たて)糸160本,緯(よこ)糸120本を数え,幅約150cm以上におよぶ亜麻布がある。織機の模型は中王国時代の副葬品にあり,またその図は中王国・新王国時代の壁画に描かれているが,それによると水平織であったことがわかる。つづれ織も古くから行われ,トトメス3世,アメンヘテプ2世など,第18王朝の王の名を入れた遺物がある。
なおエジプトの工芸品には牙角製品や皮革製品,その他にも見るべきものがあるが,いろいろな有機物を材料として用いた朽廃しやすいものまでが,数千年の長い年月をへて今日に至るまで伝わっていることは,エジプトの乾燥した風土のたまものである。
執筆者:新 規矩男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報