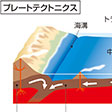関連語
精選版 日本国語大辞典 「中央海嶺」の意味・読み・例文・類語
ちゅうおう‐かいれいチュウアウ‥【中央海嶺】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央海嶺」の意味・わかりやすい解説
中央海嶺
ちゅうおうかいれい
Mid-Oceanic ridge
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「中央海嶺」の意味・わかりやすい解説
最新 地学事典 「中央海嶺」の解説
ちゅうおうかいれい
中央海嶺
mid-oceanic ridge
⇒ 大洋中央海嶺
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
岩石学辞典 「中央海嶺」の解説
中央海嶺
世界大百科事典(旧版)内の中央海嶺の言及
【海底地形】より
…これらプレートの運動によってプレート境界に起こる相対的運動は,プレート同士が離れるか,ぶつかるか,すれ違うかの3種類に限られる。 離れるプレート境界ではアセノスフェアが海底近くまで上昇し,中央海嶺を形成する。中央海嶺は,北極海,大西洋,インド洋などの大洋のほぼ中央に連なる海底の大山脈で,太平洋では南東部に走る東太平洋海膨となっている。…
【海膨】より
…地形の規模や成因に関係なく形態で名付けられる。地球的規模をもつ中央海嶺の一部にもその形態から東太平洋海膨という名称がある。中央海嶺は一般に比高2~3kmであるが,幅の方は300~400kmの海嶺型と幅500kmをこす海膨型がある。…
※「中央海嶺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...