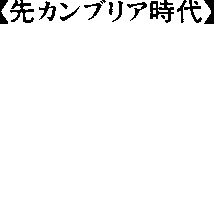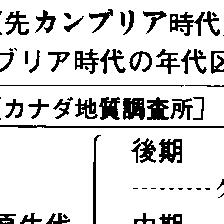精選版 日本国語大辞典 「先カンブリア時代」の意味・読み・例文・類語
せんカンブリア‐じだい【先カンブリア時代】
- 〘 名詞 〙 ( カンブリアは[英語] Cambria ) カンブリア紀以前の地質時代をいう。地球創成時より約六億年前までの約四〇億年にわたる時代。先カンブリア紀。
改訂新版 世界大百科事典 「先カンブリア時代」の意味・わかりやすい解説
先カンブリア時代 (せんカンブリアじだい)
Precambrian age
古生代カンブリア紀(5億9000万年前に始まる)に先だつ時代の意で,それ以前の地質時代をいう。地球の誕生の45億年前までの約40億年を先カンブリア時代とする考えもあるが,地球上で研究できる最古の岩石の年齢である38億~40億年前に至る約34億年を先カンブリア時代とよび,それ以前の時代を先地質時代として区別する。古生代およびそれ以降の地質時代は化石の証拠が豊富であるところから顕生代Phanerozoic eonとよばれるのに対し,先カンブリア時代は隠(陰)生代Cryptozoic eonとされたが,この語は現在はほとんど使われない。1872年,アメリカのJ.D.デーナがカンブリア時代以前に形成された片麻岩や花コウ岩などの地質系統を太古界とした。その後,非変成または弱変成の堆積岩が太古界とカンブリア系との間に存在することがわかり,C.D.ウォルコットによってアルゴンキアンとされた(1889)。先カンブリア時代は78年イギリスで提唱され,C.R.バン・ハイスにより96年にアメリカの前期カンブリア紀より前の地質系統に対して初めて使用された。
細分
変成作用を強くうけた岩石や花コウ岩で代表される太古代(始生代)の地質系統とその上位にあって変成作用をほとんどうけていないアルゴンキアン(原生代)の地質系統という二大区分は,研究が進むにつれて矛盾することがわかってきた。世界各地に分布する先カンブリア時代の地質系統を統一的に扱うことは困難である。化石の産出にとぼしいこと,変成作用による初生的特徴が失われていること,連続的露出がないことなどの理由から先カンブリア時代の年代区分は顕生代とちがって,もっぱら放射年代に頼らざるをえない。カナダ楯状地には先カンブリア時代の地質系統が広く分布し,その研究は進み,先カンブリア時代細分の模式地となっている。カナダ地質調査所では,古い方からケノーランKenoran造山(約25億年前),ハドソンHudson造山(約18億年前),グレンビルGrenville造山(約8億年前)の3回の造山運動を識別し,これらによって先カンブリア時代を4時期に細分している。ケノーラン造山以前が太古代に,他の3区分がアルゴンキアンに相当する。アメリカ地質調査所では,放射年代区分を重視し,25億年前,16億年前,8億年前を境として,古い方からW,X,Y,Zに4区分している。この区分の定義はカナダ地質調査所の細分と異なるが,現在の知識では結果はほぼ同一区分になる(表)。バルト楯状地ではアーケアン区が始生代の地質系統にあたり,20億年以前の時代とされている。
分布
大陸の中核部はなだらかな地形をなす安定地塊で,楯状地とよばれる。楯状地は先カンブリア時代の地質系統から構成され,カナダ,バルト,アンガラ(シベリア),中国大陸東部,インド,オーストラリア,ギアナ,ブラジル,プラチア,アフリカ楯状地などが知られている(図1)。先カンブリア時代の地質系統の露出面積は全陸地の8~9%にすぎないが,それらを基盤にもつ地域は全陸地の2/3に相当し,各大陸の中核部を形成する。
最古の岩石
西グリーンランドには始生代の地質系統(26億~29億年前)からなる楯状地がある。この中央部に位置する主都のゴットホープ(現,ヌーク)付近に分布するアミツォック片麻岩は,鉛-鉛全岩アイソクロン法によって38億年前,ルビジウム-ストロンチウム法によって37億年前という放射年代が与えられている。また,ゴットホープの北東150km付近のイスア地域には縞状鉄鉱層と弱変成作用をうけた堆積岩が分布し,鉛-鉛法で37.6億年前とされ,世界最古の表成岩地殻であるとされている。アメリカのミネソタ州でも,38億年前の花コウ岩が発見されている。
アフリカ楯状地とグリーンストーン帯
南アフリカ,トランスバール地方のバーバートン山地には幅30~40km,延長100kmをこす帯状分布をとるスワジランド累層群が分布する。新しい年代の花コウ岩にとり囲まれているため,それより古い地質系統はわかっていない。スワジランド累層群の層序は図2のようになっていて,16kmの厚さをもつオンフェルワクト層群が31億~34億年前の年代をもつとされている。この層群は主として溶岩とその砕屑(さいせつ)岩からなり,その中にチャート,石灰岩,ケツ岩などの堆積岩をはさむ。溶岩の性質は下部の超塩基性岩(コマチアイト)から塩基性岩(玄武岩)をへて,斜長岩質の岩石へと火成活動の一連の変化がよみとれる。変成作用によって緑色に変化している火成岩とその砕屑岩類は帯状の分布をとるところから,グリーンストーン帯とよばれている。グリーンストーン帯はアフリカのローデシア,カナダのハドソン湾をとりまく地域,オーストラリア西部にも知られ,始生代の特徴とされている。始生代のこの時期の地殻は,花コウ岩質の大陸が形成される以前の段階にあたり,斜長岩からなる月の地殻を思わせるところから,地球の発展段階における〈月の段階〉とみることもできる。
カナダ楯状地と縞状鉄鉱層
480万km2という広大な面積を占めるカナダ楯状地ではケノーラン造山運動をうけたスレーブ区,スペリオル区,ハドソン造山のベアー区,チャーチル区,サウザン区,グレンビル造山のグレンビル区などからなっている。スペリオル湖の北岸には原生代前期のガンフリント生物群で有名なガンフリント層(19億年前)が分布する。約150mの厚さをもつガンフリント層は下部のレキ岩層と上部の石灰岩層とにはさまれた厚い鉄鉱層からなる。鉄鉱床を構成する鉱物は菱鉄鉱FeCO3,針鉄鉱α-FeO(OH),赤鉄鉱Fe2O3,磁鉄鉱Fe3O4である。スペリオル湖型とよばれる縞状鉄鉱層は世界の楯状地に分布し,20億~25億年前に形成されたこの型の鉱床が世界の80%を占める。先カンブリア時代特有のこの鉄鉱床は大陸棚または劣地向斜の浅い海で形成されたもので,ラン藻植物に由来する分子状酸素によって海水にとけていた2価の鉄イオンが酸化をうけて,いっせいに沈殿したものとされている。
資源
先カンブリア時代の鉄鉱床はスペリオル湖地域だけで鉄として1011tをこす埋蔵量を有する。さらに大規模な潜在資源として1012t以上の埋蔵量をもつ地域は南アフリカのトランスバール地域,ウクライナ,オーストラリアのハマーズリー盆地,カナダのラブラドル,ブラジルのミナス・ジェライスなどで全埋蔵量は1014t以上になる。ニッケルは銅とともにカナダ楯状地のサドベリー地区から硫化物として大量に産出する。ここでのニッケルの生産量は全世界の75%に達するという。金の世界生産量の1/2は南アフリカのウィットウォーターズランドレキ岩(約25億年前)から産出する。カナダ楯状地,バルト楯状地などもその埋蔵量は大きい。その他,プラチナ(旧ソ連,カナダ),銀(カナダ),鉛・亜鉛(カナダ,アメリカ,オーストラリア),クロム(南アフリカ,旧ソ連),コバルト(カナダ),マンガン(インド,アフリカ,ブラジル),石墨(東アジア)などは楯状地に多く産出がみられ,世界の資源にとって先カンブリア時代の地質系統が重要な地位を占めている。
古生物
世界最古の化石は南アフリカのオンフェルワクト層群のティースプルート累層(34億年前)から発見されたラン藻とされているが,この構造体が化石であることに異論も出されている。この層群の最上部層(31億年前)から1~4μmの大きさのラン藻化石が報告され,全標本の25%が分裂中か二分子細胞であるとされ,エオバクテリウムとともに確実な最古の微化石とされている。ティースプルート累層の同位体組成は,炭素質隕石のそれに似ていて,生物進化以前の化学進化の段階で形成された有機物であるという意見もある。ラン藻やバクテリアなど原核生物だけからなるガンフリント生物群はカナダのガンフリント層から産出した。真核生物はカリフォルニアのベックスプリング石灰岩(約13億年前)の化石が最古のものである。腔腸動物,環形動物,節足動物などの多細胞生物は先カンブリア時代末期(6億~7億年前)にエディアカラ動物群として知られている。この動物群は次の時代のカンブリア紀のものとちがい,硬組織をもたないという特徴がある。
自然環境
地球は創成期の数億年の間に溶融し,層状構造が形成された。海洋と大気はこの時期に生じた地球内部からの脱ガスによって生成されたと推定される。したがってこの見解に従うと,地質時代が始まる約40億年前には,ほぼ現在の海洋に匹敵する水量が地表をおおったことになる。大気は窒素と二酸化炭素が主成分で,分子状酸素は存在していなかった。ラン藻などの植物が水域に発生し,光合成を行うことによって酸素の放出を行った。この分子状酸素によって,はじめに水域が酸化され,ついで大気中に酸素が放出されるようになり,地表が酸化をうけることになった。大気中に分子状酸素が増加していく歴史は,L.V.バークナーとL.C.マーシャルによって,図3のようなモデルがえがかれている。先カンブリア時代の気候がどのようなものであったかは明らかでない。オーストラリアのビタースプリングス層(9億年前),南アフリカのブラワヤン層(27億年前)にはストロマトライト石灰岩が発達している。またビタースプリングス層には大規模な蒸発岩があることなどから,温暖または酷暑の気候が推定できる。しかし,先カンブリア時代の氷期は約25億年前に始まり,その後7~8回の氷期の証拠もあり,気候の変遷史は統一的に理解できるところまでわかっていない。
→地質時代
執筆者:秋山 雅彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「先カンブリア時代」の意味・わかりやすい解説
先カンブリア時代
せんかんぶりあじだい
Precambrian
地質時代において確実な化石が目だって産出するようになるのは、約5億4100万年前の古生代のカンブリア紀に入ってからであるが、それに先だつ地質時代を一括して先カンブリア時代とよんでいる。地球が形成された約46億年前から約5億4100万年前までの約40億年に及ぶ長大な地質時代に相当する。先カンブリア時代に形成された地層を先カンブリア界という。
この時代は、最初の生命が発生した時代という意味の始生代(または太古代)と、原始的な生物の時代という意味の原生代に区分される。始生代は、地球の形成より約25億年前までの時代にあたり、地球の基本的構造が形成される。これまでに確認された最古の岩石は、約38億から約37億年前のものである。先カンブリア時代の岩石は楯状地(たてじょうち)を形成し、北アメリカ大陸北東部、南アメリカ大陸アマゾン地域、シベリア、北ヨーロッパ、アフリカ大陸南東部、オーストラリア大陸西部、インド、中国華北より朝鮮半島などに広く分布している。先カンブリア時代の地層・岩石は、粘板岩、砂岩、礫(れき)岩、火山砕屑(さいせつ)岩類、またそれらを貫く深成岩類などであるが、何回もの変成作用を受け、一般に、結晶片岩類や片麻岩になっている場合が多い。ただし、後期の地層には、石灰岩、白雲岩、赤色岩層の発達もみられ、地層の保存もよく、化石もまれにみつかる。始生代に生物が存在していたことは、生物源とみなされる石墨や鉄鉱層の発達からも推察されるが、バクテリアや藍藻(らんそう)の化石と思われるものが、南アフリカの30億年以上も前の地層より発見されている。石灰質ストロマトライトは、世界各地の後期始生代以降の地層中に普通にみられる。原生代の末期には、真核多細胞生物も出現し、エディアカラ動物相を構成する多様な軟体性多細胞が生息していた。古気候については不明な点が多いが、氷礫岩層や氷河が磨いた岩盤が各地で発見されており、何回かの氷河時代があったことがわかっている。先カンブリア時代末の8億~6億年前の氷河時代はとくに大規模で氷河が地球表面の大部分を覆いつくしていたと考えられている。
東アジアでは、中国の華北より朝鮮半島にかけて、主として結晶片岩類や片麻岩よりなる先カンブリア界が発達している。日本には、先カンブリア時代の地層は知られていないが、岐阜県の中生代の礫岩層中より約20億年前の年代を示す片麻岩礫が発見されており、礫をもたらした後背地に先カンブリア界が存在していたことが明らかになった。
[小澤智生 2015年8月19日]
『リチャード・T・J・ムーディ、アンドレイ・ユウ・ジュラヴリョフ著、小畠郁生監訳『生命と地球の進化アトラスⅠ 地球の起源からシルル紀』(2003・朝倉書店)』▽『アンドルー・H・ノール著、斉藤隆央訳『生命 最初の30億年――地球に刻まれた進化の足跡』(2005・紀伊國屋書店)』
百科事典マイペディア 「先カンブリア時代」の意味・わかりやすい解説
先カンブリア時代【せんカンブリアじだい】
→関連項目バルト楯状地
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
最新 地学事典 「先カンブリア時代」の解説
せんカンブリアじだい
先カンブリア時代
Precambrian age
古生代の始まりよりも古い地質時代。地球の生成(約46億年前)~5.64億年前までの約40億年間。かつては古生代の初めに生命は誕生したと考えられ,先カンブリア時代と古生代以降の地質時代(顕生代)とは基本的な違いがあると考えられていた。現在では生命の原始型は35億年以上前に存在し,生命体は先カンブリア時代のほとんどに存在したことがわかっている。先カンブリア時代を三分し,46億~40億年前までを冥王代または創成時代,40億~25億年前までを始生代または太古代,25億~5.64億年前までを原生代と呼ぶ。先カンブリア界は,地球上では楯状地・卓状地・造山帯の3地域に露出。楯状地には先カンブリア界が地表に広く数百kmにもわたって露出。卓状地は楯状地に隣接する安定地域である。卓状地の下には先カンブリア界の楯状地の続きが基盤として存在。さらにその外側の古生代以降の造山帯の中に先カンブリア界が認められることがある(例:アパラチア山脈)。また,陸地に近接した海洋地域の一部(例:セイシェル諸島)にも,先カンブリア界の基盤が潜在していることがあるが,大洋底の主要部には先カンブリア界は認められない。セイシェル諸島は,大陸移動によって壊された大陸断片と考えられている。
執筆者:諏訪 兼位
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「先カンブリア時代」の意味・わかりやすい解説
先カンブリア時代
せんカンブリアじだい
Precambrian time
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...