精選版 日本国語大辞典 「反応熱」の意味・読み・例文・類語
はんのう‐ねつハンオウ‥【反応熱】
- 〘 名詞 〙 化学反応に伴って発生、あるいは吸収される熱量。実熱量。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「反応熱」の意味・わかりやすい解説
反応熱
はんのうねつ
heat of reaction
化学反応に伴って出入りする熱量をいう。反応熱が出る場合を発熱反応、入る場合を吸熱反応という。たとえば、水素分子1モルが燃焼する際には、57.8キロカロリーの熱量を発生する(普通、室温・大気圧の標準状態下の発生熱量で示す)。たとえば気体の水素と酸素が反応して水を生成するときの反応熱は、系のエンタルピー(熱含量)変化として、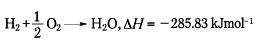
のように表す(ΔHの値は系の吸熱量をもって正とする)ことが多い。反応熱は普通、大気圧のもとで測るため、定圧反応熱ともいうが、これに対し、一定容積で測った場合を定容反応熱という。また、一つの反応を2段階あるいは数段階に分けて行ったとき、その反応熱の合計は全体の反応熱になる。これをヘスの法則という。
反応熱は反応の種類によって、燃焼熱、中和熱、生成熱、溶解熱、蒸発熱など多くの呼び名がある。
[戸田源治郎・中原勝儼]
改訂新版 世界大百科事典 「反応熱」の意味・わかりやすい解説
反応熱 (はんのうねつ)
heat of reaction
化学反応に伴って物質系に吸収,または放出される熱量の総称。反応の種類によって,生成熱,燃焼熱,中和熱,溶解熱,希釈熱,混合熱,吸着熱などに分類される(各項参照)。反応熱は多くの場合1気圧下で測定されるので,厳密には定圧反応熱と呼ばれ,燃焼熱測定などの特殊な場合に体積一定下で測定される定容反応熱と区別される。熱力学的には両者は互いに変換される。化学方程式の後に反応熱を併記したものは熱化学方程式と呼ばれる。化学結合の再編成によって物質系のもつ内部エネルギーU(定容下)またはエンタルピーH(定圧下)の増減が熱の出入りとなって表れる。たとえば,
2H2(g)+O2(g)─→2H2O(l)
⊿H=-571.68kJ
のように書き,2molの水素気体(g)と1molの酸素気体(g)が定圧下で反応して2molの液体(l)の水を生ずる際には571.68kJの熱を放出することを表現する。熱化学方程式は〈ヘスの法則〉により,そのいくつかを代数的に加算できる。
執筆者:菅 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
化学辞典 第2版 「反応熱」の解説
反応熱
ハンノウネツ
heat of reaction
化学反応に伴い,化学系に吸収されるか,または化学系外に放出される熱量をいう.反応熱は主として原系と生成系の物質の間の化学結合の組換えによる結合エネルギーの差にもとづくものである.反応熱は原系および生成系の物質の集合状態でも多少異なる.普通,定温定圧下での変化の値で表示されるが,気体の反応のときには定温定積下の値で表示することもある.前者を定圧反応熱,後者を定積反応熱といい,熱力学的にはそれぞれ化学系のエンタルピー変化および内部エネルギー変化に対応する.化学系に熱が吸収され,系のエンタルピーまたは内部エネルギーが増加する場合を吸熱反応,逆に系外に熱が放出される場合を発熱反応という.熱化学方程式の右辺に記す場合は慣習的に吸熱量を-,発熱量を+で表す.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
百科事典マイペディア 「反応熱」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の反応熱の言及
【化学反応】より
…この仮説によれば,発熱反応のみが自発的に起こることになる。しかし一連の反応熱の精密測定によって多くの反応は確かに発熱反応であるが,吸熱反応も少数ではあるが確実に起こることが確かめられ,この仮説は一般的には成り立たないことがしだいに明らかとなった。現在,化学反応が起こりうる条件は熱力学によって十分明らかにされている。…
【キルヒホフの法則】より
…比jν/aνは物質の種類によらないから黒体のそれに等しいが,黒体のaνは1なので,黒体放射の単位振動数,単位立体角あたりのエネルギー放射速度,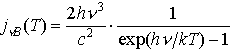 に等しいことになる(hはプランク定数,cは真空中の光速度,kはボルツマン定数)。【江沢 洋】(4)反応熱の温度変化に関する熱化学的法則の一つ。ある温度での反応熱⊿Hが知られているときに,別の温度での値を求めるのに用いられる。…
に等しいことになる(hはプランク定数,cは真空中の光速度,kはボルツマン定数)。【江沢 洋】(4)反応熱の温度変化に関する熱化学的法則の一つ。ある温度での反応熱⊿Hが知られているときに,別の温度での値を求めるのに用いられる。…
【熱】より
…例えば水素ガスが燃える反応2H2+O2―→2H2Oでは,水素1g当り約34kcalの熱が発生する。反応の種類によっては熱を吸収する場合もあるが,一般に反応が生ずるとき,温度一定に保つために吸収あるいは供給しなければならない熱量を反応熱という。
[熱の伝達]
熱は必ず高温から低温のほうへ伝わるが,その機構は,(1)物質の移動を伴わない,いわゆる熱伝導,(2)物質の移動による伝達,(3)放射による伝達に分けられる。…
※「反応熱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

