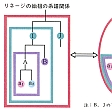精選版 日本国語大辞典 「氏族制度」の意味・読み・例文・類語
しぞく‐せいど【氏族制度】
- 〘 名詞 〙 氏族社会のしくみ。氏族社会の成員の行動を規制する規範体系。
改訂新版 世界大百科事典 「氏族制度」の意味・わかりやすい解説
氏族制度 (しぞくせいど)
ここに氏族制度というのは,家族よりも大きく,部族よりも小さい氏族とよばれる血縁的な集団が,多かれ少なかれ独立した経済的・社会的・政治的単位としての機能をいとなんでいる社会すなわち氏族社会の制度をさす。記録された歴史のはじまる古代国家形成のころには,すでに封鎖的・自給的な村落経済は交易経済に変わり,民主的な共同体は階級的な権力による支配のために再編成されつつあったことが,遺跡や文献の上からうかがわれるが,その以前の社会は一般にここにいう氏族を中心とする体制の上に立つものであったという推定が,多くの学者によってなされてきた。
しかしこの氏族が正確にはどのような組織であったかは,現在もしくは近い過去に調査された未開民族の社会構造を,断片的な古代の記録と照合して考える以外に道はない。しかるにこの方法を進めていくと,これまで氏族の名でよばれてきた組織は,けっして首尾一貫した単一な原理によって形成された固定的なものではなく,むしろその構造原理において,いくつかのカテゴリーに類別しうる多様な組織の総称であり,かつこれらのカテゴリー相互の間には,容易に一方から他方に変化しうる流動性の存することが見いだされるのである。
研究史と問題の所在
人類史における氏族制度の意義をはじめて体系的に明らかにしたのは,L.H.モーガンの《古代社会》(1877)である。モーガンは多年にわたり,みずから北アメリカ東部のイロコイ諸族の中に入って調査にあたったが,ここに発見した母系の氏族制度がイロコイ諸族の社会に占める大きな役割に対してひじょうな興味をおぼえ,この種の形態を,文明のはるか以前,人類進化の初期に生まれた原始的な氏族制度の典型と考えた。この原始的氏族は,共通の女性の祖先から出たと信ぜられる女系の子孫からなる。すなわち各世代の女子の生んだ子どもは,その氏族の成員として内部にとどまるが,男子が他の氏族の女子と結婚して生んだ子どもは,その母親の氏族に所属しなければならない。そしてモーガンは,イロコイ諸族の氏族を特徴づける成員の権利義務としてつぎの10種類をあげた。
(1)平時の首長および軍事の指揮者を選挙する権利。前者は必ず氏族員の中から選ばれねばならぬが,後者は氏族外から選挙されてもよく,またこれを欠くこともあった。(2)この2種の首領を罷免する権利。以上の任免の決定には成年に達した氏族の全員が男女ともに投票した。(3)同一氏族内の男女の結婚の禁止。族外婚exogamyとよばれるこの制度は,氏族の成員を一つの血族として結合する基本原則である。(4)死亡した氏族成員の財産を相続する相互的権利。このさい,母系社会の原理に従って,男子の財産は他氏族員であるその子は相続しえず,同氏族に属する肉親の兄弟姉妹および母の兄弟が相続した。(5)相互に援助し,防衛し,加害に対して救治をおこなう義務。氏族の一員が他族の者に殺されたときには,被害者の氏族は加害者を追及してこれを殺害せねばならぬ。これが古代諸民族の間に広くおこなわれた〈血の復讐〉とよぶ慣習である。しかし情状の酌量すべき場合,被害者の氏族内の親族が承知すれば,加害者の氏族の提議する条件をいれて,和解もおこなわれた。同じような精神で,氏族の成員同士は困難や不幸にあたって,互いに助け合ったのである。(6)その成員に名をつける権利。各氏族は同一部族内の他氏族の使用を許さない特有の個人名をもつが,家族を示す名称は存しない。個人はその氏族に属する名を承認されることによって,氏族員としての権利義務を与えられる。(7)他氏族員を養取する権利。戦争の捕虜となった婦女子その他は,氏族員の申出により,後者の兄弟姉妹もしくは息子または娘として,その氏族,したがって部族の,完全な一員にとり入れることができる。かつてイロコイ諸族の1部族たるセネカのタカ氏族は,人員の減少を補うため,オオカミ氏族から一団の人々を養取したことがあった。(8)氏族における宗教的儀礼と審問。氏族は多かれ少なかれ宗教的儀礼に関係する。イロコイ諸族には神官僧職の階級はないが,氏族ごとに幾人かの男女を〈信仰守護者〉に選び,祭典をつかさどらせた。(9)共同の埋葬地。氏族の成員は本来同一の場所に葬られた。この点はモーガンのころのイロコイ諸族については,明らかでなくなっているが,他のインディアン諸族の例から,もとは母とその子どもならびに兄弟姉妹は同じ列に,夫と妻,父と子とはそれぞれの氏族の列に分かれて,葬られたことが推定できる。(10)氏族会議。これは氏族における最高の民主的機関で,男女の全氏族員はこれに参加して平等の発言権と投票権とをもつ。首長・指揮者・信仰守護者の任免をはじめ,氏族の重要事項はこの氏族会議で決定された。
以上はモーガンが,典型的なインディアン氏族と考えたイロコイ諸族の氏族の制度であるが,これら自主的な個々の氏族はけっして単独に孤立しているのではない。とくに兄弟関係にあるといわれる数個の氏族は結合して,一定の機能をもった集団を形成し,この集団が集まって一つの部族が形成される。《古代社会》において,氏族を表すのに,ギリシア語のゲノスgenosと同意義のゲンスgensというラテン語をあてたモーガンは,上記兄弟氏族の結合体を,これに対応すると考えた古代ギリシアの組織にしたがってフラトリア(胞族)と名づけた。胞族はもと単一の氏族が膨張して,二つ以上の娘氏族に分裂した結果生じたものらしい。セネカ族にあっては,最初は胞族内部の結婚が禁じられていたが,後にこの禁止は氏族内だけに限定されるようになったという。胞族の機能は半ば社会的,半ば宗教的なもので,競技や宗教的秘儀の単位となったほか,有力者の葬儀や殺人のつぐないなどに関しても,全体として参与する場合があった。胞族会議は,部族内の氏族の首長や指揮者の選挙に反対して,これを無効とすることもできた。しかし氏族・部族および部族連合のような厳密な意味での政治的機能をもたず,胞族自体の平時の首長,軍事の指揮者,信仰守護者の類も存しない。
氏族の上に位するこうした政治的単位は,胞族の集りによって構成される部族tribeである。モーガンはアメリカ・インディアンの部族の機能と属性として,つぎのような諸点をあげた。(1)一定の領域と部族名の所有,(2)一つの方言の専有,(3)氏族が選挙した首長や指揮者を正式に任命する権利,(4)これらを罷免する権利,(5)共通の宗教的信仰および儀礼の所有,(6)各氏族の首長と指揮者とからなる最高機関としての部族会議,(7)ある場合における部族長の設定。すなわち個々の氏族が選挙した首長や指揮者は,他の氏族の承認をへねばならず,これを任免する権利は部族会議の手にある点において,部族は氏族に対して上位の権限をもつ。けれども部族長は,部族会議を開いて決定しうるまでの一時的処置として,首長の1人をこれに当てたものであって,その権限はきわめて弱く,彼のとった行動は,その後部族会議で批准されねばならなかった。
部族は大多数のアメリカ・インディアンにおける社会結合の限界をなすものであったが,イロコイ系言語を話す5部族は,分裂状態から再び結合して,血縁関係を基礎に永久的な連合(イロコイ同盟)を結び,17世紀の後半には周辺の諸民族を制圧する一大政治勢力となった。この連合の運営は,5部族中の特定の氏族から選ばれた50人の首長からなる連合議会の手にゆだねられ,平等の権限をもつ2人の軍司令官をおいたが,王にあたるような行政上の首脳者はもたない。連合議会は五つの部族会議のいずれかの動議によってのみ招集され,発言権を有する集まった人民の前で公開される。決議には部族別の投票による全議員の一致を必要とした。
モーガンは,以上のようなイロコイ諸族の氏族-胞族-部族-部族連合の組織を,記録に残されたメキシコのアステカや古代のギリシア,およびローマの諸制度と比較した結果,われわれの遠い祖先も国家を形成する以前には,氏族を基調とするこのような諸制度をもっていたものであると考えた。そして一方では,婚姻および家族の制度の進化のあとをたどることによって,氏族制度がおそらく,かのプナルア家族と名づけた群婚の形態から発生したものであろうと論じ,他方では,財産の観念とその相続規制の発達のあとをたずねて,原始の母系制が父系制に変わり,民主的な氏族共同体が貴族階級の支配に移っていく過程を考察したのである。
モーガンの《古代社会》は,いわゆる歴史以前の人間社会の研究に,先人未踏の分野を開拓した労作として,その後の学界に画期的な影響を与えたが,とくにF.エンゲルスは,A.vonハクスタウゼンやG.L.マウラー以来,インドからアイルランドにわたって,社会の原始形態であったことが発見された土地を共有する村落共同体の原初的な目的や組織が,氏族の真の性質と地位とに関するモーガンの発見によって,はじめて明らかにされたとなし,その著《家族・私有財産および国家の起源》(1884)において,モーガンの結論を全面的に採用するとともに,モーガンのわずかに言及するにとどまったケルト人およびドイツ人の氏族と,ドイツ人の国家形成とについて,それぞれ1章を設けて詳論した。ことに領土と公権力とによって特徴づけられ,階級的対立の中から階級支配の手段として生まれた国家に対し,モーガンが国家以前の社会組織として解明した氏族制度に向かっては,〈この氏族制度こそそのいっさいの天真さと単純さとにおいて驚くべき制度だ! 兵士も憲兵も警官もなく,貴族も国王も総督も知事または裁判官もなく,牢獄も訴訟もなくて,いっさいが規則正しく進行する。すべての争いはその当事者の全体,すなわち氏族または部族が,もしくは個々の氏族同士の間で裁決する〉と述べている。
このエンゲルスの著書以来,氏族社会をいわゆる〈原始共産制〉の時代として,かつてマルクスが〈アジア的・古代的・封建的・近代ブルジョア的〉と名づけた階級社会の継起的発展系列に先だつ,人類社会発展の最初の段階をなすものと規定する考え方が,多くの社会経済史学者の間に支配的となった。とくにソ連邦の歴史学・民族学界においては,氏族社会の研究は,地域共同体のそれとともに,古代階級国家の形成にいたるまでの社会進化の一般的形式の究明という目標に向かっておこなわれてきた。
他方,モーガン以後の民族学の発達は,資料と理論の両面からモーガンの所説に多くの修正を促すようになり,とくにモーガンやエンゲルスの時代の学界を支配していた,人類普遍の一線的な進化の形式を前提とする進化主義の思想が,痛烈な批判の対象となるに及んで,少なくともソ連邦以外の国際学界にあっては,先階級社会の形態究明を企てたモーガン=エンゲルスの研究のもつ積極的・建設的な意義すら忘れ去られたかの感があった。さらに1920年代以後には,現在の民族誌的資料を遠い過去からの残存と見て,これを歴史的復原の素材に用いる可能性そのものを,否定もしくは疑問視する傾向も高まり,最近のイギリス,アメリカ,フランスなどの学界では,氏族その他の血縁的または地縁的集団をめぐる未開社会の構造的・機能的研究の多くは,むしろ時と所とにかかわりなく,一定の条件のもとには,つねに反復して起こりうる超時間的の事象,ないしは一般原理の探究という方向に向かいつつある。これらの非歴史的な研究態度は,それ自体意味のある学問研究の一面を代表するものであるが,人類社会における超時間的な一般原理は,同様の条件が与えられれば,現在にも過去にも同様にはたらくはずであろう。
またイロコイ諸族のような氏族制度が20世紀のニューヨークに生まれうる条件は存在せず,階級的国家組織の形成される以前の共同体の可能な結合形式の種類も,ごく限定されたものであるとするならば,やはりモーガンの企てたような氏族社会の歴史的位置づけは,モーガン以後こんにちまでの研究の成果の上に,改めて考察し直されねばならぬ重要な問題である。ただモーガンがその研究の出発点としたイロコイ諸族的な母系氏族が氏族社会本来の原初的形態であったかどうか,また氏族結合の血縁的原理が,つねに純粋で徹底したものでありえたかどうか,さらに,はたして氏族制度が,家族という結合単位に先だって,全人類の社会に遍在的であったかどうかは,以下に述べる各種の事例から推しても,きわめて疑わしい。
氏族社会の構造と変化
まず第1に氏族クランclan,シブsibの構造原理からこの問題を追究してみよう。これまでの氏族に対する最も一般的な定義によれば,氏族とは家族と異なり,一つの共同の祖先をもつという信仰で結ばれた単系(母系もしくは父系)の血縁集団であり,集団内の婚姻の禁止,すなわち外婚制をその特徴とするものとされてきた。けれども,オーストラリア,メラネシア,アメリカをはじめ,世界各地の未開民族の社会構造に対する精密な民族学的調査の結果を総合するならば,いかなる氏族的集団も多かれ少なかれ,一定の土地と結びついており,完全に地縁を離れた純粋の血縁関係のみで,社会的・政治的な単位を構成している氏族というものは見いだしがたい。したがって,従来氏族の名でよばれてきた組織のうちでも,地縁的なつながりが上記の〈典型的〉な氏族構成の原則をゆがめている場合のほうが,むしろ多いのではないかと考えられる。
たとえば,ニューギニア南東海岸のコイタ族は,村落共同体のほかに,さらに父系の氏族iduhuに分かれているが,一つの村で数の少ない氏族が,強大な氏族の中に編入されたり,自分の氏族のいない村に移住したものが,親しい関係にあるその村の氏族員の資格を分けてもらう場合が多い。氏族員のみがその耕地に対する権利をもっているので,新来者はその村のいずれかの氏族に所属することが,土地を耕して生活する前提条件となる。そればかりでなく,嫁入りした女子は夫の氏族に入り,夫の死後も寡婦として夫の氏族内にとどまった。したがって,このさいの氏族の構成員は,父系的に結合した血縁者のみに限られない。他氏族から配偶者として迎えた女子もこれに加わり,他氏族に嫁した女子は氏族の外に出るということになる。この点でそれは,家族ないしは大家族を構成する原理の上に立つものであり,大家族が拡大してこの種の氏族となる例が少なくない。しかも後者が,その血縁的紐帯を認めて,結婚した他氏族の異性の住地に移り住んだ成員をも,なお自己の氏族員として扱うようになれば,ここに単系的血縁原理を徹底せしめた氏族が生まれる。G.P.マードックはこのような〈純粋〉の氏族をシブsibとよび,単系的・外婚的な血縁集団の中核をなす男もしくは女の住地に移り住んだその配偶者をも成員に編入する氏族を,クランclanという語でこれと区別した。
また北東アジアの極地に半ば遊動の狩猟生活を営んでいたユカギール族も,かつては氏族とよばれる組織を最大の社会単位としていたが,彼らの氏族も共通の祖先から出たという血縁者の家族を中核として,これに同一地域に住むその他の家族を包括した。ユカギール以外に,ツングースやコリヤークなど,他種族の家族さえ,住地の共同と婚姻関係とによって氏族員に編入された。しかもこのユカギール族は,同一部落以外の自己の氏族員と結婚する。いまもしこのような族内婚endogamyが,一つの地域共同体の内部でおこなわれ,かつその共同体の中が,別に単系的な血縁集団に分かれていない場合には,この共同体は地縁集団であると同時に,双系的な(すなわち父方・母方の双方の血縁者または血縁者と信ずるものとの親族関係を認める)血縁集団となりうるであろう。この種の単位集団は,これまで多くの民族学者の注意しなかったものであるが,実際にはその例がかなり多い。マードックはこれをディームdemeの名で類別している。
しかるに親族集団は族外婚に向かう傾向をもつため,この外婚制は容易にディームにも延長される。このさい婚姻にさいして男女いずれの住地に夫婦が住むかは,従来の慣習によって,父処婚もしくは母処婚の居住規制をとり,これに従ってやがてはディームそのものが,父系もしくは母系の血縁系統を枢軸とするようになれば,それは前記のクランとなるであろう。マードックは彼のいわゆるクランが,大家族のほか,ディームのような地縁的・血縁的組織からも生まれうることをしめそうとした。しかしまた,厳重な外婚制をとる単系的氏族的組織の内部に,外部の文明の影響などによって,族内婚の普及していく例も少なくない。この場合,氏族員は父方と母方との血縁者の間に区別をつけにくくなり,単系の原則も,氏族そのものの構造も,くずれていくことになろう。
以上のわずかの例からもうかがわれるように,ふつう氏族とよばれる血縁集団は,必ずしも一貫した原理のもとに固定した制度ではない。また,モーガン=エンゲルス以来,ソ連邦時代の民族学者にいたるまで,歴史的発展の一般形式として疑わなかった,母系氏族から父系氏族へという系列も,すべての民族が一様に経過した普遍的な段階とは考えられない。家族たると氏族たるとを問わず,母系・父系の別は,主として婚姻後の居住規制が,妻方もしくは夫方のいずれか一方にかたよる場合にあらわれ,このような単処婚的居住規制はまた,男女いずれか一方がその社会の経済生活に演ずる中心的な役割に対応する傾向がある。
したがって,たとえば,男子による狩猟または牧畜を生活の基調とするような民族にあっては,母系氏族の段階を経ないで,最初から父系氏族を形成する場合もありうるであろう。けれども狩猟をはじめ,本来男子の分業とする経済活動は,その成長した土地に対する多年の知識経験を必要とし,未知の環境に新たに順応することが,採取や農耕のような女子の分担する生業におけるよりも概してむずかしい。そのため,母処婚は父処婚におけるよりも,同一共同体の内部でおこなわれる傾向があるばかりでなく,母処婚的・母系的な氏族の内部においても,男子の経済的地位が高まってくると,女の父親に支払う代償によって妻を自家にむかえる父処婚がしだいに一般的となり,これにともなって父と子との関係は緊密の度を増す。そして財産も自己の氏族員である姉妹の子にゆずるかわりに,妻の氏族員たる実子に相続させるようになると,ここに母系氏族から父系氏族への転化がはじまることになる。
こんにち母系氏族といわれるものの中には,このような父処婚の居住規制が一般化していく例が少なくない。たとえば,ソロモン諸島ブーゲンビル島の南西に原始的な農耕をいとなむシウアイ族は,母系氏族からなっているが,女子が夫の家に住むことが多いので,生まれた子どもは父親の血縁者と親しくなり,父方の氏族員に代償を払って,父の土地を相続することもある。これに反して,父系の氏族社会が直接に母系に変化していくという例はこれを見ない。これは父処婚がひとたび確立すると,そこから母処婚に転ずるには,上に述べたように,生地の環境に精通するまでに多年の経験を必要とする男子の生業上,多くの困難をともなうからであり,さらに男子の財力や地位が高まって,一夫多妻制の流行するようになった社会では,これがいっそう母系への変化を阻止する要因となるであろう。
氏族社会の歴史的形成と崩壊
そこで第2に,長い人類史の時間的過程における氏族ないしは氏族制時代なるものの位置づけについては,こんにちの知識でどの程度の規定が可能であるかを考察してみよう。先にあげたモーガンも,氏族制度が人類の起源にまでさかのぼるほど古いものとは考えていない。こんにち民族学上から認められる一般的傾向としては,大家族が社会結合の単位として独立の地位を占めるような社会では,氏族制度が発達しない点を指摘することができる。また小集団をなして遊動の生活をいとなみ採取・狩猟を生業とするような種族の社会にも,本来的な氏族制度を見ない。
たとえば,アンダマン諸島民は,平均30~50人の,相互に血縁関係にある男女老幼の,地縁的共同体を最大の単位集団としているけれども,この集団は婚姻関係の規制にはなんの関係もなく,ただ兄弟と姉妹,伯叔父母と甥・姪間の近親婚をタブーとしているにすぎない。またマレー半島の熱帯密林に採取狩猟の生活を送るセマング族やサカイ(セノイ)族などは,夫婦と子どもとからなる単独の1家族,もしくは血縁関係にある数家族が,一つの経済的・社会的単位をなして,一定地域内を移動して歩く。後者の場合は,結婚した幾人かの息子がその父親のキャンプに屋根だけを別にしてとどまるところから生じた,一種の父系的大家族であって,その大きさは10人ないし20人余りくらいを常とする。極北の環境にかなり高度の技術をもって異常な適応をしめしたエスキモーの単位的社会集団もせいぜい20戸から30戸くらいの小部落の範囲をこえず,氏族にあたる組織をもたない。
以上のような採取狩猟民にあっては,一定面積内で可能な食糧獲得の制約が,人間の単位的結合の限界を規定しているもののごとく,言語や生活様式の共同にもとづいて第三者が部族とよぶようなカテゴリーも,彼ら自身にあっては,なんら社会構成上の意義はもちえないのである。しかるに,上記のイロコイ諸族のように安定した農耕経済や,北アメリカ北西海岸のいわゆる北西インディアンの諸部族のように豊かにめぐまれた漁労経済を基礎に,相当量の人口が定住の生活に入った社会においては,氏族的な制度の発達を見る傾向がある。思うに外婚的な婚姻規制を原則とする氏族制度は,各氏族がそれぞれ独立の社会的・政治的単位を形成しつつも,少なくとも2個以上の氏族共同体の存在と連係とを前提とするのでなければ成立しえないものであり,この意味において,氏族はたんなるホルド的な地縁共同体にくらべて,いわば高次の発展形態といいうるであろう。
われわれは,先史時代の社会構造を具体的に跡づけることはできないが,上記の一般的傾向から,たとえば西ヨーロッパの後期旧石器時代や日本の縄文時代のように,定住的な性格の見られる文化遺跡では,たとえ採集経済の上に立っていても,氏族的な単位集団の生まれうる可能性があり,他方,小集団が孤立して遊動して歩くような採取狩猟民の場合は,先史時代にもやはり,氏族制度は未発達の状態にとどまったものと推定して大過あるまい。
いま先史学上の遺跡についてみるならば,最古の人工的住居址が1単位家族をいれるにふさわしい小さなもので,その後の時代にこの種の小屋が一つの屋根の下に結合されたと思われる証跡や,あるいは大きな共同墳のあらわれるような場合,われわれは,これらの遺跡をのこした人々の具体的な親族構造や婚姻の規制は知ることができないが,そこに少なくとも大家族的ないしは氏族的な単位集団の形成された可能性をみとめることはできるのである。たとえば南ロシアのドン川上流ガガリノの最古の住居址は,4.5m×5.5mの1室にすぎないが,その後の時代については,ガガリノ南方のコスチョンキでは,長さ34m,幅5.6mの長い一つの竪穴に,8個のかまどの跡がならんだもの,その北西方のティモノフカでは,10m×5mの住居が,1対ずつ,一つのかまどをはさんでむらがったものなどが発見された。ダニューブ文化の初期農耕民の家屋も,小氏族をいれるに足りるほど大きなものであり,同時代のイギリスや北ヨーロッパの村落遺跡にも,集団埋葬のあとが見いだされる。またメソポタミアやエジプトにおける,世界最古の農耕村落遺跡の発達のあとをたどってみても,多くの部屋に仕切ったアパート式の住居址と,1~2の大型家屋を中心に散在する小家屋の1群との,二つの様式があるが,かまどは各部屋ないし家ごとに設けられているのに対し,穀物の貯蔵庫は一つより発見されないことが多い。村落の共同墓地と思われるものにみる墳墓の規模や副葬品の量質はほとんど一様であって,当時の小規模な村落共同体に,まだ階級や貧富の差の生じていなかったことを物語っている。これらの事実を民族学的に知られた氏族的集団の共同大家屋や共同墳の例と対比し,制限された可能性の範囲においてその意味を考えることは,学問的にも当然ゆるされるべき操作であろう。
つぎに古代の階級的国家制度の形成は,同時に政治的単位としての氏族共同体の崩壊を意味するものとして,その歴史的過程を跡づけようとしたモーガンとくにエンゲルスの研究は,その後明らかにされた民族学,考古学,歴史学の資料に照らしても,こんにちなお高い価値をもつ。
前にも指摘したように,氏族的な単位は,婚姻を規制するためのみの純粋な血縁集団ではなく,一定の土地の占用を基礎とした自給自足的な単位共同体でもある。これに反して,古代の村落が都市的な国家に発展したあとをかえりみると,必ず,共同体の内部には職業や階級の分化と貧富の差とがあらわれ,封鎖的な自給経済にかわって,広い地域をふくむ交易経済の証左が見うけられてくるのである。ことに貨幣や商品や奴隷ばかりでなく,氏族的共同体から割り当てられた土地が,富と勢力のある個人の私有に帰し,相続や売買の対象となりうるようになると,氏族的所有形態の基盤は失われざるをえない。このような条件のもとでは,たとえ氏族的な結合が祭祀その他の伝統の中に存続するとしても,経済的単位としての氏族共同体の機能は,家族ないし大家族のそれに解消していくのは避けがたい過程であろう。
サモアをはじめ,ポリネシアにおける氏族制解体の過程についてみるならば,世襲的な身分や階級の差別が,支配・被支配の権力関係によって強められていくと,まず一方では家族の,他方では地縁集団としての村落の役割が,氏族にかわって前面にあらわれてくる。これに対し,旧来の氏族は,カヌーや家々に飾られた,鳥やイヌや木の葉のたばなどの紋章の形でそのなごりをとどめるにすぎない。アメリカ合衆国ニューメキシコ州のプエブロ・インディアン,ズニ族の場合には,大は400人,小は3~4人よりなる旧来の15の母系氏族が,いちおう外婚的な単位をなしてきたけれども,いろいろの点で,父と子との家族的関係も深く,父の氏族の成員でも近い世代の血縁者との婚姻は忌避されている。氏族の政治的機能は消失して,氏族会議も氏族長も氏族集会所ももたない。わずかに祭礼の際の供犠や舞踊に氏族のはたらきは残されているが,ここに注意すべきことは,近年のズニ社会にあっては,その宗教的ならびに世俗的な権力が,ある種の神官たちの手に握られ,もともと1氏族の特定家族に限られた神官の階級や,祭祀結社その他の団体が,それぞれ大きな役割を演じて,氏族制度そのものを崩壊に導いたという点である。またシベリアの遊牧民ヤクート族にあっては,ウマの大群を氏族が共有していた間は,緊密な氏族的結合が保たれていたのに反し,ウシの飼育をはじめるとともに,牧畜と所有の単位は家族に分解し,財産の相続をめぐる氏族と家族との矛盾衝突がはげしくなった。別に共同の祭祀と供犠とによって結ばれた,遠い血縁関係にある氏族同士の連合があったが,連合の会議も氏族の会議も,第1に首長と弁士,第2に貴族と戦士,第3に庶民と若者の3部からなり,連合の会議では,各氏族員はそれぞれの第1部を代表に立ててその背後にならんだという。
これらの事実は,おそらくモーガンのあげたイロコイ諸族のそれに近い民主的な組織の内部にきざした階級的分化の芽ばえを示すものであろう。しかるに主要な生産手段に対する私有権が確立し,交易経済の上に,自給的な村落共同体よりも大きな都市的中心が生まれ,直接の生産にたずさわらないで,生産された巨大な余剰の富を自由にしうる少数者が,信仰と武力との両面から支配階級としてこれに君臨するようになった地方では,ここに国家と名づけうる権力機関が成立する。たとえ都市的中心を離れた村落に,従前の氏族的共同体ないしは農業共同体が,ある程度までその自治的機能を残すとしても,それらは都市を中心に起こった国家の権力を握る階級の支配下に立ち,余剰生産物や賦役労働の供出の源泉として,その独立性を喪失するとともに,やがてはみずからも,個人的財産権の発達にともなって,容易に本来の体制を解体せしめるであろう。こうした過程は,階級的国家権力が,氏族的ないし村落的な共同体の内的発展から成立した場合にも,また外的な勢力の征服によって生まれた場合にも,ひとしくあてはまるものである。メソポタミア,エジプト,黄河流域,アンデス地帯などにおける古代国家の形成は,おそらく多くの村落共同体の協力を必要とする灌漑農耕を基礎におこなわれたもので,灌漑を統制する神官の階級,ついで軍事をつかさどる貴族の階級が,直接生産者の余剰労働の上に,強大な権力機構をきずきあげたのであった。
歴史的記録にあらわれた氏族
以上述べたところは,主としてこんにちまでの民族学的資料にもとづいて知りえた人間の社会結合の一般的な基本形式から推して,古代国家成立に先だつ相当長期にわたる期間,社会的・経済的・政治的な結合単位が,最も広い意味の氏族ないしは氏族を基盤とする共同体であったと考えうる根拠を示したものである。もとより文献記録の徴すべきものはなく,考古学的遺跡のみから,これを残した人々の社会構造の細部にわたって知ることは不可能であるから,この種の歴史的復原はどこまでも一つの作業仮説の域を出ない。
しかし文字のはじまる歴史時代に入ってからの諸民族の古代の記録の中にも,彼らがかつて,氏族と解しうるような組織をもっていたことをうかがわしめるものがある。このことはモーガンをして,彼がイロコイ諸族その他の未開民族に発見した氏族制度とその民主的な原則とが,これを解消せしめていく都市的国家の根底にも,その成立の当初においては,なおしばらく存続したことを示すものとして,彼の所説の正しさを証明する一つの有力な証左と信ぜしめたところのものであった。
ギリシア
この意味においてモーガンは,古代の記録に残るギリシア人およびローマ人の初期の部族的組織の中に,イロコイ諸族の氏族-胞族-部族-部族連合の組織の発展形態にあたるものを見いだしたのであった。アリストテレスによれば,アッティカのアテナイ人は,本来,四つの部族(フュレー)からなり,各部族は三つのフラトリア(胞族),各フラトリアは30のゲノス(氏族)からなったという。その他の記録もまた,古典時代のギリシア人の社会が家族および大家族のほかに,氏族・胞族・部族にあたると思われる三つの単位集団をもっていたことを示す。そしてここに氏族と訳したゲノスは,(1)祖先を同じくすると信じられる男系の子孫からなるが,(2)他族のものを成員として養取することを妨げず,(3)ある祖先の祭りを共同におこない,(4)正式の氏族員の名簿を管理し,(5)毎年くじによってその統治者(アルコン)をえらび,(6)共有の財産とその管理者とをもち,(7)全員の会議によってこれらゲノスの事務を処理したことも,少なくともアッティカについては記録の上からほぼたしかめうるのである。
モーガンはこれらのほか,〈共同の墓地,死んだ成員の財産を相続する共同の権利,援助・防衛および加害に対する救治の相互的義務,孤児の娘および女相続人の場合には氏族内で結婚する権利,一定の場合のほか氏族内で結婚しない義務〉をゲノスの特性として列挙しているが,これらに対する文献的な裏づけは,前の諸項目ほどには確実明白とはいいがたい。それに古典時代のアテナイでは,ゲノスの成員となるものは,人民の全部ではなくて,一部の少数者にすぎなかったことも知られているので,《古代史》(1884-1902)の著者E.マイヤーをはじめ,多くの歴史家は,この種の氏族制度は,ポリスの成立後,エウパトリデスすなわち貴族階級の支配の組織としてつくられた,新しいものであるという見解を表明してきた。けれども他方,フラトリアには,太古から全人民が,個人としてではなく,中間の下部組織を介して加入していたことが伝えられ,その下部組織としてあげうるもののうちで,ゲノス以外の祭祀的集団は比較的後期の所産であることも証明しうるし,事実手工業者など,貴族階級以外のゲノスの残存と推定しうるものも見られるので,もしフラトリアが全人民の加入したものであるとすれば,ゲノスもまた,おそらくはポリス以前から,すべてのギリシア人に本来的な,血縁的な単位集団ではなかったかという考証が,最近の歴史学者によっておこなわれている。
ローマ
同様の推定は,古代ローマのトリブス,クリアcuria,ゲンスgensについてもいいうるところである。古伝によれば,ローマ人はもと三つのトリブスが集まって形成され,各トリブスは10のクリア,各クリアは10のゲンスに分かれていたという。モーガンは,この3者をそれぞれ部族・胞族・氏族に比定し,氏族すなわちゲンスの特性として,つぎの9項目をあげた。(1)死亡した氏族員の財産を相続する相互の権利,(2)共同墓地の所有,(3)共同の宗教儀礼sacra gentilicia(氏祭),(4)氏族内で結婚しない義務,(5)土地の共同所有,(6)援助・防衛,および加害に対する救治の相互的義務,(7)氏族名を名のる権利,(8)異族者を氏族内に養取する権利,(9)その首長を選挙し,罷免する権利。
以上の中には,歴史上の記録に明示されておらず,間接的な手がかりによる類推にすぎぬものも若干あるが,ローマのゲンスが,本項で扱った広義の氏族もしくは少なくともこれに近い単位的な集団であったと考えさせる文献資料はかなり多い。そしていわゆる王政時代には,各氏族内のパトリキウスpatricius(貴族)とよばれる一定家族から選ばれた300の氏族長patres(〈父〉の意)が元老院を構成し,別に各クリアごとに1票をもったクリア民会(コミティア・クリアタ)が,元老院で下相談した法律の採否を決定し,いわゆる王rexをふくむ高級官吏を選挙し,戦いを宣し,死刑の判決を与えたという。
したがって,当時のローマ国家は,英雄時代のギリシアのポリスと同様,階級的な分化をとげながらも,本来の氏族的な組織を基盤とした軍事的民主制の形をとり,歴史家のいわゆる王は,ギリシアの〈バシレウス〉に相当して,軍司令官であり,神官長ではあっても専制的な君主ではありえなかった。他方,増大していく新たな移住者や,被征服地域の住民は,以上の組織を構成する本来のローマ国民populus Romanusのほかに,公権をもたぬ平民(プレブス)として,一大勢力を形成することになったのである。
ケルトとゲルマン
西ヨーロッパ諸国語の氏族を意味するクランの語源となった古アイルランド語のクランclann(子たち)は,ふつう部族よりも小さい大家族的ないしは小氏族的な血縁集団を意味し,一定の土地を共有する単位をなしていた。この種のクランの遺制は,18世紀に入るまでのスコットランドに見られ,たとえばウォルター・スコットの《ウェーバリー》は,高地スコットランドのクランの描写に詳しい。モーガンは《古代社会》の中で,スコットランドのクランは,〈組織においても,精神においても,氏族のすぐれた典型であり,氏族生活がその成員に及ぼす力のすばらしい一例である。……もしサー・ウォルターが,いくつかの点で,物語の事態に応じて,これらの特性を誇張したとしても,それらは現実の基礎をもっていたのだ。……われわれは,彼らの確執や血の復讐に,氏族による彼らの領地の分割に,彼らの共同の土地利用に,クランの成員のその首領ならびに成員相互に対する忠誠に,氏族社会につねに見られる不変の特徴を見いだす。スコットに描かれたように,それは,われわれがギリシア人やローマ人の氏族……に見いだしうるよりも,もっとはげしい,勇武な氏族生活であった。……血統は男系によったので,男子成員の子どもたちは,その氏族の成員としてとどまったが,女子成員の子どもたちは,彼らのそれぞれの父のクランに属した〉と述べている。イギリス政府はその統治の目的を達するため,これら高地スコットランドのクランの組織を破壊しなければならなかった。
ゲルマン人についても,カエサルはその《ガリア戦記》の中で,その当時スエウィ族が,〈氏族および親族ごとに〉定住したと述べており,その後1世紀半をへだてたタキトゥスの《ゲルマニア》には,ゲルマン人の戦闘隊形が,〈家族および近親別に一団を結んで〉編成されたという文字がある。これらの記録を,古代ゲルマン人の共同体や,民主的な合議制に関する他の記事とあわせて考察するならば,彼らが,本来,なんらかの氏族的な単位集団を基礎に,その部族組織を形成していたことをうかがいうるであろう。
タキトゥスの中には,また,〈母の兄弟は,彼の甥を自分の息子と同様に見ている。いな,ある人々は,母方の伯叔父と甥との血のつながりを,父と息子との間のそれよりも,もっと神聖で緊密なものと考えており,したがって,もし人質が要求されるときには,拘束しようとする男自身の息子よりも,彼の姉妹の息子のほうが,より大きな保証とみなされた〉という意味の文章がある。これは,母系の氏族制度と関連してしばしば見られる叔権avunculate的な現象であり,ゲルマン人もまた,かつて母系氏族をもっていた証拠として,重要視されてきた資料であるが,この種の関係は,父系社会にあっても,たとえば母の兄弟の娘と結婚する交叉いとこ婚の制度化している場合や,とくに姉妹に対する兄弟の緊密な責任関係が,結婚後にも持続するような場合にも,起こりうるわけであるから,必ずしもゲルマン人の母系制の〈残存〉とのみ見ることはできない。
なおアングロ・サクソン語のシブsib,古高ドイツ語のジッパsippa,ゴート語のシブヤsibjaなどの系統の語は,ケルト語系のクランclanの語とならんで,こんにち氏族を意味する術語として用いられているが(英語sib,ドイツ語ジッペSippe),その本来の意味は明確ではない。むしろ,原始インド・ヨーロッパ語の語根ganに由来するサンスクリットのガナスganas,ギリシア語のゲノスgenos,ラテン語のゲンスgensなどと同系統の,ゴート語のクニkuni,古代北ヨーロッパ語やアングロ・サクソン語のキンkyn(英語のキンkin),中高ドイツ語のキュンネkünneなどの中に,ゲルマン人自身が氏族を意味したことばがあって,後日〈国王〉を意味するクニングkuning(ドイツ語ケーニヒKönig)の語は,もと氏族長あるいは部族長を意味したものではないかという。
アステカとインカ
モーガンは,16世紀の初めにスペインの征服者と対決したメキシコのアステカ族の政治機構を,ヨーロッパ人の諸記録にもとづいて検討した結果,歴史家がこれを王国とか帝国とか称するのは,まったく想像上の擬制にすぎず,事実は,アステカの国家なるものは,イロコイ諸族と同様の,氏族-胞族-部族という組織の上に形成された3部族の連合体であったことを,とくに《古代社会》の1章をさいて詳論している。スペイン人がアステカの王もしくは皇帝と考えた職は,もともと旧大陸の専制君主にあたるようなものではなく,一種の議会の手で選挙された最高の軍司令官であった。こんにちのメキシコ市にあったアステカの首都テノチティトランは,四つの地区に区画され,そのおのおのはまた,カルプリcalpulliという集団の占める小地区に分かれる。各カルプリはそれぞれ独自の職業に従事し,各自の神と神殿と土地と,そしてある程度の自治的な制度とをもつ。各カルプリから1人ずつの代表者がテノチティトランの最高議会に送られる。この議員はトゥラトアニ(話し手)とよばれて,行政や司法をつかさどり,また4地区のおのおのから1人ずつ軍事指揮者を選ぶ。上記の最高の軍司令官は,この4人の軍事指揮者の中から選挙され,〈人々の長〉とよばれたが,その権能はもっぱら軍事にとどまり,宗教上・内政上の指導権は,彼に次ぐもう1人の指導者に託された。スペインの征服当時,軍司令官の地位は世襲の王位に近いものになってはいたが,奴隷を除く各階級は,カルプリを通じて,この種の軍事的民主制に参与しえたことは事実らしい。
ただモーガンをはじめ,多くの学者は,断片的な資料をもとに,このカルプリおよび4地区に分かれ住んだ集団が,それぞれ近い血縁関係によって結ばれたものと解し,これを父系の氏族および胞族に比定してきた。これはありうべきことではある。事実メキシコの西部や南部のある部族は,父系氏族をもっていたと推定されるし,ユカタン半島南部の山中に,先スペイン期のマヤの文化を保持するこんにちのラカンドン族も,二つの外婚的氏族に分かれている。けれども現存の記録のみでは,アステカのカルプリを父系氏族と断定しうるだけの根拠はきわめて乏しい。これらをたんに軍事上の目的による組織にすぎないと考える学者もあり,モーガンの説は,すべてを先験的に,イロコイ諸族の尺度に合わせようとするものであるとも批判されている。
同様の問題は,南アメリカのインカ帝国についてもいいうる。インカ帝国に包摂された諸部族は,いくつかのアイルaylluという集団から構成された。アイルは経済的にも宗教的にも1単位をなし,その首長は,最高の裁判官であると同時に,戦時には指揮官ともなった。古い記録は,同一アイルの成員が,父系の血縁関係によって結ばれていたらしいことを示すというので,しばしばこれは父系氏族と解される。けれどもインカ帝国をつくっていたアイマラ族やケチュア族が,こんにちアイルとよんでいる組織は,相互に関係なく,それぞれ別々の祖先から出たという大家族の連合体で,内婚制の傾向が強い。
日本および中国
日本の古文献に残る大和朝廷時代の〈うじ〉(氏)の制度については,すでに史学者の考証が山積しているが,要するに支配階級たる貴族・豪族の父系的血縁集団を,国家機関の一節として,政治に利用したものと見ることができよう。〈うじ〉は氏上(うじのかみ)に統率され,共同の氏神を祭り,〈やっこ〉(奴婢)のほか,〈かきべ〉(民部・部曲)といわれる隷民の集団をその支配下にもつ。〈かきべ〉はその所属する〈うじ〉の血縁者として擬制され,支配者の〈うじ〉の名をとって,何々〈べ〉(部)などとよばれた。また〈うじ〉の序列を規制する公的な制度として,貴族・豪族の家格や職掌をあらわす数種の〈かばね〉(姓)の称呼が,〈うじ〉の朝廷に対する関係に応じて与えられた。〈うじ〉は明らかに国家の制度であるが,もともとは氏族にあたる自治的な血縁集団を基礎に形成されたものと考えられている。日本語の〈うじ〉をツングース語あるいはモンゴル語系統のものとする説もあるが,別に日本語の〈うから〉〈やから〉〈はらから〉〈ともがら〉などに見る〈から〉は,満州語をはじめ,こんにち多くのツングース諸族の父系氏族をあらわすハラxalaあるいはカラkalaと同系と思われ,〈かばね〉の語も,新羅の骨品制などと同じく,骨の語をもって氏族をあらわすアルタイ語系諸族と思想的に相つらなるものがある。大和朝廷を中心とする支配階級の〈うじ〉の制度は,おそらくアジア大陸のアルタイ語系諸族の父系氏族と歴史的な連関をもつものかもしれない。
古代の中国においてもまた,殷の王族の青年男子が多子族という集団をつくって,祖先の祭祀や王の親衛の単位となる一方,多父多母などの名で多数の父母を祭ったという卜辞(ぼくじ)金文の記録が,一種の氏族制度の存在を証するものという所説が唱えられた。また祖母を妣(ひ)とよんで,祖先の祭りに合祭するなど,母性の神格化のあとは,すでに卜辞に見いだされ,周の先妣姜嫄(きようげん)についても,夫なくして始祖后稷(こうしよく)を生む,と伝えられるが,これらの記録をもって,母系氏族制のなごりを物語るものと見る解釈もおこなわれた。
これらは資料として,もとより不十分であるけれども,中国における同姓不婚の慣習は,氏族外婚制の根本原則にひとしい。とくに宋代のころからうかがわれ,明・清以後の文献に明らかな宗族(そうぞく)の制は,おそらく国家の制度とは独立に,民間に自然に発達した相互扶助的な父系的外婚氏族である。宗祠(そうし)を宗族結合の中心として,儒教的な祭儀をいとなみ,祭田・義荘・祖墓その他の族産をもち,族譜・宗譜・家乗などとよばれる宗族全体の系図を印刷し,ときに族塾(じゆく)を開いた。宗族は華南において最も発達し,華中がこれに次ぐ。あるいは宗族内の富家の利益に隷属する形になることもあるが,宗族の強大化をはかることは,けっきょく成員の生活の安定を意味した。
未開社会の氏族制と似た構造原理をもつこのような組織が,文明の時代にも,国家機構とは別個に,民間を横につらぬいて形成されうる可能性が,中国の宗族によって実地に示されたことは,きわめて興味ふかい事実である。
→氏族
執筆者:石田 英一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「氏族制度」の意味・わかりやすい解説
氏族制度
しぞくせいど
氏族が社会の主要な構成単位として、経済的・政治的・社会的な機能を果たしている場合に、氏族制度という名称がしばしば用いられる。19世紀後半から20世紀にかけての進化主義者が、氏族制度について語っていたころの用語法では、氏族はリネージと区別されず、漠然と、家族より大きな単系の親族集団をさすものであった。たとえば、L・H・モルガンの所説では、氏族制度は人類進化の一段階として重要な地位を与えられている。彼は、氏族は、家族が発達する以前の人類史上もっとも早期に、家族にかわって普遍的に存在していた親族集団であり、当初の母系制から、しだいに父系制へと移行していったものである、と主張した。多方面に多大な影響を与えたこの学説は、今日では否定されており、氏族制度を人類史上の一段階とする見方も力を失っている。単系出自集団に関する用語法もまた、当時よりは、はるかに明確なものになってきている。
アフリカ南部のサン(いわゆるブッシュマン)や、コンゴ森林に住みピグミーと総称されてきた狩猟採集民、シベリアの一部の部族のように、もともと氏族の制度をもたない社会も多い。西欧や日本も、氏族制度をもたない社会に属している。また、単系出自によらない親族集団が重要な社会もある。しかし人類学者が対象とする社会の大多数では、単系出自集団が社会の重要な構成単位となっている。ローウィは単系出自の形成において、財産に対する諸権利の伝達と結婚後の居住形式が重要な要因だと考えた。これはマードックの研究によっても確認されている。もっとも、中央アジアの遊牧民におけるように、生態学的な要因も軽視することはできない。
氏族がとる具体的な形態は、さまざまである。オーストラリア先住民の間でみられるように、地域的な氏族が、外婚半族などの、より大きな単位に組織されている例もある。ニューギニア高地の一部の部族では地域的な氏族のいくつかが緩い同盟を組んでおり、この同盟の内部では戦争が行われない。氏族の内部には、数世代の系譜深度をもち成員相互の系譜がはっきりたどれる小出自集団、リネージがみられるのが通常であるが、このリネージを何段階にも高度に組織化した氏族もある。アフリカのヌエルの人々の社会では、一つの氏族の系譜深度の異なるリネージが特定の領土区分に結び付いている()。同一レベルのリネージ同士は互いに対立し、共通の敵に対しては連合して、一段階上のリネージを出現させる。たとえば相対立するa1とa2は、共通の敵Bに対しては、兄弟リネージとして連合し、リネージAとして行動する。AとBは、Jとの紛争においては連合し、より上の単位Iとして行動する。このような系譜的距離に基づく補完的対立のシステムは、分節リネージ体系とよばれる。同様なシステムは中央アジアの遊牧民の間にもみられる。
多くの氏族制度のもとでは、氏族成員同士、同じレベルのリネージ同士は互いに対等であるが、氏族の構成員やリネージが、氏族創始者に対する系譜的近接関係に応じて序列づけられている場合もある。円錐(えんすい)クランと名づけられた、ポリネシアの首長制社会にみられる集団がその代表例である。もっともここでは、かならずしも系譜上父方、母方を区別しておらず、外婚規制も伴わないため、これを単系出自集団とみることは疑問である。しかし、一般的にいって、首長職などの特別な政治的役職や経済的利権が絡む場合、系譜上の年長性に従って、氏族を構成するリネージの間に序列が生じる傾向があるようである。
広い地域に分散し他の氏族と混住し、けっして集合体としては行動しない分散氏族も広くみられる氏族形態である。このような分散氏族においては、内部にリネージの複雑な組織化もみられないのが普通である。アフリカ、ザンビアの民族集団トンガのように、氏族成員の一部が一定地域に多少まとまって住み、全体氏族の地方分枝を形づくっていることもあるが、こういった地域集団も、リネージとは異なり、かならずしも系譜関係に基づいた内部構造をもっているとは限らない。このように、氏族がとる具体的な形態はさまざまであり、それに伴い、政治的・社会的機能も社会ごとにけっして一様ではない。
氏族制度は、国家なき社会においてもっとも重要な政治的機能を果たしている。人は特定の氏族に所属することを通じて、さまざまな社会的権利・義務を受け取る。氏族の成員には他の成員の死に対し復讐(ふくしゅう)の義務があり、危急時においては助け合う。氏族の一成員が犯した罪に対する責任は、その氏族の他の成員に無差別に負わされる。もちろん氏族制度は国家なき社会だけの現象ではなく、首長制社会や王国においても、地域レベルでは重要な役割を保持している例もある。
[濱本 満]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「氏族制度」の意味・わかりやすい解説
氏族制度
しぞくせいど
clan system
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「氏族制度」の解説
氏族制度
しぞくせいど
父系もしくは母系的に親子関係の連鎖を通して特定の祖先につながることを認知した親族集団を氏族といい,この氏族を基盤にした社会制度を氏族制度という。祖先との系譜関係を明確に認知した親族集団であるリニッジで構成されている場合がある。クランの訳語であるが,日本古代の氏族(うじぞく)制度とは相違する。日本古代の氏は,5~6世紀に大和朝廷に政治的に組織された首長層の体制であり,始祖からの一系系譜にもとづく組織で,父系に傾斜しているが母系も混入しており,父系的単系出自集団ではなく,成員も流動的で族外婚規制もともなわない。したがってクランやリニッジなどの氏族制度ではない。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...