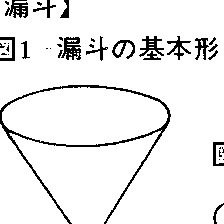翻訳|funnel
精選版 日本国語大辞典 「漏斗」の意味・読み・例文・類語
じょう‐ごジャウ‥【漏斗】
- 〘 名詞 〙 ( 上戸の意で、酒を吸い込むところから。また、「承壺(しょうこ)」の音からとも )
- ① 上が広く、下が細くすぼまって穴のある金属または木・竹製の器。口の狭い器に、水や酒など液体状のものを注ぎ入れるのに用いる。ろうと。
- [初出の実例]「Iǒgode(ジャウゴデ) サケヲ ツグ」(出典:日葡辞書(1603‐04))
- ② 歌舞伎の幽霊の衣装で、裾が①の形に上から下へ次第に細くなっているもの。
- ③ Vの字を伏せたような形。寄席芸人などが、舞台の飾りつけや、人の整列などにいう語。
- [初出の実例]「下座の所町木戸、此間漏斗(ジャウゴ)に往来の遠見」(出典:歌舞伎・夢結蝶鳥追(雪駄直)(1856)二幕)
ろう‐と【漏斗】
- 〘 名詞 〙 口の狭い容器などに物をそそぎ入れるのに用いる器具。上が広く、下は容器の口へ挿し入れるように細くなっている。じょうご。〔新編異国料理(1861)〕
改訂新版 世界大百科事典 「漏斗」の意味・わかりやすい解説
漏斗 (ろうと)
funnel
液体を細い口の容器に移したり,液体と沈殿をこしわけたりする目的に用いられる器具。〈じょうご〉とも呼び一般家庭でも用いる。ろ過するときは,ろ紙などのろ材とともに全体をろ過器あるいはフィルターといって,漏斗とは区別している。ガラス製のものが多いが,目的に応じて磁器製,金属製,ポリエチレンその他のプラスチック製などのものもある。形もいろいろなものがあるが,基本的には図1のように円錐に細い管がついたものである。これにろ紙を適当に折って取り付ければろ過器として用いることができる。このとき,ひだつきろ紙を取り付けて迅速ろ過をしやすくするため漏斗の内壁にひだをつけたひだつき漏斗もある。また小さな目皿をつけた目皿漏斗は,ろ紙をのせると少量の結晶の吸引ろ過ができる。かなりな量の結晶を吸引ろ過するのにはブフナー漏斗(図3)が用いられる。ブフナー漏斗は,磁器製で,図のように小孔を数多くあけた部分があって,これにろ紙をのせて吸引ろ過することができるので,吸引漏斗とも呼ばれている。ブフナー漏斗と同じ目的で使われるガラスフィルターあるいはガラスろ過器と呼ばれているものは,全体がガラス製で,半融ガラスのろ過層を備えているのでろ過器であり,漏斗とは呼ばないのが普通である。通常の漏斗に適当な外とう部分をつけて高温または低温に保ったままろ過できるようにしたものを,保温漏斗あるいは熱漏斗(図4),氷漏斗(図5)などといっている。また,上部に共栓をつけ,下部にコックを有する図6のようなものを分液漏斗といっている。たがいに混じり合わない2種の液体を混和したり,分離したりするのに用いられる。溶媒抽出などには普通に用いられる。たとえば,まずBを閉じておいて容器内に試料溶液を入れ,次にこれを試料溶媒とは混じり合わないが溶解している試料を溶かすことのできる溶媒を適当量入れ,Aを閉じ,これを回してCの穴を閉じ,容器全体を逆さまにして両手でもって,A,Bを押さえてよく振る。ついで倒立のままBを開いて溶媒蒸気を追い出した後,Bを閉じ,再び正常位に立てて放置して2液層が分離してからCの穴を開き,Bを開いて2液を分離することによって試料を抽出することができる。
→漏斗(じょうご)
執筆者:中原 勝儼
漏斗 (じょうご)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「漏斗」の意味・わかりやすい解説
漏斗
ろうと
funnel
filter funnel
広い開口部をもち、下部が細くくびれた、主として液体を移すのに用いられる器具。一般にじょうごといわれるものも漏斗の一種である。化学実験に用いられる漏斗は、液体と固体とを濾別(ろべつ)分離するためのもので、円錐(えんすい)形の開口部に細い脚がついた管である。濾材には濾紙を使うが、円盤状の融着ガラスを濾材とする全ガラス製のものはガラスフィルターとよばれる。吸引濾過には、陶器製のブフナー漏斗あるいは円柱状の開口部をもつガラスフィルターが使われる。分液漏斗は、二相に分かれる液体混合物の分離に使われる。脚が短く、容器部が円柱状の分液漏斗に似たものは滴下漏斗(安全漏斗)で、液体試薬を反応容器に滴下するのに使われる。
[岩本振武]
百科事典マイペディア 「漏斗」の意味・わかりやすい解説
漏斗【ろうと】
→関連項目ろ(濾)過
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漏斗」の意味・わかりやすい解説
漏斗
ろうと
funnel
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
食器・調理器具がわかる辞典 「漏斗」の解説
じょうご【漏斗】
普及版 字通 「漏斗」の読み・字形・画数・意味
【漏斗】ろうと
字通「漏」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
栄養・生化学辞典 「漏斗」の解説
漏斗
世界大百科事典(旧版)内の漏斗の言及
【脳下垂体】より
… 腺下垂体はさらに,上に向かってのびている隆起部(既出の隆起葉),下垂体の前部を占める前葉(主葉),前葉の後部に位置する中間部(中葉)の3部に分けられる。神経下垂体は腺下垂体の後部にあり,漏斗と後葉(神経葉)からなる。なお漏斗は正中隆起と漏斗茎に分けられる。…
【怪談】より
…1804年(文化1)河原崎座初演の《天竺徳兵衛韓噺(てんじくとくべえいこくばなし)》(4世鶴屋南北作)における乳母五百機(いおはた)の霊(初世尾上松助所演)がその嚆矢(こうし)とされる。松助はこの役で,乱れ髪や漏斗(じようご)と称する先細りの裾の鼠色の衣装などを円山応挙の絵を参考に工夫し,また引込みには仏壇へ飛びこむなどの手法で演じ,観客を驚かせた。いらい松助は夏芝居として新工夫の怪談物を続演し,さらにその子3世尾上菊五郎,3世の孫の5世菊五郎らによって継承,集大成された。…
※「漏斗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...