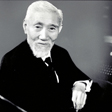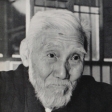精選版 日本国語大辞典 「田中館愛橘」の意味・読み・例文・類語
たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「田中館愛橘」の意味・わかりやすい解説
田中館愛橘
たなかだてあいきつ
(1856―1952)
物理学者。陸奥国(むつのくに)二戸(にのへ)郡福岡(岩手県二戸市)生まれ。家は代々南部藩兵法師範を勤めた。藩校で和漢学を修め、1872年(明治5)父稲蔵の教育方針により一家をあげて上京。慶応義塾、外国語学校で英語を学び、東京開成学校大学予科から、1878年東京大学理学部に入学、菊池大麓(だいろく)、山川健次郎(1854―1931)、お雇い外人教師ユーイング、メンデンホールらに学んだ。外人教師の指導の下に重力測定、地磁気測定に取り組み、またエジソンのフォノグラフ発明後、ただちにその試作を行い、音響や振動の解析を手がけた。これがローマ字への関心の端緒となり、のちにローマ字運動の指導者ともなった。1882年卒業とともに準助教授、1883年助教授。1887年全国地磁気測定では日本の南半、朝鮮半島南部の測定を担当した。1888年イギリス、グラスゴー大学に留学、ケルビンに師事し、ついでベルリン大学に転じ、1891年帰国し帝国大学理科大学(現、東京大学理学部)教授となった。この年10月の濃尾地震(のうびじしん)では震源地調査を行い、岐阜県根尾谷(ねおだに)の大断層を世界に紹介し大きな話題をよんだ。これを機に地震の予防策を議会に建議し、翌1892年文部省に震災予防調査会が設置されると委員として活躍。木村栄(ひさし)らを指導して岩手県水沢に緯度観測所(現、国立天文台水沢VLBI観測所)を設立するなど、日本の地球物理学の確立に尽くした。1917年(大正6)還暦を機に退官、その後の定年制の先駆となった。航空力学の開拓的研究もあり、東京帝国大学航空学調査委員長、帝国学士院会員、学術研究会議委員、貴族院議員など要職にあって、科学・技術の振興に尽くすとともに、国際的な科学の交流に精力的に取り組んだ。一方、科学の普及・啓蒙(けいもう)のため通俗講演に力を注ぎ、さらに1907年(明治40)日本人初の国際度量衡委員会委員に就任、メートル法の普及にも努めた。日本物理学界の指導者としてその確立に貢献し、1944年(昭和19)文化勲章を受けた。多数の論文のほか、随筆集『葛の根(くずのね)』(1936)がある。
[井原 聰]
改訂新版 世界大百科事典 「田中館愛橘」の意味・わかりやすい解説
田中館愛橘 (たなかだてあいきつ)
生没年:1856-1952(安政3-昭和27)
物理学者。岩手県福岡町の生れ。14歳のとき盛岡に出て藩校などで和漢学を学び,1872年に上京,慶応義塾英語学校,開成学校などを経て,78年東京大学理学部に入学。82年卒業し,翌年同大学助教授に就任。88年から私費でヨーロッパへ留学,グラスゴー大学ではW.トムソン(ケルビン)に師事した。91年に帰国,同年帝国大学理科大学教授となり,1917年までその職にあった。学生時代からT.C.メンデンホールの指導と影響の下に各地の重力測定を行い,次いで地磁気測定に従事した。ヨーロッパから帰国した1891年に起こった濃尾地震の際にはその影響による地磁気の変動の観測を行い,その調査中に根尾谷断層を発見した。この地震の直後に設立された震災予防調査会に参加,また測地学委員会委員として緯度変化の観測に取り組み,木村栄らを指導して98年水沢に緯度観測所を設立した。このほか,メートル法の普及,ローマ字の普及にも努め,また東京帝国大学航空研究所の創設に参加するなど,航空の分野でもその研究の推進に力をつくした。1944年文化勲章を受章。
執筆者:山崎 正勝 なお,愛橘の養子として同家を継いだ田中館秀三(1884-1951)は岩手県福岡町の旧家,下斗米(しもとまい)家の三男。自然地理学者で,火山学,湖沼学に関する研究を主とし,東北大学理学部地理学科の創設に尽力した。
執筆者:滝沢 由美子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
20世紀日本人名事典 「田中館愛橘」の解説
田中館 愛橘
タナカダテ アイキツ
明治〜昭和期の地球物理学者,ローマ字論者 東京帝大名誉教授。
- 生年
- 安政3年9月18日(1856年)
- 没年
- 昭和27(1952)年5月21日
- 出身地
- 岩手県二戸市
- 別名
- 別名=田中館 政師(タナカダテ マサノリ)
- 学歴〔年〕
- 東京帝大理科大学数学物理学星学科〔明治15年〕卒
- 学位〔年〕
- 理学博士
- 主な受賞名〔年〕
- 朝日文化賞〔昭和19年〕,文化勲章〔昭和19年〕,文化功労者〔昭和26年〕
- 経歴
- 明治16年東京帝大理科大学助教授となり、22〜23年英国のグラスゴー大学、ドイツのベルリン大学に留学。24年帰国後教授に就任し、大正6年まで務めた。この間明治24年の濃尾大地震には根尾谷断層を発見し、以後震災予防調査会の中心となって活躍、日本全国の地磁気測定に大きな業積を残した。日本の学術上、重力、地磁気、地震、測地、度量衝、航空の諸方面での創始者であり、また万国地球物理学会議など多くの国際会議にたびたび出席し、学術的外交官として活躍した。大正14年貴院議員、15年太平洋学術会議副会長。一方明治18年に「羅馬字用法意見」を刊行、ローマ字つづり方の理論を主張し、42年日本式ローマ字運動の団体を芳賀矢一らと結成した。昭和19年第1回文化勲章受章。随筆に「葛の根」がある。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
最新 地学事典 「田中館愛橘」の解説
たなかだてあいきつ
田中館愛橘
1856.9.18~1952.5.21 岩手県に生まれ,1882年東京大学理学部物理学科卒,翌年理学部助教授。89年グラスゴー大学に留学し,91年帰国して教授となり,1917年退職。初期の業績としては重力・地磁気測定があり,震災予防調査会,測地学委員会,航空研究所などでも貢献するところが多い。日本地球電気・磁気学会(現地球電磁気・地球惑星圏学会)は彼の業績にちなんで,47年以来田中館賞を設けている。参考文献:中村清二(1943) 田中館愛橘先生,中央公論社
執筆者:藤井 陽一郎
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「田中館愛橘」の意味・わかりやすい解説
田中館愛橘
たなかだてあいきつ
[没]1952.5.21. 東京
物理学者。東京帝国大学理学部物理学科を卒業 (1882) 。 1889年から2年間イギリスとドイツに留学。東京帝国大学教授として物理学を担当 (91~1917) 。 93~96年日本全国の地磁気測量を行い,震災予防調査会 (1892) ,緯度観測所 (99) ,航空研究所 (1921) などの設立などに貢献。熱心な日本式ローマ字論者でもあった (→日本式綴り方 ) 。 1944年文化勲章受章。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「田中館愛橘」の意味・わかりやすい解説
田中館愛橘【たなかだてあいきつ】
→関連項目二戸[市]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「田中館愛橘」の解説
田中館愛橘 たなかだて-あいきつ
安政3年9月18日生まれ。イギリス,ドイツ留学後,明治24年帝国大学教授。日本各地で重力・地磁気を測定し,32年岩手県水沢に緯度観測所を設立。航空分野での開拓的研究,メートル法や日本式ローマ字つづりの普及にもつくした。貴族院議員。昭和19年文化勲章。昭和27年5月21日死去。95歳。陸奥(むつ)二戸郡(岩手県)出身。東京大学卒。
山川 日本史小辞典 改訂新版 「田中館愛橘」の解説
田中館愛橘
たなかだてあいきつ
1856.9.18~1952.5.21
明治~昭和期の物理学者。陸奥国二戸郡生れ。東大卒。ヨーロッパに留学し,帰国後帝国大学教授。1891年(明治24)の濃尾地震の研究中に根尾(ねお)谷の大断層を発見。震災予防調査会の設立に努力し,全国の地磁気測定を行う。緯度観測所設立に尽力,測地学委員会委員として緯度変化の観測を進めた。万国度量衡会議常置委員。一方,日本式ローマ字の普及に努めた。文化勲章受章。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「田中館愛橘」の解説
田中館愛橘
たなかだてあいきつ
明治〜昭和期の物理学者
陸奥(岩手県)の生まれ。東大卒業後,イギリス・ドイツに留学。帰国後東大教授となる。全国の地磁気測定・緯度観測所設置に業績をあげ,1918年の航空研究所設立に尽力,航空学・気象学・メートル法の普及をはかった。日本式ローマ字論者としても有名,国際学界でも活躍した。1944年文化勲章受章。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「田中館愛橘」の解説
田中館 愛橘 (たなかだて あいきつ)
明治時代-昭和時代の物理学者。帝国大学教授
1952年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の田中館愛橘の言及
【藤井実】より
…1902年の東大運動会で,100m競走に10秒24の驚異的な記録を出した。このとき初めて田中館愛橘考案の電気計測が用いられ,寺田寅彦が助手を務めたが,現在ではどこかに計時の誤りがあったとみられている。さらに06年の運動会では棒高跳びに3m90cmを記録した。…
※「田中館愛橘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...