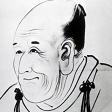精選版 日本国語大辞典 「竹田出雲」の意味・読み・例文・類語
たけだ‐いずも【竹田出雲】
改訂新版 世界大百科事典 「竹田出雲」の意味・わかりやすい解説
竹田出雲 (たけだいずも)
江戸中期の浄瑠璃作者,竹本座座本。出雲の名は大坂道頓堀からくり芝居興行師竹田近江の最初の受領名から出る。(1)初世(?-1747(延享4)) 元祖出雲と呼ばれる。本名不詳。号は千前,奚疑(けいぎ),千前軒奚疑,外記(2世)。1705年(宝永2)以後,竹本座の座本として座の経営や舞台演出に腕をふるい,《国性爺合戦(こくせんやかつせん)》の趣向を工夫し,23年(享保8)から近松の指導添削で浄瑠璃執筆を始め,以後単独作や合作に作者として活躍した。竹本義太夫の死(1714)後,近松を中心として義太夫の遺弟たちが力を合わせて興行に努めたが成績は振るわず,この不調を一気に回復したのが出雲の頓智発明による近松老功の一作《国性爺合戦》であったと《今昔操(いまむかしあやつり)年代記》はいう。日本の武力による大明国の再興という雄大な構想が出雲の発案であった。晩年の傑作《菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゆてならいかがみ)》では出雲みずから総指揮をとり,各段担当の作者に腕を競わせ,各段担当の太夫にその芸風を競わせるという行き方であった。彼は竹本座の見事な経営,舞台技巧の改良,それを活用した浄瑠璃の執筆によって人形浄瑠璃を近世化した。その結果,太夫の語り方の複雑化,人形機構の発達による3人遣いの出現など人形浄瑠璃を一変させ,歌舞伎にもまさる盛況を実現した。この文化史的意義は大きい。おもな単独作や合作は,《右大将鎌倉実記》(1724),《蘆屋道満大内鑑》(1734),《小栗判官車街道》(1738),《ひらかな盛衰記》(1739),《男作五雁金(おとこだていつつかりがね)》(1742),《児源氏道中軍記(ちごげんじどうちゆうぐんき)》(1744),《菅原伝授手習鑑》(1746)など。(2)2世(1691-1756・元禄4-宝暦6) 親方出雲と呼ばれる。元祖の子。本名清定。初世在世中は竹田小出雲と称した。号は千前軒,外記(3世)。大坂の人。初世出雲の没後2世出雲となり,浄瑠璃執筆とともに竹本座座本を兼ねた。初世のころから浄瑠璃の合作制は見られたが,2世出雲の時期になると,合作制が定着,発達し,その首位に立つ出雲は一作中の作者配分の如何によって浄瑠璃の優劣を生ずる困難な事情に直面した。さらに人形の発達や種類の増加により舞台演出は従前の比ではなく,こうした時期の作者ならびに座本として,優れた手腕を発揮した。作風は従来の時代物の5段組織を多段形式に改め,冒頭から多くの事件を展開させ,部分的描写では細かい写実的表現が見られ,後期浄瑠璃の先駆ともいえる形式をとっている。また趣向の面でも,一見不自然な技巧が重ねられるにもかかわらず,舞台構成上は優れた効果をあげていることは《忠臣蔵岡目評判》などが指摘するところである。歌舞伎の影響もあって舞台本位に急なあまり,文章上の矛盾もまた見られた。さらに人形遣いの発言力も増し,1748年(寛延1)《仮名手本忠臣蔵》初演のとき,吉田文三郎と竹本此太夫との衝突事件で座本の出雲が文三郎に加担したため,此太夫ほかの太夫が豊竹座に移り,以後,竹本西風の芸と豊竹東風の芸との乱れを生じたことは座経営上の失敗であった。おもな作品(小出雲時代を除く)は《傾城枕軍談》(1747),《義経千本桜》(1747),《仮名手本忠臣蔵》(1748),《粟島譜嫁入雛形(あわしまけいずよめいりひながた)》(1749),《双蝶々曲輪日記(ふたつちようちようくるわにつき)》(1749)など。(3)3世 生没年不詳。2世の子。本名は清宜。号は和泉掾,因幡掾,伊豆掾,竹田文吉。大坂の人。3世出雲の座本時代は竹本座が衰運をたどった時期で,座本としての最後。文吉の合作浄瑠璃には《関取千両幟》(1767),《傾城阿波の鳴門》(1768)など。
執筆者:横山 正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「竹田出雲」の意味・わかりやすい解説
竹田出雲
たけだいずも
浄瑠璃義太夫節(じょうるりぎだゆうぶし)の作者、興行者。
初世
(?―1747)別号千前軒(せんぜんけん)、外記(げき)。1705年(宝永2)初世竹本義太夫の跡を継いで竹本座の座本として経営に才腕を振るい、出語(でがた)り、出遣(でづか)いの創始、からくり応用、舞台技巧の改良などによって、人形浄瑠璃隆盛のもとをつくった。また、近松門左衛門の指導を受けて浄瑠璃を書き、『大内裏大友真鳥(だいだいりおおとものまとり)』『芦屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)』『三荘太夫五人嬢(さんしょうだゆうごにんむすめ)』などの単独作を11編、ほかに長谷川千四・文耕堂らとの合作12編を残した。没する直前に出た『操曲浪花蘆(そうきょくなにわのあし)』は名人極上上吉(ごくじょうじょうきち)の位付けをし、「ふつふつと智恵(ちえ)の吹出雲(ふきいずるくも)」との評語を与えている。
[山本二郎]
2世
(1691―1756)初世の子で、初め小出雲、初世没後に2世出雲、また千前軒、外記を襲名した。座本として手腕を振るい、親方出雲と称せられ操(あやつり)界を抑えたが、浄瑠璃作者としては、先輩格の並木千柳(なみきせんりゅう)・三好松洛(みよししょうらく)との合作で『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』『義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)』『仮名手本忠臣蔵』『双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)』などの名作を書き、浄瑠璃の最盛期を飾った。ただし立作者(たてさくしゃ)としての出雲は名目だけで、実際には千柳がおもに執筆したとの説もある。
[山本二郎]
3世
生没年未詳。2世の子で和泉掾(いずみのじょう)、竹田文吉を名のり、『関取千両幟(せきとりせんりょうのぼり)』『傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)』などに合作者として名を連ねている。彼の代になってから竹本座はしだいに衰退し、1767年(明和4)に退転、やがて3代にわたる出雲の竹本座経営も終わった。
[山本二郎]
百科事典マイペディア 「竹田出雲」の意味・わかりやすい解説
竹田出雲【たけだいずも】
→関連項目上方文学|葛の葉|信田妻|菅原伝授手習鑑|近松半二|並木宗輔|双蝶々曲輪日記
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「竹田出雲」の解説
竹田出雲
たけだいずも
大坂竹本座の座本・浄瑠璃作者。江戸中・後期に3世を数える。初世(?~1747)は初世竹田近江(おうみ)の子。俳号千前軒奚疑(せんぜんけんけいぎ)。1705年(宝永2)竹本座の座本となり,太夫(たゆう)竹本義太夫,作者近松門左衛門との協力体制を確立,竹本座の経営基盤を固める一方,近松のもとで浄瑠璃作者としての修業を積む。23年(享保8)の「大塔宮曦鎧(おおとうのみやあさひのよろい)」が松田和吉(文耕堂)との合作で第一作,翌年の「諸葛孔明鼎軍談(しょかつこうめいかなえぐんだん)」が単独作の第一作。46年(延享3)の「菅原伝授手習鑑(てならいかがみ)」が最終作。2世(1691~1756)は初世出雲の子。本名清定。通称親方出雲。はじめ竹田小出雲と名のり,1747年(延享4)初世出雲の死去で2世を襲名。興行師としても作者としても手腕を発揮,並木宗輔(そうすけ)・三好松洛(しょうらく)らとともに竹本座全盛期の諸作に名を連ねる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「竹田出雲」の意味・わかりやすい解説
竹田出雲(2世)
たけだいずも[にせい]
[没]宝暦6(1756).11.4. 大坂
江戸時代中期の浄瑠璃作者,大坂竹本座の座本。親方出雲と称される。名は清定。号は千前軒。1世竹田出雲の子。初め小出雲と称した。父のあとをうけ,竹本座の座本兼作者として活躍。元文2 (1737) 年の『太政入道兵庫岬』をはじめ,豊竹座の並木千柳 (宗輔) を作者に迎えてからの合作に著名なものが多い。小出雲時代の『夏祭浪花鑑』 (45,合作) ,『菅原伝授手習鑑』 (46,合作) などのほか,延享4 (47) 年,父の死去による2世出雲襲名後は『義経千本桜』 (47,合作) ,『仮名手本忠臣蔵』 (48,合作) などがある。
竹田出雲(1世)
たけだいずも[いっせい]
[没]延享4(1747).6.4. 大坂
江戸時代前期の浄瑠璃作者,大坂竹本座の座本。元祖出雲と称される。号は千前軒奚疑 (けいぎ) 。宝永2 (1705) 年竹本義太夫から経営権を引継いで竹本座の座本となり,近松門左衛門をあらためて座付作者に迎え,衣装,仕掛けなどに工夫を凝らすなど企画者,経営者として手腕をふるった。一方,作者としても近松の指導のもと,享保8 (23) 年文耕堂との合作『大塔宮曦鎧 (おおとうのみやあさひのよろい) 』を発表して以来,合作,単独作ですぐれた作を出した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「竹田出雲」の解説
竹田出雲(初代) たけだ-いずも
初代竹田近江(おうみ)の次男。宝永2年大坂竹本座の座本となる。初代・2代竹本義太夫,近松門左衛門の協力をえて座の経営や舞台の演出にあたり,人形浄瑠璃の全盛時代をきずく。「蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)」,「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)」(合作)などをかいた。延享4年6月4日死去。号は千前軒奚疑。
竹田出雲(2代) たけだ-いずも
元禄(げんろく)4年生まれ。初代竹田出雲の子。延享4年初代の没後大坂竹本座の座本となる。並木宗輔らと合作で「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」などの名作をのこした。宝暦6年11月4日死去。66歳。名は清定。初名は竹田小出雲。号は千前軒,外記。通称は親方出雲。
【格言など】女は嫉妬に大事を漏らす(「義経千本桜」)
竹田出雲(3代) たけだ-いずも
2代竹田出雲の子。大坂竹本座の座本となり,和泉掾(いずみのじょう),因幡(いなばの)掾,伊豆掾,文吉と改名をかさねる。明和4年(1767)竹本座が歌舞伎興行にかわり,安永2年名代を吉川屋惣兵衛にゆずった。作品に「姫小松子日(ねのひ)の遊」(合作)など。名は清宜。
旺文社日本史事典 三訂版 「竹田出雲」の解説
竹田出雲
たけだいずも
江戸中期の浄瑠璃作者
大坂の人。竹本座の座元。近松門左衛門に師事。『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』などが傑作。興行経営の才に長じ,座の繁栄と人形劇の最盛期を現出した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の竹田出雲の言及
【蘆屋道満大内鑑】より
…5段。竹田出雲作。1734年(享保19)10月大坂竹本座初演。…
【竹田座】より
…元禄から享保(1688‐1736)ごろが最盛期で,同じ道頓堀の他の人形芝居や歌舞伎芝居にも大きな影響を与えた。ことに竹本座では,初世近江の弟の竹田出雲を初世義太夫ののちの座本に迎え,竹田からくりのスペクタクル性を舞台にとり入れ,義太夫浄瑠璃の全盛時代を出現させた。【諏訪 春雄】。…
【近松門左衛門】より
…殺しや心中といった生臭い世俗の事件は当世的な歌舞伎によりふさわしい題材であったが,歌舞伎作者でもあった近松はそれを人形浄瑠璃に持ち込み,新しい世話悲劇へと発展させた。一方,《曾根崎心中》の興行的な成功によってそれまでの負債を一挙に返すことのできた義太夫は,それを機会に座本の位置を退き,替わって竹田出雲が竹本座の経営に当たることになるが,近松はその座付作者となり,竹本座再発足の旗揚げとして上演された《用明天王職人鑑》(1705)を書いた。この年のはじめ近松は京から大坂に移住しているが,座付作者として執筆に専念できるようになった近松は義太夫,出雲と協力して,これより本格的な作者活動を展開しはじめる。…
【人形浄瑠璃】より
…若太夫はこの暗い戯曲に派手な東風の節付けを巧みに施し,興行的にも成功を収めた。一方,竹本座では近松門下の文耕堂,初世竹田出雲(竹本座経営者兼作者)らが,2世義太夫の質実剛健な語り口にふさわしい,英雄的な男性主人公の活躍を力強く描いた(《ひらかな盛衰記》など)。45年(延享2)両座の太夫の世代交替を機に,並木宗輔は竹本座に移り,2世竹田出雲,三好松洛らと合作《菅原伝授手習鑑》《義経千本桜》《仮名手本忠臣蔵》など,時代物の最高傑作を次々に著し,文三郎の人気と相まって人形浄瑠璃は隆盛の極に達し,〈歌舞伎はなきが如し〉とまでいわれた。…
【文耕堂】より
…ほかに,三好松洛との合作として36年(元文1)5月の《敵討襤褸錦(かたきうちつづれのにしき)》,37年1月の《御所桜堀川夜討(ごしよざくらほりかわようち)》,38年1月の《行平磯馴松(ゆきひらそなれまつ)》がある。竹田出雲との合作には,38年8月《小栗判官車街道(おぐりはんがんくるまかいどう)》,39年4月の《ひらかな盛衰記》,40年7月の《将門冠合戦(まさかどかむりがつせん)》などがある。41年(寛保1)5月の《新薄雪物語(しんうすゆきものがたり)》を,三好松洛,小川半平,竹田小出雲と合作した後は,文耕堂の署名入りの作品は消える。…
【用明天王職人鑑】より
…山路の子を身ごもった玉世は継母に憎まれ,堕胎させられようとするが,仏力の奇瑞で聖徳太子が誕生,山彦一派の外道は滅びる。初世竹田出雲が竹本座の座本に迎えられた第1作で,からくり応用のスペクタクル性に特色がある。【諏訪 春雄】。…
【小野道風青柳硯】より
…5段。竹田出雲・吉田冠子・中邑閏助・近松半二・三好松洛の合作。1754年(宝暦4)10月大坂竹本座初演。…
【双蝶々曲輪日記】より
…1749年(寛延2)7月大坂竹本座初演。竹田出雲,三好松洛,並木千柳(並木宗輔)合作。《摂陽奇観》にある角力取の濡れ紙長五郎が,武士を殺害した罪で捕らわれた事件に拠っているらしい。…
※「竹田出雲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

 (初世)[?~1747]別号、
(初世)[?~1747]別号、 (2世)[1691~1756]初世の子。名は清定。別号、小出雲、のち千前軒・外記。竹本座座元として経営・演出に
(2世)[1691~1756]初世の子。名は清定。別号、小出雲、のち千前軒・外記。竹本座座元として経営・演出に