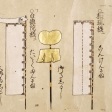精選版 日本国語大辞典 「幟」の意味・読み・例文・類語
のぼり【幟】
- 〘 名詞 〙 ( 「のぼり(上)」と同語源 )
- ① 旗の一種。細長い布帛の上部と横の一方に乳(ち)をつけ、それに横上(よこがみ)の棒と竿を通し、軍陣や寺社、また船首などに標識として用いる。幟旗(のぼりばた)。
- [初出の実例]「のぼり三十本、紺地に金の丸」(出典:伊達日記(1600頃か)下)
- ② 端午(たんご)の節供に立てる五月幟。こいのぼり。《 季語・夏 》
- [初出の実例]「幟(ノボリ)は紙をつぎて、素人絵を頼み」(出典:浮世草子・好色一代女(1686)六)
- ③ ( ②から転じて ) 男の子。
- [初出の実例]「お妾は幟を産て立られる」(出典:雑俳・柳多留‐六六(1814))
- ④ 近世、山城国紀伊郡(京都市南区)吉祥院の近くに住み、二条城外の清掃に従事した人々の称。罪人を道にさらすときに、その姓名、罪状をしるした幟を持って先行したところからいう呼び名。〔雍州府志(1684)〕
- ⑤ 江戸時代、仕置場または罪人引回しの際、立てたり、持ち歩いたりした、罪状を記した幟。紙幟。〔刑罪大秘録(1814か)(古事類苑・法律三四)〕
改訂新版 世界大百科事典 「幟」の意味・わかりやすい解説
幟 (のぼり)
旗の一種,昇旗(のぼりばた)の異称。本来は神を迎える招代(おぎしろ)として立てられたが,のちに一般に標識として用いられるようになった。幡(ばん)形式の流れ旗が風にひるがえりよじれ,保持が困難で,明示の用を欠くので,竿頭に折りかけの金具を差しこみ,これに幡の紐を結びつけ,幡の左側の縁に,一定の間をおいて,〈乳(ち)〉という布・革製の輪をとじつけ,竿を通し,布地を広げた形に保持した。後には上縁にも乳をつけるようになった。乳がはしごのように見え,旗が風に上下するために〈のぼり〉といったものか。普通二布を下部まで縫合する。軍陣には幟杭(くい)(枠,旗籬(はたかき))に固定し,数幟(かずのぼり)と呼び,同一のものを数多く,諸方より見えるよう,鍵形に立てて威勢を示す。幟を移動させるときは足軽・中間数人によって綱で引く。竿頭には笹,杉葉などを差したり,招きと呼ぶ小幡を立てることが多く,招代のなごりを示す。近世以降は,芝居,相撲などの興行の看板に,特殊な例には罪人引回しの際に罪状を記すのに用いられた。祭礼には社頭に,端午の節供には庭前に立てられ,神名・吉祥文言,勇壮な画像が描かれる。下端のおもりとして括り猿(くくりざる)を下げるのもある。小さいものには,四半,小旗の類があり,その変形に,共布で縁すべてを筒状に縫い合わせた袋乳としたものもある。
→旗
執筆者:加藤 秀幸
歌舞伎の幟
贔屓(ひいき)が俳優などに贈る。〈〇〇丈江〉などと大書して劇場前に立てる。1731年(享保16)5月,大坂竹本座に3度目の《国性爺》の祝儀として贔屓が立てたのに始まる。江戸では1794年(寛政6)仁左衛門初下りの都座が最初。この風は大坂が盛んで,操りでは延享期(1744-48)の竹本・豊竹両座の競争,歌舞伎では化政期(1804-30)の璃寛・芝翫の対抗に,数百本の幟が林立し,華やかに競ったのが語り草になっている。
執筆者:青木 繁
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「幟」の意味・わかりやすい解説
幟
のぼり
旗の一種。古式の旗である長旗の上辺に横上(よこがみ)をつけ、緒を設けて旗竿(はたざお)に結び付けたいわゆる流(ながれ)旗に対し、上辺と縦の一辺に乳(ち)をつけ、竿を通して二辺を固定した形式の旗をさす。流旗は、長くなびき竹木に絡まって不便なため案出された(『武用弁略』)というが、長旗の文様、意匠がより顕示されるためのくふうであり、集団戦の発達とともに、その軍事拠点、階層、所属などを明示する必要に応じた旗の一形式である。『南方紀伝』に、1456年(康正2)、畠山政長(はたけやままさなが)、義就(よしなり)の同族の戦争のおり、両者同じ旗で敵味方の識別がむずかしいので、政長が自軍の流旗に乳をつけ、竿を通して押し立てたのが幟の起源とあるが、確証はない。『三儀一統大双紙』に「旗の乳」の語があり、『日葡(にっぽ)辞書』(1598刊)にも「Nobori」と立項され、軍陣所用の旗とあるので、中世末期、戦国時代には普及していたのであろう。したがって『伊達(だて)日記』『水沢軍記』『大友興廃記』『安土(あづち)日記』『清正(せいしょう)記』などの軍記類、『長篠(ながしの)合戦図屏風(びょうぶ)』『関ヶ原合戦図屏風』『大坂夏の陣図屏風』などにみえる幟の描写は、後代の成立ではあるが、ほぼ戦国時代以降の実状を物語るものと考えられる。一般には、横手を竿の上端近くにつけて、長旗の上辺と、縦の左側に乳または縫含(ぬいぐるみ)(袋乳(ふくろち))をつけて、竿を通して張り立て、横手の上に招(まねき)と称する小形の長旗をつけるのが近世の定形で、乳付の長旗、縫含旗とも称される。大馬印(おおうまじるし)、旗指物(はたさしもの)の類には幟旗形式が多く、中世末期から近世初頭以降、流旗は衰退して軍陣から姿を消してしまう。したがって、幟旗が軍陣の旗の定式となり、意匠は簡明、闊達(かったつ)、長大なものとなり、1か所に同意匠のものを多数そろえて林立せしめ、自軍の勢力を誇示し、士気を高揚するとともに敵を威嚇した。武田信玄(しんげん)の孫子の旗5張、武田菱(びし)の紋の旗5張、また、徳川将軍家の総白(そうじろ)の旗20張、紋の旗7張などはその例であって、近世、軍陣の旗とは幟をさすのである。
[山岸素夫]
百科事典マイペディア 「幟」の意味・わかりやすい解説
幟【のぼり】
→関連項目はた(旗/幢/幡/旌)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「幟」の意味・わかりやすい解説
幟
のぼり
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の幟の言及
【端午】より
…また,この日の食品には各地で特色あるものが作られる。 男児の初節供を祝い,前もって母親の実家や親戚から幟(のぼり)や鯉幟,武者人形,冑などを贈り,当日はそれらの人々を招いたりして返礼の行われることは全国的である。幟は両親の家紋がつけられ勇ましい鍾馗像等が描かれたもので,庭先に立てられたが,最近では屋内へ飾るものが多くなった。…
※「幟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

 〈シ〉目じるしとする旗。「
〈シ〉目じるしとする旗。「 〈のぼり〉「
〈のぼり〉「