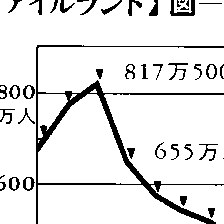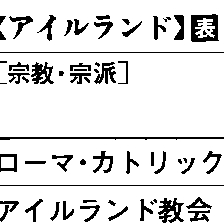日本大百科全書(ニッポニカ) 「アイルランド」の意味・わかりやすい解説
アイルランド(共和国)
あいるらんど
Ireland 英語
Éire アイルランド語
ヨーロッパの共和国。正称アイルランドIreland。イギリス諸島の西側に位置するアイルランド島にあり、憲法では全島を国土としているが、実際にはイギリス領に残された北アイルランドを除く地域である。面積は7万0273平方キロメートル、北海道よりやや小さい。人口391万7203(2002センサス)。88%はローマ・カトリック教徒である。首都はダブリン。主要都市は次の5市である(かっこ内は人口)。ダブリン(約49万6000)、コーク(約12万3000)、リムリック(約5万4000)、ゴールウェー(約6万6000)、ウォーターフォード(約4万5000)。全島は古くから4地方にほぼ均等に区分されている。東部のレンスター地方は12県で人口約210万6000、そのうちダブリン・カウンティ(ダブリン市を含む県)だけで約112万3000を数える。南部のマンスター地方は7県で約110万1000、そのうちコーク・カウンティ(コーク市を含む県)だけで約44万8000、西部コノート地方は5県約46万4000、そのうちゴールウェー・カウンティ(ゴールウェー市を含む県)が約20万9000となっている。北部のアルスター地方は歴史的には9県であったが、そのうち東北部の6県が1922年以来、北アイルランドとしてイギリス領にとどまっているため、西と南の3県のみが共和国に残っており、人口は約24万7000である。都市(とくにダブリン)への人口集中と西部の人口希薄が非常に顕著である。
[上野 格]
国語・国旗・国歌
伝統的言語であるアイルランド語(ゲール語)で生活している人々は西部のゲール語地域とよばれるところにわずかに残るのみで、人々の日常語はおもに英語であるが(ゲール語を解する人はかなり多い)、憲法では第一公用語はアイルランド語、第二公用語が英語と定められている。憲法をはじめ、すべての法律はこの2言語で書かれており、そのどちらも正文である。そのため、正式の国名も二つになっている。1937年の新憲法により、国名はアイルランド語でエールÉire、英語でアイルランドIrelandと定められた。エールという国名は通常アイルランド語の文中でのみ用い、アイルランドという国名は英語またはそれを翻訳した他の言語で用いることになっている。日本では国名をアイルランドとしている(例、アイルランド大使。アイルランド共和国大使ではない)。
国旗は、緑、白、オレンジの三色旗と憲法で定められている。形は横2、縦1の割合の長方形で、旗竿(はたざお)側から緑、白、オレンジに3等分する。緑はゲールおよびアングロ・ノルマンの人々(おもにカトリック)で古くからのアイルランドを表し、オレンジはプロテスタント入植者の子孫やオレンジ公ウィリアム(ウィリアム3世)の遺徳を偲(しの)ぶプロテスタントの人々、つまり新しいアイルランドを示し、白は両者の平和共存を表す。最初にこの旗が翻(ひるがえ)ったのは1848年の青年アイルランド運動の集会においてであり、フランスの三色旗と並んで掲げられた。独立運動でしだいに多く用いられるようになり、独立達成後、憲法で国旗と定められた。
国の紋章はハープで、中世からアイルランドの紋章として用いられてきた。現在は紺地に銀の弦を張った金色のハープが国の紋章として用いられており、また、すべての鋳貨の裏面にハープが彫り込まれている。モデルはマンスター王ブライアン・ボルーBrian Boru(941ころ―1014、在位975~1014)のハープとして知られる名品(14世紀に製作)である。ブライアン・ボルーはアイルランドに侵入したバイキングを1014年に撃退したことで有名。アメリカの元大統領レーガンは、この王の血を引くとされているが、ブライアン・ボルーの子孫といわれる人々は現在約10万人いるといわれる。国歌は独立運動の軍事組織アイルランド義勇軍の愛唱歌だった行進曲「兵士の歌」で、1926年に国歌と定められた。建国記念日に相当する国民休日はアイルランドをキリスト教化したとされる聖パトリックの命日3月17日で、この日はアイルランドばかりではなく、アメリカのニューヨーク、シカゴなどでの大パレードをはじめ、全世界に住むアイルランド人達が盛んな祝賀行事を行う。日本でも、東京原宿をはじめ各地でパレードが行われる。これは、全世界でアイルランド人の子孫と自称する人々が7000万人、アメリカにはそのうち4000万人もいるためでもあろう。
アイルランド自由国(イギリス連邦内の自治領)として事実上の独立を達成したのは1922年、その当時は統治権の及ぶ範囲が(北東の6県が裂かれたため)26県に分かれていたが、現在はティペレリー県が南北に分かれて27県となっている。1937年にデ・バレラ首相のもとで新憲法が制定され、大統領を国家元首とし、イギリス国王への忠誠宣誓条項を廃した。さらに、1916年の復活祭蜂起(ほうき)開始の日を記念して、1949年の復活祭月曜日からアイルランド共和国法を施行し、国の政体を共和国と規定し、イギリス連邦から完全に離脱した。ただし、国名は変更されず、エールまたはアイルランドのままである。なお、自然と歴史については「アイルランド(島)」の項目を参照。
[上野 格]
政治・外交
アイルランドに居住する18歳以上の国民が投票によって国政に参加する。それには(1)大統領(任期7年)選挙、(2)下院議員(任期5年)選挙、(3)憲法改正の国民投票、(4)ヨーロッパ議会議員(任期5年)選挙、(5)地方議会議員(任期5年)選挙の5種類がある。なお、イギリス国籍をもつ居住者は、一定の条件を満たせば、下院、ヨーロッパ議会および地方議会議員の選挙を行うことができ、EU(ヨーロッパ連合)加盟国の市民権をもつ居住者も、一定の条件を満たせば、ヨーロッパ議会と地方議会議員の選挙を行うことができる。また、すべての居住者は、その国籍がどこであろうとも、一定の条件を満たせば、地方議会議員の選挙を行うことができる。
大統領(被選挙権35歳以上)は国民の直接選挙(比例代表制)で選ばれ、任期7年、再選は1回のみ。行政権はなく、国家元首として議会および首相の申し立てに従い、首相および閣僚の任免、議会の招集および解散を行う。議会で承認されたすべての法案は大統領の署名により発効するが、大統領が必要と認めた場合は、国家評議会(首相、副首相、最高裁長官、高裁長官、下院議長、上院議長、司法長官等、および大統領の任命する7名以下の者からなる)への諮問を経た後、最高裁判所に違憲審査を請求できる。1997年の大統領はメアリ・ロビンソンMary Robinson(1944― )、同国で最初の女性大統領であったが、任期満了直前の同年9月に辞任し、国連人権高等弁務官に就任した。同年10月に行われた大統領選挙では、第8代大統領にクイーンズ大学(ベルファスト)教授メアリ・マッカリースMary McAleese(1951― )が当選した。北アイルランドのベルファスト生まれでカトリック教徒であり、ナショナリストである。この1997年の大統領選挙の際、被選挙権35歳以上というのは民主主義の原則に反するという若者からの批判が強く出された。マッカリースは2004年に再選されている。議会は二院制(議員の被選挙権は21歳以上)で、下院議員定数は2008年時点で166名。定員5名ないし3名の41選挙区から単記委譲式(当選に必要な最低得票数を超えた余剰票および当選不可能な最下位者の得票を選挙人が付した移譲順位にしたがって他候補に移譲する)比例代表制で選出される。定数配分は議員1名につき人口3万人以下2万人以上で、最長12年以内に選挙区の調整を行うことと定められているが、実際には5年ごとの国勢調査結果にしたがって調整が行われている。ゲリマンダー(特定の政党または候補者にとくに有利なように不自然な形で選挙区の境界線を定めること)の弊を避けるため、この調整は独立の委員会が行う。上院は議員定数60名。下院解散後90日以内に選挙が行われる。議員のうち11名は首相の指名、43名は、文化教育、農業、労働、商工業、官公庁の5分野から選出され、残る6名はアイルランド国立大学とダブリン大学から各3名ずつ選出される。これは職能代表の会議とするためであるが、投票権をもつのが、新下院議員、解散時の上院議員、各県の地方議会議員(合計約1000名)であり、往々にして落選した下院議員立候補者などが浮上する。大学の有権者はその大学で学位を得た卒業生で、現在は国立大学約7万名、ダブリン大学約2万名。この不均衡は、ダブリン大学の歴史の長さ(1592年創立)、さらにこの大学の出身者がかつてはほとんどプロテスタントであったことからくる少数派宗派への配慮、選出された上院議員の質の高さにより許容されているという。ロビンソン前大統領もかつては同大学で教鞭(きょうべん)をとり、上院議員に選出されていた。なお、この選挙も下院と同じ比例代表制である。
おもな政党には共和党(フィアナ・フォイル)、統一アイルランド党(フィネ・ゲール)、労働党、進歩民主党(1985年に共和党から分離独立)、緑の党などがある。共和党は1926年にデ・バレラが創設した共和主義中道右派の政党で、つねに第一党。統一アイルランド党は1933年創設の中道左派といわれる万年第二党。この両党の起源は、北アイルランドの分離を認めて自由国を発足させるか否かをめぐる分裂抗争にあり、賛成派が統一アイルランド党、反対派が共和党の祖先といえる。労働党は1912年にコノリーJames Connolly(1868―1916)、ラーキンJames Larkin(1874―1947)の指導で創設された。近年は1党で安定政権をつくるのが困難になり、1997年の選挙では、解散前の政権が統一アイルランド党、労働党、民主左翼党の三党連立政権(虹の連立)であったのに対して、新政権は共和党と進歩民主党の連立政権になった。なお、この選挙では、IRA暫定派の合法政治組織シン・フェイン党がはじめて1議席を獲得した。なお1997年のイギリス庶民院(下院)選挙では、北アイルランドでシン・フェイン党から2名当選した。ただしこの2名は、女王への忠誠宣誓を拒否して、議席にはついていない。
2002年、任期満了に伴い、総選挙が実施され、共和党が第一党を獲得、シン・フェイン党も5議席を得た。2007年の総選挙では、過半数に達しなかったが、共和党が第一党を維持、緑の党、進歩民主党と連立を組んでいる。1997年以来、三次にわたって内閣を組織したアハーン首相は2008年に辞任、後任にカウエンBrian Cowen(1960― )副首相が選出された。
地方自治は27県会、5自治都市会、6市会、49準市会、30町行政委員会によって行われている。いずれも比例代表制により議員が選出される。司法制度は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所および巡回裁判所よりなる。
国際諸機関との関係をみると、まず、1955年に国連加盟、1973年にEC(ヨーロッパ共同体)加盟、1979年にはEMS(ヨーロッパ通貨制度)に加盟して150年に及ぶポンド・スターリング(イギリス・ポンド)との額面同額の関係を断った。1992年6月にはマーストリヒト条約に国民投票で賛成し、1993年11月、EU(ヨーロッパ連合)発足時からメンバー国になった。ヨーロッパ議会へは比例代表制で選出した15名の議員を送っている。なお、北アイルランドからも3名が選出されている。アイルランドはEU重視の政策をとっているが、2008年6月に行われたEUの基本条約となるリスボン条約批准についての国民投票では、その批准が否定された。第二次世界大戦では中立政策を堅持し、小規模な常備軍はあるがNATO(ナトー)(北大西洋条約機構)などの軍事同盟にはいっさい加盟していない。しかし、国連平和維持活動(PKO)には参加し、中東、アフリカをはじめ、各地に出動している。世界各地の難民救済活動には積極的に参加しており、ボランティアの数は非常に多い。そうした積極的活動を行う原因には、150年前に経験した悲惨な大飢饉(ききん)の経験が培った互助の精神があるといわれ、また、長い伝統をもつキリスト教の伝道活動に由来するものともいわれる。
[上野 格]
経済・産業
「あいるらんどのやうな田舎へ行かう」という詩を、昔日本の詩人が歌った。たしかに、アイルランドには素朴な人々が住む貧しいけれど緑豊かな農業の国というイメージがある。1997年にはウシの頭数は710万頭と人口のほぼ2倍に達し、そのほかヒツジ300万頭、ブタ100万頭という酪農の国である。産業別就業人口をみても、農林業12%、鉱工業28%、サービス業60%と農業の比率が他国より格段に高い。
しかし、1997年5月17日号で『エコノミスト』(ロンドン)誌は、ヨーロッパの輝く光、と題してアイルランド経済の近年の躍進ぶりを特集した。「10年前にはアイルランド経済はヨーロッパでもっとも貧しく、そのまま続くと思われていた。今日それはこの地域の星である。何が起こったのか?」。こう問いかけた後、『エコノミスト』誌は一つのグラフを示す。それは1人当りGDP(国内総生産)の10年間の変化である。当時のEU15か国の平均を100として、1986年にはアイルランドは65、ギリシア、ポルトガルに次いで貧しかった。それが1996年にはほぼ97、イギリスをも抜いたのである。この躍進する姿を『エコノミスト』はエメラルド・タイガーとよんだ。1994年からの実質成長率は平均8%とEUの平均2.3%をはるかに上回り、他方、インフレ率は2%台と安定している。
この変化をもたらしたものは、1960年代以降一貫して行った工業化政策、そのための国内基盤整備、各種公団・公社による産業の指導育成、そして、海外企業の積極的な誘致政策であった。1997年時点で、アメリカからの500社を筆頭に、外資系企業は1000社を超え、エレクトロニクス、エンジニアリングを中心に、アイルランドの製造部門の総生産高の55%、雇用の44%、輸出の70%が、外資系企業に支えられている。なかでもエレクトロニクス関連産業の進出は著しく、たとえばアメリカのヨーロッパにおける関連投資の50%以上が、アイルランドで行われ、ヨーロッパで販売されるパソコンの30%はアイルランドで生産されている。医薬品、医療機器などの産業も盛んで、世界のトップ企業がアイルランドに進出しており、日本からもアステラス製薬、武田薬品工業などが進出している。こうした成功の一つの鍵(かぎ)は徹底した優遇措置であって、たとえば製造業の法人税は2010年まで10%に据え置き、資本支出(土地、建物、機械設備)、工場賃貸料、研究開発費等への補助金は返済不要とするなどである。こうして、GNP(国民総生産)は1996年約6兆1000億円、輸出は約5兆2000億円。1995年の輸出の主要相手国はイギリス26%(1970年65%)、その他のEU加盟国47%(同12%)と大きく変化し、輸出内訳も1995年には薬品、化学製品17%(1980年8%)、農産物、食品19%(同36%)、エレクトロニクス28%(同14%)、ソフトウェア6%(同0%)と様相を一変させた。
このような成長と変化を支える他の一つの鍵は、29歳以下の人口が50%弱という若い労働力の存在と、高い進学率に示される労働力の質の高さであろう。しかし、このような外国企業への依存は、アイルランドのように規模の小さな経済ではGDPとGNPの間に大きな差異を生じさせる。外国企業が本国に送る収益が全体のなかに占める割合が大きくなるのである。そのため、アイルランドではGNPはGDPの90%ないし88%と推計されている。アイルランド人の手元に残る分が10%以上削減されるのである。これが、依然としてアイルランド人の生活水準が低い理由であり、かれらが電話、自動車、洗濯機など豊かさを示す資産をイギリス人より少ししかもてぬ理由だ、とイギリスの『エコノミスト』誌は解説した。この皮肉に応えて、アイルランドで発行されている1997年8月1日の『アイリッシュ・タイムズ』は新しく発表された家計調査報告を解説する記事のなかで、1987年と1995年で家計支出は40%増加し、生活水準は上昇し、「1987年には電話は2軒に1台であったが今は4軒に3台、電気掃除機、皿洗い機、ビデオ、パソコンをもつ家も増えた」と記している。相手がイギリスだと、経済の解説にも火花が散るようである。
こうして、1986年にはGNPの10%を超えていた予算の赤字が、近年は3%以下に落ち着いている。国債残高も1987年にはGDPの112%もあったものが、1994年には90%まで下がり、以来急速に減少している。国際収支も大幅な黒字に転じた。
1990年代には高い経済成長を示していたが、2001年後半に至ると、その成長率が鈍化した。インフレ、賃金の高騰、ユーロ高などにより国際競争力が低下したのに加えて、2008年の世界的金融不安の影響で、さらに景気が後退している。
[上野 格]
教育
教育制度は6歳~12歳までの小学校(約3000校)、13歳~17歳または18歳までの中等学校(788校)と実業学校(248校)、41の大学レベルの学校(第3水準とよばれる)からなっている。義務教育期間は6歳~15歳まで。教員1人当り生徒数は小学校で24名、中等学校18名、第3水準で19名。中等学校で大学入学資格を得た生徒の約50%が第3水準に進学しており(1993~1994)、近年進学熱が急増している。授業料は小学校から大学(学部)まですべて無料。初等・中等教育を受け持つ学校の教員の給与は、学校施設が国の出資か、宗教団体その他民間の出資かを問わず、すべて国庫負担。私立学校にも国が補助金を支出している。第3水準では、総合大学が4校。もっとも歴史の古いダブリン大学はトリニティ・カレッジ1校だけをもつが、全学問分野を網羅しており、国立アイルランド大学はダブリン、コーク、ゴールウェー、メイヌースの4カレッジをもつ。1989年にリムリック大学とダブリン市立大学が独立の大学として発足した。このほか、法学院、工科大学、医科大学、芸術学院などがある。
医療については、生計費調査に従い、全人口の約3分の1がすべての公的医療サービスを無料で受けられ、他の約3分の2の人々も低額で受診できる。このほか各種社会保障制度が実施されている。
[上野 格]
文化
1982年に、アイルランドではショパンに大きな影響を与えたノクターンの作曲家、ピアニストのジョン・フィールドJohn Field(1782―1837)生誕200年と『ユリシーズ』の作者ジェームズ・ジョイスの生誕100年が祝われた。アイルランドは詩人、小説家を多く生むことで知られている。古くは『ガリバー旅行記』などで知られるジョナサン・スウィフト、オスカー・ワイルド、ジョージ・バーナード・ショーなどもダブリン生まれである。また、詩人、劇作家のウィリアム・バトラー・イェーツ、サミュエル・ベケット、さらに1995年には詩人シェイマス・ヒーニーがノーベル文学賞を受けている。このほか劇作家グレゴリー夫人Lady Isabella Augusta Gregory(1852―1932)、ジョン・ミリントン・シング、ショーン・オケーシーなどの名前も、かれらの作品を上演したダブリンのアビー座とともにアイルランドの誇りとなっている。ほかにワイルドの学友であり、『吸血鬼ドラキュラ』(1897)の作者でダブリン生まれの作家ブラム・ストーカーがおり、1997年には生誕150年と出版100年の記念パーティが東京でも行われた。
最近では音楽の分野でもアイルランドは世界の注目を集めている。ビートルズのメンバーがアイルランド系であることはよく知られているが、歌手のエンヤEnya(1961― )、メアリ・ブラックMary Black(1955― )、ロックのU2、伝統音楽のチーフタンズ、黄金のフルート奏者といわれるジェームス・ゴールウェイJames Galway(1939― )なども、世界的名声を博しており、日本での演奏もかなり聴衆をあつめている。近年アイリッシュ・ダンスをショー化したリバー・ダンスがアメリカやアイルランドで盛んに公演され、人気を呼んでいる。
スポーツの分野では、かつてはアメリカのボクシング・チャンピオンにはアイルランド系が目だった。オリンピックでは1996年のアトランタ・オリンピックに出場した水泳のM・スミスMichelle Smith(1969― )が有名である。伝統的なスポーツには、ホッケーによく似たハーリング、ゲーリック・フットボールなどがあり、毎年夏に全国大会決勝戦がダブリンで行われる。このほか競馬、ドッグレースなども盛んである。
[上野 格]
日本との関係
日本との貿易は、かつてはアイルランドの甚だしい入超であったが、急速な経済成長と外国企業誘致政策の成功により、1990年代に取引高が急成長し、両国間の輸出入額が、とくに日本への輸出の激増により、ほぼ均衡したまま倍増するに至った。1991年から1996年までに、日本からの輸入はコンピュータ、エレクトロニクス関連、化学製品、自動車などを中心に1200億円から2080億円へと75%以上の伸びを示し、日本への輸出はコンピュータ、有機化学製品、エレクトロニクス関連、医薬品などを中心に1110億円から2290億円へと2倍以上の伸びを示している。食品および酒類の日本への輸出は全体のわずか5~6%を占めるにすぎない。
日本企業のアイルランド進出は一時かなり盛んであったが、日本経済の低迷などにより2000年以降撤退の動きがあり、2003年時点で日系企業は38社、医薬品、金融、コンピュータ関連等がある。
1869年(明治2)に出版され、沼津兵学校で使われた日本最初の英語の経済学教科書は、19世紀中葉にアイルランドの国民学校(小学校)で教えられていた政治経済学という教科のテキストであった。原著者はダブリン大司教(元オックスフォード大学経済学教授)のホエイトリーRichard Whately(1787―1863)である。長く、彼の著書そのもののリプリントと思われていたが、編別構成その他に原著とかなり違うところがあり、その理由がわからずにいたものである。明治20年代の大ベストセラーであった東海散士(とうかいさんし)『佳人之奇遇(かじんのきぐう)』には、女主人公の一人としてアイルランドの若い女性が登場し、イギリスに支配されているアイルランドの惨状を克明に語る。大正期にはアイルランド文学が多く翻訳された。文学者ばかりではなく、日本の保護貿易政策、議会開設、朝鮮支配、土地制度改革など明治大正期の政治社会問題を論ずる学者、官僚、言論人たちはしばしばアイルランド問題に論及していた。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が父の郷里ダブリンで幼少のころから育てられたことは、いまではよく知られており、1995年(平成7)、訪日したロビンソン大統領も八雲ゆかりの地、松江を訪れた。1997年8月からダブリンの作家博物館に八雲の写真が飾られて、アイルランド作家の仲間入りをした。日本の国際電信網の発展に非常な貢献をしたストーンWilliam Henry Stone(1837―1917)もアイルランド出身であった。イェーツは日本の能の技法を取り入れた劇『鷹(たか)の井戸』をつくっており、その初演には伊藤道郎(いとうみちお)が出演している。この劇は後に日本の新作能になっている。近年、日本から英語研修その他でアイルランドを訪れる人が多くなり、また、東京や大阪にはアイリッシュ・パブが多く開店し人気を集めている。
なお、2005年5月、天皇・皇后両陛下がアイルランドを訪問している。また、2007年は日本とアイルランドの外交関係樹立の50周年にあたり、各種記念行事が行われた。
[上野 格]
『J・C・ベケット著、藤森一明・高橋裕之訳『アイルランド史』(1972・八潮出版社)』▽『堀越智著『アイルランド民族運動の歴史』(1979・三省堂)』▽『松尾太郎著『アイルランド問題の史的構造』(1980・論創社)』▽『T・W・ムーディ、F・X・マーチン編著、堀越智監訳『アイルランドの風土と歴史』(1982・論創社)』▽『松尾太郎著『アイルランドと日本』(1987・論創社)』▽『上野格著『イギリス史におけるアイルランド』(青山吉信・今井宏編『概説イギリス史』新版・所収・1991・有斐閣)』▽『盛節子著『アイルランドの宗教と文化』(1991・日本基督教団出版局)』▽『上野格著『アイルランド』(『イギリス現代史』所収・1992・山川出版社)』▽『堀越智著『北アイルランド紛争の歴史』(1996・論創社)』▽『波多野裕造著『物語アイルランドの歴史』(中公新書)』
アイルランド(島)
あいるらんど
Ireland
ヨーロッパ大陸北西の大西洋縁辺部にある大島。イギリス諸島の西側を占め、アイリッシュ海を隔ててグレート・ブリテン島に対する。北緯51度30分~55度30分、西経5度30分~10度30分に位置し、ほぼ菱形(ひしがた)の扁平(へんぺい)な島。北端のマリン・ヘッド(岬)から南端のミズン・ヘッドまで486キロメートル、東西275キロメートル。面積8万4421平方キロメートルで、北海道(本島7万8073平方キロメートル)よりやや大きい。グレート・ブリテン島との最短距離は、ノース海峡の部分で22キロメートル。政治的には、アイルランド共和国と、イギリス領の北アイルランドとに分かれている。人口はアイルランド共和国391万7203(2002国勢調査)、北アイルランド168万5267(2001)。
[上野 格]
自然
地形
中央部に平野が広がり、ヨーロッパから延びる二つの山系が相接して周辺部の山地を形成している。一つは古いカレドニア山系で、スカンジナビア、スコットランドにつながり、アイルランドでは北部から北西部の海岸地帯を構成している。花崗(かこう)岩と堆積(たいせき)岩の山地で、エリガル山(752メートル)、ネフィン・ベッグ、トウェルブ・ベンズなどの、低いが美しい山々と、不毛なカルスト台地、侵食による河川、湖、リアス海岸、フィヨルドがみられる。南東部海岸地帯のウィックロー山地もこの山系に属し、削剥(さくはく)による花崗岩の露出と、U字谷、カール(圏谷)などが存在する。南西部には、中央ヨーロッパからブルターニュ、南西イングランドを通ってふたたび現れる新しい山系(アルモリカン)に属する砂岩の山地がある。主峰キャラントゥール山(1041メートル)は、全島で1000メートルを超す唯一の山である。また、北部には玄武岩質の丘陵がある。これはスコットランド西部から、イギリス諸島北部の大西洋上にあるフェレルネ諸島(英語名フェロー諸島、デンマーク領)へと延びる第三紀始新世の火山活動によるものである。
この島は少なくとも二度、氷冠に覆われた。それが消滅したのは1万2000年前ごろであり、氷食と堆積が地形をつくりあげた。中央部の大半は、石灰岩床が氷河堆積物に覆われている。西海岸のクルー湾から東海岸まで、アルスター地方の境に沿って広く帯状に連なる小丘陵(ドラムリン)、その南の砂礫(されき)丘(ケーム)と堤防状のエスカーなどがそれである。
河川も数多く、シャノン川(370キロメートル)をはじめ、バン川、ボーイン川などいずれも緩やかに流れている。イギリス諸島中最大の湖ネー湖(396平方キロメートル)は、ヨーロッパ有数のウナギの産地である。このほか、コリブ、マスク、リー、デルクなど湖沼が数多い。キラーニー地方は湖の美しさで知られている。湿原も多く、泥炭地(ピート・ボグpeat bog)が広く分布している。
[上野 格]
気候
メキシコ湾流の影響で緯度のわりには気温が高く、1月の平均気温は南部で7℃、北部山地でも4℃、7月は南部15.5℃、北部でも14.5℃である。風向は偏西風が年間7割を超え、とくに風の強い西海岸では樹木の生育も妨げられるほどだが、これが山地で年間1250~2000ミリメートル、平野部で750ミリメートルの雨を、年中ほぼ平均してもたらしている。天候は非常に変わりやすく、1日のうちに晴雨交代を繰り返すことも珍しくないが、これが、島を緑一色に染め上げている。雪はあまり降らず、西部では霜もまれで冬期も牧草が成育する。
[上野 格]
動植物
海面上昇によりアイルランド島がグレート・ブリテン島から離れたのは8000年前ごろで、これがかなり急速であったため、氷河期後は動植物があまり移入せず、アイルランドには土着の動植物の種類が比較的少ない。かつてはカシ、カバなど広葉樹の原生林が広く存在したが、数百年前にほとんど消滅し、現在は針葉樹を主にした植林で森を再生させる試みが続けられている。哺乳(ほにゅう)動物には、アザラシなどのほか、テン、アイルランドノウサギ、アカシカなど27種が認められるが、モグラはいない。野鳥はスズメ目(燕雀(えんじゃく)類)を主に380種が観察されており、そのうち135種が島内で繁殖している。爬虫(はちゅう)類は小トカゲ1種のみで、ヘビはいない。
[上野 格]
歴史
アイルランドの有史時代は鉄器をもって来島したケルト人とともに始まる。多くの巨石墳墓や貝塚の存在はそれ以前の新石器人の存在を示している。ケルト語と鉄器文化をもって来島し、部族共同体を形成したケルト人が現在のアイルランド人の先祖、先住(ネイティブ)アイルランド人である。
[堀越 智]
ケルト人来島からイギリス支配の確立まで――古代・中世
紀元前6世紀ごろより来島したケルト人は、やがて紀元後2世紀ごろにはたくさんの小王国を形成し、3世紀には権力は弱いが大王制も始まって、一つの国として緩やかに発展していった。ダブリン近郊のタラの丘で開かれた祭典は、大王の前に全自由民が集まって物語や詩の朗読を聞き、スポーツを楽しんだ民族の祭典であった。タラTaraの名は民族の故郷としていまもアイルランド人の心に深く刻まれている。
キリスト教が伝わったのは4世紀であった。聖パトリック(432年来島)などの優れた指導者によってアイルランド独特のキリスト教文化が発展し、「聖者と学徒の島」として、ヨーロッパ中に知られた。円環をもった石の十字架や「ケルズの書」など聖書の写本は、この時代の教会美術を美しく現在に伝えている。
8世紀末から始まったノルマン人の侵入と、続くイギリス王の侵略は、アイルランドの歴史を一変した。アイルランド教会は熱心なカトリックとなり、イギリス王によって開設されたアイルランド議会は、ノルマン・アイリッシュやアングロ・アイリッシュの権勢を表した。ケルトの諸部族は何度も反乱を繰り返したが、それも17世紀なかばのアルスターの反乱(1641年暴動、翌年カトリック連盟結成、アイルランド独立を宣言)を最後に終わった。これはイギリス革命のときであった。革命によって成立したイギリスの新しい政権から、アイルランドはいっそう強力な支配を受けることになった。O・クロムウェルのドロヘダDroghedaの虐殺(1649)と土地没収や、ウィリアム3世の植民政策に始まり、一連のカトリック刑罰法をもって市民としての諸権利をカトリック教徒から奪い、プロテスタント支配という形で、イギリスの植民地支配は確立した。
[堀越 智]
イギリスへの抵抗から自由国へ――近代
アイルランド議会の権利を認めず、経済的自由を制限したイギリスの支配に対しては、先住アイルランド人だけでなく、アングロ・アイリッシュも、ノルマン・アイリッシュも、スコッチ・アイリッシュも一体となって抵抗した。『ガリバー旅行記』の著者J・スウィフトたち知識人がまず自治を主張し始め、アメリカ独立革命の開始とともにアイルランド議会の内外で強力な運動が展開された。グラタン議会とよばれる自治議会(1782~1801)が実現し、後のナショナリストに具体的な目標を残したのはこのときである。
1801年のイギリスによる併合は、アイルランド史上重要な意味をもっている。第一は、これによって自らの権益を守る手段を失ったアイルランドがイギリスの収奪のままにさらされたことであり、第二は、世界一の先進国の一部としての利益を得たことである。一方では競争に敗れて工業が衰退し、不在地主の厳しい取り立てにたくさんの農民が国を出なければならなかったが、他方、教育の普及や鉄道の建設など、近代化も早かったのである。しかし教育の普及がアイルランド語人口を減少させ、産業革命が北アイルランドと他の地方の格差を広げるなどのゆがみは、自治議会を失ったことによるところが多かった。
カトリック教徒解放法や国教会制度の廃止によって宗教問題が解決し、アイルランド土地法によって土地問題が基本的に解決すると、自治、独立の問題が焦点となった。しかし第一次、第二次自治法案に際してみられたように、反対はアイルランド内部からもおこった。北アイルランド・ユニオニスト(イギリスとの連合を支持した人々)の強い反対は、ついにアルスター地方9県のなかの6県を「北アイルランド」として分離し、連合王国に残すことになった。1916年のイースター蜂起(ほうき)は民族感情をかき立て、1919年からの独立戦争によって「アイルランド自由国」を実現することになるのだが、1920年の「アイルランド統治法」によって、北アイルランドの分離という現在の紛争の原因となる事実をつくってしまったのである。
[堀越 智]
自由国から共和国へ――現代
1922年に成立したアイルランド自由国は、国土の一部北アイルランドを連合王国に残し、領海の警備、港湾の管理、軍事力など一部制限されてはいたが、独立国に近い地位を得て、1923年に国際連盟に加盟した。独立運動を推進してきたシン・フェイン党は、自由国を支持するゲール党と、条約に反対する共和党に分裂した。その後、デ・バレラたちが共和党から離れて1926年にフィアナ・フォイル(運命の戦士、日本では共和党と訳している)を結成し、自由国議会に参加した。ゲール党政府は親英保守政策でしだいに国民の支持を失い、1932年の総選挙ではデ・バレラが勝利して労働党との連立政府を組織した。ゲール党も1933年、統一アイルランド党(フィネ・ゲール、ゲール同盟)と衣替え、現在までこの二大保守党が、時に応じて労働党と連立を組んで政権を担当している。
デ・バレラ政府は反英民族主義政策を打ち出し、まず土地年賦金の不払いをイギリスに通告した。これは農民が一連の土地法で取得した農地の代金を、イギリス政府に年賦で支払っていたものを、自由国成立後は自由国を通して支払っていたものであるが、1930年代の不況でアイルランド農民の重い負担となっていた。これに対してイギリス政府が関税を強化し、自由国政府も高関税で応じ1938年までこの経済戦争が続いた。経済戦争を終結した協定で、イギリスは在アイルランド駐留軍の完全撤退とイギリスが管理する軍港の返還も約束した。その前年1937年、デ・バレラはアイルランドを独立した民主的主権国家と規定した新憲法を国民議会で可決し、国民投票でも承認されて、事実上共和国となり、国名を「エール」(英語名アイルランド)とした。領域はアイルランド島全土とし、言語はゲール語を第一国語、英語を第二国語とした。緑(アイルランドそのもの、カトリックを表す)、白(友愛、平和、協調)、オレンジ(オレンジ公ウイリアム3世にちなんでプロテスタントを表す)の三色旗(1848年にフランスの三色旗にならって青年アイルランド党がつくったもの)を制定した。国歌はイースター蜂起のときに歌われた「兵士の歌」が自由国時代に決まっていた。初代大統領はゲール語復興運動の中心的活動家ダグラス・ハイドであった。
デ・バレラのナショナリズムは第二次世界大戦にあたっての中立政策となった。といっても連合国側に事実上加担した中立であったが、イギリスのチャーチル首相からは激しく非難された。この中立政策は大戦後も継続され、NATO(ナトー)(北大西洋条約機構)不参加となって示されている。
戦後まもなく1948年にイギリス連邦から離脱、翌1949年にアイルランド共和国となり、国連には1955年に加盟した。完全独立を果たしたものの植民地時代からの経済的困難が続き、海外移民も19世紀と変わらないほどであった。また首都ダブリンへの人口集中も激しく農村の過疎化が進んだ。しかし1958年から始まった外資導入による工業化政策は政府の積極的な優遇措置と低賃金もあって、英米中心に多くの企業誘致に成功し、1960年代に入ると急速な成長をみせた。とくに1973年にEC(ヨーロッパ共同体)に加盟したことがその勢いを加速した。日本からも旭化成、富士通、ブラザー工業、ノリタケ、日本電機(NEC)、アサヒビールなどが進出している。1980年代に入るとアップル・コンピュータ(現アップル)、マイクロソフト、インテル社などアメリカのコンピュータ企業の進出がアイルランドの経済成長をさらに促し、1990年代にはアイルランド・ポンドの価値がイギリス・ポンドを上回るようになった。こうした経済成長に伴って、ナショナリズムとカトリシズムの強かった伝統的なアイルランド社会の変革を求める動きも活発になってきた。しかし中絶問題、離婚問題などカトリックの基本理念に触れる問題は国民投票でも否決されるなど、民衆に対するカトリック教会の影響力は依然として強いが、離婚については1995年11月、国民投票で僅差(きんさ)ながら憲法改正派が勝利することになった。さらに避妊合法化運動など女性の社会的地位の改善を訴え続けたメアリ・ロビンソンが、女性団体、人権擁護団体などの支援で下馬評を覆して1990年に大統領に当選し、続いて1997年、メアリ・マッカリースMary McAleese(1951― )が第8代大統領に当選した。2代続いての女性大統領で、しかもマッカリースは北アイルランド出身であった。アイルランドはこのように大きな変革を遂げようとしている。
[堀越 智]
『堀越智著『アイルランド民族運動の歴史』(1979・三省堂)』▽『T・W・ムーディ、F・X・マーチン編著、堀越智監訳『アイルランドの風土と歴史』(1982・論創社)』▽『堀越智著『アイルランドイースター蜂起1916』『アイルランド独立戦争 1919―1921』(1985・論創社)』▽『P・B・エリス著、堀越智・岩見寿子共訳『アイルランド史――民族と階級』上下(1991・論創社)』▽『小野修著『アイルランド紛争――民族対立の血の精神』(1991・明石書店)』▽『鈴木良平著『IRA』(1991・彩流社)』▽『上野格著「アイルランド」(松浦高嶺著『イギリス現代史』所収1992・山川出版社)』▽『松尾太郎著『アイルランド民族のロマンと反逆』(1994・論創社)』▽『堀越智著『北アイルランド紛争の歴史』(1996・論創社)』▽『S・マコール著、小野修編、大渕敦子・山奥景子訳『アイルランド史入門』(1996・明石書店)』▽『波多野裕造著『物語アイルランドの歴史』(中公新書)』▽『R・フレシュ著、山口俊章・山口俊洋共訳『アイルランド』(白水社文庫クセジュ)』▽『オフェイロン著、橋本槙矩訳『アイルランド――歴史と風土』(岩波文庫)』