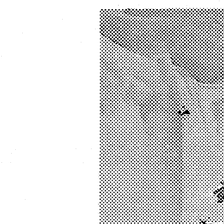精選版 日本国語大辞典 「虎渓三笑」の意味・読み・例文・類語
こけい‐さんしょう‥サンセウ【虎渓三笑】
四字熟語を知る辞典 「虎渓三笑」の解説
虎渓三笑
[使用例] 妙心寺にも、狩野山楽が描いた立派な虎渓三笑があり[秦恒平*廬山|1971]
出典 四字熟語を知る辞典四字熟語を知る辞典について 情報
百科事典マイペディア 「虎渓三笑」の意味・わかりやすい解説
虎渓三笑【こけいさんしょう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「虎渓三笑」の意味・わかりやすい解説
虎渓三笑
こけいさんしょう
日本・中国画の画題で、中国の故事を扱ったもの。中国六朝(りくちょう)の東晋(とうしん)に、景勝地また仏教の霊場として名高い江西省廬山(ろざん)に慧遠(えおん)(334―416)という学僧がおり、白蓮社(びゃくれんしゃ)を結成、西方往生を期し、30年の間、山を出なかった。ある日、陶淵明(とうえんめい)と陸修静の両人が彼を訪ねて清談し、両人の帰る際、慧遠は送りに出たが、話が尽きず、いつもは虎渓に架かる石橋を出たことがないのに、気づいたときには、虎渓を数百歩も過ぎていたので、3人は手を打って大いに笑ったという。この禅味のこもった題材は、日本では禅宗が広まってから水墨画に好んで描かれるようになり、雪舟、曽我直庵(そがちょくあん)、狩野山楽(かのうさんらく)、池大雅(いけのたいが)の作品がある。
[永井信一]
改訂新版 世界大百科事典 「虎渓三笑」の意味・わかりやすい解説
虎渓三笑 (こけいさんしょう)
Hǔ xī sān xiào
中国,廬山の東林寺に住していた晋の慧遠(えおん)法師が安居禁足の誓いをたて虎渓を渡らずにいたところ,ある日,陶潜(淵明),陸修静の2人を送りながら,知らぬまに虎渓を渡ってしまったことに気づき,3人で大笑したという故事。東洋画の画題としてとりあげられることが多く,中国では宋以降禅宗系の絵画に,日本では室町以降漢画系の絵画に,その作例を残している。
執筆者:戸田 禎佑
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「虎渓三笑」の意味・わかりやすい解説
虎渓三笑
こけいさんしょう
Hu-hsi San-hsiao
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...