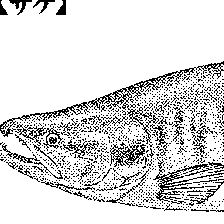日本大百科全書(ニッポニカ) 「サケ」の意味・わかりやすい解説
サケ
さけ / 鮭
chum salmon
dog salmon
[学] Oncorhynchus keta
硬骨魚綱サケ目サケ亜目サケ科の1種。一般にサケといえばシロザケをさすが、ベニザケ、ギンザケ、カラフトマスなど、ほかのサケ類も「サケ」と総称することもある。サケは降海型で、アジア側では北極海に注ぐロシア連邦領レナ川から東、アナディリ地方、カムチャツカ、オホーツク地方、樺太(からふと)(サハリン)、千島列島、南は沿海州、日本、朝鮮半島東岸、アメリカ側は北極海のカナダ領マッケンジー川水系からアラスカ、カナダのブリティッシュ・コロンビア、南はアメリカのカリフォルニアおよび北太平洋水域に広く分布している。日本では太平洋側は茨城県、日本海側は長崎県以北に分布する。
体形は比較的細めで、いくらか側扁(そくへん)、尾柄(びへい)部(尾びれの付け根)も細い。海洋における体色は背面が暗青色、体側は銀白色、体とひれに黒色斑点(はんてん)がない。尾びれに銀白色の放射線が走っている。産卵期に河川に遡上(そじょう)すると銀白色も消失し、全体に黒みが強くなり、さらに黒、黄、桃、紫の色が混じった不規則な縞(しま)模様が体側に現れる。成熟が進むにつれて頭部が伸び、とくに雄の吻端(ふんたん)が下方に、下顎(かがく)が上方に湾曲し、両あごの歯も強大になる。このようなサケは、一般に「鼻曲がり」、あるいは「鼻曲がりサケ」とよばれる。肉色がベニザケに比べて白っぽいため、北洋漁業関係者はシロザケとよんでいる。成熟卵径は7、8ミリメートル、卵色は赤みがかったオレンジ色で、1腹に約3000粒の卵をもち、川の中流域に産卵する。稚魚は海に下ったのち、もとの川に戻ってくる習性(母川回帰(ぼせんかいき))がある。
日本海側は本州中部の石川県、太平洋側は茨城県より北方の川に上って産卵するが、北の地方ほど量的に多い。初秋から冬にかけて産卵する。北海道と本州の東北地方各県ではサケ資源を増やすため、事業規模で人工孵化(ふか)、放流を行うとともに、健全な稚魚を放流するため、各地で海中飼育を行っている。日本では、古くから魚肉、卵(イクラ・すじこ)ともに重要な食用魚として好まれている。
[疋田豊彦]
サケ科の種類
サケ科には、サケ属、ニジマス属、イワナ属、イトウ属の4属が含まれる。このうちサケ属各種を総称して太平洋サケ類ともいう。サケ属には、サケ、カラフトマス、サクラマス(河川残留型をヤマメあるいはヤマベという)、ベニザケ(湖水型をヒメマス)、マスノスケ、ギンザケ、ビワマス(河川残留型をアマゴ)の7種がある。大西洋に生息するアトランチック・サーモンを大西洋サケとよんでいる。
サケ科魚類に共通な特徴は、体がやや細い紡錘形で、背びれの後方に小さい膜状の脂びれがあり、腹びれは体の腹面中央にあって、6本以上の条数からなっている。また腹びれ基部の皮膚の中に1本のとがった三角形の薄い骨質付属突起がある。体は円鱗(えんりん)で覆われている。カラフトマスの稚魚を除いて、体側に沿って暗青色の小判形斑紋(パーマークparr mark)が並んでいる。卵は沈性卵で、卵数は多くなく、砂礫(されき)底に産卵する。
[疋田豊彦]
回遊
稚魚が平均35ミリメートル(人工孵化では給餌(きゅうじ)して40~50ミリメートル)になる3~5月に、川を下って海に入るが、しばらくの間はごく浅いなぎさ帯で過ごす。成長するにつれて生息水域を広げ、体長70ミリメートル、体重3グラム以上になる6月末から7月中旬ごろに沖合いに移動し、表面水温15、16℃になるとまったく姿がみられなくなる。その後の稚幼魚の移動についてはあまり明らかでないが、おそらく沿岸沿いの沖合いを通って太平洋に出て、外洋への大回遊に移るものと考えられる。
日本、アメリカ、カナダ3国の漁業条約に基づき、長年にわたり外洋においてタッギングtaggingとよばれる標識(迷い札)をつける放流(標識放流)試験を行ってきた結果、北洋水域の若齢魚、未成魚の分布、回遊、季節的移動、成長などがしだいに解明されている。また、川から放流したひれ切れ標識(マーキングmarking)の稚魚が、成長して北洋水域で再捕されたことから、この水域のシロザケ群に加わることが明らかになった。幼稚魚の沿岸から外洋への回遊、外洋での移動、外洋から沿岸までの回遊について次のような説がある。
(1)太陽コンパスや偏光を利用して移動する。
(2)海流の方向または海流に逆らって移動する。
(3)均一条件をもつ水塊にのって移動する。
(4)適水温と餌(えさ)を求めて移動する。
(5)磁気を感知して移動する。
以上の諸説があるが、いまだ決定的な解明はされていない。しかし、これらの回遊、移動には、沿岸域の複雑な海況条件と潮流、沖合いの海流、環流、水温などと深い関係があることがうかがわれる。
沿岸域に達した産卵魚が母川を上るのは、いままでの嗅覚(きゅうかく)遮断実験やそのほかの実験によって、おそらく稚魚が下った川の匂(にお)いを嗅覚によって探知するためであろうということがわかってきた。
北洋水域は、北太平洋を囲む各国の川から降海した稚幼魚が、若齢魚、未成魚として、成熟年に達する数年間を過ごすシロザケ群の大きな混成域ということができる。
シロザケ群は、夏季に沿岸に来遊するナツザケと、秋から冬に沿岸に来遊するアキザケを含む総称である。産卵を目ざして沿岸に向かういくつかの回遊経路が知られている。アジア系の大きいシロザケ群は、4~5月ごろにアリューシャン列島とアラスカ半島の南部沖合いを生育水域にしているが、主群は6~7月にアリューシャン列島を越えてベーリング海に入り、カムチャツカ東岸に来遊する。一方、アメリカ系の一部はこの水域からアラスカのブリストル湾と、その南西海域、カナダ、アメリカ沿岸に達する。アジア寄りに生育する群に2系群があり、一つは6~7月に千島列島を通ってオホーツク海に入り、カムチャツカ西岸に来遊する群と、ほかは7~8月にオホーツク沿岸に来遊、アムール川にも上る系群である。なお、4~5月にさらに南部水域に分布し、6~7月にオホーツク海に入り、オホーツク沿岸の川およびアムール川に上るナツザケ群がある。
日本沿岸にはトキシラズとアキザケが来遊する。トキシラズ群は5月ごろ宮城県気仙沼(けせんぬま)沿岸に現れ、太平洋岸沿いに北上するナツザケ群の一部で、北海道沿岸では5月下旬から7月にかけて漁獲され、トキシラズとよばれている。大部分は千島列島の択捉(えとろふ)海峡を通ってオホーツク海に入り、樺太、オホーツク地方とアムール川を上る。一部は列島沿いに北進して北千島、カムチャツカ西岸の諸川に上る。
アキザケ群の生育水域はシロザケ群と同じで、もっとも大きい回遊をする群である。5~6月にアリューシャン列島を通ってベーリング海に入り、7~8月にはカムチャツカ東岸沖合い水域に達し、そのあとは千島列島に沿って南下、9月から翌年1月にかけて北海道、本州東北地方沿岸に来遊して川を上る。
[疋田豊彦]
生活史――産卵と発生
サケは3~6年魚で成熟産卵するが、4年魚がもっとも多い。川を上り始めると餌をまったくとらずに一路産卵場に向かう。産卵域が近くなるとしだいに分散して雌雄1対になる。産卵場に達するとただちに卵床(らんしょう)の造成にかかる。卵床は、流速が1秒間に10~30センチメートルの、浅くて泥が少なく、砂礫径0.5~3.0センチメートルの川底で、しかも湧水(ゆうすい)が出ている所が選ばれる。砂礫底をゆっくり泳ぎながら頭の先(吻)で湧水を探る行動をする。さらに水流を確かめ、ときに尾びれで掘ってみて、卵床をつくる場所を決める。場所の選定と卵床掘りは雌だけが行い、雄はほかの雄の侵入やあたりの警戒にあたる。
雌は流れを利用して、体を横にし、尾びれで川底を激しくあおりながら前進する行動を繰り返す。その間、雄はときどき雌に寄り添って体を震わせ、雌の産卵行動を促す。約1時間で径50~100センチメートル、深さ30~50センチメートルのくぼみの卵床ができる。卵床が完成すると、雌雄は頭部を上流に向け、卵床に身を沈めて互いに体を接触させ、ひれを広げ、えらを張って口を大きくあけ、体をけいれんさせて10~20秒間で一気に放卵、放精をする。普通1回で全卵を放出する。産卵後、雌はすぐに卵床上流部の掘り返しを始める。掘り返しによって飛ばされた砂礫は卵床内の渦流(かりゅう)によって卵床を埋め、さらに盛り上がる。
産卵後の雌は傷だらけになり、体力も消耗してまもなく死んでしまう。雄も1週間くらいのうちに同じ運命をたどる。
卵(受精卵)は通水性のよい水温変化の少ない卵床内で発生が進む。発生速度は水温によって変わるが、8℃の水温で30日目には卵膜を通して目が認められる(発眼期)。受精後60日(2か月間)、積算温度(平均温度と日数の乗積)480℃で卵から孵化する。
[疋田豊彦]
稚魚と降下移動
孵化直後の稚魚は透明で、腹側にしばらくの間、稚魚の栄養となる臍嚢(さいのう)とよばれる卵黄の袋をつけている。1週間くらいで体に色素が出始め、日数経過に伴って臍嚢吸収が進むと体側に特有な斑紋が現れる。稚魚は臍嚢吸収まで卵床内で静かに過ごすが、臍嚢吸収完了すこし前から稚魚の運動が順次活発になって、砂礫の間を縫って上方に移動を始める。孵化後60日で臍嚢を完全に吸収して卵床から離れる。卵床からは1、2週間で次々に脱出し、ただちに遊泳して摂餌活動をする。
この時期は、川の水温はまだ1~3℃と低いため、比較的水温の高い産卵床付近の流水の緩い所に群れをつくっている。その後、水温の上昇とともに遊泳も活発になり、生活領域を広げる。川にとどまっている間、上流から流されてくる小さいユスリカ、カゲロウの幼虫や蛹(さなぎ)などの流下昆虫や、川面に落ちる落下昆虫を盛んに摂食する。この時期の稚魚には明瞭(めいりょう)なパーマークがあるので一名パー稚魚parr fryとよばれる。
稚魚は、おもに日没から夜間にかけて降下移動する。日中群れをつくっている稚魚が、暗くなると群れを崩壊し、浮上して流れとともに下る。日中、流水が清く澄んでいれば、ほとんど流下しない。しかし、日中でも濁り(透視度20センチメートル以下)があれば夜と同じように下る。夜間、流水の中では餌をとらない。また、日中の稚魚の摂餌量が不十分なほど、夜間に活発な流下現象をおこすのに反して、十分な摂餌量の個体は浮上も少なく、流下も不活発である傾向がある。
川を下る稚魚は、体色も銀白色に変わり、パーマークも淡くなり、背びれと尾びれが黒変する。降下移動の盛期は雪解け時期と重なる4~5月で、海に下った稚魚は、沿岸水域の餌料生物の多くなる時期とほぼ一致して、盛んに橈脚(とうきゃく)類をはじめオキアミ類、各種の幼生、魚卵、仔魚(しぎょ)などを摂食して成長する。
[疋田豊彦]
人工孵化
歴史
人工孵化法が導入される以前、川に遡上したサケを保護し、天然繁殖させる種川(たねがわ)制度があった。宝暦(ほうれき)、明和(めいわ)の間(1751~1772)、最初に新潟県三面(みおもて)川、ついで山形県月光(がっこう)川で行われて以後、本州、北海道の各河川にも広まり、明治まで続けられていた。
1876年(明治9)、人工的に初めて茨城県那珂(なか)川で採卵、東京の新宿試験場に運んで孵化に成功、本州各地に移殖放流された。一方、北海道では1878年、札幌の偕楽(かいらく)園内の川から、同年遊楽部(ゆうらっぷ)川のマス、茂辺地(もへじ)川のサケから採卵、試験的に七重(ななえ)勧業試験場で翌年稚魚が孵化、河川に放流している。1881年にアメリカ東岸メーン州のバックス・ポート孵化場に倣って千歳(ちとせ)中央孵化場が建設され、名実ともに国が行うサケ・マス人工孵化センターとなった。1934年(昭和9)まで全道に孵化場が設立され、盛んに事業規模で人工孵化放流が行われ現在に至っている。
[疋田豊彦]
孵化行程
孵化場の施設は地域によって相違があるが、原則的に卵を孵化する孵化室、臍嚢をつけた稚魚を育てる養魚池、稚魚に給餌する飼育池を備えている。多くのじょうぶな稚魚をつくるには、引網、魚止(うおど)め(ウライ)、捕魚車などによる親魚の捕獲から、次のような一連の工程が慎重に行われる。
(1)蓄養 捕獲魚の未熟な魚を成熟まで安静にしておく池(蓄養池)に入れる。
(2)採卵 蓄養池から随時成熟魚を選別、雌数尾の腹を切開、円形の採卵盆に入れ、複数の精子をかけ、静かに攪拌(かくはん)後、水を加えて受精させる。卵を流水槽に入れて吸水と洗浄をする。卵が硬くなった段階で孵化場に運ぶ。
(3)孵化 卵の多少によって各種の孵化器に収容する。孵化器にはアトキンス式、立体式、増収型、ボックス型があり、これで孵化まで静かに管理する。その間、死卵の除去、消毒を行う。
(4)飼育 孵化稚魚は砂利を敷いた養魚池に散布し(1平方メートル当り1万2000~1万5000尾)、臍嚢吸収まで暗くして養う。浮上して餌をとり始めるころ、飼育池(1平方メートル当り1万尾)に移し、放流まで餌を与える。
[疋田豊彦]
展開
国土が狭く、開発の進んでいる日本の河川では、ほとんど天然産卵がないので、サケ資源を長く確保利用していくためには、人為的に管理する孵化増殖に頼らざるをえない。本州では民間ベースで、また北海道ではおもに国営、道営、民間の3者が協力して増殖事業を行い、沿岸来遊量が著しく伸びてきている。概して本州系は昭和40年代前半の7倍以上の400万尾台に、北海道は昭和30年代は200万~300万尾であったのが、昭和56年(1981)から2000万尾を超え、平成に入ってからは4000万~5000万尾となり、回帰率も上昇している。
今後も永続的にサケ資源を安定させるためには、未利用河川の利用や地域の偏りを解消する施策を講じ、魚種もサクラマス、カラフトマス、そのほかの増殖拡大を行うことが人工孵化の大きな役目である。
[疋田豊彦]
漁業
産卵のため河川に遡上(そじょう)するサケ(シロザケ)は、古くからアイヌの重要な食料であり、マレップ(矠(やす))やウライ(簗(やな))などの方法で捕獲されていた。しかし、北海道への移住者によって、相次いで漁法が改良され、文化期(1804~1818)に建網(たてあみ)が考案されてのち、河川漁業から沿岸漁業へと著しい発展を示した。漁場の開発も進み、1889年(明治22)ごろにピークを示したが、乱獲と河川の荒廃によって以後漁獲は減少傾向をたどった。一方、1870年代(明治初期)樺太(からふと)(サハリン)へ進出した一部漁業者が、沿海州・アムール方面にまで進出し、ニシンとともにサケ漁業を行った。
1907年(明治40)日露漁業条約の締結によって、競売方式により露領漁区を借地して行ういわゆる露領漁業が軌道にのり、最盛期には日本人経営の漁区は308漁区に達した。しかし、絶えずロシアの圧迫があり、これを打開する方法として母船式流し網漁業がカムチャツカ西岸沖合いで企業化され、1933年(昭和8)には19隻の母船が出漁した。また、同じころ北千島を根拠地とする流し網漁業が始まり、旧ソ連領沿岸での漁業とともにサケ・マス漁業は北洋漁業の代表的なものとなった。
第二次世界大戦の勃発(ぼっぱつ)、そして終戦によりソ連領沿岸および沖合い、北千島での漁業は壊滅し、40年間にわたる北洋サケ・マス漁業は歴史を閉じた。戦後のマッカーサー・ラインによる漁業海面の規制が1952年(昭和27)に撤廃されると同時に、母船式、基地独航方式、延縄(はえなわ)などのサケ・マス漁業が復活、わずか数年のうちに戦前をしのぐほどの規模にまで発展した。1956年、ソ連がブルガーニン・ラインを設定して操業海域規制を宣言、漁獲量の制限、オホーツク海域への出漁禁止などが相次ぎ、母船団規模の縮小を余儀なくされた。さらに1977年には200海里漁業専管水域の設定(その後、1982年国連海洋法条約により200海里排他的経済水域が設定され、1996年より日本でも施行された)、母川国主義の主張など、アメリカ・カナダ・ソ連(現在ではロシア)3国による規制がいっそう厳しくなり、1978年以降、基地独航方式の減船、延縄漁業の禁止があり、母船式も1989年(平成1)を最後に幕を閉じた。さらに、1991年には国連で大規模な公海流し網の停止が採択、また1993年に北太平洋のサケ・マス類の保存に関する新たな条約が発効したことに伴い、公海におけるサケ・マス漁業は消滅した。現在は、日本とロシア間の協議に基づいてロシアおよび日本200海里水域においてサケ・マス流し網漁業が行われている。沖取り漁業が衰退した反面、日本沿岸では孵化(ふか)放流事業の成功により、サケの回帰量が飛躍的に増大し、定置網漁業の主要な資源となっている。
アメリカやカナダでは、太平洋・ベーリング海沿岸において、主として刺網、巻網、引網などで漁獲されており、資源保護のため厳しい管理のもとに行われている。また、ロシアにおいては、アメリカ、カナダのような沖取り漁業はなく、主として建網を用い沿岸で漁業が行われ、一部では簗や引網の使用が許されている。
[三島清吉・高橋豊美・小倉未基]
食用
歴史
サケは産卵のため河川に上るので捕獲しやすく、非常に古くから食用とされていたと考えられる。サケが重要な食品の地位を占めてきたことは、サケに関する宗教儀礼の発達、豊富な民話・伝説の伝承によって知ることができる。海外でもサケの食用とされた歴史は古く、南フランスのピレネーで、紀元前1万年のものと思われるトナカイの骨の一片にサケの図を彫刻したものが発見されている。これは、おそらくサケが人類によって記録された最初のものであるといわれている。また紀元後1世紀の後半には、フランスから雪詰めにしたサケが、当時のローマ帝国に送られたといわれている。
わが国では、とくに東北地方を中心として、縄文文化の形成はサケ・マスに依存することが多かったといわれる。サケらしい魚を線刻した魚文刻石(鮭石(さけいし))が秋田県子吉(こよし)川流域の各遺跡から多く発見され、長野県北相木(きたあいき)川上流の栃原(とちばら)遺跡(縄文早期)などでもサケ骨が出土している。平安時代には多くのサケが貢租として京都に運ばれた。『延喜式(えんぎしき)』(927年完成)には、生鮭のほか楚割(すわやり)(魚肉を割(さ)いた干物)、鮭子(すじこ)、氷頭(ひず)(頭部の軟骨)などが食用とされていたことがみえる。このころのサケの漁獲の大部分は河川におけるものであった。江戸時代には、サケ漁も大いに発達したが、それでもその大部分は河川で漁獲されていた。北海道のサケ・マス缶詰製造は、1875年(明治8)渡米してアメリカの製造技術を学んだ関沢明清(のち水産伝習所長)が、帰国後政府に建議して始まった。
[河野友美・大滝 緑]
料理
サケ・マス類の肉は、サーモンピンクといわれるように紅色をしている。この紅色のとくに強いのがベニザケで、欧米ではこの肉の赤いものをたいへん喜ぶ。日本でも、このベニザケに対する嗜好(しこう)が高まっている。しかし、ベニザケは日本沿岸の海域ではとれず、主として北洋で漁獲されたものが利用されている。サケのもっとも味のよい時期は、産卵のため近海にきたときである。川に上り始めると、体力が順次消耗してやせてくるので味が落ちる。また産卵後は体力を消耗し尽くし、味もとくに劣っている。以前は、産地から遠い所では、なまのサケを調理することはむずかしかったが、最近は、急速凍結によるサケが多く出回るため、産地以外でも塩をしないサケを調理することができるようになった。
なまのサケは、塩焼き、フライなどにする。また、冷凍したものを凍ったまま刺身状に切り、半解凍でしょうがじょうゆをつけて食べるものをサケのルイベという。塩ざけは、焼き物、石狩鍋(いしかりなべ)、三平(さんぺい)汁、粕(かす)汁、氷頭なますなどに使われる。また、塩ざけを酢でしめ、さけずしにも利用できる。
氷頭なますは、新潟県や富山県の郷土料理として有名である。サケの頭の先から目のあたりまでに含まれる軟骨を氷頭とよび、これを薄く刻み、せん切りのダイコン、ニンジンといっしょに調味酢で和(あ)えたものである。サケの紅葉漬け(もみじづけ)は、福島県の郷土料理で、晩秋から初冬にかけて川をさかのぼってくるサケを腹子(はらこ)とともに、麹(こうじ)、みりん、しょうゆに漬ける。2~3か月ほどで食用となる。さけずしは、サケのいずしともいい、北海道や東北地方でみられるすしで、塩ざけあるいは生ざけを米飯と麹で漬け込み、乳酸発酵させてつくる。ニンジン、ダイコン、キュウリなどの野菜を加えることもある。
[河野友美・大滝 緑]
加工品
サケの加工品としては、すじこ、イクラ、めふんなどがある。すじこはサケの卵巣を塩蔵したもので、塩ざけを製造するときに、腹を裂いて卵嚢(らんのう)のまま摘出し、これを塩漬けにする。イクラは産卵期近くのサケの卵を人工的に絞り出したもので、これを塩漬けにしたものである。めふんはサケの腎臓(じんぞう)の塩辛である。また、えらの塩蔵品で「ささめ」というものもある。そのほか、塩ざけや新巻(あらまき)、缶詰、薫製などの各種の加工品がある。サケの薫製は、サクラ、ナラ、シラカバなどの木をいぶし、薄く塩をしたサケを冷薫して仕上げるものである。身が柔らかく、薄く切ってレモンを添え、オードブルなどによく使用される。そのほか加工品としては、さけ茶漬け、粕漬けなどもつくられる。
[河野友美・大滝 緑]
民俗
サケは北太平洋沿岸でもっとも主要な魚であるため、伝承も多く、アイヌでは「カムイ・チェップ(神の魚)」とよび、カナダのブリティッシュ・コロンビア地方の先住民は「首長(しゅちょう)」と尊称して、霊魂をもつ魚とする。
北海道や東北地方の各地では、10月から12月にかけてサケの祭りが盛んに行われるが、これはサケの回帰性を神が与えてくれるものと感謝し、その豊漁を祈願するもので、縄文時代から行われている。秋田県由利本荘(ゆりほんじょう)市矢島町地区や北秋田市阿仁(あに)地区などには、石にサケを線刻した同時代の祭祀(さいし)遺跡があるほか、鳥取市国府町の鷺山(さぎやま)古墳や大阪府八尾(やお)市から出土した銅鐸(どうたく)にも、サケらしい魚が描かれている。また福岡県嘉麻(かま)市大隈(おおくま)には、サケを祀(まつ)る鮭(さけ)神社があり、氏子はサケを禁食している。
千葉県香取(かとり)市山倉の山倉大神にはサケ祭りがあり、東日本の各地には、「鮭女房」や「鮭の大助(おおすけ)」の伝説があり、旧暦11月15日にサケの王者が「大助、小助いま上る」と部下を引き連れて川を上ってくる声を聞いた者は、3日以内に命を失うといい、その声を聞かないように耳ふたぎ餅(もち)を搗(つ)く地方もある。これは、乱獲をやめて繁殖管理の必要性を教える伝説であろう。古代の人々はサケの帰郷本能に霊的なものを感じ、神の恵みの魚としてハレの日にふさわしい食物とした。そこから新巻鮭(あらまきざけ)を歳暮の贈答品や年越魚とする習慣が生まれた。
[矢野憲一]
文学
平安中期の『賀茂保憲女集(かものやすのりのむすめしゅう)』(993年ころ成立か)の序文に「鮭といふ魚(いを)の、冬出(い)で来(く)れば、北へ流るる水すらも友とせり」とみえるのは、その生態を述べたものといえよう。『続本朝往生伝(ぞくほんちょうおうじょうでん)』や『発心(ほっしん)集』巻1などには、増賀上人(ぞうがしょうにん)が師の良源(りょうげん)の宮中参内に、乾鮭(からざけ)を太刀(たち)のかわりにさし、やせこけた牝牛(めうし)に乗って供をしたという奇行が伝えられている。『徒然草(つれづれぐさ)』には、四条流の庖丁(ほうちょう)の家の人、藤原隆親(たかちか)が天皇の食事に乾鮭を出したところ人が非難したので、鮎(あゆ)の白乾(しらぼ)しをさしあげるのだから、乾鮭だって差し支えないと応酬したという話が記されている。俳諧(はいかい)では秋の季語、「乾鮭」は冬の季語である。
[小町谷照彦]
『松下高・高山謙治著『鮭鱒聚苑』(1942・水産社)』▽『J・W・ジョーンズ著、松井宏明訳『世界動物記シリーズ4 サケ』(1974・思索社)』▽『A・ネットボーイ著、松下友成・今村弘二訳『ザ・サーモン』(1975・同文書院)』▽『市川健夫著『日本のサケ』(1977・日本放送出版協会)』▽『岩本由輝著『南部鼻曲鮭』(1979・日本経済評論社)』▽『佐野誠三著『サケ・マスの仲間』(1982・つり人社)』▽『秋庭鉄之著『鮭の文化誌』(1988・北海道新聞社)』▽『谷川健一編『日本民俗文化資料集成19 鮭・鱒の民俗』(1996・三一書房)』▽『出口晶子著『川辺の環境民俗学――鮭遡上河川・越後荒川の人と自然』(1996・名古屋大学出版会)』▽『佐野蘊著『北洋サケ・マス沖取り漁業の軌跡』(1998・成山堂書店)』▽『日本水産学会監修・帰山雅秀著『最新のサケ学』(2002・成山堂書店)』▽『前川光司編『サケ・マスの生態と進化』(2004・文一総合出版)』