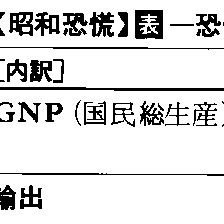精選版 日本国語大辞典 「昭和恐慌」の意味・読み・例文・類語
しょうわ‐きょうこうセウワキョウクヮウ【昭和恐慌】
- 〘 名詞 〙 昭和三年(一九二八)の金融恐慌、さらに同五年から翌年にかけて日本で起こった恐慌。前年、ニューヨークのウォール街に始まった大恐慌が日本にも波及したもの。
改訂新版 世界大百科事典 「昭和恐慌」の意味・わかりやすい解説
昭和恐慌 (しょうわきょうこう)
1930年代の日本の恐慌。1929年アメリカの株式恐慌からはじまった世界大恐慌の一環をなす。
原因と経過
1929年10月,ニューヨークのウォール街に端を発したアメリカの恐慌は,前後約4ヵ年余にわたる世界恐慌(大恐慌)にまで発展した。〈繁栄の1920年代〉を謳歌しつづけてきたアメリカ経済が,20年代最後の年に一転して最悪の経済不況に追い込まれたのはなぜか。第1は,20年代のアメリカ経済の発展を主導してきた自動車,電機,住宅建設などの産業が27年ころから過剰生産に陥り,生産能力を低下させたためである。しかも生産過剰にもかかわらず,大企業は独占価格を設定して製品価格を下げなかったため,消費は伸びず不況はいっそう悪化した。第2に,20年代の繁栄の過程で貧富の差が大きくなり,所得の悪分配が生じた。29年には人口の5%のものが全個人所得の約3分の1を得ていた。とくに20年代は農業が慢性的不況状態にあったため,農民の所得は工業労働者ほどには伸びず,それが工業の発展を制約した。第3に,1928年末から29年秋にかけての高金利が,経済の実態を反映しない異常な株式ブームを巻き起こしていた。したがって,ひとたび株式暴落が起これば,空前の〈繁栄〉という摩天楼が大きく音をたてて崩れ落ちるのは必至であった。29年に1040億ドルであった国民総生産(GNP)は,31年760億ドル,33年には560億ドルにまで激減した。失業者も1930年に430万人に達し,1年後にはさらに倍加して800万人におよんだ。この数字は6人に1人が失業していることを示す。32-33年にはついに1200万人を超え,失業率は約25%に達した。こうしてアメリカ経済は史上最悪の大不況に見舞われたのである。
このアメリカの恐慌は翌1930年に入って,日本経済を直撃した。この年1月11日,浜口雄幸民政党内閣は金解禁を実施したばかりであった。金解禁とは,一言でいえば通貨と金の兌換を自由にすることであり,国際間の金の移動を自由にすることである。日本では第1次大戦の影響で1917年以降,金輸出を禁止していた。それ以来,金解禁は12年間にわたり10人の大蔵大臣が取り組んできて果たせなかった難事業であった。浜口内閣の蔵相井上準之助は,緊縮財政,在外正貨の補充,合理化の推進,消費節約と貯蓄奨励など一連のデフレ政策を採用して,金解禁にそなえた。そして井上は〈暗黒の木曜日〉のニューヨーク株式取引所の株価暴落を,大恐慌のはじまりとは思わず,むしろ円相場の上昇を金解禁の好機と錯覚したのである。しかし金解禁は,あたかも吹きすさぶ大恐慌の嵐に向かって雨戸を開けはなつようなものであった。解禁後わずか2ヵ月で1億5000万円の正貨が流出し,30年中に2億8800万円,翌31年もイギリスの金本位離脱をきっかけに総額4億3300万円もの巨額の金が流出した。結局,日本はわずか2ヵ年で約8億円の正貨を失った。そればかりでなく,金本位の放棄を余儀なくされ,かつ未曾有の大不況に突き落とされたのである。
恐慌の実相
恐慌の激しさをはかる中核的指標は,株価と物価の暴落である。東京・大阪株式取引所の有力株140社・246銘柄について,金解禁前の1929年6月末と最低の31年11月とを比較すると平均下落率は50.4%,時価総額で25億3500余万円の巨額が損失に帰した。卸売・小売物価もじりじりと低下をつづけ,30年1月から2年間で30%下落した。なかでもアメリカの恐慌の影響をまともにうけた生糸は,30年1月の高値から31年の最低値にかけて55%の下落であり,同様に綿糸約52%下落,米約50%下落というように,主要商品はいずれも半値以下に暴落した。さらに貿易においても1929年から31年にかけて,輸出は43.2%,輸入は約40%それぞれ減少した。とくに生糸は,日本の輸出総額の約4割を占め,その9割以上がアメリカに輸出されていた。この生糸輸出が激減したため,貿易収支は悪化の一途をたどった。国民総生産は,1930年からいっきに落ち込んだ。1929年を100とすると,30年89.1,31年80.6,32年82.8で,この3年間がもっとも落込みが激しい(表にみるとおり,他の経済指標を総合すれば1931年が恐慌の底であったことがわかる)。三井,三菱,住友の三大財閥本社も軒並み純益を低下させ,中小企業でも倒産・休業,工場主の夜逃げ,賃金不払いなどが続出した。失業者が激増し,1930年237万人,31年250万人,32年242万人,失業率は8.3~8.9%に達した。職を失った者は郷里に帰るにも旅費がなく,道をとぼとぼと群れをなして歩き,夜は野宿するありさまであった。
労働・農民運動の高まり
日本の庶民の伝統的な生活感覚は,窮乏生活に直面したとき,これまでの生活のなかで最も悪い生活状態を思い出し,それに比べれば現在のほうがいくらかよいといって現状を納得することであった。あるいは下の者をみて,それより自分のほうがまだましだといって自己の逆境をなぐさめることを常としてきた。この傾向は労働者や農民についてもあてはまる。しかし大恐慌期の生活窮乏は,このような自己説得,現状肯定の論理だけでのりきれるほどなまやさしいものでなかった。食生活にもこと欠く生存の危機にさらされたのである。統計的にみて,労働争議は1931年に戦前最高の2456件,小作争議は35年に同じく6824件を記録している。1929年から31年にかけて東京市電,横浜ドック,鐘紡,東洋モスリンの争議など歴史的な大争議が激発するとともに,富士瓦斯紡,芝浦製作所,筑豊炭田,住友製作所などの大資本における労働者の反抗が巻き起こった。さらに参加人員50人以下の〈群小争議〉が年々増加し,31年には全体の3分の2を超すにいたった。これらの争議は,不況と合理化を反映して,賃金減額反対,解雇反対,解雇手当の支給など消極的・防衛的性格の要求が多かった。農村では,小作争議の嵐が吹き荒れた。争議の主要な原因は,中小地主による土地引揚げであった。恐慌と小作争議の高揚に直面した中小地主は,小作人に貸した土地を取り上げ自作化することによって,この危機に対処しようとしたのである。だが地主に土地を引き揚げられてしまっては,小作人は死刑宣告を受けたにもひとしい。それだけに小作貧農層は必死であった。小作料減免,借金棒引き,小作地引揚げ反対などの対地主闘争のみならず,電灯料値下げ,肥料代値下げ,税金延納など,この時期の争議は生活防衛闘争としての色彩をおびるにいたった。
不景気と世相
不景気はその時代に特有の思想・文化状況を生みだすものである。民衆は前途に生きる望みを失い,刹那的・享楽的な生活を追い求めた。不安,憂うつ,懐疑,モダン,エロ・グロ・ナンセンスなどの言葉が流行した。モガやモボ,〈やじゃありませんか〉も,この時代を風靡した言葉である。大阪千日前を中心に漫才ブームが起こり,東京の浅草,新宿などの盛場は民衆的娯楽センターとしての性格をつよめた。ジャズ,ダンス,カフェなどのモダニズム文化がサラリーマンや知識人をとらえるとともに,剣劇映画,落語などの大衆文化が庶民をひきつけた。蓄音機とレコードが登場し,流行歌全盛時代がおとずれた。《君恋し》《東京行進曲》など歌謡史上に残るヒット曲が生みだされたのは1929年のことである。ついで不景気が底に達した31年に入ると,古賀政男作曲の《酒は涙か溜息か》《影を慕ひて》などの哀調をおびた旋律が人々の心をとらえた。他方,この不景気の時代は,知識人・青年のあいだに反体制的機運を生みだした。《マルクス=エンゲルス全集》の刊行をはじめマルクス主義関係の書物が読者を獲得し,プロレタリア文学,プロレタリア芸術運動が台頭した。映画界でも思想問題を主題にした〈傾向映画〉がつくられた。1930年2月には,プロレタリア作家藤森成吉の《何が彼女をさうさせたか》が,浅草で5週間続映の新記録をつくった。挫折と逃避,現状打破の交錯する地点に,この時代の文化状況は成立していたといえよう。
不景気回復と侵略への道
1930年,満鉄が創業以来初めて赤字をだした。満州特産の大豆をはじめ農産物価格が暴落し,運賃収入が激減したためであった。30年末から〈生命線満蒙の危機〉が叫ばれはじめた。翌31年9月,ついに関東軍が謀略的に柳条湖(溝)事件を引き起こし,満州侵略が開始された。同年12月,第2次若槻礼次郎民政党内閣は金解禁政策の失敗と閣内不統一によって総辞職に追い込まれた。かわって政友会の犬養毅内閣が成立し,高橋是清が大蔵大臣に就任した。高橋蔵相は,内閣が成立すると即日金輸出を禁止して,管理通貨への体制をかためた。高橋蔵相の任務は,国内的には恐慌からの脱出,国外的には満州侵略のための軍備強化,この二つの課題をいかにして遂行するかにあった。高橋財政は,この任務を遂行するにあたって,井上財政とはまったく逆の道をえらんだ。すなわち井上が緊縮財政と高金利によって物価を引き下げ,国際収支の改善をはかろうとしたのに対して,高橋は低金利と公債発行によるインフレ政策を採用して,経済に刺激をあたえ,これによって景気の回復をはかろうとしたのである。だが,むやみに公債を発行すれば悪性インフレに転化する危険がある。そこで高橋は,この公債政策を展開するにあたっていくつかの基礎工作を行った。政府は,(1)32年の3,6,8月の3度にわたって日銀金利を1銭6厘から1銭2厘に下げ,公債の利回りを5%から4%へ引き下げ,郵便貯金の利子を4.2%から2%の低利へと引き下げた。(2)32年6月,兌換銀行券条例を改正して,日銀券の保証発行限度額を1億2000万円から一挙に10億円に引き上げた。(3)日銀引受公債発行制度を創設して,オープン・マーケット・オペレーション(公開市場操作)を開始した。これらの措置は,いずれも日銀の発券能力を拡大させ,また低金利政策によって,赤字公債が無理なく消化される条件をつくりだすことに狙いがあった。このような改革を基礎に高橋財政は展開されたが,32年度予算は前年に比して5億円増加し,財政規模は一挙に19億5000万円に達した。以降,歳出予算は年々膨張をつづけ,36年には22億8200万円の巨額に達した。財政膨張の最大の原因は軍事費の突出である。32-36年度の歳出に占める軍事費の割合は35.2~47.2%に急上昇した。軍需インフレによって,軍需産業,重化学工業は息を吹き返し,32年下期から日本経済は回復に転じ,33-35年には他国に先がけて好況局面を迎えた。軍事費散布を中心とした景気回復策が高橋財政の一方の柱だったとすれば,もう一つの柱は時局匡救事業,つまり農村救済をめざす公共土木事業であった。政府は,道路建設,河川改修,治山治水,橋梁建設,港湾改良などの事業をおこして,貧窮農民や失業者に就労の機会をあたえようとしたのである。総額で8億6487万円が支出されたが,これは軍事費圧迫のため3ヵ年で打ち切られてしまった。そのほか重要な柱として11億円におよぶ対満投資がある。満州を重化学工業資本のための原料供給地・商品輸出市場として再編成するのがその目的であった。最後に,高橋財政期の特徴として為替ダンピングがある。為替の低落は金輸出再禁止の直後から進行し,1931年12月には最低34ドルにまで急落し,翌32年6月にはついに30ドル台を割り,11月には20ドルの線を下回るところまで暴落した。しかるに国内の物価とくに実質賃金は,逆に低下したため日本の商品は世界市場で強い競争力をもつことができた。綿織物を中心とする日本商品の集中豪雨的な輸出攻勢は,各国の警戒をつよめ経済ブロック形成の引き金となった。高橋の景気回復策はたしかに一定の成功をおさめたが,他面で財政の軍事化に拍車をかけ,軍部勢力の台頭をゆるした。35年,高橋はこれ以上軍事費を増やしては国家財政が破綻するとして軍拡に歯止めをかけようとしたが,二・二六事件で悲劇的な最期をとげた。昭和恐慌は日本が戦争とファシズムの時代に向かう曲り角に位置していた。
執筆者:中村 政則
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「昭和恐慌」の意味・わかりやすい解説
昭和恐慌
しょうわきょうこう
いわゆる金解禁を契機に、1929年(昭和4)以降の世界大恐慌と重なって、30年から翌年にかけて日本経済を危機的状態に陥れた、第二次世界大戦前におけるもっとも深刻な恐慌。
第一次世界大戦最中の1917年(大正6)9月、日本はアメリカに続いて金輸出禁止(事実上の金本位制停止)を行った。アメリカは戦後の19年早くも金輸出を解禁し、金本位制に復帰した。しかし日本は、19年末には内地・外地あわせて正貨準備も20億4500万円に上り、国際収支も受け取り超過であったにもかかわらず、金解禁を行わなかった。1920年代には世界の主要国は次々と金本位制に復帰し、金為替(かわせ)本位制を大幅に取り入れた国際金本位制の網目(ネットワーク)が再建され、アメリカの好況と対外投資をてことして世界経済は「相対的安定期」を享受した。日本政府もこの潮流に応じて幾度か金解禁を実施しようとした。しかし20年(大正9)の戦後恐慌、22年の銀行恐慌、23年の関東大震災、さらにはそれまでたび重なった財界救済のための特別融資の整理強行を契機におこった27年(昭和2)の金融恐慌など、相次ぐ経済危機にみまわれて、踏み切ることができなかった。28年6月にはフランスも新平価(5分の1切下げ)による金輸出解禁を行ったので、主要国では日本のみが残された。同年には日本の復帰思惑も絡んで円の為替相場は激しく変動し、為替安定(金解禁による旧平価での為替レートの固定)の要求は、輸出・輸入業者の別なく、財界全体の要求となって高まった。
1929年7月、張作霖(ちょうさくりん)爆殺事件(同年6月4日)の処理をめぐり田中義一(ぎいち)政友会内閣が瓦解(がかい)し、かねてから金解禁即行を迫っていた浜口雄幸(おさち)民政党内閣が成立、井上準之助(じゅんのすけ)大蔵大臣、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)外務大臣の布陣で、「金解禁・財政緊縮・非募債と減債」と「対支外交刷新・軍縮促進・米英協調外交」を掲げて政策転換を断行した。井上は対外準備の補充や財政金融引締めのデフレ政策を推進し、30年1月に金解禁を実施した。しかし、解禁を見越して輸出代金回収を早め、輸入代金支払いを繰り延べる、いわゆるリーズ・アンド・ラグズleads and lagsを伴う国際収支の好調と為替相場の上昇は、解禁後一転して逆調となった。緊縮財政と農業恐慌とが重なって未曽有(みぞう)の不況となり、ルンペン時代を現出した。恐慌の深刻さは、29年を100%とした30、31年の経済諸指標の萎縮(いしゅく)にはっきり現れている。国民所得は81%、77%に減少、卸売物価は83%、70%に下落、米価は両年63%に暴落、輸出品の二本柱の綿糸は66%、56%、生糸は66%、45%に大暴落している。輸出は68%、53%、輸入も70%、60%への激減であった。会社の減資解散が激増し、生産制限、共同販売、合理化が広がり、企業連合(カルテル)、企業合同(トラスト)の結成が進んだ。したがって、雇用は減り、実質賃金水準は下がり、労働争議が激増した。30年には、温情主義経営を誇った鐘紡(かねぼう)にも大争議がおこり、東京市電、市バスのストで市民の足が麻痺(まひ)した。30年の失業者は250万余と推定されている。生糸の暴落は養蚕農家を打ちのめしたが、30年の大豊作、31年の凶作による農産物価格の下落、収入の減少は、零細経営の自作・小作農家に破滅的な打撃となった。東北地方では飢餓水準の窮乏に陥った。雑穀はもとより、野草で飢えをしのぐありさまで、娘の身売りが盛んに行われ、農村の小学校教員の給料不払いが続出した。「キャベツは50個でやっと敷島(しきしま)(刻みたばこ)一つ、蕪(かぶ)は百把なければバット(巻きたばこ)一つ買えません。これでは肥料代を差引き一体何が残りますか」(埼玉県北足立(あだち)郡の農民の陳情)という状況であった。農工価格差(シェーレ)は、租税負担の加重と相まって、農民の窮迫を強め、農家総負債額は約49億円、1戸当り827円に上った。
政府は農民への低利資金の融通や米、生糸の市価維持対策をとったが、緊縮財政の枠のなかではまったく不十分にしか行えなかった。工業面では、1930年6月に臨時産業合理局を設け、31年4月に工業組合法、重要産業統制法を制定して、輸出中小企業を中心とした合理化やカルテルの結成を促進した。しかし、大恐慌の荒波のなかに船出した金解禁・緊縮政策は、31年9月のイギリスの金本位制離脱と満州事変勃発(ぼっぱつ)で暗礁に乗り上げ、大量のドル買い(資本逃避)を誘発した。同年12月には第二次若槻(わかつき)礼次郎内閣が瓦解し犬養毅(いぬかいつよし)政友会内閣が成立すると、ただちに再禁止となり、金本位制復帰はわずか2年の短命に終わった。この2年間の深刻な産業および農業恐慌は社会的危機を激化し、浜口、井上、団琢磨(だんたくま)らを襲った右翼テロとなって暴発し、戦争とファシズムへの道を準備する結果となった。
[長 幸男]
『長幸男著『昭和恐慌』(岩波新書)』
百科事典マイペディア 「昭和恐慌」の意味・わかりやすい解説
昭和恐慌【しょうわきょうこう】
→関連項目井上財政|産業組合|重要産業統制法|高橋財政|日本
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「昭和恐慌」の意味・わかりやすい解説
昭和恐慌
しょうわきょうこう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「昭和恐慌」の解説
昭和恐慌
しょうわきょうこう
1930年(昭和5)に勃発した第2次大戦前の日本で最大の深刻な恐慌。世界恐慌の一環としての性格をもつが,国際的に最も遅れた金本位制への復帰と前後して恐慌が発生したこと,物価・企業利潤・労賃は大幅に下落したが生産数量の縮小は軽微であったこと,深刻な農業恐慌を併発したこと,早期に景気回復に転じたことなどの特徴があった。恐慌は,1929年夏からの綿製品・重化学工業品の価格下落,30年5月の生糸価格暴落,同年10月の米価暴落の3段階をたどった。この過程でカルテルがほとんどの産業にいきわたって産業合理化が進められ,連盟融資などの救済政策も展開された。31年末の金本位離脱とその後の高橋財政によって,この恐慌からの脱出が実現された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「昭和恐慌」の解説
昭和恐慌
しょうわきょうこう
日本経済は,第一次世界大戦後の戦後恐慌に始まり,震災恐慌・金融恐慌・農業恐慌と深刻化する。とくに,世界恐慌の最中に,日本は,金解禁を断行したため,正貨の大量流出,企業の操業短縮,倒産,賃下げ・首切りが相次ぎ失業者が増大した。これを一般に昭和恐慌という。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...