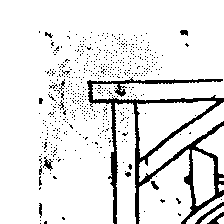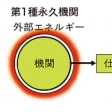精選版 日本国語大辞典 「永久機関」の意味・読み・例文・類語
えいきゅう‐きかんエイキウキクヮン【永久機関】
改訂新版 世界大百科事典 「永久機関」の意味・わかりやすい解説
永久機関 (えいきゅうきかん)
perpetuum mobile[ラテン]
技術史的には人力や畜力によることなく運動し続ける機械を指し,物理学の概念としては外部に対して仕事をするが,それ自身には何ら変化を残さないような装置をいう。西洋では天の運動を除いて永遠なものはないと考えられていたので,地上でのそのような機械の製作は不可能とみなされていたが,すべてを輪廻のもとに考えるインドで,永久機関が着想された。具体的には1150年ころインドの天文学者で数学者だったバースカラ2世が《第一真理論》という書物の中で永久機関の考案を叙述している。彼の考案には2種類あって,その一つは〈軽い木材で車輪をつくり周囲に同じ直径の中空の棒を等距離に取り付ける。垂直から少しずれた位置に保っておいて各中空棒の中に水銀を半分だけ入れる。2本の柱で軸を支えれば車はおのずから回転するであろう〉というのである。もう一つの案については,〈車輪の外側に溝を掘ってターラの葉を蠟ではりつけ,溝の半分に水を満たす。残りの半分には水が漏れ始めるまで水銀を入れて穴をふさげば,車は水の回転によっておのずから回るであろう〉と書いている。1200年ころイスラム圏で活躍したイブン・リドワーンIbn Riḍwānの書物には重力を利用した6種類の永久運動機械が記されているが,その一つはバースカラの第1の考案と同じで,バースカラの影響があったことが知られる。13世紀ヨーロッパは技術革新の時代だったので永久機関の考案が流行した。たとえばビラール・ド・オヌクールの《画帳》には,奇数個の槌をつけた水銀入りリム付車輪の図が出てくる。そのほか,14世紀後半の無名の著者によるラテン語の著作にはバースカラの第2案に似たものが記述されており,1440年ころにはタッコラMariano di Jacopo Taccola(1381-1458)がちょうつがいつきの棒を取り付けた機械の図を描いている。
近代になっても種々の考案が提出されたが,そのうち著名なのはウースター侯(サマセットEdward Somerset,1601-67)で,彼の《発明百集》(1663)には,車輪のリムと外輪との間に球を転がす方式の永久運動装置が記されている。重さ50ポンド(22.7kg)の球を40個使った直径14フィート(4.3m)の車輪である。これはアイデアだけであったが,ベスラーJohann Ernst Elias Bessler(ラテン名オルフュレウスOrffyreus,1680-1745)が直径12フィート(3.7m),幅1フィート2インチ(36cm)の木製車輪を実際につくってみせた。この装置については目撃者がニュートンに報告しているが,布を掛けて内部が見えないようにしてあり,軸に外力が働いていないかどうかは不明であった。
その他の方式のものとして,流体を循環させる永久運動機械の代表はJ.ウィルキンズの《数学的魔術》(1648)に述べられているもので,〈アルキメデスのらせん〉によって水を揚げ,その水力を利用してらせんを回そうとするものであった。パパンも静水力利用の永久運動について論文を書いている。液体を利用するものとして毛管現象を利用するものもあった。有名なのはコングリーブWilliam Congreve 卿(1772-1828)の考案で,海綿製のベルトと重量物でつくったベルトを重ねて斜めに二つの滑車に掛け,下半分を水中に置く方式であった。磁気を利用するものとしては,13世紀にP.deマリクール(ペトルス・ペレグリヌス)が永久に針が回転する装置を図に描いているほか,カルダーノが磁気を利用した永久機関の可能性を示唆したことをアントニウス・デ・ファンテスAntonius de Fantesが記しているが,これについてはW.ギルバートが実験ぬきの思いつきにすぎないと批判している。上述のウィルキンズも,斜面に穴をあけ磁石で鋼球を引き上げては落とす装置を考案している。電気利用に関しては,電池が考案されたとき永久機関を可能にするものと考えられたが,電流を流し続けるうちに損耗することがわかった。
このように古来人々が開発努力を続けてきた永久機関は外力を加えることなく永久に運動し続ける機械で,この場合の外力は人力や畜力を意味していた。したがって風車や水車や気圧計や温度計も〈perpetuum mobile〉と呼ばれていた。この種の永久運動機械はアイデア玩具で実現している。しかし原動機の開発が進むと,風力や水力は動力源として珍しくなくなり,それらを利用した機械は永久運動機械とみなされなくなっただけでなく,永久運動にとどまらず外部に仕事をなしうる機械が努力目標となった。この種の永久機関が不可能であることは,すでに16世紀にレオナルド・ダ・ビンチやステビンらによって指摘されており,17世紀に入ってからはホイヘンス,ライプニッツ,ニュートンらによって主張されていた。しかし産業革命の波の中で永久機関への模索が続き,1775年にパリ科学アカデミーはこの種の考案の受理を拒否したが,新発明の提唱はあとを絶たなかった。19世紀に入って熱機関についての物理的研究が進み,N.L.S.カルノーが《火の動力についての考察》(1824)で永久機関不可能の原理をうちたてて熱力学の基礎をつくり,〈単に最初の衝撃の後かぎりなく続く運動というだけでなく,動力を無限につくり出し,自然界のすべての静止物体をつぎつぎにその状態から引き出し,それによって慣性の法則を否定することができ,究極には全世界を運動に投げ込んでその運動を保持し,かつ絶えず加速するに足る力を自分からくみ出すことのできるような装置〉を〈永久機関〉と規定した。カルノーは〈もしそれが可能なら水や空気の流れや可燃物の中に動力を求める必要はなく,欲しいだけくみ出しうる尽きることのない動力の源泉が利用できることになろう〉と言っている。この永久機関不可能の原理はのちに熱力学の第1法則(エネルギー恒存の法則)と熱力学の第2法則(エントロピー増大の法則)に定式化され,第1法則で不可能になるような永久機関は〈第1種の永久機関〉,第2法則で不可能になるようなものは〈第2種の永久機関〉と呼ばれるようになった。従来の試みはおもに第1種の永久機関であったが,恒存されるエネルギーの熱に変わったものを元の力に戻すことができればエネルギー恒存の法則に矛盾しない永久機関が得られることになる。これは一つの物体から熱を取って冷やすことにより永久に作業する機関をつくることを意味するが,オストワルトが熱力学の第2法則に別の表現を与えるために仮想したものであって,最初から不可能であることが前提にされている。
こうして永久機関の試みはことごとく失敗したのであるが,その過程で自然に関する認識を深めさせたと言うことができる。また古来の永久機関開発の努力は,結局は人手を借りない自動機械の実現に向けられていたのであり,その基本方向は現在もなお進行中で実現しつつあるといってよいであろう。
→熱力学の法則
執筆者:坂本 賢三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「永久機関」の意味・わかりやすい解説
永久機関
えいきゅうきかん
永久に仕事をし続けることができるという、架空の動力機関。エネルギーの供給を受けないで仕事をし続ける機械を第1種(の)永久機関といい、ただ一つの熱源から熱(量)を吸収して、これをそのまま外部への仕事に変え続ける機械を第2種(の)永久機関という。この両者をまとめて永久機関という。
熱力学が確立される以前には、このような永久機関、とくに第2種永久機関は可能かもしれないと考えられ、いろいろ議論されたり、実験されたりしたが、それらは不可能であることが明らかとなった。しかし重要なことは、錬金術への幾多の試みが近代科学への道を切り開いたと同じく、この永久機関をつくろうとする努力の積み重ねによって熱力学が確立されていったことである。
[沢田正三]
第1種永久機関
熱力学ではまず、熱の性質は、力学的、電気的、磁気的、化学的エネルギーと同じく、エネルギーの一つの形態であることが示される。熱がエネルギーであれば、熱の場合も含めてエネルギー保存則が成り立つはずである。これは熱力学第一法則とよばれる。熱力学で取り扱うエネルギーはまず、物体系のもつ内部エネルギーについてである。熱力学第一法則は、一つの物体系の内部エネルギーは、この物体系に外部から加えられた力学的、電気的、磁気的、化学的エネルギーおよび同じく外部から加えられた熱と同等量だけ増大することを示す。したがって、外部からエネルギーの供給を受けなければ、内部エネルギーも増大せず、外部への仕事をなすこともできない。こうして、第1種永久機関は不可能であることが熱力学第一法則から証明される。
[沢田正三]
第2種永久機関
熱が関与する限り、自然界の法則はエネルギー保存則を満たす、というだけでなく、いっそう厳しく熱現象が一般には不可逆的であるという条件も付加される。これが熱力学第二法則である。たとえば、氷と沸騰している水を混ぜると、氷は溶けて、その水全体は、ある温度に落ち着くが、この逆に、この温度の水がひとりでに氷と沸騰している水に分かれることはない。熱力学第二法則を、熱力学の創始者の一人であるイギリスのW・トムソン(ケルビン卿(きょう))は次のように表現した。「ある物質が熱力学的なサイクル(カルノー・サイクル)をたどるとき、ただ一つの熱源から熱を吸収して、それを当量の仕事に変えるような熱機関はありえない」。同時代のドイツのクラウジウスは、同じ内容を「なんらかのほかの変化を残さずに、熱は低温物体から高温物体へ移ることはできない」と表現した。第二法則をそのように設定することは、とりもなおさず、第2種永久機関の不可能性を宣言したことにほかならない。われわれが実際につくりうる熱機関は、吸収した熱の一部分を放出し、その差の当量の仕事を外部にするのである。第1種永久機関はエネルギー保存則に反するために不可能であることは比較的理解しやすい。しかし第2種永久機関はエネルギー保存則には矛盾しない。それが不可能なことは、熱が物質を構成するきわめて多数の分子の運動の結果であることから説明される。熱力学第二法則に表された熱現象の特異な性質は、微視的立場にたつことによって十分に理解される。
[沢田正三]
化学辞典 第2版 「永久機関」の解説
永久機関
エイキュウキカン
perpetual motion
第一種と第二種の2種類がある.第一種の永久機関とは,外部に対して仕事をするのみで,ほかになんらの変化も残さないような循環過程をなす装置をいう.このような装置は古来種々工夫されてきたが,19世紀半ばごろ,J.R. Mayer,J.P. Joule,H. Helmholtz(ヘルムホルツ)らによって熱的現象を含めた一般的なエネルギー保存則(熱力学第一法則)が打ち立てられて,はじめて不可能であることが認められた.第二種の永久機関とは,一つの熱源から熱をとり,これを仕事に変えるばかりでほかになんらの変化も残さないような循環過程をなす装置をいう.この装置は,第一種の永久機関の存在を否定した熱力学第一法則を満たしているが,存在不可能であることが確立された.F.W. Ostwald(オストワルト)はこの意味で,熱力学第二法則として“第二種の永久機関は存在しない”といういい方を使っている.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
百科事典マイペディア 「永久機関」の意味・わかりやすい解説
永久機関【えいきゅうきかん】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「永久機関」の意味・わかりやすい解説
永久機関
えいきゅうきかん
「永久運動」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...