精選版 日本国語大辞典 「ライプニッツ」の意味・読み・例文・類語
ライプニッツ
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ライプニッツ」の意味・わかりやすい解説
ライプニッツ
らいぷにっつ
Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646―1716)
ドイツの哲学者、数学者、自然科学者。その業績は法学、歴史、神学、言語学の多方面に及び、さらに外交官、実務家、技術家としても活躍した。道徳哲学教授の子としてライプツィヒに生まれた。1661年ライプツィヒ大学で法律を学ぶこととなり、そのかたわら哲学や歴史にも興味をもった。1666年スイスのアルトドルフの大学に移り、翌1667年法律学の学位を得た。大学卒業後ニュルンベルクでマインツ侯国の有名な政治家ボイネブルクJohann Christian von Boyneburg(1622―1672)と出会い、以後マインツの国政に関係し、法典改革などに従事した。しかしこうしたうちにも力学の論文を作成し、これによってロンドンやパリの学界にその名を知られるようになる。1672年から外交上の仕事のためパリに滞在、そこで諸学者と交わり、当時の学問の先端に触れる機会をもち、とくに数学などの研究に没頭した。
しかし、1676年ヨハン・フリードリヒ侯Duke Johann Friedrich(1625―1679)からの招きに応じてハノーバーに向かい、以後ハノーバー公の図書館長兼顧問官の職につくことになる。後継者のエルンスト・アウグスト公Duke Ernst August(1629―1698)もその夫人、公女とともに彼を信任し、ハノーバー家の家系史の編纂(へんさん)をその仕事として課した。これらの君主たちは彼に対して理解があり、この時代に彼は学問的な研究をはじめ種々の活躍をした。たとえば1700年ベルリン科学アカデミーを設立し、その初代院長になっている。しかし1698年エルンスト・アウグストが死去し、その子ゲオルグ・ルードウィヒGeorg Ludwig(1660―1727)が後継者になってからは、ただ本来の課題である家系史の完成が催促され、あまり恵まれぬ晩年であった。『形而上学叙説(けいじじょうがくじょせつ)』(1686)、『弁神論』(1710)、『単子論』(1714、1715年ごろ作成、1720年ドイツ訳刊)などが哲学上の代表著作である。
このような学術的な研究活動とベルリン科学アカデミー創設、カトリックとプロテスタントの統一の試みなどの外的活動とは、一見ばらばらのようにもみえるが、その根底には一貫した姿勢がうかがえる。ひとことでいえば、それは神を背景にすべてのものに調和をみいだそうとする思想的努力であり、調和への確信である。そしてこの点は、以下のような彼の多元論的な調和の哲学体系にはっきりと現れている。
彼の哲学体系(単子論)では、まず単子(モナド)とよばれる新しい実体概念が導入され、世界は無数の単子から成立しているとされる。すなわち単子とは、不可分で単一的なものであるが、いわゆる原子とは異なり非延長的であり、表現représentationという非物質的な働きをその本質とするものである。そしてここでいう表現とは、単子がその単一性を保ちながらも単子自身の内なる素質に基づく自発的な展開によって、その単子にとっての外的世界(他の単子群)と対応するということであり、けっして外的世界との因果的な相互関係のようなものではない(「単子は窓をもたない」)。つまり単子は、この表現という働きの形で、多(世界全体)を己の内に含むような一であるともいえ、「宇宙の生きた鏡」ともよばれるのである。ところで、世界を構成する無数の単子は完全に同じものはなく、すべて互いに異なっているが、大きく3種に分けられる。混乱した表現をする物質単子(「裸の単子」)、意識と記憶を伴う霊魂単子、普遍的なものを認識する精神の単子である。そしてどのような単子からなるかによって、物質、動物、人間、神などの存在が考えられている。しかし同時にこれらは互いに不連続的な形で存在しているのではなく、連続的な系列をなしているとされている(「連続律」)。
さらにライプニッツは、それぞれの単子の自発的な展開があらかじめ神によって与えられていると考え、互いに独立し、相互に因果関係のない無数の単子からなる世界にも秩序と調和が成立しているとしたのである(「予定調和」)。したがって、単子の活動の総体としての現実の世界は彼にとって最善なものとみなされてくることにもなる(「最善観」)のである。
[清水義夫]
科学的業績
ライプニッツの数学上、自然科学上の活動は、1672年パリでホイヘンスに会い、また翌1673年、短期間であったが、ロンドンに滞在中、ボイルらの数学者との出会いから始まった。ロンドン滞在中、ニュートンの曲線を扱ううえでの数学的方法、いわゆる微積分法を聞いた。彼は1672年から1676年まで外交使節としてパリに滞在しているが、その間ホイヘンスの下で数学の研究に専念している。ニュートンとともに微分積分学の発展に決定的な役割を果たしたライプニッツの記号法は、この期間に培われた数学の研究によるものであった。なお、微積分法をめぐって、その優先権がニュートンとライプニッツのどちらにあるか、学界のなかで多年の論争が続いたことは有名である。
ライプニッツは多方面で仕事をしているが、なかでも重要な貢献は論理学、哲学と数学の分野である。ライプニッツは、イスパニアのレイモンド・ルルスの真理を発見する自動的方法をつくろうという考えを、いくつかの計算原理で置き換え、合理的に発展させようとした。学位論文「Dissertatio de Arte Cornbinatoria」(1666)は、その推論法則やその様式の整理を試みたもので、さらに数学の組合せについても論述している。さらに人間の思考過程を記号化し、記号間の演算によって完全な結論へと導くことを考えた。これは今日の命題計算の思想であった。ライプニッツにとってこの考え方は生涯つきまとった。論理学において、yがxのもっているすべての特性をもっているとき、xとyは同一であると定義する同一性の原理は、ライプニッツによるものである。また彼は、代数学が量の科学であるように、位置についての解析ができるような真の幾何学は構成できないかを研究した。この思想はのちに、線形代数やトポロジーへと発展した。
微積分法についてのライプニッツの研究は1673年から発表されだした。そこでは、曲線に接線を引く接線問題、つまり微分法、一方、逆接線の問題、つまり無限小を集める積分法の基礎を与えた。級数とその和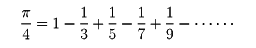
はライプニッツによって得られた。ベルヌーイ一家と文通し、有理関数の積分、簡単な微分方程式を解く方法を完成した。1693年には行列式の思想をもった。また関係、座標、算法など多くの用語を導入し、無限小に使う記号dx、積分記号∫はライプニッツによって考え出された。また、1682年から学術雑誌『Acta Eruditorum』を刊行している。
[井関清志]
『園田義道訳『ライプニッツ論文集』(1976・日清堂書店)』▽『石黒ひで著『ライプニッツの哲学――理論と言語を中心に』(1984・岩波書店)』▽『河野与一訳『形而上学叙説』(岩波文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「ライプニッツ」の意味・わかりやすい解説
ライプニッツ
Gottfried Wilhelm Leibniz
生没年:1646-1716
ドイツの哲学者,数学者。歴史学,法学,神学などについても重要な業績を残し,政治家,外交官など実務家としても活躍した。ライプチヒに生まれ,ライプチヒ大学で哲学を,イェーナ大学で数学を,アルトドルフ大学で法律を学んだ後,マインツ侯国の前宰相ボイネブルクJohann Christian von Boyneburg(1622-72)と相識り,1670年侯国の法律顧問官となる。侯国の外交使節として72年以降パリに滞在したが,このパリ派遣は,彼自身の起草になる〈エジプト計画〉(フランスの対外拡張政策,特にオランダ侵攻を阻止し,エジプト征服を勧めることによって,ひいてはドイツの安全を図ろうとするもの)を,ルイ14世に奏上することが直接の目的であった。この試みは実現しなかったが,彼はフランスの学者グループに仲間入りし,またイギリスにも渡り,R.ボイルを知るなどして刺激を受けた。オランダでのスピノザとの会見を経て,76年末ドイツに帰国,以後生涯変わることなくハノーファー家に司書官,顧問官として仕える。その間,ハノーファー家の系譜の歴史学的探求,そのためのイタリア旅行,ヨーロッパ各地でのアカデミー設立(自身1700年設立のベルリンのアカデミーの初代総裁となった),さらにカトリックとプロテスタント両教会の間の融和統一等の仕事に尽力する。その膨大な著作の大半は,現在においても未刊の断片的草稿のままに,ハノーファーの〈ライプニッツ文庫〉に日の目を見ずに保存されている。刊行されたもののうちまとまりのある主要な著作は,《形而上学叙説》(1686),《新人間悟性論》(1704),《弁神論》(1710),《単子論》(1714)等である。
哲学
ライプニッツ哲学の根本的特質は普遍的調和(予定調和)の思想と個体主義にある。論理・認識思想に関しては,思考のアルファベットと結合法の思想にもとづく普遍学の理念,および認識の経験論的理説と合理論的理説を独自に統一した表出説が重要である。自然学思想ではライプニッツに特有の力動的な活力の概念の発見(力動説)のうちに,デカルトの静力学的自然学に取って代わるべき新たな力学説の成立を見ることができよう。これらを基礎として単子論的形而上学思想(モナド)が確立されるに至った。ライプニッツが物体の形相的要素とみなす根源的力は,物質における運動の力動的原理であり,自然現象の連続性と多様性の条件である。すなわち宇宙が秩序も統一も欠く混沌ではなく,また多様な変化の認められる余地のない同質的集塊でないために,物質のうちに根源的力がなければならず,実体の活動が多様な変化の現象を可能にするのでなければならない。ライプニッツは原子論(アトミズム)の批判によっても同一の結論に達した。真に実在するものは不可分であり不滅である。真に〈一なる〉存在でないものは,真に〈存在する〉ものではない。同質的で無限に可分的な物質的アトムは理性に反する。実体の不可分性は形相の不可分性である。それゆえ形相的アトムは魂に類似したものとして把握されうる。すなわち生命,エンテレケイア,魂が物質の最小の部分のうちにも存在するのである。この意味でライプニッツの形而上学説は汎心論もしくは汎生命論とも呼ばれうる。なお,彼の哲学はライプニッツ=ウォルフ学派により,一面的にではあるが継承された。
執筆者:増永 洋三
数学,自然学
ライプニッツは,大学時代にはほんの初等的な幾何学・算術を学んだにすぎなかったが,学位論文《結合法論考》(執筆1666)における普遍記号法の理念は後年,数学・論理学の革新を計る際開花することになる。数学における能力はパリ滞在期に大きく飛躍する。当時アカデミー・デ・シアンスの中心的科学者であったホイヘンスやローヤル・ソサエティの知識人たちによってヨーロッパの第一線の知的世界に導かれたためである。最初の数学の天分は計算機作製において示された。この計算機は加減乗除の四則演算が可能となるように計画されたものであった。また73年以降,求積法・接線法の研究を急速に発展させ,手初めにパスカルの無限小幾何学についての著作から示唆を受けて円の算術的求積に成功し,円周率の無限級数展開に関する〈ライプニッツ公式〉(π/4=1-1/3+1/5-1/7+……)を得た。さまざまな求積問題・逆接線問題にとり組む中から,76年秋までには今日の微分記号dや積分記号∫を用いる微分積分法の概念に到達したものと思われる。この成果は84年から徐々に公表された。ライプニッツ的微分積分法の特質はすぐれた記号法によった点にある。今日の位相幾何学の考え方にも通ずる《位置解析について》の書簡をホイヘンスあてにつづっている(1679)が,ホイヘンスはこれに好意的でなかった。このように同時代人は必ずしも代数的普遍記号法の理念を歓迎したわけではない。ニュートンなどイギリスの数学者たちがライプニッツ的数学を受け入れたがらなかった理由の一つも,このような記号法的特質のためであった。だが,96年のロピタルの微分法の教科書《曲線の理解のための無限小解析》がライプニッツ思想にもとづいて書かれたのをかわきりに,ベルヌーイ兄弟,バリニョンPierre Varignon(1654-1722)など大陸の数学者たちはライプニッツ的記号数学を普及させた。ライプニッツ的形式主義は論理学の変革にも力を及ぼし,論理学は論理計算に改変させられた。この試みは19世紀末以降,数学的論理学者たちによって再評価された。彼はまた二進法,行列式の考えにも到達していたことが今日ではわかっている。
自然学においては,デカルト学派が運動量(質量と速度の積mv)保存の法則を動力学の世界にもち込もうとしたのに反対し,保存されるのは〈活力〉(mv2)であると主張,活力論争をひき起こした。デカルトと同じく機械論的哲学を基本的には支持しながらも,独断的な機械論には反対であったものと思われる。ニュートン学派のS.クラークとも論争し,ニュートン的神,絶対時空概念を批判した。彼の相対的時空論は現代の相対性理論的観点から高く評価されている。ライプニッツ哲学はカント以降ほとんど見捨てられたものの,以上のような個々の科学的言明は後代に大きな影響を及ぼしたわけである。
執筆者:佐々木 力
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「ライプニッツ」の意味・わかりやすい解説
ライプニッツ
→関連項目オプティミズム|キルヒャー|根拠律|主意主義|生気論|ニュートン|微分積分学|ベルヌーイ|力動説|ルルス
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ライプニッツ」の意味・わかりやすい解説
ライプニッツ
Leibniz, Gottfried Wilhelm
[没]1716.11.14. ハノーバー
ドイツの哲学者,数学者。12歳のときほとんど独学でラテン語に習熟。1661年ライプチヒ大学に入学,法学と哲学を学ぶ。1666年アルトドルフ大学で法学博士号を取得。1667年からマインツ選帝侯に仕えて政策立案などを行ない,1672年にフランスのパリに派遣された。1676年帰国して死ぬまでハノーバー侯に仕えたが,晩年は不遇であった。広範な問題を取り扱ったが,数学では 1675年独自に確立した微積分法がある(→微分,積分)。また彼の哲学はクリスティアン・ウォルフによって変形されつつ体系化され,普及してドイツ啓蒙主義の主潮であるライプニッツ=ウォルフ学派を形成した。主著『形而上学叙説』(1686),『人間悟性新論』(1704),『弁神論』Essais de théodicée(1710),『単子論』(1714)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
図書館情報学用語辞典 第5版 「ライプニッツ」の解説
ライプニッツ
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
占い用語集 「ライプニッツ」の解説
ライプニッツ
出典 占い学校 アカデメイア・カレッジ占い用語集について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「ライプニッツ」の解説
ライプニッツ
Gottfried Wilhelm Leibnitz
1646~1716
ドイツの哲学者,数学者。諸学に優れ,政治,外交などにも活躍した。微分・積分学の創造,『単子論』『弁神論』などの哲学的著作のほか,その論理学上の業績は記号論理学の先駆をなすものとして重視されている。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「ライプニッツ」の解説
ライプニッツ
Gottfried Wilhelm Leibniz
ドイツの数学者・哲学者・政治家
数学では微積分法を発見。哲学では『単子(モナド)論』を著し,予定調和の哲学を樹立。宗教対立の融和につとめたほか,マインツ選帝侯国の外交官になるなど,活躍は多方面にわたった。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のライプニッツの言及
【エネルギー】より
…この意味で彼らはI.ニュートンの運動の法則のまさに一歩手前まで到達していたといってよい。これに対し,86年にG.W.ライプニッツは当時の常識であった〈運動する物体のもつ力は物体に固有のものでなければならぬ〉という考えから,mv2という量こそがこの“ちから”を表し,宇宙全体で保存されるのはこの量の総和であるとし,静力学のつり合いで現れる“死んだ力vis mortua”に対して,これを“活力vis viva”と呼んだ(なお,C.ホイヘンスもこれに先だって複合振子の取扱いでmv2という量を使ったが,とくにその重要性を強調することはしなかった)。ライプニッツの議論は次のようなものであった。…
【オプティミズム】より
…ラテン語のオプティムスoptimus(最善の意)に由来し,世界や人生の価値や意義を究極的には肯定的に認める立場をいい,日常の用語としては,ものごとや事態のなりゆきをすべて良い方向に考える心理的傾向をいう。哲学の分野では古来諸種のタイプが知られるが,ライプニッツの学説に見られる考え方が典型的である。ライプニッツによれば,神は神の知性のうちにあるすべての可能な世界のうちから,最善の世界を選び創造した。…
【空間】より
…その意味では,空間は,存在論的にいっさいの事物に先行するものであり,その点で〈絶対的〉でもあることになる。一方これに対して,アリストテレス的な関係論的解釈を洗練徹底し,ニュートンの絶対主義的な空間解釈と対立したのはライプニッツであった。ライプニッツは,事物の存在に存在論的に先立つ空間という考え方を否定し,事物の存在に伴って初めて現れるさまざまな関係(順序,位置など)がわれわれに空間という概念を与えるにすぎないと考えた。…
【偶然】より
…それは,〈もっとも完全なる者〉という神の本質にはいかなる欠如もありえず,したがって〈存在しない〉ということもありえない,つまり必然的に存在せざるをえないのに対して,被造物は存在しないことも可能であり,その存在が神の意志,つまり他の存在者に依存しているからである。(2)ライプニッツは,〈三角形はその和が2直角に等しい内角を有する〉というような,その反対が不可能である事態およびその認識を〈必然的真理(理性の真理)〉とよび,それに対して〈カエサルはルビコン川を渡った〉というような,その反対が必ずしも不可能ではない事態およびその認識を〈偶然的真理(事実の真理)〉とよんだ。(3)個々のできごとに関しても必然的―偶然的ということが言われる。…
【計算機械】より
…フランスの哲学者,数学者B.パスカルは,父親の煩雑な税務計算を助けるために,42年に歯車式の加減算機を作り,その後10年間に数十台を試作・製作した。ドイツの哲学者,数学者G.W.ライプニッツも,1671‐94年にかけて加減乗除のできる計算機を試作している。これは,加減算を行う操作ハンドルを回転することによって乗除算を実現するものであった。…
【爻】より
…卦中における爻の位置に関して〈位〉〈中〉〈正〉〈応〉〈比〉〈承〉〈乗〉といった,易学特有のタームが使われる。なお,二進法の原理を創始したドイツの哲学者ライプニッツは,易の卦につよい興味をいだき,![]() を0,
を0,![]() を1に数式化した。現代のコンピューターが0と1との二進法を基礎にしていることを考えるとき,易は案外現代的なメカニズムを備えているといえるかもしれない。…
を1に数式化した。現代のコンピューターが0と1との二進法を基礎にしていることを考えるとき,易は案外現代的なメカニズムを備えているといえるかもしれない。…
【根拠律】より
…充足理由律,理由律とも言われる。矛盾律と並ぶ二大原理としてライプニッツによって提唱されたもので,〈何ものも根拠のないものはない〉という形で表現される。その意味するところは〈一つの事物が存在し,一つの事件が起こり,一つの真理が生ずるためには,十分な根拠がなければならない〉ということであり,したがってこれは論理学的原理であるとともに形而上学的原理でもある。…
【時間】より
…ただ,後世この概念が,時間の問題を論ずるためにはしばしば援用されるようになったことは事実である。例えばニュートンの代弁者S.クラークとライプニッツとの著名な論争のなかでもニュートン的時間とライプニッツ的時間の対立は鮮明である。この論争では,ニュートン的時間は,事物の存在や変化とは独立に措定されるべきものとして主張されており,ライプニッツ的時間は,事物の生起する順序関係の結果として構成されるものと主張されている。…
【自由意志】より
…デカルトは自由意志を理性活動にだけみとめて,理性的である限り意志の自律と自足を主張した。カントはライプニッツとともに自然の因果性を超える自由の事実(ライプニッツのいう〈事実の真理〉)をみとめ,これを神,不死とならんで道徳のための要請とした。理性的存在者の道徳的行為は自由の要請のもとで,自律的な〈定言的命令〉に従う限りで成立するのである。…
【神義論】より
…ライプニッツが最初に用いた哲学・神学用語。〈弁神論〉ともいい,世界における悪の存在が神の全能と善と正義に矛盾するものでないことを弁証しようとする議論をいう。…
【人工言語】より
…またキルヒャーは暗号術とルルスの〈要約術〉を基礎として,異言語の交流を可能にする〈新複式記述法〉を提案した(1663)。ライプニッツも数学における数字をモデルに,〈組合せに応じて新たな真理が自動的に表現されうる〉記号論理学的な人工言語の創造を夢見た。彼はその過程で,0と1だけで全数字を表現できる二進法の卓越性を確信したが,今日のコンピューター言語は二進法による人工言語システムの成功例ともいえよう。…
【数学】より
…パスカルは晩年書き残した宗教的断章によって知られる思想家でもあった。 しかしこの世紀の数学史,科学史上のもっとも大きな人物としては,R.デカルト,I.ニュートンおよびG.W.ライプニッツを挙げるべきであろう。 デカルトは,近世合理主義の基礎を定めた哲学者である。…
【数理哲学】より
…近代においては,数学者で同時に哲学者であるという人が多いために,近代数学形成の内部において哲学的思索がなされた。17世紀においてはデカルトとライプニッツが特に注目される。デカルトは記号的代数学を発展させ,その方面で近代数学の真の建設者となった。…
【生気論】より
…それは活動力ないし対話の対象とみなされたので,エネルギー概念および情報概念の先駆とも見られる。この思想的伝統はヘルメス思想の中に生き続け,ライプニッツの活力説(彼は力=エンテレキアentelechiaを実体とした)を経て,19世紀ドイツの〈自然哲学〉にまで及んだ。すなわちシェリングは〈自然は目に見える精神,精神は目に見えない自然である〉と主張し,ロマン派の思想家はさらに民族精神や世界精神についても語った。…
【精神】より
…そのため,デカルト以後の近代初期の哲学においては,これら異なる秩序に属する心身がどのような関係にあるのかという問題をめぐって,相互作用説,平行論,機会原因論,予定調和説など多様な仮説が提出されることになる。 一方,アリストテレスやその流れをくむ中世スコラ哲学,そして近代においてもライプニッツらは,精神を超自然的秩序に属する実体としてではなく,できるかぎり自然の内部でとらえようとし,したがって心身の関係も連続的ないし階層的に考えようとする。アリストテレスは身体を質料(ヒュレ),精神をそこに宿る形相(エイドス)と見るが,これは現代風に言いかえれば,精神を身体に宿る高次の機能と見るということになろう。…
【多元論】より
… 一と多との対立はピタゴラス学派,クセノファネス,パルメニデスとヘラクレイトスとの対立に起源するが,多元論者の代表は哲学史上,古代では,世界を構成する地・水・火・空気の四根rizōmataの愛・憎による結合・分離を説くエンペドクレス,無数の種子spermataを精神nousが支配して濃淡・湿乾などが生じ世界を成すとするアナクサゴラス,形・大きさ・位置のみ差のある不生不滅で限りなく多数の原子atomaが,空虚kenonの中で機械的に運動して世界が生じるとするデモクリトス,さらにはエピクロスなどを挙げることができる。近世では,表象能力と欲求能力とを備えて無意識的な状態から明確な統覚を有する状態まで無数の段階を成すモナドを説くライプニッツ,近代ではその影響下にあって経験の根底に多数の実在を認め心もその一つとするJ.F.ヘルバルト,真の現実界は物質界を現象として意識する自由で個体的な多数の精神的単子から成ると説くH.ロッツェなどである。さらにまたW.ジェームズは自己の根本的経験論は多元論であり,世界はどの有限な要素も相互に中間項によって連続せしめられており,隣接項とともに一体を成しているが,全面的な〈一者性oneness〉は決して絶対的に完全には得られぬとして,多元論の立場から多元的宇宙を説き,一元論的な絶対的観念論の完結した全体的な宇宙観を退けた。…
【力】より
…彼はそれを物体の速さと大きさの積として定義し〈運動の力vis motus〉と呼んだ。ライプニッツは,あらためてそうした力を〈活力vis viva〉と呼んで,質量と速さの2乗との積で定義し,デカルトを批判した(ウィス・ウィウァ論争)。現在の古典力学では,物体に外から与えられ,運動の変化(加速度)を生じさせる原因を力として定義するため,ある意味ではデカルトの態度,つまり,物質およびその運動状態から力を構成しようとする発想が最も徹底されている,と考えることができる。…
【パースペクティビズム】より
…〈遠近法主義〉と訳される。18世紀初頭にライプニッツが〈単子論〉を説き,すべての単子(モナド)はそれぞれの視点から,それぞれの表象能力に応じて全世界をおのれのうちに映し出すと主張した。1880年代にニーチェが,すべての存在者の根本性格を〈力への意志〉と見るその最後期の思想においてこの考えを受けつぎ,認識とはけっして客観的な真理の把握などではなく,〈力への意志〉を本質として不断に生成しつつある存在者が,その到達した現段階を確保せんがために,それぞれの力の段階に応じて遠近法的に世界を見る見方にすぎないと主張した。…
【微積分学】より
…微積分学は微分学(微分法)と積分学(積分法)とを合わせた名称であるが,この二つは別々に考えるべきではなく,いっしょに考えるべき数学の体系であるから,両方を合わせて微積分学,あるいは略して微積分という。微積分は1670年ころにI.ニュートンとG.W.ライプニッツによってほとんど同時に発見された。発見の当初には,2人のうちどちらの発見が早かったか,またどちらかが他方の発見を知っていたのではないかということについて,激しい論争があった。…
【表象】より
…個人によってそのいずれかの優位が認められるのである。 さらに,この語の現代の用法からみると例外的であるが,ライプニッツの哲学にあっては表象はperceptioの訳語としても用いられる。ライプニッツはすべての存在者の究極の構成要素つまり実体を〈単子(モナド)〉と呼び,その基本的属性を〈欲求appetitus〉と〈表象perceptio〉にみる。…
【複雑系】より
…きわめて単純な方程式の計算を反復することによって,定数の変化とともに無限な多様性が出現する決定論的カオスは,従来の〈単純なものは単純なものから,複雑なものは複雑なものから〉という,西洋思想を規定してきた発想を打ち破ろうとしている。そして,例えばスピノザとライプニッツの間で戦われた〈偶然〉の本質をめぐる議論の意味にも,新たな光があてられることになるだろう。 この思想史上画期的な視点を無にしないためにも,(1)(2)の両側面の往復運動の中で,単純な法則と複雑な現象の関係について細心の注意を払いながら,複雑系研究が進められることが望まれる。…
【目的論】より
…彼は,中世スコラ哲学以来の目的論的有機的原理にもとづく自然現象の説明を徹底的に排して,人間を別とするすべての動物は,一つの機械とみなしうることを説いた。一方,前述のウォルフの師にあたるライプニッツは,それを批判して,いわば機械論的パラダイムのホームグラウンドともいえる力学においてすら,一種の目的論的原理を復権することなしに事象の十分な解明はありえぬことを主張して,大きな反響を呼んだ。ここには,原子論的発想にたいする全体論的発想,幾何学主義と代数主義,決定論と自由論,因果論と表現論といった,時代を超えて現代にまでおよぶ基本的な発想の対立の幾組かが複雑にからんでおり,機械論的思考と目的論的思考の対立が,ある文脈においては今日なお開かれた問いであることを早くも予示している。…
【論理学】より
…(4)近・現代――近・現代論理学は記号論理学ともいわれる。記号論理学は早くも17世紀に,ライプニッツによってその口火がきられたが,実質上の成立は,イギリスの数学者兼論理学者であるG.ブールの著《論理学の数学的分析》(1847)においてである。ブールによる論理学の数学化・記号化の試みは,一方においてはブール代数という形でコンピューターの基礎理論にまで発展し,他方では記号論理学という形で現代最新の論理学にまで発展する。…
※「ライプニッツ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

