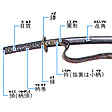鐔/鍔 (つば)
古くは〈都美波〉として《和名抄》は〈つみは〉と読んでいる。刀身と柄の境にかけ,敵の刃から拳を守った。古墳時代の大刀(たち)には環頭大刀,頭椎大刀,圭頭大刀などがあるが,その鐔は金銅あるいは鉄製で,多くが倒卵形をし,車輪状に透かしを施したり,鉄には金・銀で渦巻文を象嵌(ぞうがん)するなど,装飾を加えたものもすでにみられる。奈良時代では,正倉院に伝わる太刀の鐔をみると,概して形は小さく,単なる板金製のほか,唐大刀(からたち)形式の作には分銅形の唐鐔(からつば)が用いられている。平安時代に入ると太刀は儀仗用と兵仗用とに使い分けられるようになるが,鐔も同様で,儀仗用の飾剣には唐大刀の形式を受けついで唐鐔が使われた。一方,兵仗用の毛抜形(けぬきがた)太刀や兵庫鎖太刀には葵鐔,粢鐔(しとぎつば)が用いられた。葵鐔は四葉形の4辺の中央に稜をたてた形で,江戸時代の武家所用の糸巻太刀まで長く使用されている。粢鐔は神饌用の粢餅の形から名づけられたもので,楕円形をなし,後に馬具の障泥(あおり)の形状によく似るところから障泥形ともいわれている。兵庫鎖太刀にみる粢鐔は,鞘(さや)や他の金具と同一文様を彫った大切羽(おおせつぱ)を組み合わせたもので,当時の鐔の中で最も高度な技術をみせている。また,同じ兵仗の黒漆太刀や革包太刀には,鉄の薄板を心にして革で包んだ鐔,革を数枚張り合わせて漆で固めた鐔も出現し,鎌倉時代から室町時代にかけて盛行した。
室町時代の末期には,太刀の佩用(はいよう)がすたれて打刀(うちがたな)が流行するが,鐔も打刀用となった。その初期には刀匠自身や甲冑師によって作られた鐔があるが,それらは鉄の板鐔で,小さな透彫(すかしぼり)を加えた程度の素朴な作であった。室町末期から桃山時代にかけて,山城国伏見の地に鐔の専門工として金家が現れ,鐔にはじめて絵画風の文様を表した。ほぼ同じころ尾張に信家がおり,鍛えのよい鉄鐔に,毛彫で文字や草花を巧みに表現した。桃山時代に入り,京や尾張に透彫の鉄鐔をもっぱら製作する集団があり,従来の透彫鐔に一段の進歩をみせた。また山城西陣の埋忠(うめただ)明寿は各種の色金を用いて文様を平象嵌の技法で表し,色彩的な変化を与え,さらに平田道仁は七宝技術を取り入れ,ますます装飾性を加えることとなった。
江戸時代初期には九州肥後に肥後金工が繁栄し,林,西垣,志水,平田の諸派が大きな勢力を誇った。これらは細川家の抱工として,武人好みの意匠と象嵌,透彫の技法に特色をみせている。江戸中期になると太平の世となって,鐔も他の装剣金具と同様にますます華美となり,高彫色絵や象嵌のほか,肉合(ししあい)彫,片切彫など新しい技法が開発された。横谷宗珉は後藤家流の技法を汲む家に生まれながらその作風にあきたらず,構図に新生面を築いたほか,片切彫を創始し,以後の工人に大きな影響を与えた。また奈良三作の土屋安親,奈良利寿(としなが),杉浦乗意も斬新な意匠と独自の彫技をみせている。安親は鐔の形,意匠に,利寿は雄渾な高肉象嵌・色絵に,また鐔の作は少ないものの乗意は肉合彫の創始者として名工の名をほしいままにした。中期以後は江戸,京をはじめ各地に流派が生まれ,時代の好尚を受けた華美なものが多く製作された。しかし濃厚に過ぎたり繊細におちいるなどで雅趣の乏しいものも少なくなかった。浜野政随・矩随,大森英秀・英満,石黒政常・政美,岩本昆寛,染谷知信,鉄元堂正楽,大月光興,藻柄子宗典らが著名である。幕末には後藤家の掉尾を飾る一乗(1791-1876)が,原則として鐔を製作しなかった後藤家一門にあって鐔の製作に乗り出し,格調ある作風を展開した。また加納夏雄は対象を写生画風に鉄鐔に表現して独自の作風を樹立した。1876年(明治9)の廃刀令後は鐔は無用となったが,輸出品として製作された。だがこれらは装飾過剰で,実用にはならないものであった。
→装剣金具
執筆者:原田 一敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
鐔
つば
刀装の一具。鍔とも書く。『本朝軍器考』には都美波(つみは)の音の詰まったものとあるが明らかではない。鐔は柄(つか)を握る手が刀身のほうへ滑らないため、また相手の攻撃から自らの手を保護するための盤状の装具であるが、最大の役割は刀剣のバランスを整えることにある。古今を通じて大小、形状、材質、技法とも変化に富み、奈良時代までは小さく、分銅(ふんどう)形のものなどもあるが、それ以降は直径8~11センチメートル程度で、円形を基本に角形、撫角(なでがく)形、木瓜(ぼけ)形、葵(あおい)形などがある。材質は鉄が主であるが、銅、黄銅、朧(おぼろ)銀、金銅などのほか、鎌倉・室町期には鉄板を革で包んだり、数枚の革を貼(は)り合わせて漆で固めたものなども出現した。加飾技法としては透(すかし)彫り、鋤出(すきだし)肉彫り、片切(かたきり)彫り、毛彫り、肉合(ししあい)彫り、平象眼(ひらぞうがん)、布目(ぬのめ)象眼、色絵など種々の金工技法が駆使されている。
古墳出土の直刀(ちょくとう)につく倒卵形の鐔や、奈良時代以降の文官が佩用(はいよう)した儀仗太刀(ぎじょうたち)(飾剣(かざたち))につく唐様式の唐(から)鐔、また平安時代以降の武官の兵仗(ひょうじょう)太刀(衛府(えふ)太刀)につく葵(あおい)鐔など太刀拵(ごしらえ)の金具の一具としてのものや、これら太刀に用いられた練革(ねりかわ)鐔とか障泥(あおり)形鐔などは別にして、現在一般に鑑賞の対象としている鐔は、室町時代以降の、太刀にかわって刀剣の主流を占めるに至った打刀(うちがたな)(日本刀)につく鐔である。
打刀鐔には、初めは単なる丸形の鉄板鐔であったものに梅や桜の小透(こすかし)がつけられて透鐔に発展していった系統と、高彫りや毛彫りを施した太刀鐔から変化したものとの二様があり、やがてこの両者が相混じって、単に刀装の一具としてでなく独立した工芸品へと発展を遂げ、室町中期になって正阿弥(しょうあみ)のような鐔造りの専門金工が現れた。この一派は江戸時代には伊予、京、会津、庄内(しょうない)、江戸をはじめ全国的に広がる最大の流派となっている。ちなみに専門金工の出現する前の室町前期には、甲冑(かっちゅう)師や刀匠が余技的に鐔を制作したといわれ、その作品も現存しているが、これは分類上の仮説であって、実証されたわけではない。室町後期では、後藤祐乗(ごとうゆうじょう)の名も特筆される。後藤家はのちに多くの分家を擁し、明治まで17代続いて、日本の刀装ならびに彫金に多大の影響を及ぼした。
桃山期になると、厚手の鐔に独特の毛彫り文様を施す信家(のぶいえ)、絵画的構図を得手とした金家(かねいえ)、色彩に富む色金を使い平象眼で文様を表現する埋忠明寿(うめただみょうじゅ)などが現れ、鐔の芸術性を一挙に高めている。京透鐔、尾張(おわり)透鐔、古萩鐔などの透鐔も桃山期初期のものである。
江戸期に入るとまず九州肥後(熊本県)に肥後鐔がおこって、林、西垣、志水、平田などの諸派が繁栄するが、一般に鐔などの装剣金工に名人上手といわれる人物が輩出したのは江戸後期になってからで、元禄(げんろく)を過ぎて刀鍛冶(かじ)が急速に衰退したことに反比例している。後藤家の流れをくむ江戸の横谷宗珉(よこやそうみん)、奈良三作といわれた利寿(としなが)、乗意(じょうい)、安親(やすちか)、京の一宮長常(いちのみやながつね)、また幕末には後藤一乗、加納(かのう)夏雄などの名工を数える。透鐔には赤坂鐔、長州鐔、越前(えちぜん)記内などに優作が多い。1876年(明治9)の廃刀令後には、とくにみるべき作品はない。
[小笠原信夫]
『小笠原信夫著『鐔』(保育社・カラーブックス)』▽『若山猛著『刀装小道具銘字大系』全3巻(1978~1979・雄山閣出版)』
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
鐔
つば
鍔とも書き,刀盤ともいう。柄 (つか) を握るこぶしを防護するため,刀身と茎 (なかご。→刀 ) の境である区 (まち) にかける刀装具。古くは上古時代古墳出土の『金銅装環頭大刀』や頭椎大刀 (かぶつちのたち) の金銅倒卵形鐔,鉄装頭椎大刀の鉄製倒卵形鐔がある。奈良時代の鐔はその様相を一変して,正倉院宝物の『金銀鈿荘唐大刀』にみられるように分銅形の唐鐔がつき,『金銀荘大刀』の類には金銅帽額形鐔や木葉形鐔,『黒作大刀』の鐔はすべて分厚い鉄喰出鐔である。平安時代以降公家儀仗の飾太刀,細太刀の鐔は唐鐔をもっぱら用い,武家太刀の黒漆太刀や革色太刀には練り革の帽額形鐔がつき,兵庫鎖太刀には金銅猪目透かしの四葉形鐔 (葵鐔) を普通とする。室町時代末期以降,太刀と腰刀に代り打刀 (うちがたな) と脇差の盛行によって,鐔の材質や意匠にも画期的な変化が起り,また鐔,小道具を専業とする金工が出現,諸国に各流派が発展した。鐔に作者銘を切るようになったのも室町時代末期からである。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の鐔の言及
【金属工芸】より
…金属を素材として作られた日常品や装飾品,またその加工技術で,一般に金工と呼ばれている。人類が金属の使用を開始した時期は非常に古く,前5000年ころのエジプトですでに金と銅の使用が知られている。金属のうち金,銀,銅,隕鉄は最も早くから人類が採取した自然金属で,はじめは天然の状態のものを打ったり切ったりして使用していたが,やがて冶金技術が発達すると同時に鋳造技術もおこり,銅,錫(すず),鉛,アンチモンなどが鉱石から採取されるようになり,青銅,白銅など銅合金が作られるようになった。…
【古墳文化】より
…古墳時代は弥生時代に継続する時代である。弥生時代に始まった農耕生活は,比較的はやく,日本の大部分の地域にひろがっていったが,さらに鍬,鎌などの農具に鉄の刃先を使用するようになるまでには,若干の年月が経過した。やがて鉄器の普及などによって耕地の拡張がさかんになり,生産量はしだいに増大していった。古墳時代は,こうした経済力の上昇が,ついにこの国土に国家としての統治形態の出現を導くにいたった時代である。また,国家的統一の進行にともなって,その統治機構のなかに組みこまれていった首長層と,一般の農民とのあいだにみる生活状態の差違が,大きくひらいてきた時代である。…
【大刀】より
…長大な刀。横刀とも書く。〈たち〉は〈断ち〉の意味という。大刀,横刀は記紀の用字であって,小刀,刀子と書く〈かたな〉と対比して用いた。《日本書紀》天智天皇3年(664)2月条に〈大氏の氏上には大刀(たち)を賜う。小氏の氏上には小刀(かたな)を賜う〉とあるのは,その例である。しかし,一方では大刀と書いて〈つるぎ〉と読むこともあって,記紀では大刀と剣との形の区別は厳密でない。また,古墳時代から奈良時代までの,主として直刀に属するものを〈大刀〉と書き,平安時代以降の外反り(そとぞり)刀を〈[太刀]〉の文字であらわすのが習慣であるが,考古学用語としては,古墳時代の内反りの素環頭(そかんとう)大刀も,便宜上〈大刀〉と書いている。…
【刀剣】より
…刀は切るに便利な片刃の武器であり,剣は突くに便利な両刃の武器である。日本でも《和名抄》調度部征戦具に,刀は〈似剣而一刃曰刀〉,剣は〈似刀而両刃曰剣〉とあるように,片刃のものを刀,両刃のものを剣として,形体を区別するものであった。したがって刀剣といった場合,広義には打物武器を汎称するものであり,剣,大刀(たち),[太刀](たち),[刀],[脇指](わきざし),短刀などのことをいい,そのほか槍(やり)や薙刀(なぎなた)なども含まれる。…
※「鐔」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by