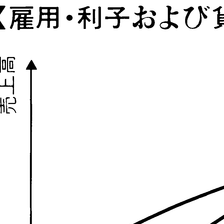改訂新版 世界大百科事典 の解説
雇用・利子および貨幣の一般理論 (こようりしおよびかへいのいっぱんりろん)
The General Theory of Employment,Interest and Money
イギリスの経済学者J.M.ケインズの主著。1936年刊。その出版は経済学にケインズ革命と呼ばれる革新の波を生ずるとともに,第2次大戦後の世界各国の経済政策の考え方に大きな影響を与えた。経済学者J.R.ヒックスは,20世紀中葉の第3四半世紀は後世〈ケインズの時代〉とみなされるようになるにちがいない,と述べている。
《一般理論》成立の背景
1929年の世界的な大恐慌はイギリスにも大きな影響を及ぼし大量の失業が生じた。これに対して,後にケインズの論敵となったA.C.ピグー,D.H.ロバートソンらを含めて多くの経済学者は失業救済のための公共事業を支持したが,政府とくに大蔵省を説得して積極政策に転換させるまでには至らなかった。31年,ケインズの小冊子〈ロイド・ジョージはそれをなしうるか〉に触発され,R.F.カーンは,政府が公共投資を行って一定数の人を雇用すると,その人の収入が支出され,それが生産を高めて,さらに雇用を増大するというようにして,政府が最初に雇用した数倍の雇用が生ずるという〈乗数の理論〉を展開した。この乗数理論は失業対策としての公共投資に理論的根拠を与えることになった。同時に,これはまた《貨幣論》(1933)の出版後,同書に対して加えられた批判に答える必要を感じていたケインズに新著を書く契機を提供することになった。
《一般理論》の考え方
成立の事情からも明らかなように,《一般理論》の狙いは,産出量と,生産に必要な雇用量の変動に焦点をあて,その決定要因を分析することであった。《一般理論》が〈一般〉理論と名づけられたのは,古典派の理論が完全雇用という特殊な場合にしか妥当しないのに対して,その理論は失業が存在する場合にも妥当する一般理論であるという趣旨である。つまり,古典派の理論では,土地・労働・資本といった資源がさまざまな用途に配分され,配分された資源はすべて有効に利用されるという(完全利用・完全雇用の)前提のもとで,それらの資源に対する報酬,生産物の相対価格がどのように決定されるかという問題を取り扱い,なにが利用可能な資源の実際の使用量を決定するかという理論をもたなかったのに対して,なぜ失業や設備の遊休が生ずるかを明らかにしている点に《一般理論》の第1の特徴がみられる。
この点について《一般理論》は,雇用量ないし産出量は,財に対する総需要と総供給との関係によって決定されるものであり,失業の原因は,有効需要(〈有効需要の原理〉の項参照)の不足にほかならないと主張したのである。
いま,企業がN人を雇って生産を行い生産物を販売することによって得られると期待される売上高を総需要と呼ぶことにしよう。総需要は雇用量に依存し,雇用量が増加すれば増大する。この関係をグラフで示したのが図のD-D曲線である。他方,技術や資源が与えられた場合,企業がどれだけの雇用を行うかは,雇用によって生ずる生産物の売上高の期待値(これをケインズは総供給価格と呼んだ)に依存し,期待値が増大すれば雇用は増大する。この関係をグラフで示したのがS-S曲線である。雇用量は,この二つの売上高の期待値が一致する点,つまり需要曲線と供給曲線の交点に決まる。しかし,このようにして決定される雇用が完全雇用と一致する保証はない,というのがケインズの主張である。
ところで,総需要は,消費と投資という二つの部分に分けられる。いま,人々の消費性向が変わらないとすれば,雇用量が増え,所得が増えるにつれて消費は増大するが,所得ほどには増えない。したがって所得が増え,所得と消費の差つまり貯蓄が増えるのにつれて自動的に投資が増えないかぎり,需要曲線は供給曲線を下回る。そこで,投資水準が与えられると,それに応じて所得したがってまた雇用の水準が決まるというのが《一般理論》の基本的な考え方であり,〈貯蓄に等しい投資が自動的に生み出される〉とか,〈供給はそれ自身の需要をつくり出す〉という意味での〈セーの法則〉を否定したところに,その特徴がみられる。
投資が増加すれば総需要が増大し,需要曲線が右上方に移動することになり,需要曲線と供給曲線の交点は右上方に移り,雇用量は増大する。このとき,最初の投資の増加に対して数倍の所得の増加が生ずる。これが乗数効果である。
ところで,投資は資本の限界効率と利子率によって決定されるが,資本の限界効率は企業家の,将来についての〈期待の状態〉〈確信の程度〉に依存して浮動する性質をもち,これが景気を左右する。このように〈期待の状態〉が経済活動に決定的な影響をもたらすことを明らかにしたのが,《一般理論》のいま一つの重要な特徴である。
さらに,ケインズは,貨幣の役割を重視して,貨幣のように流動性が高く,しかも持越しに費用がかからない資産が存在するために,利子率や資本の限界効率が一定水準以下になると人々は資本や債券よりも貨幣の保有を選ぶようになり,投資が阻害され,その結果,景気が停滞する可能性を明らかにした。これが,〈流動性のわな〉とか〈ケインズのケース〉と呼ばれる現象である。
このように《一般理論》は,失業の問題の解明に大きな光をあてたが,価格の問題には必ずしも十分な注意が向けられなかった。また,長期的なストックの問題よりも,短期のフローの分析に主眼が置かれた。その結果,1970年代に入ると,現実面でのケインズ的な政策の行詰りもあって,ケインズの理論に対する批判(たとえばマネタリズム)が高まり,反革命の動きが強まっている。なお《一般理論》の邦訳は,1941年に塩野谷九十九訳で東洋経済新報社から刊行された。
執筆者:館 龍一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報