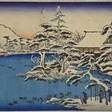日本歴史地名大系 「龍安寺」の解説
龍安寺
りようあんじ
 新堀
新堀 、西限
、西限 勝法院領
勝法院領 、南限
、南限 池堤
池堤 、北限
、北限 主山嶺
主山嶺 、松在之巽限
、松在之巽限 橋、坤限
橋、坤限 山尾
山尾 、乾限
、乾限 大谷
大谷 、艮限
、艮限 谷、悉皆絵図有之 右雖
谷、悉皆絵図有之 右雖 為
為 家領
家領 、依
、依 細川殿所望
細川殿所望 、令
、令 寄
寄 附龍安寺
附龍安寺 之上者、永代不
之上者、永代不 可
可 有
有 違変之儀
違変之儀 之状如
之状如 件」とあり、勝元は徳大寺公有より徳大寺の敷地と山を譲り受け、そこに龍安寺を移している。
件」とあり、勝元は徳大寺公有より徳大寺の敷地と山を譲り受け、そこに龍安寺を移している。
龍安寺
りようあんじ
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「龍安寺」の意味・わかりやすい解説
龍安寺
りょうあんじ
京都市右京区御陵(ごりょう)ノ下町(したまち)にある臨済(りんざい)宗妙心寺派の寺。四円寺の一つ円融寺の跡地にあたる。大雲山(だいうんざん)と号し、俗に石寺(いしでら)、鴛鴦(おしどり)寺という。本尊は釈迦如来(しゃかにょらい)。1450年(宝徳2)細川勝元(かつもと)は自領と交換して徳大寺家の山荘を入手し、この地に一寺を建立、妙心寺第5世義天玄承(ぎてんげんしょう)を招いて住持とし、義天はその師日峰宗舜(にっぽうそうしゅん)を勅請(ちょくしょう)の開山とした。応仁(おうにん)の乱には西軍山名氏の軍の兵火にあい焼失、1488年(長享2)細川政元(まさもと)の招請を受け徳芳禅傑(とくほうぜんけつ)が住持となり、仏殿を造営して中興の祖となった。一時は塔頭(たっちゅう)21を数える大寺であったが、1797年(寛政9)火災にあい、以後衰微した。方丈庭園(特別名勝・史跡)は、細川勝元が幕府同朋衆(どうぼうしゅう)の相阿弥(そうあみ)につくらせた枯山水式石庭で、俗に「虎の子渡し」とよばれる。一面の白砂を敷き、大小15個の石のほか一木一草もない、簡浄で象徴的な石庭として古来名高く、豊臣(とよとみ)秀吉などもその風趣を愛し、たびたび歌会を催したりした。方丈は塔頭西源院(さいげんいん)から移したもの。そのほか総門、中門、唐門、開山堂、弁天堂などの建造物がある。本堂天井の蟠竜(ばんりゅう)および迦陵頻伽(かりょうびんが)の画は兆殿司(ちょうでんす)の筆として知られる。寺宝の西源院本『太平記』12冊は国重要文化財。境内にある鏡容(きょうよう)池はオシドリの名所として有名。龍安寺は1994年(平成6)、世界遺産の文化遺産として登録された(世界文化遺産。京都の文化財は清水寺など17社寺・城が一括登録されている)。
[平井俊榮]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「龍安寺」の意味・わかりやすい解説
龍安寺
りょうあんじ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「龍安寺」の解説
龍安(りょうあん)寺
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...