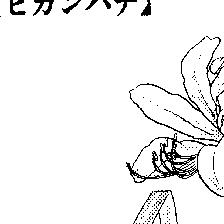ヒガンバナ (彼岸花)
Lycoris radiata Herb.
秋の彼岸のころ(9月下旬)に群生して鮮やかな赤い花をつけるヒガンバナ科の多年草。マンジュシャゲ(曼珠沙華)ともいわれる。花は花茎頂端の散形花序につき,6枚の花被がある。花被は広線形でへりが著しくちぢれ,先端が外側にそりかえる。おしべ6本とめしべの花柱が花冠より長く突き出し,上向きに湾曲する。子房は3室。花茎は高さ30~50cmで,葉はつかない。花時には根出葉もない。根出葉は花後展開し,やや多肉質で長さ30~50cm,幅6~8mm,先端は円い。翌春には枯れる。いわゆる冬緑型多年草の一例である。地下には鱗茎がある。この鱗茎は寸断されたときの再生能力が高く,ヒガンバナが耕作地の近辺などに群生するのはこの性質のためである。日本産のヒガンバナは大部分が三倍体のため,子房は不稔で種子を結ばない。鱗茎は多量のデンプンを含み食用となるが,毒性のあるアルカロイドも含むので,すりつぶした後,数回水洗してアルカロイドをとり除く必要がある。アルカロイド成分は去痰(きよたん)・催吐薬として薬用に利用される。
ヒガンバナ属Lycorisは東アジアに分布し,約10種が知られている。いずれも花が美しく,観賞用に栽培される。これらの種の進化には種間交雑と倍数体形成が重要な役割を果たしたことがわかっているが,中国産植物についての細胞学的資料が少ないため,現状ではまだ種の系統についての結論は得られていない。シロバナヒガンバナL.albiflora Koidz.は,花が白色または白地に黄色か紅色の条がある。花被はヒガンバナほど外側にそりかえらず,葉もやや幅が広い。ヒガンバナとショウキズイセンの交雑に起源したと推定されている。ショウキズイセン(別名ショウキラン)L.aurea(L'Hérit)Herb.(英名golden spider lily)は西南日本から中国,台湾,インドシナにかけて広く分布する種で,花は鮮黄色で,花被はヒガンバナよりも幅広く,ヒガンバナほど外側にそりかえらない。分布が広いうえに変異が多く,種の実体の正確な把握はなされていない。日本産のものはL.traubii Haywardとして狭義のL.aureaとは別種扱いされることもある。ナツズイセンL.squamigera Maxim.(英名hardy amaryllis)は花が淡紅紫色で,上記3種のように花被のへりが著しく波打つことはない。本州中部以北の人家付近に野生状態のものが見いだされるが,本来の野生かどうか疑問視されている。普通は庭園に栽培される。ヒガンバナ同様三倍体で,種子を結ばない。キツネノカミソリL.sanguinea Maxim.は本州,四国,九州に広く野生し,花は朱色で花被のへりは波打たない。花色,花被の形や大きさなどにいろいろな変異があり,いくつかの変種が区別されている。種内分化についての包括的な研究を必要とする種である。
ヒガンバナ科Amaryllidaceae
単子葉植物。約75属1000種を含み,熱帯・亜熱帯域に広く分布する。北半球の温帯には少なく,アジアでは日本が分布の北限である。ユリ科に近縁だが,子房下位である。地下に球茎をもつ多年草。葉は細長くすべて根出葉となる。花茎は分岐せず,先端に苞に抱かれた散形花序をつける。スイセン属などでは散形花序あたりの花数が少なく,しばしば1個に退化する。花には6枚のよく目だつ花被があり,しばしば副花冠が発達する。花被は合着して筒状の花冠となることが多い。子房は3室で通常中に多数の胚珠がある。果実は蒴果(さくか)。花が美しく観賞用に栽培されるものが多い。ヒガンバナ属,スイセン属,ヒッペアストルム属(アマリリス),ホンアマリリス属,ハマオモト属(ハマユウ),ヒメヒガンバナ属(ネリネ),タマスダレ属,スノードロップ属,スノーフレーク属などがその代表的なものである。ヒガンバナ属,スイセン属,スノードロップ属などは植物体にアルカロイドを含み,薬用植物として利用される。ヒガンバナ属の鱗茎はデンプンを多量に含み,食用となる。
執筆者:矢原 徹一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヒガンバナ
ひがんばな / 彼岸花
[学] Lycoris radiata (L' Hér.) Herb.
ヒガンバナ科(APG分類:ヒガンバナ科)の多年草。マンジュシャゲ(曼珠沙華)、シビトバナ(死人花)ともいう。鱗茎(りんけい)は広卵形で径5~6センチメートル、黒褐色の外皮がある。葉は線形で長さ30~50センチメートル、幅6~8ミリメートル、花茎が枯れたあとに出て越冬し、翌春に枯れる。秋の彼岸(ひがん)のころに高さ30~50センチメートルの花茎を出し、散状に緋紅(ひこう)色花を5、6個横向きに開く。花被(かひ)裂片は倒披針(とうひしん)形で長さ約4センチメートル、幅5~6ミリメートル、強く反転し、基部に鱗片状の副花冠がある。雄しべ、雌しべともに花被裂片よりはるかに長く、弓状に上向きに曲がる。寺院の境内や墓地をはじめ、土手や田の畦(あぜ)など人里に生え、東北地方南部から沖縄に広く分布するが、いずれも三倍体で果実はできない。中国には二倍体のシナヒガンバナがあり、これは結実する。シナヒガンバナとショウキズイセンの雑種がシロバナマンジュシャゲ(シロバナヒガンバナ)で、園芸上でリコリスとよばれている。
[清水建美 2019年3月20日]
ヒガンバナは中国が原産の史前帰化植物の一つとされ、渡来には漂着説と伝播(でんぱ)説があるが、中国の野生は染色体数が二倍体で、日本には二倍体はなく、稔(ねん)性のない三倍体のみであり、分布が古い農耕集落地に集中し、中国と使用目的が共通するなどの諸点から、現在は伝播説が有力である。ヒガンバナはアルカロイドのリコリンを中心とする猛毒成分を含むが、中国では腫(は)れ物などの湿布剤(『本草綱目(ほんぞうこうもく)』)に、また、球根を砕き水に溶かした殺虫剤や乾燥させた粉末を殺鼠(さっそ)剤に使い、球根のデンプンを織り糸の糊料(こりょう)や紙漉(かみす)きの粘料にし、救荒時の食物にした(松江幸雄(ゆきお)『ひがんばな』)。日本でも、幾度も水にさらして食用にし、球根をすりおろした汁を1滴湯飲みの水に入れて飲み、ジフテリア様の症状の治療に使ったという民間伝承も残る。ただし、毒抜きが十分でないと死亡する。古くは土蔵の壁土に混ぜてネズミの侵入を防止したり(『和漢三才図会』)、ふすまの糊(のり)にして虫を防いだ(『退私録』)。墓地に多いのはネズミや獣による土葬の死体荒らし対策に、また畦(あぜ)や土手にはネズミやモグラの穴あけ防止に植えたとみられる。かつては葉がミカン輸送のパッキングにも使われた。
ヒガンバナは江戸以前の古典や文献には登場しない。例外は『万葉集』の「壱師花(いちしばな)」で、ヒガンバナとする説も出されている。確実にヒガンバナを取り上げたのは蕪村(ぶそん)の句「曼珠沙華(まんじゅさげ)蘭(らん)に類(たぐ)いて狐(きつね)鳴く」が最初とされる。
[湯浅浩史 2019年3月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヒガンバナ
マンジュシャゲ(曼珠沙華)とも。ヒガンバナ科の多年草。古く中国から渡来したといわれ,本州〜九州の,田のあぜ,堤などにはえる。鱗茎は広卵形で黒い外皮がある。葉は線形で花の終わったあと初冬に出,4月に枯れる。9月(秋の彼岸)ごろ高さ30〜50cmの花茎を立て,数個の朱紅色の花を開く。6枚の花被片は細く,強くそり,6本のおしべは長く突出する。日本に分布するものは3倍体で,結実しない。全草にリコリンなどのアルカロイドを含み有毒。昔は救荒植物として鱗茎を水でさらして有毒成分を除き,食用とした。近縁のシロバナヒガンバナ(シロバナマンジュシャゲ)は花が白い。栽培されるが,九州には自生するともいわれる。
→関連項目帰化植物|ナツズイセン(夏水仙)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ヒガンバナ(彼岸花)
ヒガンバナ
Lycoris radiata
ヒガンバナ科の多年草で,マンジュシャゲともいい,他にシビトバナ,シタマガリ,テンガイバナなど多くの呼称がある。日本および中国の暖帯から温帯に分布し,堤防,墓地,田のあぜなどに生える。皇居の内堀に面した土手の群落は有名である。外皮の黒い球形の鱗茎で,葉は花後に出る。秋に,鱗茎から 50cmほどの中空の花茎を1本出し,茎頂に赤い有柄の花を数個輪生状につける。下部に膜質の総包片が数枚ある。花被片は6枚あって狭い披針形で外側に著しくそり返る。葉は厚質で光沢のある線形で鱗茎から叢生し,晩秋に伸び出し翌年の春には枯れる。三倍体のため種子は通常できないが,中国の中部には結実するもの (二倍体) がある。鱗茎はリコリンという毒物を含むが,水でよくさらしてデンプンをとり救荒食物とした記録もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のヒガンバナの言及
【マンジュシャゲ(曼珠沙華)】より
…ヒガンバナ科[ヒガンバナ]の別名。有毒植物であるが鱗茎(球根)をすりつぶして水にさらし毒抜きをし食べられるので,縄文時代に食用にするため中国から持ちこまれ野生化したものであろう。…
【有毒植物】より
… 以上のような有毒植物に対しワラビのプタキロサイドやソテツのサイカシンなどにはいずれも,長期の摂取による発癌性が認められている。ヒガンバナなどリコリンやシュウ酸を含む植物と同様に,水にさらせば無毒化する。カラシナなどアブラナ科の植物は体内でゴイトリンを形成し,甲状腺でのヨウ素の取込みを阻害して甲状腺腫多発の原因となる。…
※「ヒガンバナ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by